「がん」と診断されたとき、多くの方が大きな不安を感じるでしょう。しかし、「がん」と一言でいっても、その性質や特徴は千差万別です。
がんは、発生した場所、細胞の見た目、進行の度合いなど、さまざまな視点から細かく分類します。この分類を正しく理解することは、ご自身の状態を把握し、医師の説明を深く理解する上で非常に重要です。
この記事では、複雑に見えるがんの分類と種類について、基本的な考え方から専門的な内容まで、一つひとつ丁寧に解説していきます。
正しい知識を身につけ、治療への第一歩を踏み出しましょう。
がんの基本的な分け方
がんの理解を深めるためには、まず基本的な分類の考え方を知ることが大切です。
ここでは、がんを語る上で基本となる「良性・悪性」「原発・転移」「固形・血液」という3つの視点から、それぞれの違いと関係性を解説します。
これらの区別は、治療方針を決定する上で最も重要な基盤となります。
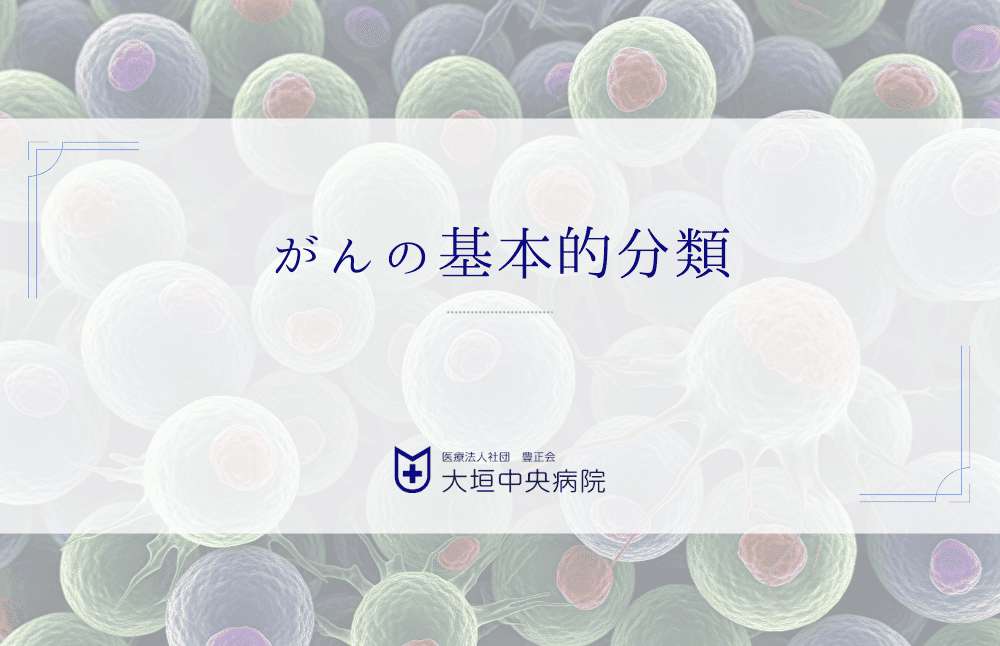
良性腫瘍と悪性腫瘍の違い
「腫瘍」とは、体の細胞が異常に増殖してできた塊のことです。腫瘍には「良性腫瘍」と「悪性腫瘍」の2種類があり、一般的に「がん」と呼ぶのは後者の悪性腫瘍です。
両者の最も大きな違いは、増殖の仕方と周囲への影響にあります。良性腫瘍は、増殖のスピードが比較的ゆっくりで、大きくなっても周囲の組織を圧迫するだけです。
正常な組織との境界もはっきりしており、他の臓器に広がる(転移する)ことはありません。一方、悪性腫瘍は、自律的に無制限に増殖し続けます。
周囲の組織に染み込むように広がり(浸潤)、血管やリンパ管を通って体のあちこちに飛び火し、そこで新たな塊を作ります(転移)。
この浸潤と転移という性質が、悪性腫瘍を生命にとって危険なものにしています。
良性腫瘍と悪性腫瘍の性質比較
| 性質 | 良性腫瘍 | 悪性腫瘍(がん) |
|---|---|---|
| 増殖速度 | ゆっくり | 速い |
| 境界 | 明瞭 | 不明瞭 |
| 転移 | しない | する |
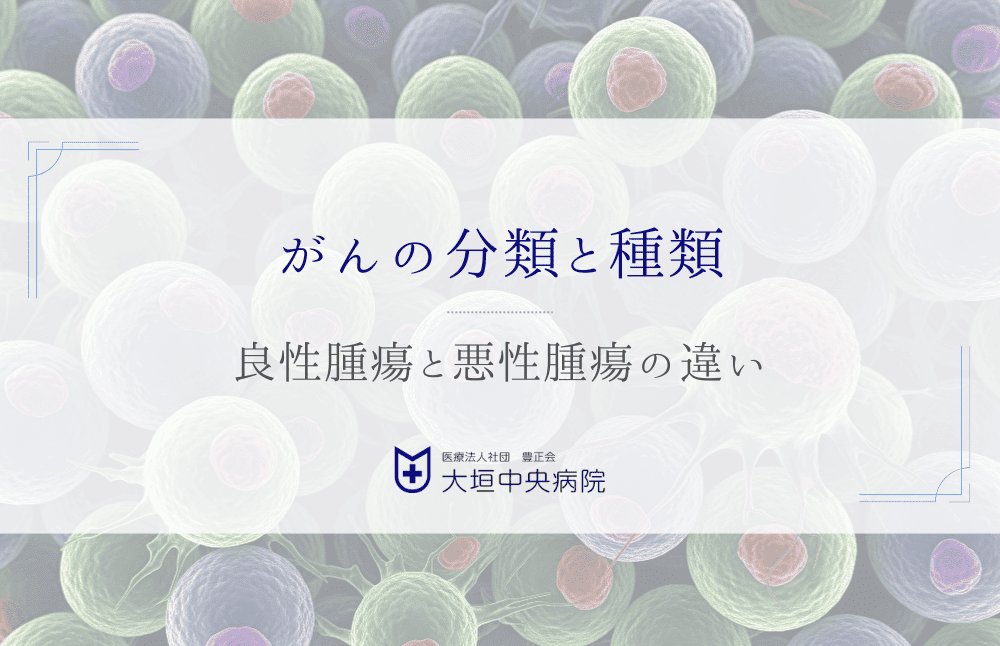
原発がんと転移がんの区別
がんは、最初に発生した場所(臓器)によって「原発がん(原発巣)」と呼びます。例えば、肺で最初に発生したがんは「原発性の肺がん」です。
この原発巣からがん細胞が血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器に移動し、そこで増殖して新たな腫瘍を作ることがあります。これを「転移がん(転移巣)」と呼びます。
例えば、肺がんが脳に転移した場合、脳にできた腫瘍は「転移性脳腫瘍」であり、脳の細胞ががん化した「原発性脳腫瘍」とは区別します。
転移がんは、もとになった原発がんの性質を受け継いでいるため、治療法も原発がんの種類に基づいて選択します。
肺がんが脳に転移した場合、脳腫瘍に対する治療ではなく、肺がんに対する薬物療法などを中心に行うのが一般的です。
どこでがんが見つかったかだけでなく、どこから来たがんなのかを特定することが、治療方針を決める上で極めて重要です。
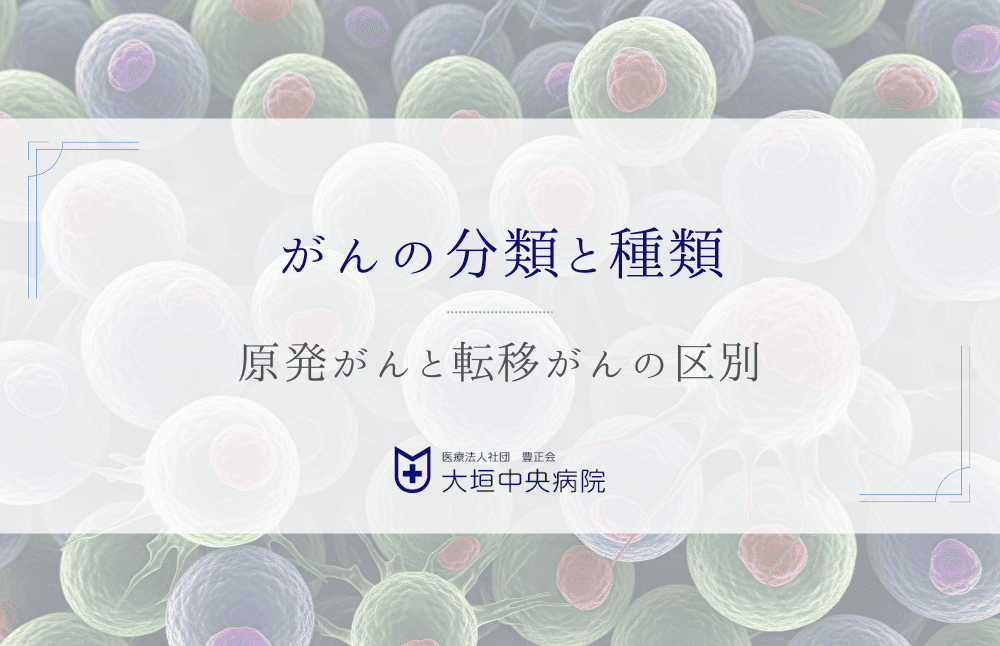
固形がんと血液がんの分類
がんを発生する場所や形態によって大きく分けると、「固形がん」と「血液がん」の2つに分類できます。
固形がんは、胃、肺、大腸、乳房など、特定の臓器に細胞の塊(腫瘍)を作るタイプのがんです。がん全体の約90%を占めており、多くの人が「がん」と聞いてイメージするのはこの固形がんといえるでしょう。
一方、血液がんは、白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など、血液やリンパ組織の細胞ががん化するものです。
特定の場所に塊を作らず、がん細胞が血液やリンパの流れに乗って全身を巡るのが特徴です。そのため、手術で取り除くという考え方が当てはまらず、主に抗がん剤などの薬物療法で治療を行います。
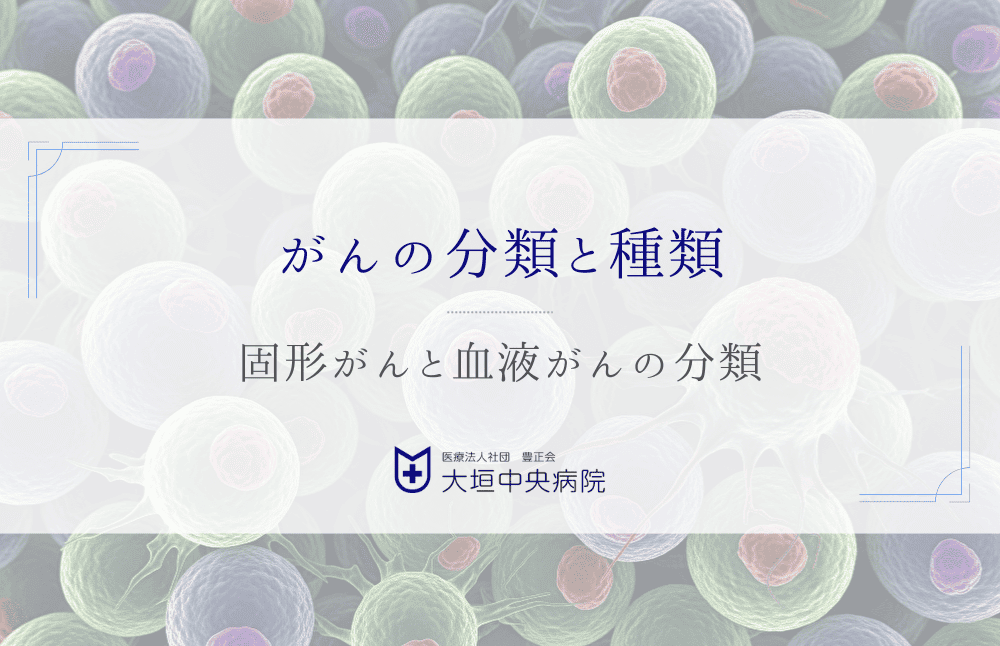
組織学的な分類-発生した組織による分け方
がんは、どの種類の細胞から発生したかによっても分類します。これを「組織学的分類」と呼びます。
私たちの体は、皮膚や臓器の表面を覆う「上皮組織」、骨や筋肉、血管などを構成する「非上皮組織」、血液やリンパの成分を作る「造血器組織」などから成り立っています。
このどの組織の細胞ががん化したかによって、がんの名称や性質が大きく異なります。
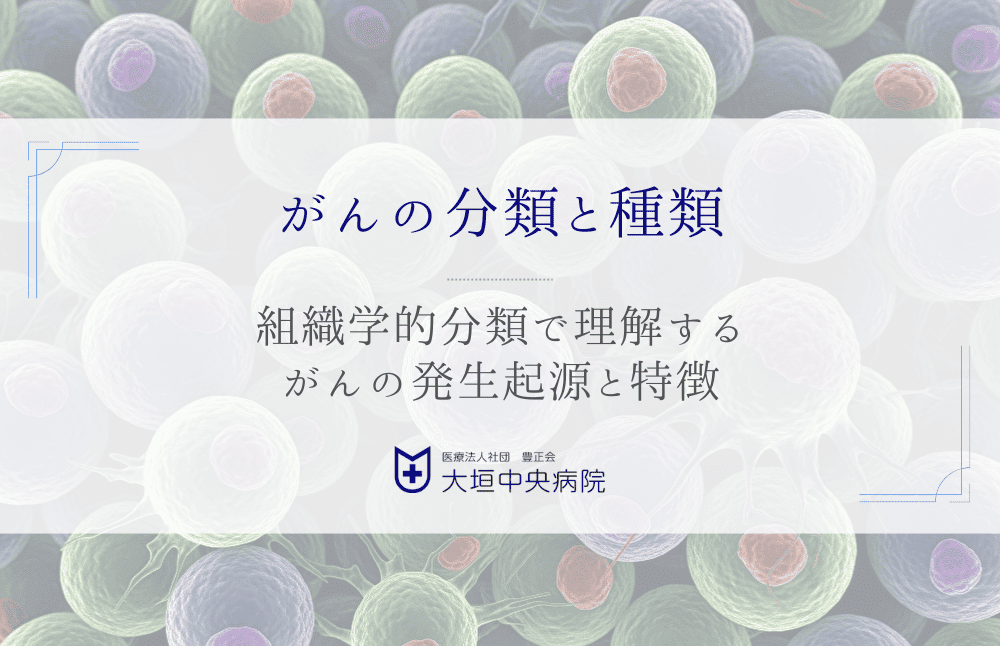
上皮性腫瘍(癌腫)
体の表面や臓器の粘膜などを覆っている上皮細胞から発生する悪性腫瘍を「癌腫(がんしゅ、Carcinoma)」と呼びます。
胃がん、肺がん、大腸がん、乳がんなど、一般的に知られる固形がんの多くがこの癌腫に分類されます。癌腫はさらに、細胞の形や構造によって「腺がん」や「扁平上皮がん」などに細かく分けられます。
腺がんは、粘液などを分泌する「腺細胞」に由来するがんで、胃や大腸、肺、乳房、前立腺などに多く見られます。
一方、扁平上皮がんは、皮膚や食道、気管、子宮頸部などの表面を覆う「扁平上皮細胞」から発生するがんです。この区別は、がんの悪性度や治療法の選択に影響します。

非上皮性腫瘍(肉腫)
骨、軟骨、脂肪、筋肉、血管といった、体を支えたりつないだりする非上皮性の組織から発生する悪性腫瘍を「肉腫(にくしゅ、Sarcoma)」と呼びます。
癌腫に比べて発生頻度は非常にまれで、がん全体の1%程度です。
肉腫は全身のあらゆる場所に発生する可能性があり、骨にできる「骨肉腫」、脂肪組織にできる「脂肪肉腫」、筋肉にできる「平滑筋肉腫」など、発生した組織の名を冠して呼ばれます。
癌腫がリンパ節に転移しやすいのに対し、肉腫は血液の流れに乗って肺などに転移しやすいという特徴があります。治療法も癌腫とは異なる場合が多く、専門的な知識と経験を持つ医療機関での治療が重要です。
癌腫・肉腫・造血器腫瘍の比較
| 分類 | 由来する組織 | 代表的ながん |
|---|---|---|
| 癌腫 (Carcinoma) | 上皮組織(皮膚、粘膜など) | 胃がん、肺がん、大腸がん |
| 肉腫 (Sarcoma) | 非上皮組織(骨、筋肉、脂肪など) | 骨肉腫、脂肪肉腫、平滑筋肉腫 |
| 造血器腫瘍 | 造血器組織(骨髄、リンパ節) | 白血病、悪性リンパ腫 |
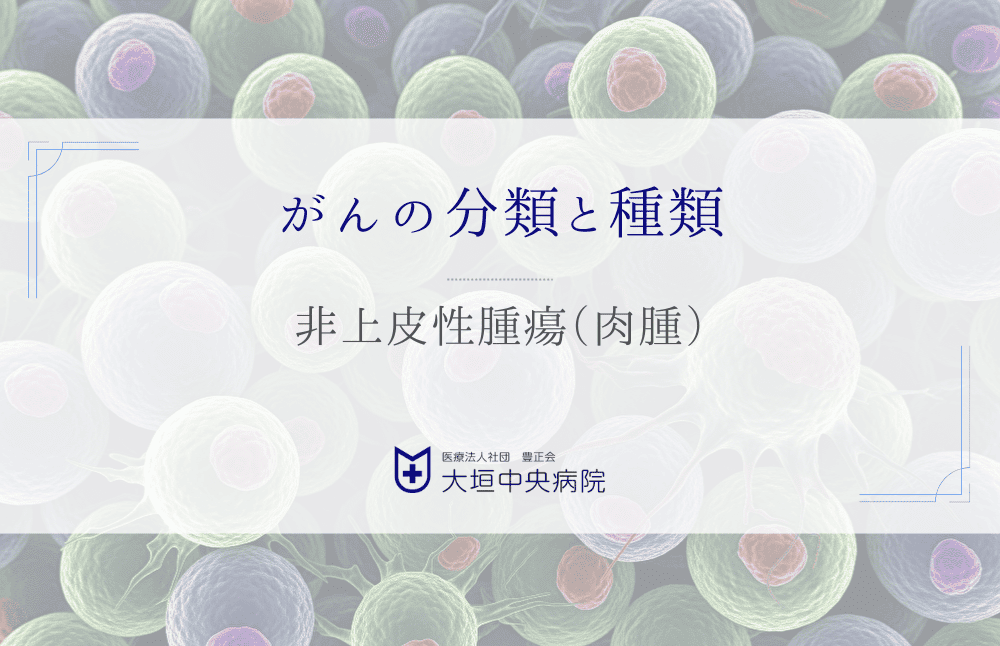
造血器腫瘍
血液細胞(白血球、赤血球、血小板)やリンパ球が作られる骨髄やリンパ節といった造血器組織から発生する悪性腫瘍を「造血器腫瘍」と呼びます。これらは「血液がん」とも呼ばれます。
代表的なものに、血液細胞が異常に増える「白血病」、リンパ球ががん化してリンパ節などが腫れる「悪性リンパ腫」、骨髄で抗体を作る形質細胞ががん化する「多発性骨髄腫」があります。
これらの腫瘍は、固形がんのように特定の場所に塊を作るのではなく、がん細胞が血液やリンパ液に乗って全身に広がるという特徴を持ちます。

その他の特殊な腫瘍
上記以外にも、特殊な発生起源を持つ腫瘍が存在します。
例えば、神経細胞やその支持細胞から発生する「神経系腫瘍」、ホルモンを産生する細胞から発生する「神経内分泌腫瘍」、複数の種類の細胞が混じって発生する腫瘍などがあります。
また、皮膚の色素を作るメラノサイトががん化する「悪性黒色腫(メラノーマ)」や、胎児期の細胞に由来する「胚細胞腫瘍」なども特殊な腫瘍に分類されます。
これらのまれな腫瘍は、それぞれ特有の性質を持ち、診断や治療には高度な専門知識が必要です。
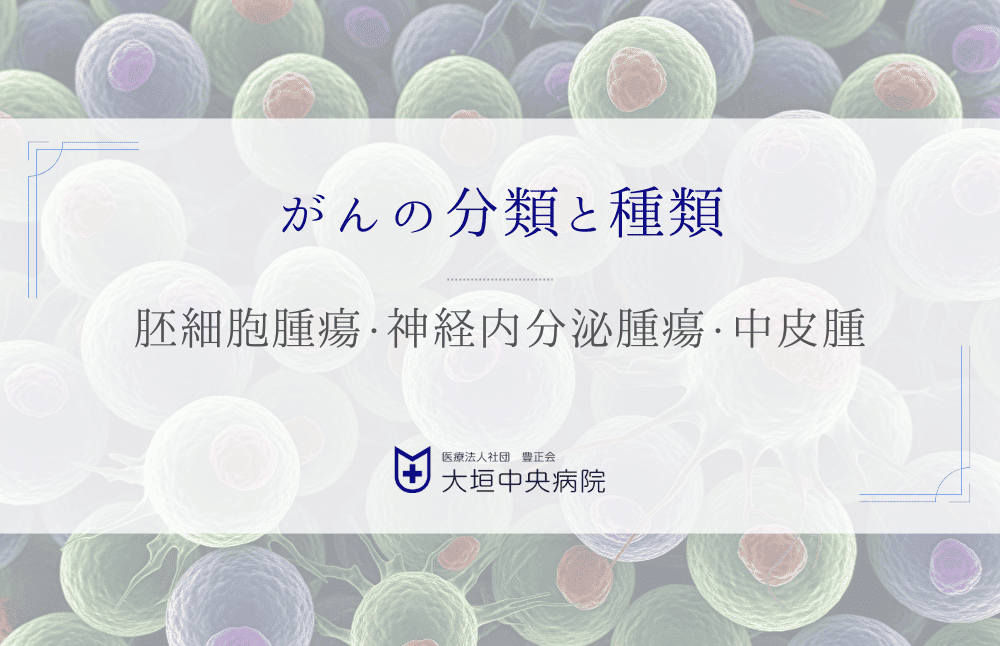
臓器別の分類-発生した部位による分け方
がんの分類で最も一般的で分かりやすいのが、発生した臓器や部位による分類です。肺にできれば肺がん、胃にできれば胃がんというように、原発巣のある臓器の名前で呼びます。
同じ臓器のがんでも、組織型や遺伝子変異によって性質が異なるため、より細かく分類しますが、まずはどの臓器のがんなのかを把握することが診断と治療の出発点となります。
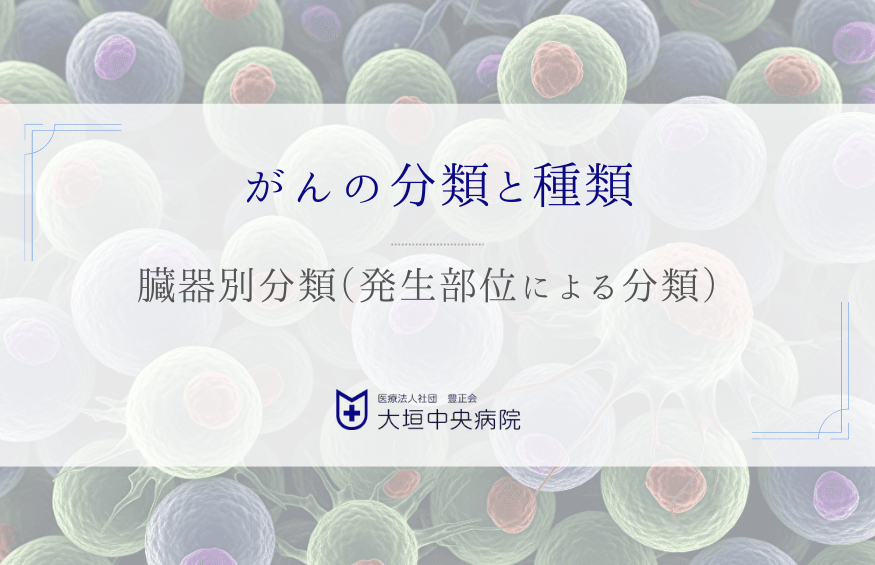
消化器系のがん
消化器系は、食べ物の通り道である消化管(食道、胃、十二指腸、小腸、大腸)と、消化を助ける臓器(肝臓、胆のう、膵臓)から構成されます。これらの臓器に発生するがんを総称して消化器がんと呼びます。
日本では、胃がん、大腸がん、肝臓がん、膵臓がんなどが比較的多く見られます。特に大腸がんは近年増加傾向にあります。
消化器がんは、早期の段階では自覚症状が乏しいことが多く、検診による早期発見が重要です。
治療法は手術、化学療法、放射線療法などを組み合わせますが、臓器の機能温存も考慮しながら治療方針を決定します。
主な消化器系のがん
| がんの種類 | 主な特徴 | 関連する要因 |
|---|---|---|
| 胃がん | ピロリ菌感染との関連が深い | 塩分の多い食事、喫煙 |
| 大腸がん | 食生活の欧米化で増加傾向 | 動物性脂肪の過剰摂取、肥満 |
| 肝臓がん | 肝炎ウイルス感染が主な原因 | アルコール、脂肪肝 |
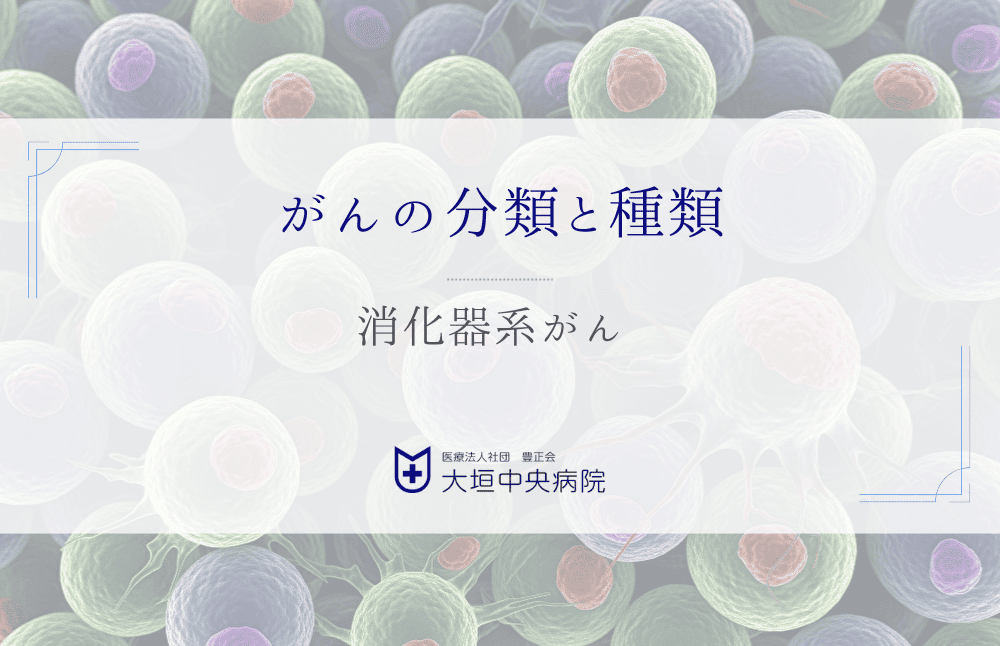
呼吸器系のがん
呼吸器系のがんには、気管、気管支、肺に発生するがんが含まれます。この中で最も多いのが肺がんです。
肺がんは、組織学的に「小細胞肺がん」と「非小細胞肺がん」に大別され、それぞれで性質や治療法が大きく異なります。非小細胞肺がんはさらに腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんなどに分類されます。
喫煙が最大の危険因子であることは広く知られていますが、非喫煙者でも発症することがあります。近年、特定の遺伝子変異を標的とした分子標的薬の進歩により、治療成績が向上しています。
主な呼吸器系のがん
- 肺がん(小細胞がん、非小細胞がん)
- 悪性胸膜中皮腫
- 喉頭がん
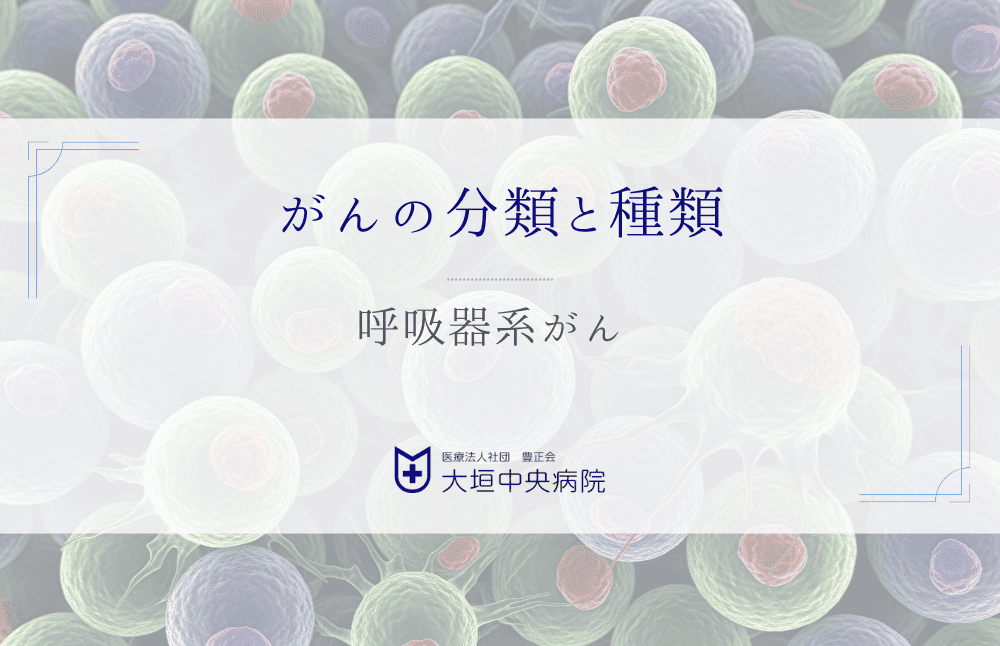
泌尿生殖器系のがん
泌尿器と生殖器に発生するがんを指します。男性では前立腺がんや膀胱がん、精巣腫瘍、女性では腎がんや膀胱がんなどが含まれます。特に前立腺がんは高齢男性で増加しています。
血尿や排尿困難などの症状で発見されることが多いですが、症状が出にくい場合もあります。
治療は、がんの種類や進行度、患者さんの年齢や全身状態を考慮して、手術、放射線療法、薬物療法(ホルモン療法、化学療法など)を使い分けます。
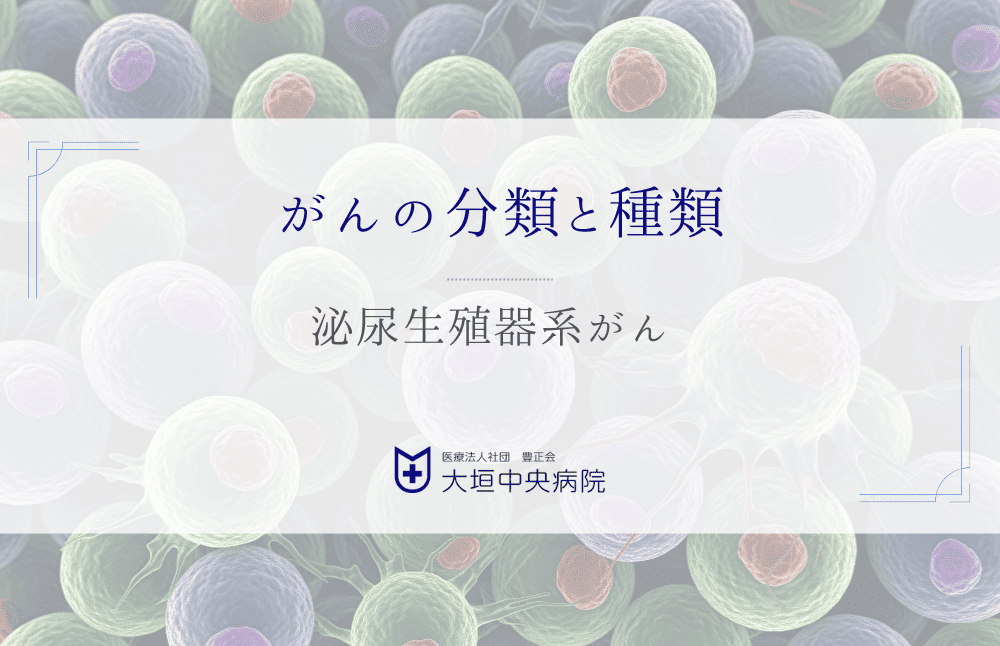
婦人科系のがん
女性特有の生殖器に発生するがんで、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん、外陰がん、腟がんなどがあります。
子宮頸がんはヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が主な原因であり、ワクチン接種による予防や検診による早期発見が可能です。
子宮体がんは閉経後の女性に多く、不正出血が主な症状です。卵巣がんは「サイレントキラー」とも呼ばれ、早期発見が難しく、進行した状態で見つかることが多いのが特徴です。
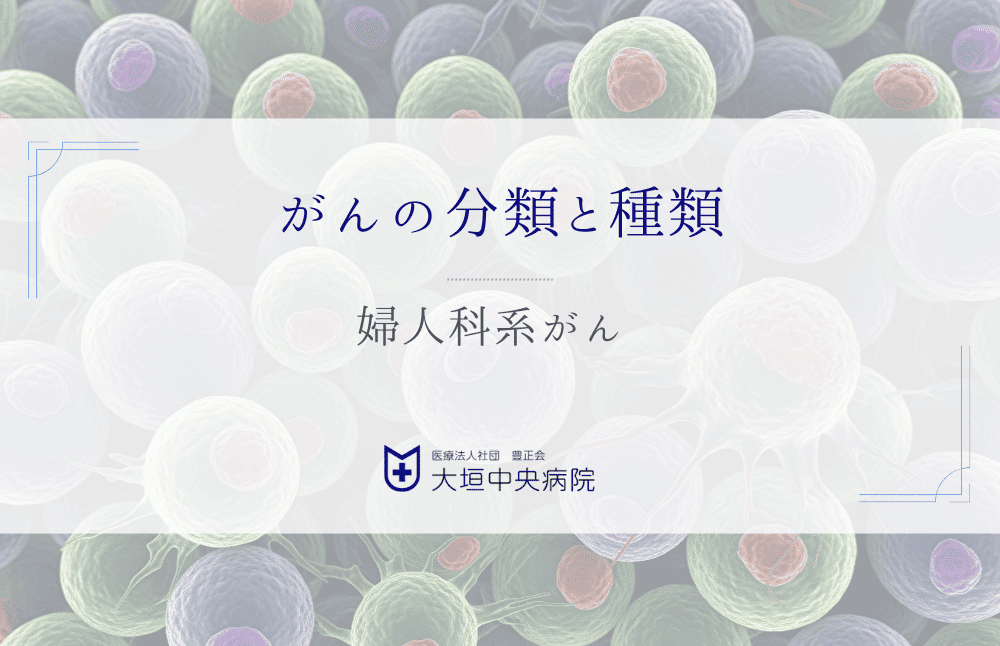
内分泌系のがん
ホルモンを産生・分泌する内分泌器官に発生するがんです。甲状腺がん、副腎がん、下垂体腫瘍などがあります。
甲状腺がんは進行が比較的ゆっくりなタイプが多いですが、中には悪性度の高いものもあります。
ホルモンを過剰に産生するタイプのがんでは、ホルモン異常による特有の症状(高血圧、動悸、体重減少など)が現れることがあります。
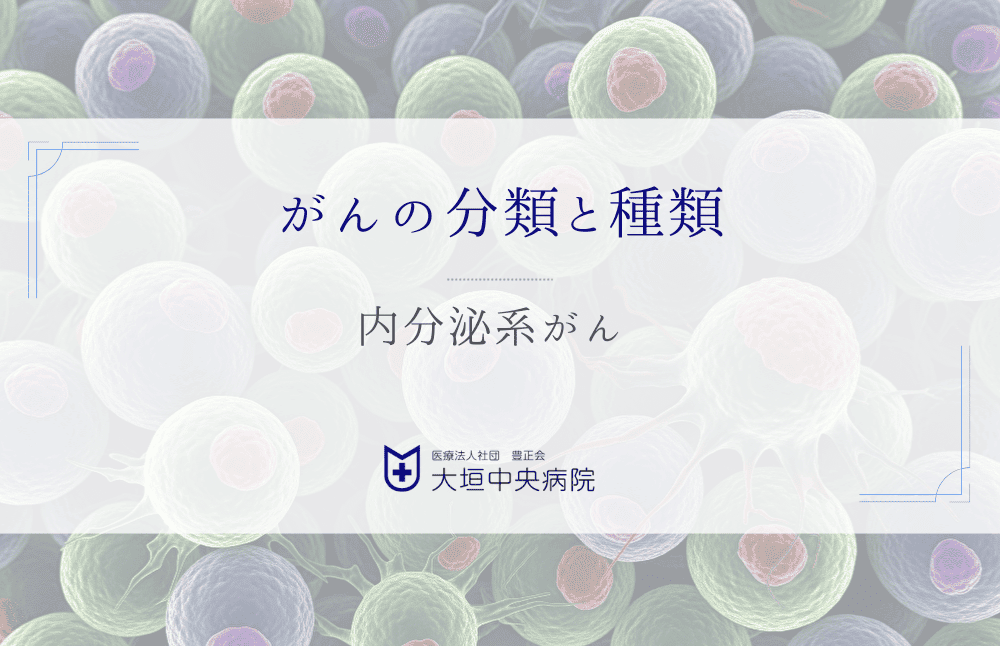
頭頸部のがん
頭頸部(とうけいぶ)がんは、脳と眼を除く、頭から首までの範囲に発生するがんの総称です。具体的には、鼻、口、喉(咽頭・喉頭)、唾液腺などにできるがんが含まれます。
話す、食べる、呼吸するといった重要な機能に関わる部位であるため、治療においては機能温存が大きな課題となります。
主な原因として喫煙や過度の飲酒が挙げられますが、近年ではHPVが関連する中咽頭がんも増えています。
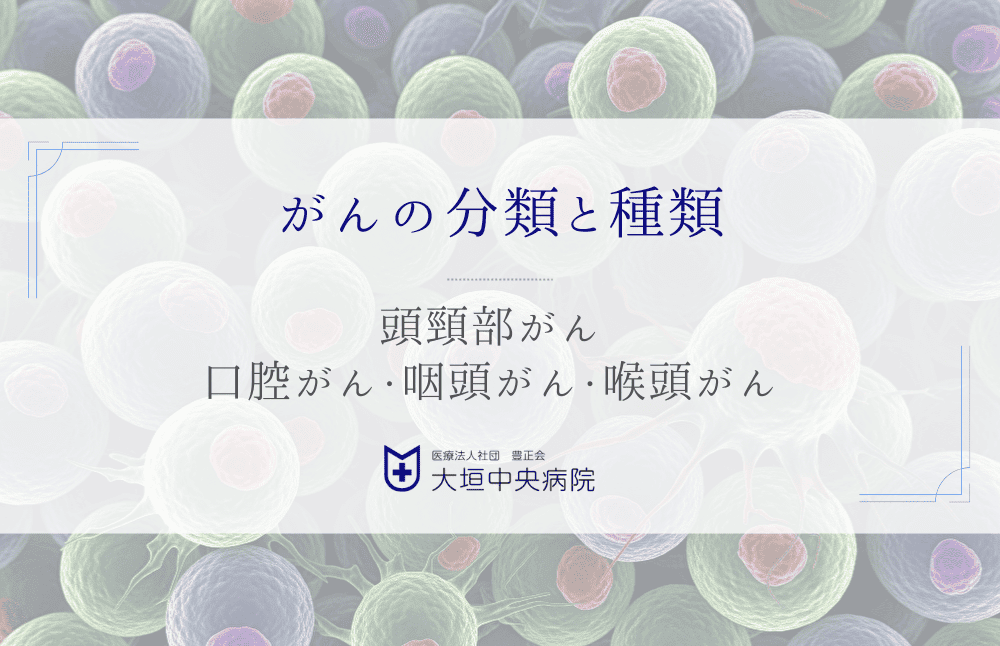
脳・神経系のがん
脳や脊髄、末梢神経に発生する腫瘍です。脳そのものから発生する「原発性脳腫瘍」と、他の臓器のがんが脳に転移した「転移性脳腫瘍」があります。
原発性脳腫瘍には多くの種類があり、良性のものも悪性のものも含まれます。頭痛、吐き気、手足の麻痺、けいれんなど、発生した場所に応じた様々な神経症状を引き起こします。
頭蓋骨の内側にできるため、良性であっても大きくなると脳を圧迫し、重篤な症状を引き起こすことがあります。
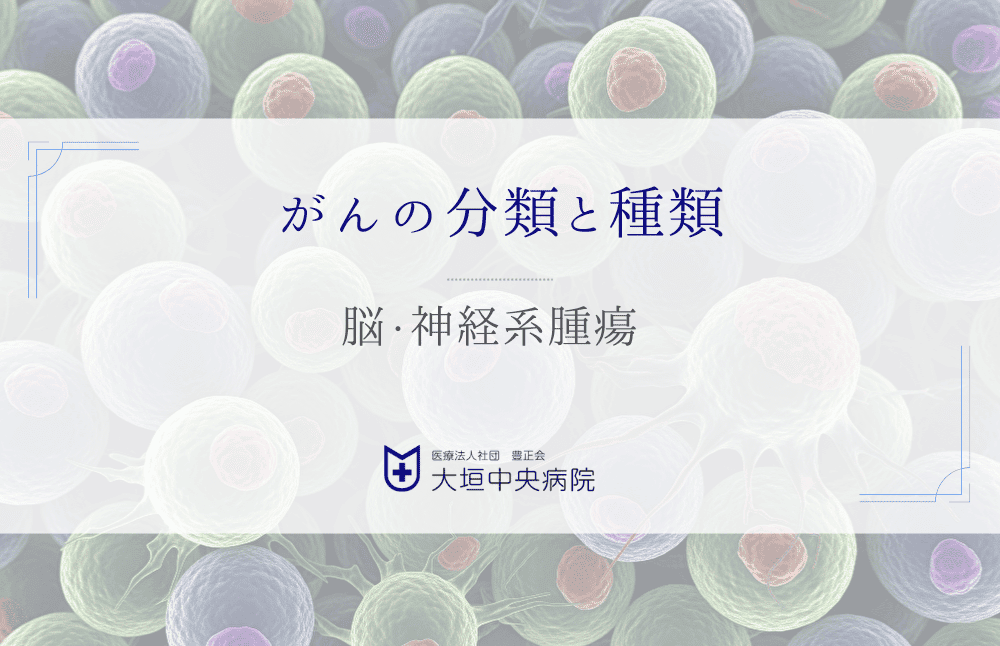
皮膚のがん
皮膚に発生するがんの総称で、いくつかの種類があります。最も多いのは「基底細胞がん」で、転移することはまれです。次いで「有棘細胞がん」があり、こちらは転移する可能性があります。
そして、悪性度が高いことで知られるのが、ほくろのがんとも呼ばれる「悪性黒色腫(メラノーマ)」です。紫外線が主な原因とされ、早期発見と治療が非常に重要です。
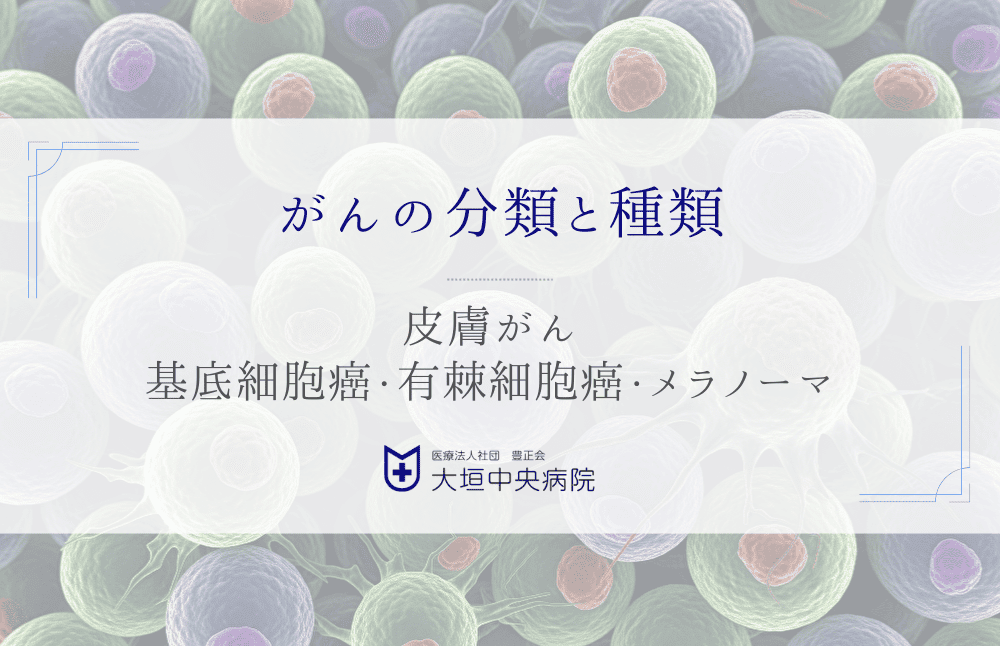
病期分類 – ステージによる進行度の分け方
がんの進行度合いを示す国際的な基準が「病期(ステージ)」です。病期は、がんの大きさ、リンパ節への転移の有無、他の臓器への転移(遠隔転移)の有無という3つの要素を組み合わせて決定します。
これにより、がんの状態を客観的に評価し、最適な治療方針を立て、治療効果の予測や比較検討を行います。
医師から「ステージ」について説明を受けることは、ご自身の病状を理解する上で不可欠です。
TNM分類システム
病期を決定するために世界中で広く用いられているのが「TNM分類」です。
これは、国際対がん連合(UICC)が定めた国際的な基準です。TNMは以下の3つの要素の頭文字から取られています。 T(Tumor)は原発巣の腫瘍の大きさと周囲への広がりを示します。
T1、T2、T3、T4と数字が大きくなるほど、腫瘍が大きく、周囲の組織へ深く浸潤していることを意味します。 N(Nodes)は所属リンパ節(原発巣の近くにあるリンパ節)への転移の有無と範囲を示します。
N0は転移なし、N1、N2、N3と数字が大きくなるほど、転移の範囲が広がっていることを示します。 M(Metastasis)は遠隔転移の有無を示します。M0は遠隔転移なし、M1は遠隔転移ありを意味します。
TNM分類の各因子
| 因子 | 評価する内容 | 進行度の目安 |
|---|---|---|
| T (Tumor) | 原発腫瘍の大きさと広がり | T1(小) → T4(大) |
| N (Nodes) | 所属リンパ節への転移 | N0(無) → N3(広範囲) |
| M (Metastasis) | 遠隔臓器への転移 | M0(無) → M1(有) |
病期(ステージIからIV)の定義
TNM分類の評価を総合して、がんの進行度をステージI(1期)からステージIV(4期)までの4段階に分類します。
これはあくまで一般的な目安であり、がんの種類によって定義は異なりますが、大まかな考え方は共通しています。
病期の一般的な考え方
- ステージI:がんが原発巣に限局しており、小さい。リンパ節転移もない。
- ステージII:がんが原発巣の近くの組織に広がり始めているか、リンパ節にわずかに転移している。
- ステージIII:がんがさらに広範囲に広がるか、リンパ節転移が明確になっている。
- ステージIV:がんが原発巣から遠く離れた他の臓器に転移している(遠隔転移)。
一般的に、ステージの数字が小さいほど早期のがんであり、治療成績も良好な傾向があります。
逆に、数字が大きくなるほど進行したがんであり、より集学的な治療が必要となります。
臓器特異的な病期分類
TNM分類は多くのがんで使用される国際標準ですが、がんの種類によっては、その特性に合わせて独自の病期分類を用いることがあります。
例えば、血液がんである白血病や悪性リンパ腫では、病変が全身に広がっていることが前提となるため、TNM分類は用いず、病型や進行の速さ、特定の遺伝子異常の有無などに基づいた分類法で治療方針を決定します。
また、婦人科がんでは、手術所見に基づいて病期を決定する「FIGO(国際産婦人科連合)分類」が広く用いられています。
それぞれの臓器の解剖学的な特徴や、がんの広がり方を考慮した分類法が存在します。
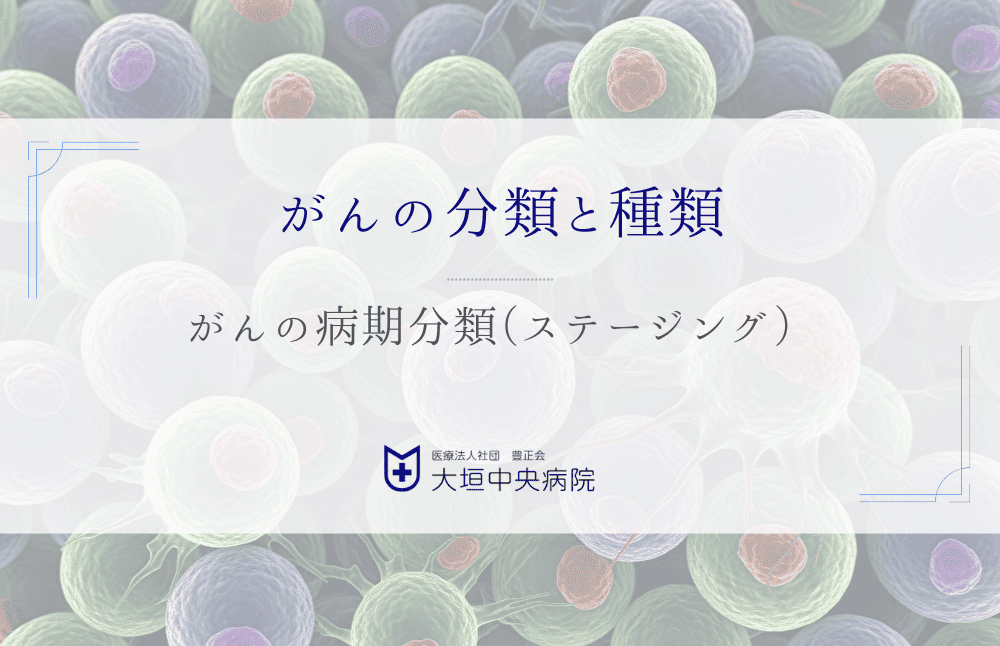
悪性度分類 – グレードによる顔つきの分け方
がんの進行度を示す「病期(ステージ)」とは別に、がん細胞そのものの性質、いわば「顔つきの悪さ」を示す指標として「悪性度(グレード)」があります。
これは、採取した組織を顕微鏡で観察し、がん細胞が正常な細胞とどれくらい異なっているか(異型度)、どのくらいの速さで増殖しているか(分裂像)などを評価するものです。
悪性度が高いがんほど、増殖が速く、転移しやすい傾向があります。
分化度による分類
悪性度を評価する上で最も重要な指標が「分化度」です。
分化とは、細胞が特定の役割を持つ成熟した細胞に変化していくことです。正常な細胞は、どの臓器の細胞なのかがはっきりと分かる形をしています(高分化)。
一方、がん細胞は、この分化の能力が低下し、未熟な細胞の形(低分化・未分化)になります。分化度が高い(正常細胞に近い)がん細胞は、比較的おとなしい性質で、増殖もゆっくりです。
逆に、分化度が低い(正常細胞からかけ離れている)がん細胞ほど、悪性度が高く、増殖が速いと考えられます。
分化度によるグレード分類
| グレード | 分化度 | 細胞の見た目と性質 |
|---|---|---|
| G1 (Grade 1) | 高分化型 | 正常細胞に似ており、増殖が比較的遅い |
| G2 (Grade 2) | 中分化型 | G1とG3の中間の性質を持つ |
| G3 (Grade 3) | 低分化型 | 正常細胞とは大きく異なり、増殖が速い |
組織学的悪性度
組織学的悪性度は、分化度に加えて、がん細胞が作る構造の異質性や、細胞分裂の頻度などを総合的に評価して決定します。
例えば、乳がんでは、核の異型度、核分裂像の数、腺管形成の度合いという3つの要素をスコア化し、その合計点によってグレード1から3に分類します。
このように、がんの種類ごとに特有の評価基準が設けられています。グレードの情報は、手術後の追加治療(補助化学療法など)の必要性を判断する際や、予後を予測する上で重要な情報となります。
核異型度
がん細胞の「核」(細胞の設計図である遺伝情報が入っている部分)の形態異常を評価することも、悪性度を判断する上で重要です。これを「核異型度」と呼びます。
正常な細胞の核は形や大きさが均一ですが、がん細胞の核は以下のような異常を示します。
核異型度で評価する主な点
- 核の大きさの不均一性
- 核の形の歪み
- 核の色の濃さ(クロマチンの増量)
これらの異常が強いほど、がん細胞の悪性度が高いと判断されます。核異型度は、特に甲状腺がんや婦人科がんなどの診断において重要な指標となります。

分子生物学的な分類
近年のがん研究の進歩により、がんの発生や増殖に特定の遺伝子や分子が深く関わっていることが解明されてきました。
これまでの組織型や病期による分類に加え、がん細胞が持つ遺伝子の変異やタンパク質の発現パターンといった分子レベルの情報に基づいてがんを分類する「分子生物学的分類」が、治療方針の決定において急速に重要性を増しています。
遺伝子変異による分類
がん細胞では、細胞の増殖をコントロールする遺伝子に異常(変異)が生じています。特に、がんの増殖の直接的な原因となる遺伝子変異を「ドライバー遺伝子変異」と呼びます。
例えば、非小細胞肺がんの一部では、EGFR遺伝子やALK融合遺伝子といった特定のドライバー遺伝子変異が見つかります。
このような遺伝子変異の有無を調べる「がん遺伝子パネル検査」などによって、がんをより細かく分類し、それぞれの変異に応じた治療薬を選択することが可能になっています。
同じ肺がんでも、どの遺伝子に変異があるかによって、全く異なるサブタイプとして扱われます。
代表的なドライバー遺伝子変異と関連するがん
| 遺伝子変異 | 主ながんの種類 | 治療法への応用 |
|---|---|---|
| EGFR遺伝子変異 | 肺がん(非小細胞肺がん) | EGFR阻害薬 |
| HER2遺伝子増幅 | 乳がん、胃がん | 抗HER2薬 |
| BRAF V600E変異 | 悪性黒色腫、大腸がん | BRAF阻害薬 |
分子標的による分類
ドライバー遺伝子変異の結果として作られる異常なタンパク質は、がん細胞の増殖のスイッチ役を果たしています。
この特定の分子(タンパク質)だけを狙い撃ちして、がん細胞の増殖を抑える薬が「分子標的治療薬」です。
この治療法を適用するためには、標的となる分子ががん細胞に存在するかどうかを事前に検査し、分類する必要があります。
例えば、乳がんでは、女性ホルモンの影響を受ける「ホルモン受容体陽性」タイプ、HER2というタンパク質が過剰に発現している「HER2陽性」タイプ、どちらも陰性の「トリプルネガティブ」タイプなどに分類し、それぞれに応じた治療戦略を立てます。これは、分子標的による分類の典型例です。
主な分子標的薬の種類
- チロシンキナーゼ阻害薬
- モノクローナル抗体薬
- mTOR阻害薬
免疫学的特性による分類
私たちの体には、がん細胞を異物として認識し攻撃する「免疫」という仕組みが備わっています。
しかし、がん細胞の中には、免疫細胞からの攻撃にブレーキをかける物質(PD-L1など)を表面に出して、免疫の監視から逃れるものがあります。
近年、このブレーキを解除して、患者さん自身が持つ免疫の力でがんを攻撃させる「免疫チェックポイント阻害薬」が登場し、治療に大きな変化をもたらしました。
この薬が効くかどうかを予測するために、がん組織におけるPD-L1の発現率などを調べてがんを分類します。PD-L1の発現率が高いほど、免疫チェックポイント阻害薬の効果が期待できるとされています。
このように、がんと免疫系の相互作用に着目した分類も重要になっています。
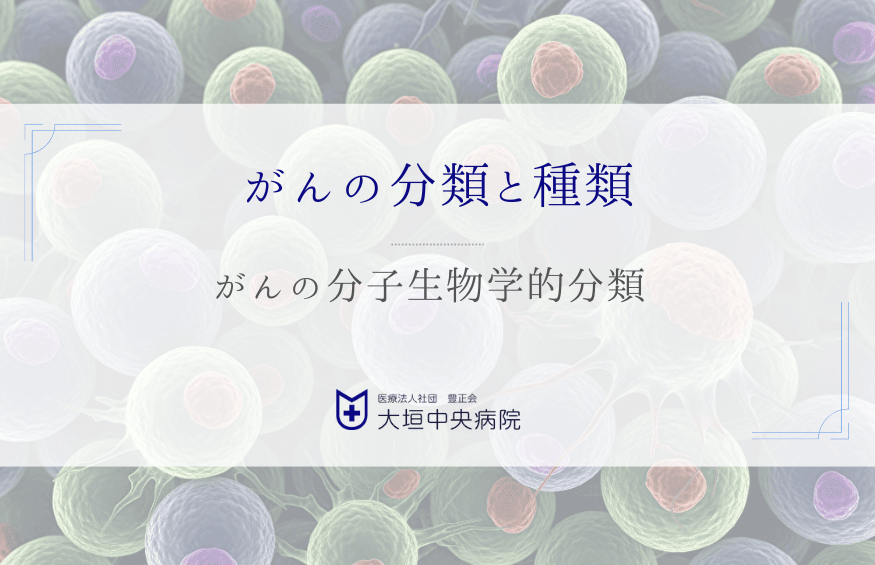
臨床的な分類
実際の医療現場では、これまでに述べた分類法に加えて、患者さんの治療経過や状態に基づいた「臨床的分類」も行われます。
これは、治療法の選択や今後の見通しを立てる上で、より実践的な視点からがんを捉える分類法です。予後(病気の経過についての医学的な見通し)、治療への反応性、転移のパターンなどが考慮されます。
予後による分類
がんの種類によって、進行の速さや治りやすさには大きな差があります。
これまでの多くの患者さんの治療データから、比較的進行がゆっくりで治療成績が良い「予後良好」ながんと、進行が速く治療が難しい「予後不良」ながんに大別することがあります。
例えば、甲状腺がんの多くや前立腺がんの一部は予後良好ながんに分類されることが多い一方、膵臓がんや悪性度の高い脳腫瘍などは予後不良ながんとされることがあります。
ただし、これはあくまで統計的な傾向であり、同じ種類のがんでも個々の患者さんで経過は異なります。また、新しい治療法の開発により、これまで予後不良とされてきたがんの治療成績も向上しています。
予後による分類の例
| 分類 | がんの例(一般的な傾向) | 特徴 |
|---|---|---|
| 予後良好群 | 甲状腺乳頭がん、一部の皮膚がん | 進行が遅く、治療による治癒が期待しやすい |
| 予後不良群 | 膵臓がん、スキルス胃がん | 進行が速く、治療抵抗性を示すことが多い |
治療反応性による分類
特定治療法が効きやすいか、効きにくいかによってがんを分類することもあります。例えば、放射線治療が効きやすい「放射線感受性」の高いがんと、効きにくい「放射線抵抗性」のがんがあります。
精巣腫瘍や悪性リンパ腫の一部は放射線感受性が高いことで知られています。
また、化学療法(抗がん剤治療)においても、薬が効きやすい「化学療法感受性」のがんと、効きにくい「化学療法抵抗性」のがんがあります。
治療を開始する前にこれらの感受性をある程度予測することもありますが、実際に治療を行ってみて、その効果(腫瘍が縮小するかどうかなど)によって判断することもあります。
治療反応性は、二次治療以降の治療法を選択する上で重要な情報となります。
転移パターンによる分類
がんの種類によって、転移しやすい臓器の傾向(転移のパターン)が異なることが知られています。
例えば、肺がんは脳や骨、肝臓、副腎に、乳がんは骨や肺、肝臓、脳に、前立腺がんは骨に転移しやすいという特徴があります。
この転移のパターンを考慮することで、転移が疑われる症状が出た際に、どの臓器を重点的に調べるべきかの判断材料になります。
また、原発巣が不明ながん(原発不明がん)の場合、転移している臓器のパターンから、もとになった原発巣を推測する手がかりとすることもあります。
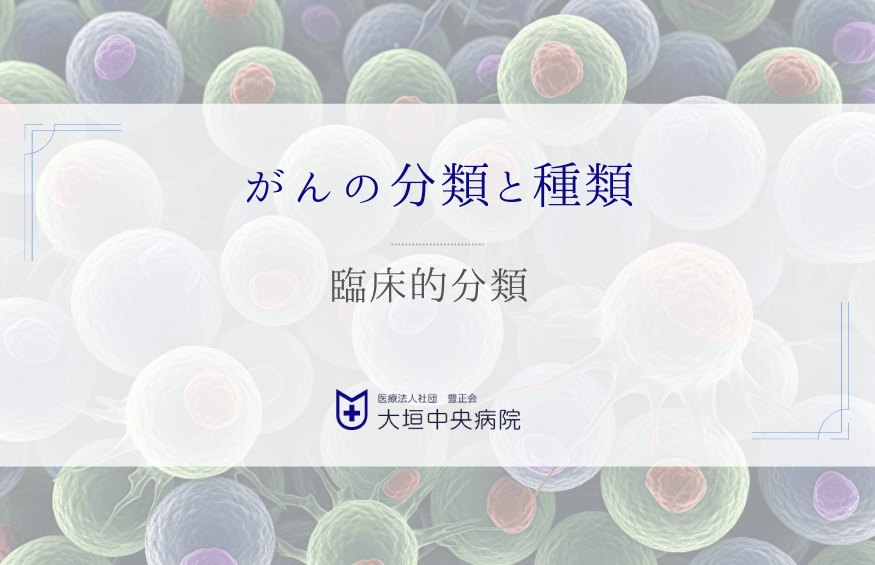
特殊な分類
これまで述べてきた分類の枠組みには収まらない、特殊な状況や背景を持つがんも存在します。
ここでは、小児に特有のがん、遺伝的要因が強く関わるがん、そして複数の異なるがんが発生するケースについて解説します。
これらの特殊な分類を理解することは、それぞれに応じた適切な対応を取るために重要です。
小児がんの分類
小児(0歳から15歳未満)に発生するがんは、成人のがんとは多くの点で異なります。
成人のがんが胃がんや肺がんなど、上皮細胞に由来する「癌腫」が中心であるのに対し、小児がんは白血病などの血液がんや、胎児期の未熟な細胞に由来する「芽腫(がしゅ)」(神経芽腫、腎芽腫など)が多くを占めます。
発生頻度も成人に比べてはるかに少なく、希少がんの一種です。進行が速いものが多い一方で、化学療法や放射線治療に対する感受性が高く、治療によって治癒する可能性も高いという特徴があります。
治療は、小児がんを専門とする医療機関で、成長や発達への影響も考慮しながら慎重に進める必要があります。
小児がんと成人のがんの主な違い
| 項目 | 小児がん | 成人のがん |
|---|---|---|
| 主な種類 | 白血病、脳腫瘍、芽腫、肉腫 | 癌腫(肺がん、胃がん、大腸がん等) |
| 原因 | 不明な点が多い、偶発的 | 生活習慣、環境要因の蓄積 |
| 進行速度 | 速いことが多い | 比較的ゆっくりなものが多い |
遺伝性がん症候群
がんの多くは遺伝しないものですが、一部のがんでは、生まれつき特定の遺伝子に変異があるために、がんを発症しやすい体質が親から子へ受け継がれることがあります。
これを「遺伝性がん症候群」と呼びます。代表的なものに、乳がんや卵巣がんのリスクが高まる「遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)」や、大腸がんなどを発症しやすい「リンチ症候群」があります。
若年でがんを発症した場合や、血縁者に特定のがんになった人が複数いる場合などは、遺伝性がん症候群の可能性があります。
遺伝子検査で診断が確定すれば、サーベイランス(定期的な精密検査)による早期発見や、リスクを低減するための手術などを検討することができます。
重複がんと多発がん
一人の患者さんに、異なる臓器や組織に由来する複数の原発がんが、同時期または異なる時期に発生することがあります。これを「重複がん」と呼びます。
例えば、胃がんと大腸がんを両方発症するようなケースです。一方、同じ臓器の中に、複数の原発がんが同時に発生する場合を「多発がん」と呼びます。
例えば、肝臓の中に複数の肝細胞がんが発生するケースなどがこれにあたります。これらの背景には、喫煙や飲酒といった共通の危険因子や、遺伝的な要因が関わっている場合があります。
一つのがんの治療が終わった後も、別の新たながんが発生する可能性があることを念頭に置き、定期的な検診を続けることが大切です。
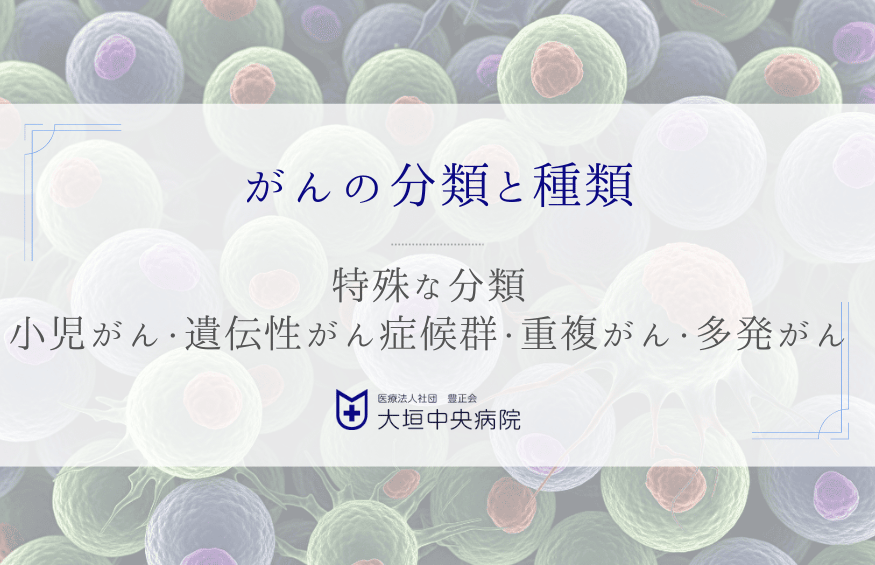
よくあるご質問
- がんはすべて悪性なのでしょうか?
-
答え いいえ、すべての腫瘍が悪性ではありません。腫瘍には「良性腫瘍」と「悪性腫瘍」があります。一般的に「がん」と呼ぶのは悪性腫瘍のことです。
良性腫瘍は転移せず、命に関わることはほとんどありません。一方、悪性腫瘍(がん)は周囲に浸潤したり、他の臓器に転移したりする性質があるため、治療が必要です。
- ステージIVと診断されたら、もう治療法はないのでしょうか?
-
答え ステージIVは、がんが他の臓器に遠隔転移している状態を示しますが、治療法がないという意味ではありません。
がんを完全に治すこと(治癒)は難しい場合もありますが、薬物療法(化学療法、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬など)や放射線療法などを組み合わせることで、がんの進行を抑えたり、症状を和らげたりして、生活の質を保ちながらがんと共に生きていくことを目指す治療が可能です。
治療法は日々進歩していますので、主治医とよく相談することが大切です。
- 「癌腫」と「肉腫」は何が違うのですか?
-
由来する細胞の種類が違います。体の表面や臓器の粘膜などを覆う「上皮細胞」から発生するのが「癌腫」で、胃がんや肺がんなど、多くのがんがこれにあたります。
一方、骨や筋肉、脂肪といった体を支える「非上皮細胞」から発生するのが「肉腫」です。肉腫は癌腫に比べて発生頻度が非常にまれです。
性質や治療法も異なるため、正確な診断が重要です。
- 自分の正確ながんの種類や分類を知るにはどうすればよいですか?
-
ご自身の正確ながんの種類や病期、悪性度、遺伝子変異の有無といった詳しい分類については、主治医からの説明が最も確実な情報源です。
診断の根拠となった病理検査の結果や画像検査の結果などについて、分からないことがあれば遠慮なく質問しましょう。診断や治療方針についてまとめた説明文書をもらうこともできます。
セカンドオピニオンを利用して、別の専門医の意見を聞くことも一つの方法です。
がんの多様な分類について理解を深めた今、次になぜがんが発生するのか、その根本的な原因やリスクについて学んでみませんか。
生活習慣や環境、遺伝など、がんの発生に関わるさまざまな要因を知ることは、ご自身や大切な家族の健康を守るための予防や早期発見につながります。
がんという病気を多角的に理解するために、ぜひ以下の記事もお読みください。
がんの原因とリスク要因
参考文献
TELLONI, Stacy M. Tumor staging and grading: A primer. Molecular Profiling: Methods and Protocols, 2017, 1-17.
CARBONE, Antonino. Cancer classification at the crossroads. Cancers, 2020, 12.4: 980.
SOBIN, Leslie H.; GOSPODAROWICZ, Mary K.; WITTEKIND, Christian (ed.). TNM classification of malignant tumours. John Wiley & Sons, 2011.
HUANG, Shao Hui; O’SULLIVAN, Brian. Overview of the 8th edition TNM classification for head and neck cancer. Current treatment options in oncology, 2017, 18.7: 40.
GREENE, Frederick L., et al. (ed.). AJCC cancer staging handbook: TNM classification of malignant tumors. Springer Science & Business Media, 2002.
COWHERD, Stacy M. Tumor staging and grading: a primer. In: Molecular Profiling: Methods and Protocols. Totowa, NJ: Humana Press, 2011. p. 1-18.
RAKHA, Emad A., et al. Breast cancer prognostic classification in the molecular era: the role of histological grade. Breast cancer research, 2010, 12.4: 207.
CSERNI, Gábor. Histological type and typing of breast carcinomas and the WHO classification changes over time. Pathologica, 2020, 112.1: 25.
PANER, Gladell P., et al. Updates in the eighth edition of the tumor-node-metastasis staging classification for urologic cancers. European urology, 2018, 73.4: 560-569.
DENARO, Nerina; RUSSI, Elvio Grazioso; MERLANO, Marco Carlo. Pros and cons of the new edition of TNM classification of head and neck squamous cell carcinoma. Oncology, 2018, 95.4: 202-210.

