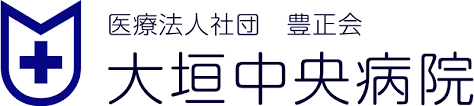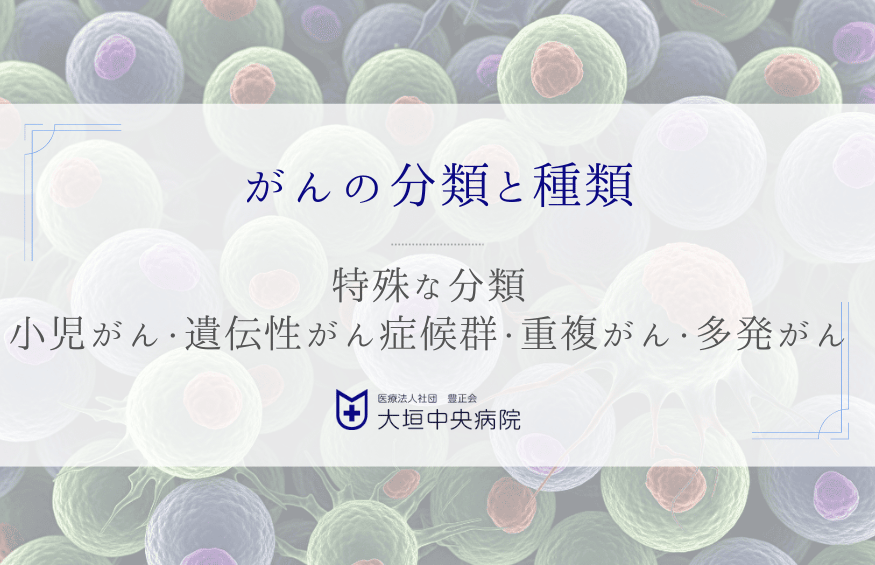がんは発生した臓器や組織の種類によって分類するのが一般的ですが、それだけでは捉えきれない特殊な分類が存在します。
患者さんの年齢、遺伝的な背景、あるいは複数のがんを発症するといった状況は、治療方針やその後の人生設計に大きく影響をおよぼすため、これらの分類を理解することはとても重要です。
この記事では、がんの多様な側面をより深く知るために、「小児がん」「遺伝性がん症候群」「重複がん・多発がん」という三つの特殊な分類に焦点を当て、それぞれの特徴や向き合い方について詳しく解説します。
小児がんの分類
子どもがかかるがんは「小児がん」と総称され、成人がんと多くの点で異なります。発生するがんの種類、進行の仕方、治療への反応性など、その性質は独特です。
そのため、小児がんは成人がんとは異なる、専門的な分類とアプローチを必要とします。
この知識は、子どもたち一人ひとりに合った治療計画を立て、健やかな未来へとつなげるための第一歩となります。
小児がんとは – 成人がんとの違い
小児がんと成人がんの最も大きな違いは、がんが発生する細胞の起源にあります。
成人がんは、長年の生活習慣や環境要因の蓄積によって、臓器や組織を覆う上皮細胞の遺伝子が傷つくことで発生する場合が多いです。
一方、小児がんは、胎児期に臓器や組織が作られる過程で残っていた未熟な細胞(胎児性細胞)から発生することが多く、特定の生活習慣との関連はほとんどありません。
発生する細胞の起源
成人がんが主に上皮細胞由来であるのに対し、小児がんは骨、筋肉、神経といった非上皮性の細胞から発生する肉腫や、血液細胞、未分化な胎児性細胞由来のがんが大部分を占めます。
この細胞起源の違いが、がんの性質や治療法の選択に大きく関わってきます。
例えば、上皮由来のがんには放射線治療や特定の分子標的薬が効果を示す一方、小児がんでは化学療法が治療の中心となることが多いです。
進行の速さと治療への反応性
小児がんは細胞分裂が活発な未熟な細胞から発生するため、一般的に進行が速いという特徴があります。診断された時点ですでに転移していることも少なくありません。
しかし、この活発な細胞分裂という性質は、裏を返せば化学療法や放射線治療への感受性が高いことも意味します。
成人がんに比べて、治療によく反応し、治癒を目指せる可能性が高いがんが多いのも小児がんの特徴の一つです。
小児がんの主な種類と分類
小児がんは、大きく「造血器腫瘍」と「固形腫瘍」の二つに分けられます。この分類は、治療戦略を立てる上で基本的な考え方となります。
造血器腫瘍
血液やリンパ組織から発生するがんで、小児がんの中では最も頻度が高いです。代表的なものに白血病や悪性リンパ腫があります。
白血病は血液のがんであり、骨髄で異常な血液細胞が無秩序に増殖します。全身に影響がおよぶため、治療は化学療法が中心となります。
固形腫瘍
臓器や組織に「かたまり」を作るがんの総称です。小児の固形腫瘍は、成人と種類が大きく異なり、神経芽腫や腎芽腫(ウィルムス腫瘍)、網膜芽腫といった「芽腫」と呼ばれる胎児性のがんが特徴的です。
これらのがんは、発生した臓器や組織の名前を付けて呼ばれます。
小児の主な固形腫瘍の例
| 腫瘍名 | 主な発生部位 | 特徴 |
|---|---|---|
| 神経芽腫 | 副腎、交感神経節 | 乳幼児に多く見られる。自然に退縮することもある。 |
| 腎芽腫(ウィルムス腫瘍) | 腎臓 | 幼児期に多く、腹部のしこりとして発見されることが多い。 |
| 網膜芽腫 | 眼の網膜 | 遺伝性のものと非遺伝性のものがある。早期発見が重要。 |
脳腫瘍
小児の固形腫瘍の中では最も頻度が高く、頭蓋内に発生する腫瘍の総称です。成人とは異なり、テント下と呼ばれる小脳や脳幹に発生しやすい傾向があります。
良性・悪性にかかわらず、発生部位によっては手術が困難であったり、重要な機能障害を引き起こしたりする可能性があります。
小児がん分類の重要性
小児がんを正確に分類することは、適切な治療法を選択し、患者である子どもたちの未来を守るために極めて重要です。
治療方針決定への影響
がんの種類や進行度、遺伝子異常の有無などを詳細に分類することで、治療方針が決まります。例えば、同じ白血病でもタイプによって使用する抗がん剤の種類や量が異なります。
また、固形腫瘍では、手術、化学療法、放射線治療をどのように組み合わせるかを、病理組織診断や画像の評価に基づいて慎重に計画します。
長期的なフォローアップの計画
小児がんの治療は、がんを治すことだけが目的ではありません。治療後も長く続く人生を見据え、成長や発達、晩期合併症(治療から数年後-数十年後に現れる影響)への配慮が必要です。
がんの種類や受けた治療法に応じて、どのような合併症が起こりうるかを予測し、定期的な検診やケアを含む長期的なフォローアップ計画を立てることが大切になります。

遺伝性がん症候群
がんの多くは遺伝しないものですが、一部のがんでは生まれつき特定の遺伝子に変異があることで、がんにかかりやすくなる体質が親から子へ受け継がれることがあります。
このような状態を「遺伝性がん症候群」と呼びます。がん全体の5-10%程度を占めると考えられており、その存在を知ることは、本人だけでなく血縁者の健康管理にとっても重要な意味を持ちます。
遺伝性がん症候群の概要
私たちの体は多くの細胞から成り立っており、それぞれの細胞には体の設計図である遺伝子が含まれています。
遺伝子には、細胞が異常な増殖をしないようにブレーキをかける役割を持つもの(がん抑制遺伝子)などがあります。
遺伝性がん症候群では、このブレーキ役の遺伝子に生まれつき変異があり、その機能が低下しているため、がんが発生しやすくなります。
原因となる遺伝子の変異
がん抑制遺伝子は、通常、父親由来と母親由来の2つが1セットで機能しています。遺伝性がん症候群の人の場合、生まれつきこのうちの1つに変異があり機能していません。
残りの1つが正常に機能している間は問題ありませんが、何らかの理由で後天的にその正常な遺伝子にも変異が起こると、ブレーキ機能が完全に失われ、がんが発生すると考えられています。
家族歴の重要性
遺伝性がん症候群を考える上で、家族や親族にがんにかかった人がいるか、いる場合はどのようながんに何歳でかかったか、といった情報(家族歴)が非常に重要です。
特定の遺伝子変異は、特定のがんのリスクを高めることがわかっているため、家族歴を詳しく聴取することで、遺伝性がん症候群の可能性を推測する手がかりになります。
代表的な遺伝性がん症候群
現在、多くの遺伝性がん症候群が見つかっていますが、ここでは代表的なものを二つ紹介します。
遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)
BRCA1遺伝子またはBRCA2遺伝子の変異が原因で、乳がんや卵巣がんのリスクが著しく高くなる症候群です。その他、男性の乳がん、前立腺がん、膵臓がんなどのリスクも高まることが知られています。
若くして乳がんと診断された場合や、家族に複数の乳がん・卵巣がん患者がいる場合にこの症候群を疑います。
リンチ症候群
MLH1、MSH2、MSH6、PMS2といった遺伝子のいずれかの変異が原因で、大腸がんや子宮体がんのリスクが高くなります。
その他、胃がん、卵巣がん、小腸がん、腎盂・尿管がんなど、多様ながんのリスクも上昇します。大腸がんが若年で発症したり、複数回発生したりする特徴があります。
遺伝性がん症候群を疑う特徴
- 若年(50歳未満など)でがんに罹患した
- 一人で複数回、異なる種類のがんに罹患した
- 両側の乳房や腎臓など、対になった臓器の両方にがんが発症した
- 血縁者に同じ種類や関連するがんの罹患者が複数いる
- 男性で乳がんに罹患した
遺伝カウンセリングと遺伝子検査
遺伝性がん症候群が疑われる場合、その可能性や遺伝子検査について専門家と相談する場として「遺伝カウンセリング」があります。
検査を受ける前に知っておくべきこと
遺伝子検査は血液などを用いて行い、原因遺伝子に変異があるかどうかを調べます。しかし、検査を受ける前には、その結果がもたらす医学的・心理的・社会的な影響について十分に理解することが重要です。
遺伝カウンセリングでは、臨床遺伝専門医や認定遺伝カウンセラーが、検査のメリット・デメリット、血縁者への影響、もし変異が見つかった場合の対策などについて、詳しく説明し、本人が納得して意思決定できるよう支援します。
検査結果の解釈と活用
検査で遺伝子変異が見つかった場合(陽性)、特定のがんのリスクが高いことが確定します。しかし、これは将来必ずがんになるという意味ではありません。
リスクを知ることで、通常より頻繁な検診(サーベイランス)や、リスクを低減するための手術(リスク低減手術)といった、予防的な対策を検討することができます。
変異が見つからなかった場合(陰性)でも、がんになるリスクがゼロになるわけではないため、一般的ながん検診は継続して受けることが大切です。
代表的な遺伝性がん症候群
| 症候群名 | 主な原因遺伝子 | 関連する主ながん |
|---|---|---|
| 遺伝性乳がん卵巣がん症候群 (HBOC) | BRCA1, BRCA2 | 乳がん, 卵巣がん, 前立腺がん, 膵臓がん |
| リンチ症候群 | MLH1, MSH2 など | 大腸がん, 子宮体がん, 胃がん, 卵巣がん |
| 家族性大腸腺腫症 (FAP) | APC | 大腸がん (多数の大腸ポリープが発生) |

重複がん・多発がん
一人の患者さんが、生涯のうちに二つ以上の異なるがんを発症することがあります。これを「重複がん」または「多発がん」と呼びます。
がん治療の進歩により、がんを克服して長生きする人が増えたことや、診断技術の向上により、重複がんを経験する人の数は増加傾向にあります。
最初のがんの治療が終わった後も、新たな別のがんの発生に注意を払う必要があります。
重複がんと多発がんの定義
これらの用語は似ていますが、異なる意味合いで使われることがあります。一般的に、異なる臓器に発生したがんや、同じ臓器でも組織型が全く異なるがんが複数見つかった場合を「重複がん」と呼びます。
一方、同じ臓器内に、同じ組織型のがんが複数個発生した場合を「多発がん」と区別することがあります。
同時性と異時性 – 発見される時期による違い
重複がんは、発見されるタイミングによって二つに分類されます。
最初のがんの診断から短い期間内(例:1年以内)に別のがんが見つかる場合を「同時性重複がん」、一定期間が経過した後に見つかる場合を「異時性重複がん」と呼びます。
同時性の場合、両方のがんを考慮した複雑な治療計画が必要になることがあります。異時性の場合は、最初のがん治療後の長期的な経過観察中に発見されることが多いです。
多中心性発生 – 同じ臓器に複数のがんができる場合
これは「多発がん」の考え方に近いものです。例えば、肝臓や乳房、甲状腺などでは、臓器内の複数の場所に、同時あるいは異なる時期にがんが発生することがあります。
これは、その臓器全体が発がんしやすい環境(発がんのフィールド)になっていることが原因の一つと考えられています。
重複がん・多発がんの原因
なぜ複数の臓器にがんが発生するのでしょうか。その原因は一つではなく、複数の要因が複雑に関係していると考えられています。
生活習慣や環境要因
喫煙や過度の飲酒、特定の食生活といった生活習慣は、複数の臓器にがんを発生させる共通のリスク要因となります。
例えば、喫煙は肺がんだけでなく、口腔・咽頭がん、食道がん、膀胱がんなど多くのがんのリスクを高めます。
これらの要因に長期間さらされることで、体のあちこちでがんが発生しやすい状態が作られてしまいます。
重複がんのリスクを高める要因
| 要因のカテゴリー | 具体的な要因 | 関連するがんの例 |
|---|---|---|
| 生活習慣 | 喫煙 | 肺、口腔、喉頭、食道、膀胱など |
| 遺伝的素因 | リンチ症候群 | 大腸、子宮体、胃、卵巣など |
| がん治療の影響 | 放射線治療 | 照射部位の二次がん(例:乳がん治療後の肉腫) |
遺伝的素因の関与
前述の「遺伝性がん症候群」も重複がんの重要な原因です。生まれつき特定の遺伝子に変異があると、全身の細胞ががん化しやすくなっているため、生涯で複数のがんを発症するリスクが高まります。
若年でがんになったり、特徴的ながんの組み合わせが見られたりする場合は、遺伝的な背景を考慮することが大切です。
がん治療の影響
最初のがんを治療するために行われた化学療法や放射線治療が、長い年月を経て新たながん(二次がん)を引き起こすことがあります。これは治療による晩期合併症の一つです。
治療法の進歩によりそのリスクは低減していますが、ゼロではありません。そのため、がんの治療を受けた人は、治療後の長期的な健康状態にも注意を払う必要があります。
診断と治療における注意点
重複がんを念頭に置いた診療は、患者さんの予後を改善する上で重要です。
全身的な検索の必要性
一つのがんと診断された際、特に重複がんのリスクが高いと考えられる場合(例:喫煙歴が長い、遺伝性がん症候群が疑われる)には、他の臓器にもがんが隠れていないか、全身を注意深く調べることがあります。
また、がん治療後の経過観察では、元のがんの再発や転移だけでなく、全く新しいがんの早期発見も目的の一つとなります。
個別化された治療計画
複数の進行がんが同時に見つかった場合、どちらのがんを優先して治療するか、あるいは両方に効果のある治療法を選択するかなど、治療計画は非常に複雑になります。
それぞれの患者さんの年齢、全身状態、がんの進行度などを総合的に評価し、最も利益が大きいと考えられる治療法を慎重に選択します。

よくある質問
- 小児がんは遺伝するのでしょうか?家族に影響はありますか?
-
小児がんの大部分(約95%)は偶発的に発生し、遺伝性ではありません。
ただし、約5-10%の小児がんは遺伝的要因が関与しており、家族性腫瘍症候群(リ・フラウメニ症候群、家族性腺腫性ポリポーシスなど)が原因となることがあります。
お子さんが小児がんと診断された場合、医師が家族歴や腫瘍の特徴を評価し、必要に応じて遺伝カウンセリングや遺伝学的検査を提案します。
- 遺伝性がんの可能性がある場合、家族は何をすべきでしょうか?
-
遺伝性がんが疑われる場合は、まず遺伝カウンセリングを受けることをお勧めします。専門家が家族歴を詳しく評価し、遺伝学的検査の必要性や意義について説明します。
陽性の場合は、定期的な検診スケジュールの立案、予防的手術の検討、家族への情報共有などの対策を医師と相談できます。
また、検査は慎重な検討が必要で、心理的サポートも重要です。
- 重複がん・多発がんとは何ですか?がんが再発したということでしょうか?
-
重複がん・多発がんは、同じ人に異なる種類のがんが発生することで、元のがんの再発や転移とは異なります。
「同時性重複がん」は同じ時期に複数のがんが見つかる場合、「異時性重複がん」は最初のがん治療後、一定期間(通常6ヶ月以上)経過してから別の臓器に新しいがんが発生する場合を指します。
例えば、肺がん治療後に胃がんが発生するケースなどです。原因として、遺伝的素因、治療の影響(放射線・化学療法)、生活習慣、加齢などが挙げられます。
早期発見のため、がん経験者には定期的な全身チェックが推奨されています。
参考文献
FERRARI, Andrea, et al. Defining and listing very rare cancers of paediatric age: consensus of the Joint Action on Rare Cancers in cooperation with the European Cooperative Study Group for Pediatric Rare Tumors. European journal of cancer, 2019, 110: 120-126.
PFISTER, Stefan M., et al. A summary of the inaugural WHO classification of pediatric tumors: transitioning from the optical into the molecular era. Cancer discovery, 2022, 12.2: 331-355.
BOYD, Niki, et al. Rare cancers: a sea of opportunity. The Lancet Oncology, 2016, 17.2: e52-e61.
MOSTAFA, Ibrahim A. Rare Tumors in Children. In: Pediatric Surgical Oncology. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. p. 1411-1427.
STELIAROVA‐FOUCHER, Eva, et al. International classification of childhood cancer. Cancer, 2005, 103.7: 1457-1467.
VOGT, Alexia, et al. Multiple primary tumours: challenges and approaches, a review. ESMO open, 2017, 2.2: e000172.
GARBER, Judy E.; OFFIT, Kenneth. Hereditary cancer predisposition syndromes. Journal of clinical oncology, 2005, 23.2: 276-292.
KRAMÁROVÁ, Eva; STILLER, C. A. The international classification of childhood cancer. International journal of cancer, 1996, 68.6: 759-765.
LINDOR, Noralane M.; GREENE, Mark H.; MAYO FAMILIAL CANCER PROGRAM. The concise handbook of family cancer syndromes. JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 1998, 90.14: 1039-1071.
STILLER, Charles A. Epidemiology and genetics of childhood cancer. Oncogene, 2004, 23.38: 6429-6444.