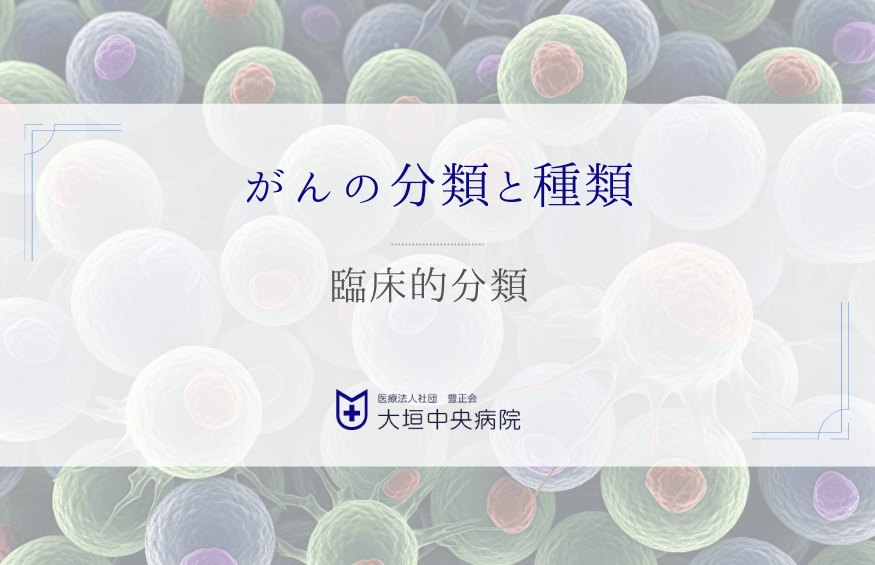がんの診断を受けると、多くの方が「ステージ」という言葉を耳にします。
これはがんの進行度を示す重要な指標ですが、治療方針を決定するためには、それ以外にも多角的な視点からがんの性質を捉えることが大切です。
そのために用いるのが「臨床的分類」です。この分類は、がん細胞の顔つき(悪性度)、治療への反応性、そしてどのように広がっていくかという転移の傾向など、がんが持つ個性を見極めるためのものです。
この記事では、ご自身の状態をより深く理解し、納得して治療に臨む一助となるよう、臨床的分類の考え方について詳しく解説します。
予後による分類
がんの治療方針を立てる上で、将来の見通し、すなわち「予後」を予測することは非常に重要です。
予後を判断するために、がん細胞の性質や増殖する速さなどから、がんの悪性度を評価します。この評価は、治療の強さや種類を選ぶ際の大きな判断材料となります。
例えば、悪性度が高いと判断した場合は、より積極的な治療を検討することがあります。逆に悪性度が低い場合は、体の負担が少ない治療法を選択したり、経過観察の期間を設けたりすることも考えます。
がん細胞の顔つき-悪性度(グレード)
がん細胞を顕微鏡で観察し、その「顔つき」から悪性度を判断する分類を「異型度」や「グレード」と呼びます。
正常な細胞とどれくらい異なっているか、細胞分裂の頻度はどのくらいか、といった点に着目して評価します。グレードは、がんの増殖スピードや転移のしやすさと関連があると考えます。
グレード分類の基準
グレードは通常、数段階に分けて評価します。例えば、G1(グレード1)は細胞の顔つきが比較的おとなしく、正常な細胞に近い状態(高分化型)です。
一方、G3(グレード3)やG4(グレード4)になると、正常細胞とは大きく異なり、未熟で攻撃的な性質を持つ状態(低分化型や未分化型)を示します。
このグレードが高いほど、がんは速く増殖し、広がりやすい傾向があります。
悪性度(グレード)の目安
| グレード | 細胞の状態(分化度) | 一般的な特徴 |
|---|---|---|
| G1 | 高分化型 | 正常細胞に近く、増殖が比較的緩やか |
| G2 | 中分化型 | G1とG3の中間の性質を持つ |
| G3/G4 | 低分化型・未分化型 | 正常細胞との違いが大きく、増殖が速い傾向 |
遺伝子情報から見るがんの性質
近年では、細胞の見た目だけでなく、がん細胞が持つ遺伝子の変異やタンパク質の発現パターンを調べることで、より詳細に予後を予測する試みが進んでいます。
特定のがんでは、特定の遺伝子変異があるかどうかで、その後の経過が大きく異なることが分かっています。
この情報は、分子標的薬という特定の遺伝子変異を狙い撃ちする薬の効果を予測する上でも、欠かすことのできない情報です。
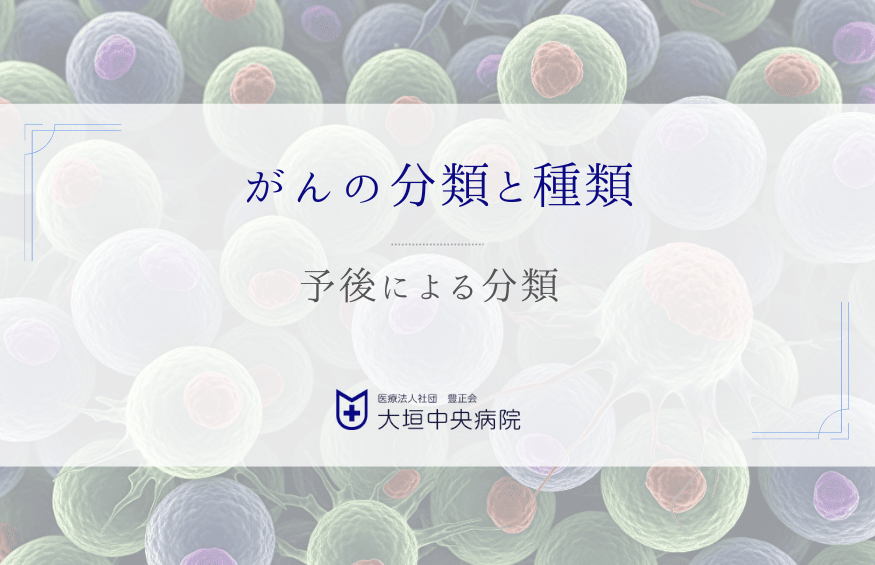
治療反応性による分類
がん治療には、手術、薬物療法、放射線治療など複数の選択肢があります。どの治療法が最も効果的かは、がんの種類や進行度だけでなく、がんそのものが持つ「治療への反応性」によっても異なります。
特定の方法が効きやすいか、それとも効きにくいかを事前に予測し、個々のがんの性質に合わせて治療法を使い分けることが、治療効果を高める上で重要です。
薬物療法の効果予測
薬物療法には、抗がん剤、ホルモン療法薬、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬など、さまざまな種類があります。
どのがんにどの薬が効くかは、がん細胞の表面や内部にある特定の目印(バイオマーカー)の有無によって決まることがあります。
ホルモン受容体の有無
乳がんや前立腺がんなど一部のがんでは、女性ホルモンや男性ホルモンを栄養源として増殖します。
がん細胞にホルモンを受け取るための鍵穴(ホルモン受容体)がある場合、その働きを妨げるホルモン療法が効果を発揮します。受容体の有無を調べることで、ホルモン療法が有効かどうかを判断します。
特定の分子(バイオマーカー)の発現
がん細胞の増殖に関わる特定のタンパク質や遺伝子を「バイオマーカー」と呼びます。例えば、乳がんにおけるHER2(ハーツー)タンパク質や、肺がんにおけるEGFR遺伝子変異などがこれにあたります。
これらのバイオマーカーを持つがんに対しては、その働きをピンポイントで抑える分子標的薬が高い効果を示すことがあります。そのため、治療開始前にこれらのバイオマーカーを調べることが一般的です。
治療反応性に関わるバイオマーカーの例
| バイオマーカー | 主ながんの種類 | 関連する薬剤の種類 |
|---|---|---|
| ホルモン受容体 | 乳がん、前立腺がん | ホルモン療法薬 |
| HER2 | 乳がん、胃がん | 抗HER2薬(分子標的薬) |
| EGFR遺伝子変異 | 肺がん | EGFR阻害薬(分子標的薬) |
放射線治療への感受性
放射線治療が効きやすいかどうか(放射線感受性)も、がんの種類によって差があります。例えば、精巣腫瘍や悪性リンパ腫などは放射線感受性が高く、根治を目指す治療にも用いられます。
一方で、骨肉腫や悪性黒色腫などは比較的感受性が低いとされています。
しかし、技術の進歩により、従来は効きにくいとされたがんに対しても、定位放射線治療(ピンポイント照射)などで効果を上げる工夫も行っています。
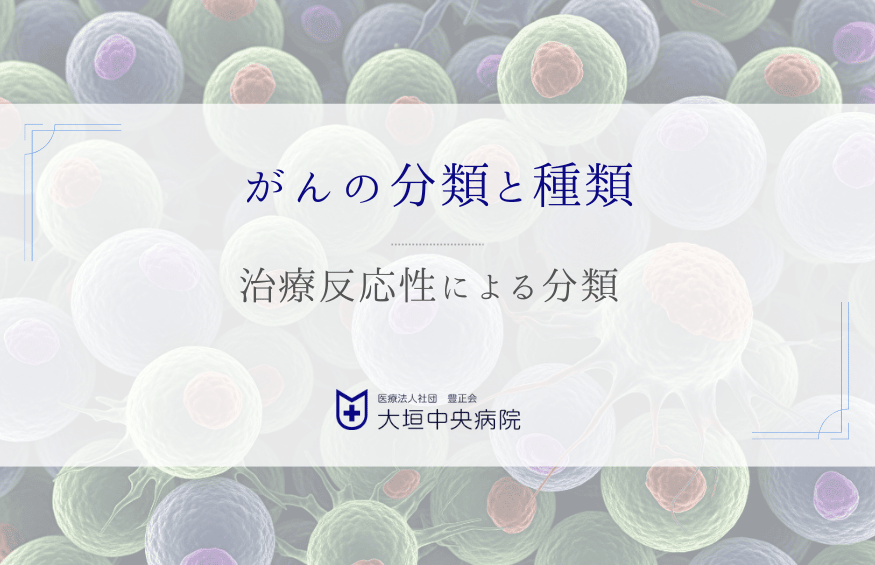
転移パターンによる分類
がんが最初に発生した場所(原発巣)から、体の他の場所へ移動して増殖することを「転移」と呼びます。
がんは、その種類によって特定の臓器や組織に転移しやすい傾向があり、この転移のパターンを理解することは、治療計画や治療後の経過観察において重要な意味を持ちます。
がんの広がり方
転移にはいくつかの経路があります。がんがどの経路で広がりやすい性質を持つかによって、検査の内容や治療の範囲を決定します。
リンパの流れに乗る転移(リンパ行性転移)
がん細胞がリンパ管に入り込み、リンパ液の流れに乗ってリンパ節にたどり着き、そこで増殖するタイプの転移です。
多くの固形がんで見られる一般的な転移形式で、手術の際には、がんの原発巣だけでなく、転移の可能性がある周囲のリンパ節も一緒に切除(リンパ節郭清)することがあります。
血液の流れに乗る転移(血行性転移)
がん細胞が血管内に侵入し、血液の流れに乗って全身のさまざまな臓器(肺、肝臓、骨、脳など)に運ばれて転移巣を形成します。
どの臓器に転移しやすいかは、がんの種類によってある程度の傾向があります。例えば、大腸がんは肝臓へ、肺がんは脳や骨へ転移しやすいことが知られています。
主な転移経路と特徴
| 転移形式 | 主な経路 | 特徴 |
|---|---|---|
| リンパ行性転移 | リンパ管 | 原発巣に近いリンパ節から段階的に広がることが多い |
| 血行性転移 | 血管(主に静脈) | 肺、肝臓、骨、脳など遠隔臓器に転移巣を形成する |
| 播種(はしゅ) | 腹腔、胸腔など | がん細胞が体腔内に種をまくように散らばって広がる |
転移の個数や場所による考え方
転移があると聞くと、治療が難しいという印象を持つかもしれません。しかし、最近では転移の状態によっても治療方針を細かく考えるようになりました。
特に「オリゴメタスタシス」という考え方が注目されています。
オリゴメタスタシスという状態
これは、転移の個数が少なく(オリゴは「少ない」という意味)、特定の場所に限定されている状態を指します。
このような状態の場合、転移巣に対しても手術や放射線治療といった局所的な治療を積極的に行うことで、長期的な病状のコントロールや、場合によっては根治を目指せる可能性があると考えます。
オリゴメタスタシスの治療で考慮する点
- 転移の個数
- 転移している臓器
- 原発巣の状態
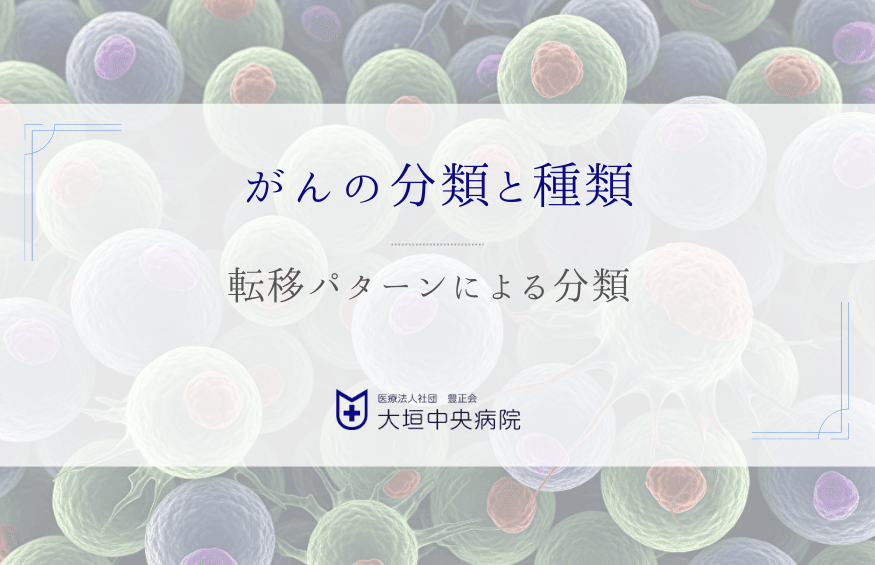
がんの病期分類に関するよくある質問
がんの診断において最も広く用いられる分類が「病期(ステージ)」です。これは、がんの進行度合いを示す世界共通の物差しであり、治療方針を決定する上で基本となる情報です。
ここでは、病期分類に関する一般的な疑問についてお答えします。
- 病期(ステージ)はどのように決まるのですか?
-
病期は主に「TNM分類」という基準を用いて決定します。
これは、がんそのものの大きさや広がり(T因子)、周辺のリンパ節への転移の有無(N因子)、他の臓器への遠隔転移の有無(M因子)の3つの要素を組み合わせて評価する方法です。
これらの評価を総合して、多くのがんではステージI(早期)からステージIV(進行)までの4段階に分類します。ステージの数字が大きくなるほど、がんが進行していることを意味します。
TNM分類の構成要素
因子 評価する内容 詳細 T (Tumor) 原発腫瘍の大きさ・広がり T1, T2, T3, T4のように数字が大きくなるほど、がんが大きいか周囲へ深く浸潤していることを示す N (Node) 所属リンパ節への転移 N0(転移なし)から、転移の範囲や個数に応じてN1, N2, N3と分類する M (Metastasis) 遠隔転移 M0(遠隔転移なし)かM1(遠隔転移あり)のいずれかで評価する - 病期は一度決まったら変わらないのですか?
-
最初に診断された時点での病期は、治療の基準となるため基本的に変わりません。これを「初回治療時病期」と呼びます。
しかし、治療後に再発した場合や、病状が進行した場合には、その時点での状態を正確に評価し直します。
例えば、手術後にリンパ節転移が見つかった場合などは、手術前の評価(臨床病期)と手術後の評価(病理病期)が異なることもあります。
治療方針は、常にその時々の体の状態を最も正確に反映した情報に基づいて決定します。
- 同じ病期でも治療法が違うのはなぜですか?
-
病期はがんの進行度を示す重要な指標ですが、治療方針を決めるための唯一の判断材料ではありません。
この記事で解説したように、がん細胞の悪性度(グレード)、薬物療法への反応性に関わるバイオマーカーの有無、転移のパターン、そして何よりも患者さんご自身の全身状態、年齢、合併症の有無、ご本人の希望などを総合的に考慮して、一人ひとりに合った治療法を検討します。
そのため、同じステージであっても、治療内容が異なることは決して珍しいことではありません。
この記事では、がんの臨床的な分類について解説しました。
しかし、がん研究の進歩は目覚ましく、近年では遺伝子パネル検査などを用いて、がんの遺伝子情報を網羅的に調べることで、さらに詳細な分類が可能になっています。
こうした「特殊な分類」は、より個人に合わせた治療法の選択につながる可能性があります。次の記事では、ゲノム医療の時代における新しいがんの分類方法について詳しくご紹介します。
参考文献
BURKE, Harry B. Outcome prediction and the future of the TNM staging system. Journal of the National Cancer Institute, 2004, 96.19: 1408-1409.
HORTOBAGYI, Gabriel N.; EDGE, Stephen B.; GIULIANO, Armando. New and important changes in the TNM staging system for breast cancer. Am Soc Clin Oncol Educ Book, 2018, 38: 457-467.
PARK, Y. H., et al. Clinical relevance of TNM staging system according to breast cancer subtypes. Annals of oncology, 2011, 22.7: 1554-1560.
LIM, Wanyin, et al. The 8th lung cancer TNM classification and clinical staging system: review of the changes and clinical implications. Quantitative imaging in medicine and surgery, 2018, 8.7: 709.
VERONESI, Umberto, et al. Rethinking TNM: breast cancer TNM classification for treatment decision-making and research. The Breast, 2006, 15.1: 3-8.
GRESS, Donna M., et al. Principles of cancer staging. AJCC cancer staging manual, 2017, 8: 3-30.
CSERNI, Gábor, et al. The new TNM-based staging of breast cancer. Virchows Archiv, 2018, 472.5: 697-703.
BRIERLEY, James D., et al. A comparison of different staging systems predictability of patient outcome: thyroid carcinoma as an example. Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer Society, 1997, 79.12: 2414-2423.
GREENE, Frederick L.; SOBIN, Leslie H. The staging of cancer: a retrospective and prospective appraisal. CA: a cancer journal for clinicians, 2008, 58.3: 180-190.
MATILLA, José-María, et al. New TNM staging in lung cancer and future perspectives. Journal of clinical and translational research, 2020, 6.4: 145.