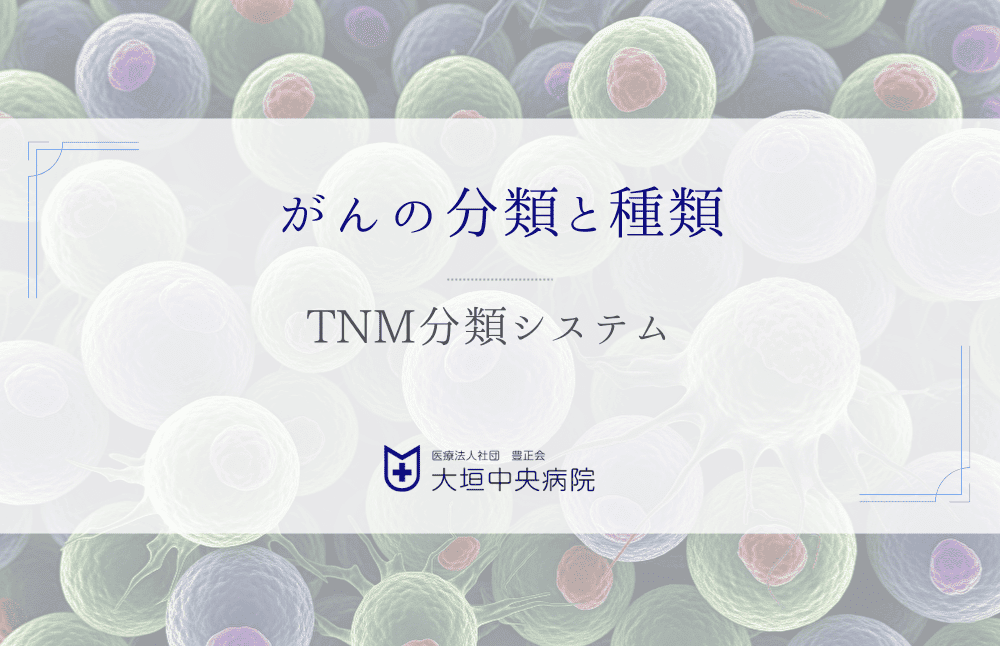がんの診断を受けると、ご自身の病状がどの程度進行しているのか、正確に知りたいと思うのは当然のことです。その際に用いられる世界共通の評価基準が「TNM分類」です。
この分類は、がんの「T(腫瘍の大きさ)」「N(リンパ節への転移)」「M(他の臓器への転移)」という3つの要素を客観的な指標で評価し、がんの進行度を正確に把握するために用います。
この記事では、TNM分類システムの基本的な考え方から、各因子の詳細、治療方針との関わりまで、患者さんがご自身の状態を理解するための一助となるよう、分かりやすく解説します。
がんの広がりを3つの要素で評価する
がんの進行度を正確に把握することは、適切な治療方針を立てるための第一歩です。
TNM分類は、そのために開発された国際的な基準であり、がんが体内でどの程度広がっているかを客観的に示すための「ものさし」として機能します。
この分類法は、国際対がん連合(UICC)によって定められ、世界中の医師が共通の理解のもとでがんの進行度を評価し、情報を共有するために広く用いられています。
TNM分類とは何か
TNM分類は、がんの解剖学的な広がり、つまり病気の進行度を評価するための分類法です。T、N、Mの3つの異なるカテゴリー(因子)について、それぞれの状態を数字や記号で表現します。
この3つの因子の組み合わせによって、がんの総合的な進行度である「ステージ(病期)」が決定します。
UICCが定期的に改訂を行い、最新の医学的知見に基づいた基準を提供しているため、信頼性の高い評価が可能です。
3つの評価因子
この分類システムの核となるのが、以下の3つの評価因子です。それぞれが、がんの異なる側面を捉えています。
T因子(Tumor)
原発腫瘍、つまり最初にがんが発生した場所での腫瘍の大きさや、周囲の組織への浸潤の深さを示します。
N因子(Node)
原発腫瘍の近くにあるリンパ節への転移の有無と、その広がり具合を示します。
M因子(Metastasis)
がん細胞が血流やリンパ流に乗って、発生した臓器から遠く離れた他の臓器(遠隔臓器)へ転移しているかどうかを示します。
なぜ医師はTNM分類を使うのか
医師ががんの診断や治療においてTNM分類を重視するのは、それが極めて有用な情報を提供するからです。
この客観的で体系的な分類法は、患者さん一人ひとりにとって最善の治療を見出すための道しるべとなります。
また、医療チーム内や他の病院の医師との間で、患者さんの病状に関する正確な情報を共有するためにも重要な役割を果たします。
治療方針決定の共通言語
TNM分類は、世界中の医師が同じ基準でがんの進行度を語るための「共通言語」です。
例えば、「胃癌 cT3N1M0」といった表現を用いれば、どの国の医師であっても、その患者さんのがんがどの程度進行しているかを即座に、かつ正確に理解できます。
これにより、標準的な治療ガイドラインの適用や、多施設共同での臨床研究が円滑に進みます。
予後を予測するための客観的指標
TNM分類によって決定されるステージは、今後の病状の見通し、すなわち予後を予測するための重要な手がかりとなります。
過去の膨大な臨床データから、同じステージの患者さんがどのような経過をたどる傾向にあるかが統計的に分かっています。
もちろん、予後は多くの要因に影響されるため、ステージだけで全てが決まるわけではありませんが、客観的な予測を行う上で基礎となる情報です。
TNM分類の主な目的
| 目的 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 治療計画の立案 | 進行度に応じた最適な治療法(手術、化学療法、放射線治療など)の選択に役立つ。 |
| 予後の予測 | 病状の見通しを立て、患者さんと家族への説明の根拠となる。 |
| 治療効果の評価 | 異なる治療法の効果を比較検討する際の客観的な基準となる。 |
臨床研究における重要性
新しい治療法の開発や、既存の治療法の改善を目指す臨床研究においても、TNM分類は極めて重要です。
研究に参加する患者さんを進行度別にグループ分けすることで、治療法の効果を科学的かつ公平に評価することが可能になります。
この分類がなければ、世界規模でのがん研究の進展は大きく遅れていたでしょう。
T(原発腫瘍)- がんの大きさと深さ
TNM分類の最初の要素である「T」は、Tumor(腫瘍)の頭文字です。これは、がんが最初に発生した場所(原発巣)にある腫瘍、すなわち「原発腫瘍」の状態を示します。
具体的には、腫瘍の大きさや、周囲の組織へどの程度深く広がっているか(深達度)を評価する指標です。
このT因子の評価は、がんの進行度を判断する上で基本となり、後の治療方針、特に手術が可能かどうかを決める上で極めて重要な情報を提供します。
T因子の評価基準
T因子の分類は、がんの種類や発生した臓器によって基準が異なりますが、基本的な考え方は共通しています。
一般的に、数字が大きくなるほど、腫瘍が大きいか、または周囲への広がりが著しいことを意味します。
T分類の基本原則
- Tis 上皮内がん
- T1〜T4 進行度を示す数字
- T0 原発腫瘍が認められない
- TX 原発腫瘍の評価が困難
Tisは、がんが粘膜の最も表面の層(上皮)にとどまり、それより深くには浸潤していない状態です。
一方、T1からT4へは、数字が大きくなるにつれて、腫瘍のサイズが増したり、臓器の壁のより深い層へ浸潤したり、隣接する臓器へ広がったりしている状態を示します。
臓器ごとのT分類の違い
T因子の具体的な基準は、臓器の構造やがんの性質を反映して細かく定められています。
例えば、胃や大腸のような管腔臓器では壁の深さへの広がりが重視され、肺や乳房のような実質臓器では腫瘍の最大径が主な基準となります。
ここでは、代表的な例として胃癌と肺癌のT分類を紹介します。
胃癌におけるT分類
胃癌のT分類は、腫瘍の大きさそのものよりも、胃の壁のどの層までがんが達しているか(深達度)を基準にします。
胃壁は内側から粘膜層、粘膜下層、固有筋層、漿膜下層、漿膜という層構造になっており、がんが外側へ向かって深く浸潤するほどT分類の数字が大きくなります。
胃癌のT分類の概要
| T因子 | 癌の深達度(がんが達している層) |
|---|---|
| T1 | 粘膜層または粘膜下層にとどまる |
| T2 | 固有筋層に達している |
| T3 | 漿膜下層に達している |
| T4 | 漿膜を越えて胃の外に出ている、または隣接臓器に及ぶ |
肺癌におけるT分類
肺癌のT分類は、主に腫瘍の最大径(大きさ)と、気管支、胸膜、心臓といった周囲の重要な組織への広がり具合によって決まります。
腫瘍が小さいほど、また周囲への広がりが少ないほど、Tの数字は小さくなります。
肺癌のT分類の概要
| T因子 | 腫瘍の大きさ・広がりの一例 |
|---|---|
| T1 | 腫瘍の大きさが3cm以下で、肺の内部にとどまる |
| T2 | 腫瘍の大きさが3cmを超えるが5cm以下、または主気管支に及ぶなど |
| T3 | 腫瘍の大きさが5cmを超えるが7cm以下、または胸壁や横隔膜などに及ぶ |
| T4 | 腫瘍の大きさが7cmを超える、または心臓や大血管、食道などに及ぶ |
N(リンパ節)- 転移の有無と範囲
TNM分類の2番目の要素「N」は、Node(リンパ節)の頭文字です。
これは、原発腫瘍からがん細胞がリンパ管を通って、近くのリンパ節に到達し、そこで増殖している状態、すなわちリンパ節転移の有無と範囲を示します。
リンパ節は、体内に侵入した細菌やウイルスを食い止める免疫器官ですが、がん細胞の通り道にもなり得ます。
N因子の評価は、がんが局所にとどまっているか、あるいは広範囲に広がり始めているかを判断する上で非常に重要です。
N因子の評価方法
N因子は、どの範囲のリンパ節に、どのくらいの数の転移があるかによって分類します。
一般的に、N0は領域リンパ節への転移がない状態を、N1、N2、N3と数字が大きくなるにつれて、転移の範囲が広がるか、転移しているリンパ節の数が増えることを示します。
評価の対象となるのは、原発巣のある臓器の近くに位置する「領域リンパ節」です。
リンパ節転移が意味すること
リンパ節に転移があるということは、がん細胞が原発巣を離れて移動する能力を持っていることを示唆します。
これは、がんの進行度が高まっていることを意味し、手術後の再発リスクや、全身に転移している可能性を考える上で重要な情報となります。
そのため、N因子の評価は、手術で切除する範囲を決めたり、手術後に補助的な化学療法を行うかどうかを判断したりする際に、大きな影響を与えます。
大腸癌のN分類
大腸癌の場合、N分類は転移が認められる領域リンパ節の個数に基づいて行います。
手術で切除したリンパ節を病理医が顕微鏡で詳しく調べ、転移のあるリンパ節の数を正確に数えることで、最終的なN分類が確定します。
大腸癌のN分類の概要
| N因子 | 転移のある領域リンパ節の個数 |
|---|---|
| N0 | 転移なし |
| N1 | 1~3個 |
| N2 | 4個以上 |
M(遠隔転移)- 他の臓器への広がり
TNM分類の最後の要素「M」は、Metastasis(転移)の頭文字です。
これは、がん細胞が原発巣から血液やリンパの流れに乗って、肺、肝臓、骨、脳といった遠くの臓器に到達し、そこで新たながんの塊(転移巣)を形成している状態、すなわち遠隔転移の有無を示します。
M因子の評価は、がんが全身に広がっているかどうかを判断するものであり、治療方針を大きく左右する最も重要な要素の一つです。
M因子の定義
M因子の分類は非常にシンプルで、基本的には遠隔転移があるかないかの2択で評価します。
M分類の基本的な考え方
| M因子 | 状態 |
|---|---|
| M0 | 遠隔転移は認められない |
| M1 | 遠隔転移が認められる |
MXという分類もありますが、これは遠隔転移の有無を評価するための情報が不十分な場合に使用します。
遠隔転移の評価
遠隔転移の有無は、CT、MRI、PET検査といった画像診断や、骨シンチグラフィなどの核医学検査を用いて全身を詳しく調べて評価します。
これらの検査によって、原発巣以外の臓器にがんを疑う病変がないかを確認します。
M1が示す病状
M1と診断される、つまり遠隔転移が認められる場合、がんは全身に広がった病気として捉えます。
この状態では、手術や放射線治療といった局所的な治療だけではがんを完全に制御することが困難なため、抗がん剤や分子標的薬などを用いた全身に効果が及ぶ薬物療法が治療の中心となります。
遠隔転移の有無は、予後にも大きな影響を与えます。
ステージ分類との関係性
これまで解説してきたT、N、Mの3つの因子の評価結果を総合的に組み合わせることで、がんの進行度を最終的に判断する「ステージ(病期)」が決定します。
ステージ分類は、複雑なTNMの情報をより分かりやすくまとめたもので、患者さんや家族が病状を理解しやすくするためにも用いられます。
一般的に、ステージはローマ数字のI(1)からIV(4)で表され、数字が大きくなるほどがんが進行していることを意味します。
TNMからステージ(病期)へ
ステージの決定は、単にT、N、Mの数字を足し算するような単純なものではありません。
がんの種類ごとに、予後との関連性が科学的に検証された上で、どのTNMの組み合わせがどのステージに該当するかが厳密に定義されています。
例えば、リンパ節転移(N1以上)や遠隔転移(M1)があれば、たとえ原発腫瘍(T)が小さくても、ステージは高くなります。
UICCによる国際的なステージ分類
このステージ分類の基準も、TNM分類と同様にUICCが定めており、世界共通の基準として用いられています。
これにより、世界中のどこで診断を受けても、同じ基準で進行度が評価され、標準的な治療を受けることが可能になります。
胃癌のステージ分類の例
| ステージ | TNMの組み合わせの一例 |
|---|---|
| ステージI | T1 N0 M0 |
| ステージII | T2 N1 M0 |
| ステージIII | T4a N1 M0 |
| ステージIV | いずれかのT, いずれかのN, M1 |
なぜステージ分類が重要か
ステージ分類は、がんの進行状況を総合的に示す指標です。これにより、医師は治療ガイドラインに沿って、そのステージの患者さんに最も効果が期待できる標準的な治療方針を立てることができます。
また、患者さん自身が自分の病状を大局的に把握し、今後の治療や生活について考える上での重要な情報となります。
がん治療方針を決める重要な判断材料
TNM分類とそれに基づくステージ分類は、単なる病状の評価にとどまらず、具体的な治療方針を決定するための最も重要な判断材料となります。
医師は、この客観的な分類に基づいて、患者さん一人ひとりの年齢、全身状態、希望などを考慮しながら、最適な治療計画を立てていきます。
進行度に応じた治療の選択
がんの治療法には、大きく分けて手術、放射線治療、薬物療法(化学療法、分子標的薬、免疫療法など)があります。
どの治療法を、どの順番で、どのように組み合わせて行うかは、がんの進行度、つまりステージによって大きく異なります。
進行度別の一般的な治療方針
- ステージI がんが局所にとどまる早期の段階。主に手術による根治を目指す。
- ステージII/III がんがリンパ節に転移しているが、遠隔転移はない段階。手術を中心に、補助的に薬物療法や放射線治療を組み合わせることが多い。
- ステージIV 遠隔転移がある段階。全身に効果が及ぶ薬物療法が治療の中心となる。
外科的治療の判断
手術でがんを完全に取りきれるかどうかは、主にT因子とN因子の評価にかかっています。
T因子が進行し、がんが周囲の重要な臓器や大血管に及んでいる場合や、N因子が進行し、広範囲のリンパ節に転移している場合は、手術が困難になることがあります。
逆に、早期の段階であれば、内視鏡治療や腹腔鏡手術といった、より体への負担が少ない治療法を選択できる可能性もあります。
薬物療法や放射線治療の適用
M因子がM1、つまり遠隔転移がある場合は、がんが全身に広がっていると判断し、薬物療法が治療の主体となります。
また、手術が困難なほど局所的に進行している場合(進行したT因子やN因子)には、手術の前に薬物療法や放射線治療を行ってがんを小さくしてから手術を行う「術前補助療法」や、手術の代わりとなる「根治的化学放射線療法」などを検討します。
検査結果の見方と理解のポイント
ご自身のTNM分類を知ることは、病状を正しく理解し、主体的に治療に参加するための第一歩です。しかし、診断報告書などに記載された専門的な表記を見て、戸惑うこともあるかもしれません。
ここでは、検査結果を理解し、主治医と円滑に話を進めるためのポイントを解説します。
診断報告書に書かれていること
TNM分類には、評価のタイミングによって「cTNM」と「pTNM」の2種類があることを知っておくと、理解が深まります。「c」はClinical(臨床的)、「p」はPathological(病理学的)を意味します。
cTNMとpTNMの違い
| 分類の種類 | 評価のタイミング | 評価の根拠 |
|---|---|---|
| cTNM(臨床分類) | 治療開始前 | CTや内視鏡などの画像診断、診察所見 |
| pTNM(病理分類) | 手術後 | 手術で摘出した組織の顕微鏡による診断(病理診断) |
一般的に、治療前の計画はcTNMに基づいて立てられ、手術後の最終的な進行度の確定診断はpTNMによって行います。
pTNMの方がより正確な情報が得られるため、手術後の補助療法の要否などを判断する上で重要です。
主治医への質問の仕方
TNM分類やステージについて分からないことがあれば、遠慮なく主治医に質問することが大切です。ただ漠然と尋ねるのではなく、要点を絞って質問することで、より理解が深まります。
確認すべき3つのポイント
まずは、ご自身のT、N、Mがそれぞれ何であるかを確認しましょう。
その上で、それが具体的にどのような状態を意味するのか、そしてその結果が今後の治療方針にどのように影響するのかを尋ねることが重要です。
主治医に確認したいこと
- 私のTNM分類とステージを教えてください。
- それぞれの因子が、具体的にどのような状態を示しているのか説明してください。
- この結果は、今後の治療方針にどのように影響しますか。
これらの質問を通じて、ご自身の病状についての理解を深め、納得して治療に臨むことができます。
予後予測に役立つ情報の読み取り方
TNM分類に基づくステージは、今後の病状の見通し、すなわち「予後」を予測する上でも参考にします。
ただし、予後に関する情報は統計的なデータであり、一人ひとりの患者さんの未来を断定するものではないことを、まず心に留めておくことが大切です。
ここでは、予後に関する情報をどのように受け止め、理解すればよいかを解説します。
ステージと生存率の関係
がんの予後を示す指標として、「5年生存率」や「10年生存率」といったデータがよく用いられます。
これは、同じがんの種類で、同じステージと診断された多くの患者さんのうち、診断から5年後や10年後に生存している人の割合を示したものです。
一般的に、ステージが進むほど、この生存率の数値は低くなる傾向があります。これらのデータは、治療法の選択や、人生設計を考える上での一つの参考情報となります。
予後予測の統計的データ
生存率などの統計データは、あくまでも過去の多くの患者さんのデータの平均値です。新しい治療法の登場により、実際の予後は年々向上している可能性があります。
また、そのデータが、ご自身の年齢層や健康状態に近い集団を対象としたものかどうかも重要です。
統計データは冷静に受け止め、過度に楽観したり悲観したりせず、主治医と今後の治療について前向きに話し合うための材料と捉えましょう。
予後を考える上での注意点
個人の予後は、TNM分類やステージだけで決まるわけではありません。以下のような、さまざまな要因が複雑に絡み合って影響します。
予後に影響を与える他の要因
- がんの生物学的な性質(悪性度の高さ、遺伝子変異の有無など)
- 患者さん自身の年齢や全身の健康状態、持病の有無
- 選択した治療法と、それに対するがんの反応性
- 治療を支える精神的なサポートや生活環境
TNM分類は非常に強力なツールですが、万能ではありません。予後について考える際は、これらの個別な要因も考慮に入れ、総合的に判断することが大切です。
よくある質問
TNM分類システムに関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- TNM分類はすべてのがんに使いますか?
-
いいえ、すべてのがんに使われるわけではありません。TNM分類は、主に最初に発生した場所が特定でき、固形の塊をつくる「固形がん」(例:胃癌、大腸癌、肺癌、乳癌など)で用いられます。
白血病や悪性リンパ腫といった、特定の臓器に塊をつくらずに全身に広がる「血液のがん」では、TNM分類とは異なる独自の分類法を用います。
また、脳腫瘍のように、遠隔転移することが稀ながんについても、特殊な分類法が適用されます。
- TNM分類は一度決まったら変わりませんか?
-
状況によって変わることがあります。前述の通り、治療前に行う「cTNM(臨床分類)」と、手術後に確定する「pTNM(病理分類)」で評価が変わる可能性があります。
また、治療後にがんが再発した場合には、再発した時点での病状を評価し直します。
例えば、治療時にはM0(遠隔転移なし)だった方が、再発時に肺に転移が見つかれば、その時点ではM1の状態として扱います。
- 自分のTNM分類を知るにはどうすればいいですか?
-
ご自身の正確なTNM分類を知る最も確実な方法は、主治医に直接尋ねることです。医師は、さまざまな検査結果を総合的に判断してTNM分類を決定しています。
診断書や診療情報提供書(紹介状)に記載されていることもありますが、専門的な内容が多いため、直接説明を受けるのが最も分かりやすいでしょう。
質問することをためらわずに、納得できるまで確認することが大切です。
- TNM分類が同じなら、治療法や予後は同じですか?
-
必ずしも同じではありません。TNM分類とステージは、治療方針を決定し、予後を予測するための非常に重要な基盤ですが、唯一の判断材料ではありません。
同じステージでも、がん細胞の性質(顔つき)、遺伝子変異の有無、患者さんの年齢や体力、持病、価値観や希望など、さまざまな要素を総合的に考慮して、最終的な治療方針を決定します。
予後も同様に、これらの個別的な要因に大きく影響されます。
がん種別のTNM分類適用の有無
がんの種類 TNM適用の有無 主な理由 固形がん(胃癌、肺癌など) 適用される 解剖学的な広がりを評価するのに適しているため。 血液のがん(白血病など) 適用されない 病気が初めから全身に存在するため、独自の分類法を用いる。 脳腫瘍 一部を除き適用されない 遠隔転移が稀であり、組織型や悪性度がより重要なため。
この記事ではTNM分類の基本を解説しましたが、TNMの組み合わせによって最終的に決定される「病期(ステージ)」について、さらに詳しく知りたい方も多いでしょう。
ステージIからステージIVまでが、それぞれどのような状態を指し、どのような治療が一般的に行われるのかを具体的に解説した記事をご用意しています。
ご自身のステージをより深く理解するために、ぜひあわせてお読みください。
参考文献
RAMI-PORTA, Ramón; OSAROGIAGBON, Raymond U.; ASAMURA, Hisao. The TNM system is adequate for making treatment decisions and prognostication in lung cancer. Journal of Thoracic Oncology, 2022, 17.11: 1255-1257.
KWON, Sung Joon. Evaluation of the 7th UICC TNM staging system of gastric cancer. Journal of gastric cancer, 2011, 11.2: 78-85.
RÖCKEN, C.; BEHRENS, H.-M. Validating the prognostic and discriminating value of the TNM-classification for gastric cancer–a critical appraisal. European Journal of Cancer, 2015, 51.5: 577-586.
D’CRUZ, Anil, et al. UICC manual of clinical oncology. Oxford: Wiley-Blackwell, 2015.
KIM, Kwangsoon, et al. Comparison of long-term prognosis for differentiated thyroid cancer according to the 7th and 8th editions of the AJCC/UICC TNM staging system. Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism, 2020, 11: 2042018820921019.
RAMI-PORTA, Ramón. The TNM classification of lung cancer—a historic perspective. Journal of Thoracic Disease, 2024, 16.11: 8053.
ZHU, Zhi; GONG, Yingbo; XU, Huimian. Clinical and pathological staging of gastric cancer: current perspectives and implications. European Journal of Surgical Oncology, 2020, 46.10: e14-e19.
ASARE, E., et al. H. Asamura, MD. TNM Classification of Malignant Tumours, 2025.
GU, Huizi, et al. The prognostic efficacy and improvements of the 7th edition Union for International Cancer Control tumor–node–metastasis classifications for Chinese patients with gastric cancer: Results based on a retrospective three-decade population study. Tumor Biology, 2017, 39.3: 1010428317694548.
DESHMUKH, Anuja, et al. Cancer Staging. In: Tata Memorial Centre Textbook of Oncology. Singapore: Springer Nature Singapore, 2024. p. 213-226.