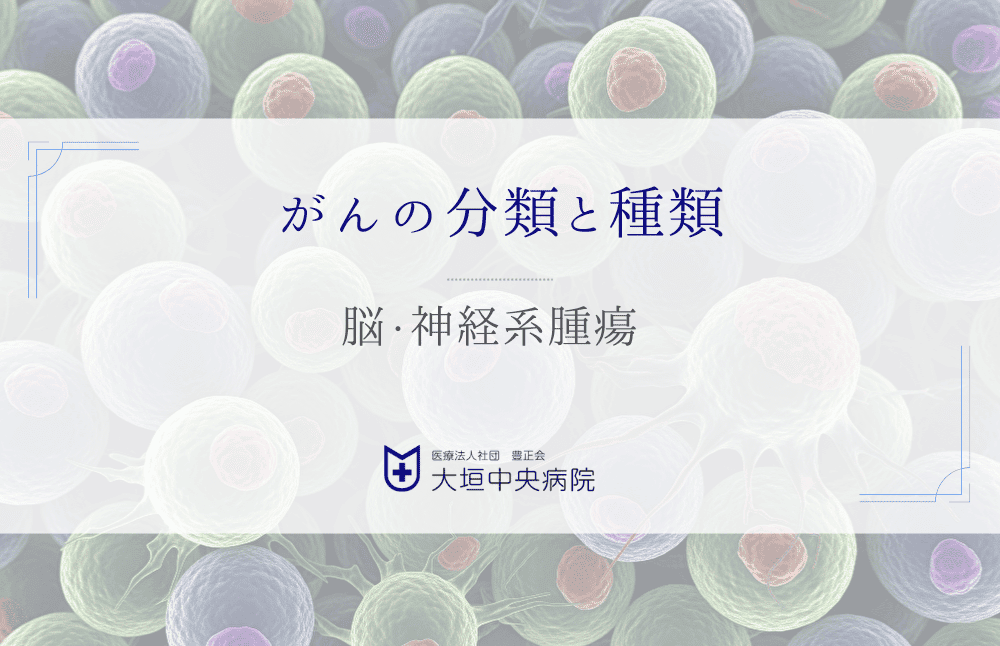脳や脊髄などの中枢神経系に発生する腫瘍は、総称して脳・神経系腫瘍と呼ばれます。
これらの腫瘍は、発生する場所や細胞の種類によって多種多様な性質を示し、症状や治療法も異なります。
頭蓋骨という限られた空間内に発生するため、良性であっても大きくなることで周囲の正常な脳組織を圧迫し、深刻な影響を及ぼすことがあります。
この記事では、代表的な脳・神経系腫瘍である「神経膠腫」「髄膜腫」「神経鞘腫」について、それぞれの特徴、症状、検査、そして治療の考え方を解説します。
神経膠腫(グリオーマ)
神経膠腫は、脳の神経細胞を支える役割を持つグリア細胞(神経膠細胞)から発生する腫瘍の総称です。
脳腫瘍の中でも発生頻度が高く、脳の実質内に染み込むように広がっていく(浸潤性)という特徴を持ちます。
この性質のため、腫瘍と正常な脳との境界が不明瞭であることが多く、治療における難しさの一因となります。
神経膠腫とはどのような腫瘍か
神経膠腫は、脳のあらゆる場所に発生する可能性があります。腫瘍が脳の中に深く広がる性質を持つため、手術で完全に取り除くことが難しい場合も少なくありません。
その性質は、比較的ゆっくり進行するものから、非常に速く増殖するものまで様々です。腫瘍の悪性度(グレード)によって、その後の経過や治療方針が大きく変わります。
発生部位と特徴
大脳半球は神経膠腫が最も発生しやすい部位ですが、小脳や脳幹、脊髄にも発生します。発生した場所の脳機能に応じて、手足の麻痺、言語の障害、視覚の異常など、多彩な症状を引き起こします。
腫瘍の周囲には、脳のむくみ(脳浮腫)を伴うことが多く、これが頭痛や吐き気などの原因にもなります。
浸潤性の性質
神経膠腫の最大の特徴は、周囲の正常な脳組織に染み込むように広がることです。画像検査で見える腫瘍の範囲よりも、実際にはさらに広範囲に腫瘍細胞が存在していると考えられています。
このため、手術で目に見える腫瘍をすべて摘出したとしても、残存した細胞から再発する可能性があります。この性質が、放射線治療や化学療法を組み合わせた集学的治療を必要とする理由です。
分類と悪性度(グレード)
神経膠腫は、その性質や由来する細胞の種類によって細かく分類されます。
世界保健機関(WHO)が定める分類が国際的な基準として用いられており、悪性度を示すグレードは治療方針を決定する上で極めて重要です。
WHOグレード分類
WHO分類では、神経膠腫をグレード1から4までの4段階に分けます。グレード1が最も悪性度が低く、グレード4が最も悪性度が高いことを示します。
グレードが上がるほど、腫瘍の増殖速度は速くなり、周囲への広がりも強くなる傾向があります。近年では、細胞の見た目による分類に加え、遺伝子変異の情報が診断に大きく関わるようになりました。
代表的な神経膠腫の種類
神経膠腫にはいくつかの種類があります。代表的なものとして、星細胞腫、乏突起膠腫、膠芽腫などが挙げられます。
これらは由来する細胞が異なり、それぞれに特徴的な性質や遺伝子変異を持っています。
星細胞腫(アストロサイトーマ)は、星細胞というグリア細胞に由来する腫瘍です。グレード2から4まで存在し、悪性度によって治療法や予後が異なります。
乏突起膠腫(オリゴデンドログリオーマ)は、乏突起膠細胞に由来し、比較的進行が緩やかで、特定の遺伝子変異を持つ場合は化学療法が効きやすいことが知られています。
膠芽腫(グリオブラストーマ)は、最も悪性度の高いグレード4に分類される神経膠腫で、増殖が非常に速く、治療が難しい腫瘍の一つです。
主な症状
神経膠腫の症状は、腫瘍が大きくなることによる頭蓋内の圧力上昇と、腫瘍が発生した場所の脳機能が障害されることによって現れます。
症状の出方は、腫瘍の大きさ、場所、増殖速度によって個人差があります。
腫瘍の増大による症状(頭蓋内圧亢進症状)
頭蓋骨の内部は容積が限られているため、腫瘍が大きくなると内部の圧力が高まります。これを頭蓋内圧亢進と呼びます。
代表的な症状は、朝方に特に強い頭痛、吐き気や嘔吐、ものが二重に見える(複視)などです。これらの症状は、病状の進行を示すサインである可能性があります。
発生部位による局所症状(巣症状)
腫瘍ができた脳の部位が担う機能が損なわれることで現れる症状を、局所症状(巣症状)と呼びます。
例えば、運動を司る領域に腫瘍ができれば手足の麻痺や動かしにくさが、言語を司る領域であれば言葉が出にくい、ろれつが回らないなどの症状が現れます。
けいれん発作で発症することも少なくありません。
検査と診断
神経膠腫が疑われる場合、まず画像検査で脳の状態を詳しく調べます。最終的な確定診断のためには、腫瘍組織の一部を採取して顕微鏡で調べる病理診断が必要です。
画像検査
MRIは、脳の構造を詳細に描出できるため、脳腫瘍の診断において中心的な役割を果たします。
造影剤という薬剤を注射して撮影することで、腫瘍の大きさ、形状、広がり、内部の性質などをより詳しく評価できます。CTは、出血の有無を確認したり、石灰化の様子を見たりするのに役立ちます。
病理診断の重要性
画像検査だけでは、腫瘍の種類や悪性度を完全に確定することはできません。確定診断には、手術によって摘出した腫瘍組織を顕微鏡で観察する病理診断が重要です。
この診断結果と遺伝子検査の結果を統合して、最も適切な治療方針を決定します。
治療の考え方
神経膠腫の治療は、手術、放射線治療、化学療法を組み合わせることが基本です。腫瘍の種類、悪性度、患者さんの全身状態などを総合的に判断し、治療計画を立てます。
手術療法
治療の第一歩は、多くの場合、手術による腫瘍の摘出です。可能な限り多くの腫瘍を摘出することで、頭蓋内圧を下げて症状を和らげ、その後の放射線治療や化学療法の効果を高めることが期待できます。
一方で、言語や運動など重要な機能を持つ部位に腫瘍が及んでいる場合は、機能障害を避けるために摘出範囲を限定することもあります。
放射線治療
放射線治療は、手術で取り切れなかった腫瘍細胞や、画像では見えない範囲に広がっている可能性のある腫瘍細胞を標的に行います。
高エネルギーのX線を照射して、腫瘍細胞の増殖を抑えたり、破壊したりする効果があります。通常、数週間にわたって分割して照射します。
化学療法
化学療法は、抗がん剤を用いて腫瘍細胞の増殖を抑制する治療法です。飲み薬や点滴で投与し、全身に行き渡ることで、脳内の広範囲に存在する腫瘍細胞に作用します。
放射線治療と同時に行ったり、手術後の補助療法として行ったりします。
遺伝子情報に基づいた治療
近年の研究により、神経膠腫の発生や進行に関わる特定の遺伝子変異が明らかになってきました。
これらの遺伝子情報を調べることで、より正確な診断が可能になり、特定の薬剤の効果を予測できるようになりました。個々の腫瘍の遺伝的特徴に合わせた治療法の選択が、ますます重要になっています。
神経膠腫のグレード別特徴
| WHOグレード | 主な特徴 | 進行の速さ |
|---|---|---|
| グレード1 | 境界が比較的明瞭で、良性に近い性質を持つ。 | 非常にゆっくり。 |
| グレード2 | 浸潤性を示すが、増殖は比較的緩やか。 | ゆっくり。 |
| グレード3 | 細胞分裂が活発で、明らかな悪性の特徴を持つ。 | 比較的速い。 |
| グレード4 | 増殖が非常に速く、壊死を伴う最も悪性度の高い腫瘍。 | 非常に速い。 |
髄膜腫(ずいまくしゅ)
髄膜腫は、脳と脊髄を覆っている髄膜という膜から発生する腫瘍です。脳腫瘍の中では比較的多く見られ、そのほとんどはゆっくりと増殖する良性の腫瘍です。
脳そのものから発生するわけではなく、脳の外側から脳を圧迫するように大きくなるのが特徴です。
髄膜腫とはどのような腫瘍か
髄膜腫は、脳を包む硬膜という膜を発生母地とします。そのため、脳の外側に存在し、大きくなるにつれて内側にある脳を圧迫します。
多くは成人、特に中高年の女性に見られます。ほとんどは良性ですが、ごくまれに悪性の性質を持つものもあります。
発生の起源
髄膜腫は、くも膜の細胞から発生すると考えられています。頭蓋内のあらゆる場所に発生する可能性がありますが、特に静脈洞と呼ばれる太い血管の近くや、頭蓋底、脊髄の周囲などによく見られます。
ホルモンの影響を受けることもあり、妊娠中に大きくなることがあります。
多くが良性であること
髄膜腫の約90%以上は良性(WHOグレード1)であり、増殖のスピードは非常に緩やかです。
そのため、偶然発見された小さな髄膜腫では、すぐに治療を開始せず、定期的な画像検査で大きさの変化を観察する「経過観察」が選択されることも少なくありません。
分類と特徴
髄膜腫も神経膠腫と同様に、WHOによって悪性度に応じたグレード分類がなされています。このグレードによって、治療後の再発率や治療方針が異なります。
WHOグレード分類
髄膜腫はグレード1(良性)、グレード2(異型性)、グレード3(退形成性・悪性)の3段階に分類されます。グレード2は良性と悪性の中間的な性質を持ち、グレード1に比べて再発しやすくなります。
グレード3は明らかな悪性腫瘍であり、増殖が速く、周囲の脳組織へ浸潤することもあります。
グレードによる性質の違い
グレード1の髄膜腫は、手術で完全に取り除くことができれば、再発の可能性は低いとされています。一方、グレード2や3では、手術で摘出した後に再発を防ぐ目的で放射線治療を追加することがあります。
グレードの診断は、手術で摘出した組織の病理診断によって確定します。
発見の経緯と症状
髄膜腫は、症状が全くないまま、脳ドックや頭部の怪我の検査などで偶然発見されることも多い腫瘍です。症状が現れる場合は、腫瘍がどのくらいの大きさで、脳のどの部分を圧迫しているかによって決まります。
無症状で発見される場合
小さな髄膜腫は脳を圧迫することがないため、多くは無症状です。
このような場合は、腫瘍が大きくならないか、あるいは非常にゆっくりとしか大きくならないことが多いため、慌てて治療する必要はなく、経過観察が第一の選択肢となります。
腫瘍の部位と大きさによる症状
腫瘍が大きくなり脳を圧迫し始めると、様々な症状が出現します。頭痛、手足のしびれや麻痺、けいれん発作、視力や視野の障害、物忘れなど、圧迫される脳の場所に応じた症状が見られます。
症状がすでに出ている場合は、治療を検討する必要があります。
検査方法
髄膜腫の診断には、主にCT検査やMRI検査といった画像検査を用います。これらの検査で、腫瘍の存在、大きさ、場所、周囲の脳との関係を詳細に評価します。
CT検査とMRI検査
CT検査では、腫瘍が白くはっきりと映し出され、石灰化の有無などを確認できます。MRI検査は、より詳細に腫瘍の性質や周囲の血管、神経との位置関係を把握するのに優れています。
特に造影剤を用いたMRI検査は、髄膜腫の診断に非常に有用です。
血管撮影検査の役割
腫瘍が非常に大きい場合や、血管が豊富な場所にある場合は、手術の前に血管撮影検査を行うことがあります。
この検査は、腫瘍を栄養している血管を特定し、手術中の出血を減らす目的で、その血管を詰める治療(塞栓術)を同時に行うこともできます。
治療方針の決定
髄膜腫の治療方針は、腫瘍の大きさや場所、増殖の速さ、患者さんの年齢や全身の状態、症状の有無などを総合的に考慮して決定します。
主な選択肢は、経過観察、手術、放射線治療です。
経過観察という選択肢
無症状で偶然発見された小さな髄膜腫の場合、定期的にMRI検査を行い、腫瘍の大きさに変化がないかを確認します。
多くの良性髄膜腫は増大しないか、増大するとしても非常にゆっくりであるため、生涯にわたって治療が不要な場合も少なくありません。
手術療法
症状の原因となっている場合や、画像検査で増大傾向が見られる場合には、手術による摘出を検討します。手術の目的は、症状の改善と、腫瘍による圧迫を取り除くことです。
可能な限り腫瘍をすべて取り除くことを目指しますが、重要な神経や血管を巻き込んでいる場合は、機能障害を避けるために一部を残すこともあります。
放射線治療
手術が難しい場所にある腫瘍、手術で取り残しがある場合、高齢や合併症で手術が困難な場合などには、放射線治療が選択されます。
特に、ガンマナイフやサイバーナイフといった定位放射線治療は、周囲の正常な脳への影響を抑えながら、腫瘍に集中的に放射線を照射することができ、有効な治療法の一つです。
髄膜腫の治療選択
| 状況 | 主な治療選択肢 | 目的 |
|---|---|---|
| 無症状・小型 | 経過観察 | 不要な治療を避け、変化を監視する。 |
| 有症状・増大傾向 | 手術療法 | 症状の改善と腫瘍の圧迫解除。 |
| 手術困難・残存腫瘍 | 放射線治療 | 腫瘍の増殖を抑制する。 |
神経鞘腫(しんけいしょうしゅ)
神経鞘腫は、神経を覆って支えているシュワン細胞という細胞から発生する、ほとんどが良性の腫瘍です。
脳から直接出る脳神経や、脊髄から出る脊髄神経など、末梢神経がある場所ならどこにでも発生する可能性があります。ゆっくりと大きくなるのが特徴です。
神経鞘腫とはどのような腫瘍か
この腫瘍は、神経そのものではなく、神経を包む鞘(さや)から発生します。そのため、腫瘍が大きくなっても、元の神経は圧迫されながらも保たれていることが多いです。
代表的なものに、聴神経にできる聴神経鞘腫や、脊髄の神経根にできる脊髄神経鞘腫があります。
神経を包む細胞からの発生
神経鞘腫は、神経線維を絶縁するように取り巻くシュワン細胞が腫瘍化したものです。通常、被膜(カプセル)に覆われており、周囲の組織との境界は比較的はっきりしています。
悪性化することは極めてまれです。
主な発生部位
頭蓋内で最も多いのは、聴覚と平衡感覚を司る前庭神経(聴神経の一部)から発生する聴神経鞘腫です。次いで、顔面の感覚を司る三叉神経や、顔の筋肉を動かす顔面神経からも発生します。
体幹や四肢の末梢神経、脊髄の神経根にも発生します。
代表的な神経鞘腫
神経鞘腫の中でも特に頻度が高いのが聴神経鞘腫と脊髄神経鞘腫です。それぞれ発生する場所が違うため、現れる症状も大きく異なります。
聴神経鞘腫(前庭神経鞘腫)
聴神経鞘腫は、実際には平衡感覚を司る前庭神経から発生することがほとんどです。内耳道という骨のトンネルの中で発生し、大きくなると小脳や脳幹を圧迫します。
早期発見と適切な治療が、聴力や顔面神経の機能を温存するために重要です。
脊髄神経鞘腫
脊髄から枝分かれする神経根から発生します。脊柱管という骨のトンネルの中で大きくなり、脊髄や神経根を圧迫することで、痛みやしびれ、運動麻痺などを引き起こします。
多くは良性で、ゆっくりと進行します。
主な症状
神経鞘腫の症状は、腫瘍がどの神経をどの程度圧迫しているかによって決まります。初期には症状が軽微なことも多く、発見が遅れることもあります。
聴神経鞘腫の症状
最も多い初期症状は、片側の耳の聞こえにくさ(難聴)や耳鳴りです。めまいやふらつきを感じることもあります。
腫瘍が大きくなると、近くを走行する顔面神経を圧迫し、顔の歪み(顔面神経麻痺)や、三叉神経を圧迫して顔のしびれを引き起こすことがあります。
脊髄神経鞘腫の症状
圧迫される神経の支配領域に応じた痛みやしびれが特徴的です。例えば、腰の神経にできれば足に、首の神経にできれば腕に症状が出ます。
腫瘍が大きくなり脊髄を強く圧迫すると、両足の麻痺や排尿・排便の障害に至ることもあります。
診断に至るまで
特徴的な症状から神経鞘腫を疑い、神経学的な診察と画像検査を組み合わせて診断を進めます。特にMRI検査は、診断を確定する上で非常に重要な情報を提供します。
問診と神経学的検査
どのような症状がいつから現れたか、詳しく話を聞きます。聴力検査や平衡機能検査、手足の感覚や力の入り具合を調べることで、障害されている神経の場所を推定します。
画像検査による確認
造影剤を用いたMRI検査が最も有用です。腫瘍の正確な位置、大きさ、形、そして周囲の神経や脳、脊髄との関係を詳細に把握することができます。
CT検査は、腫瘍による骨の変化を評価するのに役立ちます。
治療の選択
神経鞘腫も良性腫瘍であるため、治療の選択肢は経過観察、手術、定位放射線治療が中心となります。
治療方針は、腫瘍の大きさや増殖速度、症状の程度、年齢、そして患者さん自身の希望を考慮して慎重に決定します。
経過観察
高齢者や、症状が非常に軽い、あるいは全くない小さな腫瘍の場合には、定期的なMRI検査で腫瘍の大きさを監視する経過観察が選択されることがあります。
多くの神経鞘腫は増殖が遅いため、長期間にわたって治療が不要なケースもあります。
手術療法
症状が進行している場合や、腫瘍が大きく周囲の脳や脊髄を強く圧迫している場合には、手術による摘出が第一の選択肢となります。
手術の最大の目的は、神経への圧迫を取り除き、症状の進行を食い止めることです。同時に、元の神経の機能をできるだけ温存することが大きな目標となります。
定位放射線治療
比較的小さな腫瘍(通常3cm以下)に対しては、ガンマナイフなどの定位放射線治療も有効な選択肢です。手術を避けたい場合や、手術のリスクが高いと考えられる場合に検討します。
腫瘍を消滅させるのではなく、増殖を長期的に抑制することを目的とします。
神経鞘腫の主な症状
| 腫瘍の種類 | 初期症状 | 進行した場合の症状 |
|---|---|---|
| 聴神経鞘腫 | 片側の難聴、耳鳴り、めまい | 顔面神経麻痺、顔面のしびれ、歩行障害 |
| 脊髄神経鞘腫 | 神経根に沿った痛み、しびれ | 筋力低下、運動麻痺、排尿・排便障害 |
治療における機能温存の重要性
神経鞘腫の治療では、腫瘍を取り除くことと同じくらい、障害される可能性のある神経機能を守ることが重要視されます。
治療法の選択にあたっては、以下の機能の温存が大きな課題となります。
- 聴力
- 顔面神経機能
- 四肢の運動・感覚機能
よくある質問
- 脳腫瘍は遺伝しますか?
-
ほとんどの脳腫瘍は遺伝とは関係なく、偶発的に発生します。しかし、ごくまれに「神経線維腫症」などの特定の遺伝性疾患が原因で、脳腫瘍や神経系の腫瘍が発生しやすい家系もあります。
ご家族に同じような病気の方が複数いるなど、心配な点があれば主治医に相談してみてください。
- 治療後の生活で気をつけることはありますか?
-
治療内容や後遺症の有無によって異なりますが、一般的には体力の回復に合わせて、徐々に元の生活に戻していくことが目標となります。
定期的な通院と画像検査は、再発の早期発見のために重要です。また、けいれん発作の経験がある場合は、医師の指示に従って抗けいれん薬の服用を続ける必要があります。
車の運転については、病状や治療内容によって制限されることがあるため、必ず主治医に確認してください。
- Q. 手術が難しいと言われました。他に方法はありますか?
-
腫瘍が発生した場所や大きさ、性質によっては、手術によるリスクが非常に高い場合があります。そのような場合でも、放射線治療や化学療法が有効な選択肢となることがあります。
特に、定位放射線治療(ガンマナイフなど)は、手術の代わりとなり得る治療法です。また、腫瘍の種類によっては、新しい分子標的薬などの薬物療法が適応となる可能性もあります。
主治医とよく相談し、他の治療法の可能性について情報を得ることが大切です。
参考文献
PYTEL, Peter; LUKAS, Rimas V. Update on diagnostic practice: tumors of the nervous system. Archives of pathology & laboratory medicine, 2009, 133.7: 1062-1077.
BUCKNER, Jan C., et al. Central nervous system tumors. In: Mayo Clinic Proceedings. Elsevier, 2007. p. 1271-1286.
WALKER, David, et al. Central nervous system tumors. In: Cancer in adolescents and young adults. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 335-381.
APRA, Caroline; PEYRE, Matthieu; KALAMARIDES, Michel. Current treatment options for meningioma. Expert review of neurotherapeutics, 2018, 18.3: 241-249.
HANNA JR, Chadwin, et al. Review of meningioma diagnosis and management. Egyptian journal of neurosurgery, 2023, 38.1: 16.
PELLERINO, Alessia, et al. Diagnosis and treatment of peripheral and cranial nerve tumors with expert recommendations: An EUropean Network for RAre CANcers (EURACAN) initiative. Cancers, 2023, 15.7: 1930.
GUO, Xiaopeng, et al. Clinical updates on gliomas and implications of the 5th edition of the WHO classification of central nervous system tumors. Frontiers in Oncology, 2023, 13: 1131642.
BREM, Steven S., et al. Central nervous system cancers. Journal of the National Comprehensive Cancer Network, 2011, 9.4: 352-400.
LOUIS, David N., et al. The 2021 WHO classification of tumors of the central nervous system: a summary. Neuro-oncology, 2021, 23.8: 1231-1251.
GOLDBRUNNER, Roland, et al. EANO guideline on the diagnosis and treatment of vestibular schwannoma. Neuro-oncology, 2020, 22.1: 31-45.