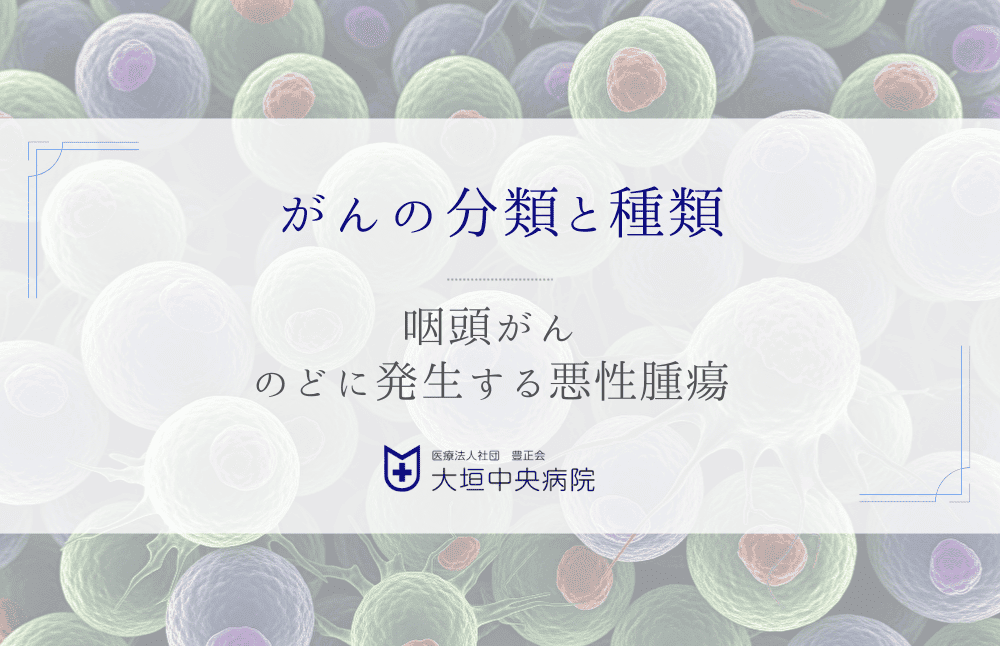「咽頭がん」という診断を受け、ご自身やご家族が大きな不安を抱えていることと思います。咽頭がんは、のど(咽頭)に発生する悪性腫瘍の総称です。
このがんは発生する場所によって性質が異なり、治療法も多岐にわたります。
この記事では、咽頭がんの基本的な知識から、原因、症状、検査、そして治療法の選択肢までを、順を追って詳しく解説します。正しい情報を得ることが、病気と向き合い、納得のいく治療を選択するための第一歩です。
咽頭がんとは何か – 発生部位と特徴
咽頭がんは、私たちの「のど」の一部である咽頭に発生するがんです。咽頭は鼻の奥から食道の入り口まで続く管状の器官で、呼吸と食事の両方に関わる重要な役割を担っています。
この咽頭は、部位によって「上咽頭」「中咽頭」「下咽頭」の3つに分けられ、がんが発生した場所によって、それぞれ異なる名称で呼ばれ、特徴や治療方針も変わってきます。
がんの進行度を示すステージ分類は、治療法を決定する上で重要な指標となります。
咽頭の構造とがんの種類
咽頭は、食べ物や空気が通る道であり、部位ごとに異なる機能を持っています。がんはこれらの部位の粘膜から発生することがほとんどです。
それぞれの部位の役割と、そこに発生するがんの特徴を理解することが、病気の全体像を掴む上で大切です。
咽頭の部位別特徴
| 部位 | 位置 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 上咽頭がん | 鼻の奥から口蓋垂(のどちんこ)の上部まで | 初期症状が出にくく、発見が遅れることがある。EBウイルスとの関連が指摘される。 |
| 中咽頭がん | 口蓋垂から喉頭蓋(気管のふた)の上部まで | 口を開けると見える範囲。近年、HPV(ヒトパピローマウイルス)関連のがんが増加。 |
| 下咽頭がん | 喉頭蓋から食道の入り口まで | 飲み込み時の違和感などの症状が出やすいが、進行が早く、早期発見が重要。 |
ステージ分類と進行度
咽頭がんの治療方針は、がんの進行度を示す「ステージ」に基づいて決定します。
ステージは、がんの大きさ(T分類)、頸部リンパ節への転移の有無と範囲(N分類)、他の臓器への転移(遠隔転移)の有無(M分類)を組み合わせて総合的に判断します。
TNM分類の考え方
TNM分類は、がんの状態を客観的に評価するための世界共通の基準です。
Tは原発巣の大きさと広がり、Nは所属リンパ節への転移状況、Mは遠隔転移の有無を示します。これらの評価を基に、がんはステージⅠ(早期)からステージⅣ(進行)に分類されます。
特に下咽頭がんや中咽頭がんは、頸部のリンパ節転移を起こしやすく、N分類の評価が治療計画に大きく影響します。
咽頭がんの主な原因とリスク因子
咽頭がんが発生する原因は一つではありません。長年の生活習慣やウイルス感染など、複数の因子が複雑に関与していると考えます。特に、喫煙と過度の飲酒は、中咽頭がんと下咽頭がんの二大リスク因子として確立しています。
また、近年では特定のウイルス感染が、がん発生の引き金となることも明らかになってきました。リスク因子を正しく理解し、可能な限り避けることが予防につながります。
生活習慣に潜むリスク
日々の生活の中に、咽頭がんのリスクを高める要因が隠れていることがあります。特に注意が必要なのが、喫煙と飲酒の習慣です。
これらは単独でもリスクを高めますが、両方の習慣があると、そのリスクは相乗的に増大します。
喫煙と飲酒の相乗効果
タバコの煙に含まれる多くの発がん性物質は、咽頭の粘膜に直接ダメージを与えます。
また、アルコールそのものに強い発がん性はありませんが、アルコールが体内で分解される過程で生じるアセトアルデヒドという物質に発がん性があります。
喫煙と飲酒を同時に行うと、アルコールが発がん性物質を溶かし、粘膜に浸透しやすくなるため、がんの発生リスクが飛躍的に高まります。
咽頭がんの主なリスク因子
| リスク因子 | 関連するがん | 概要 |
|---|---|---|
| 喫煙 | 中咽頭がん、下咽頭がん | タバコの煙に含まれる発がん物質が粘膜を傷つける。 |
| 過度の飲酒 | 中咽頭がん、下咽頭がん | 代謝物であるアセトアルデヒドに発がん性がある。 |
| HPV感染 | 中咽頭がん | ウイルスの感染ががん化の引き金になることがある。 |
| EBウイルス感染 | 上咽頭がん | ウイルスの持続的な感染が発症に関与する。 |
ウイルス感染と咽頭がん
特定のウイルスへの感染が、一部の咽頭がんの直接的な原因となることが分かっています。代表的なものが、中咽頭がんの原因となるHPV(ヒトパピローマウイルス)と、上咽頭がんの原因となるEBウイルスです。
HPV(ヒトパピローマウイルス)感染の重要性
HPVは子宮頸がんの原因として知られていますが、近年、中咽頭がんの原因としても注目されています。HPV関連の中咽頭がんは、喫煙や飲酒をしない比較的若い世代にも発症することがあり、従来のタイプのがんとは異なる特徴を持ちます。
幸いなことに、HPV関連のがんは放射線治療や化学療法が効きやすく、比較的予後が良い傾向があります。
初期に気づくべき咽頭がんの症状
咽頭がんは、発生した部位によって現れる症状が異なります。初期の段階では症状が乏しいことも多く、風邪やのどの炎症と間違えやすいサインもあるため注意が必要です。
しかし、体に現れる小さな変化を見逃さず、早期に医療機関を受診することが、良好な治療結果につながります。特に、症状が2週間以上続く場合は、専門医への相談を検討してください。
部位ごとに異なる初期症状
上咽頭、中咽頭、下咽頭では、それぞれ特徴的な初期症状が現れます。がんが小さい段階では無症状のこともありますが、進行するにつれて様々なサインが出てきます。
咽頭がんの部位別初期症状
| 部位 | 主な初期症状 | 注意すべき点 |
|---|---|---|
| 上咽頭がん | 鼻づまり、鼻血、耳の閉塞感、首のしこり | のどの症状が出にくく、耳鼻科や脳神経外科の病気と間違われることがある。 |
| 中咽頭がん | のどの痛みや違和感、飲み込むときの異物感、首のしこり | 扁桃炎と症状が似ていることがある。片側だけの症状が続く場合は要注意。 |
| 下咽頭がん | 声がれ(嗄声)、飲み込むときの痛みやつかえ感、のどの異物感 | 声の変化が比較的早い段階で現れることがある。食事がしみる感覚もサインの一つ。 |
見過ごしやすいサイン
咽頭がんの初期症状は、日常生活で経験するような些細な不調と似ているため、見過ごされがちです。しかし、がんが原因の場合、これらの症状は自然に治ることなく、持続したり、徐々に悪化したりする傾向があります。
首のしこりとリンパ節転移
咽頭がんは、頸部(首)のリンパ節に転移しやすい性質があります。特に上咽頭がんや中咽頭がんでは、のどの症状よりも先に、首のしこりを自覚してがんが発見されるケースが少なくありません。
痛みのないしこりが首にできた場合、それはリンパ節転移のサインかもしれません。大きさに変化がなくても、早めに専門医の診察を受けることが重要です。
診断の流れと検査方法
のどの違和感や首のしこりなどで医療機関を受診すると、咽頭がんが疑われる場合には、診断を確定するための詳しい検査を行います。診断では、まずがんの存在を確認し、次にがんの種類(病理組織型)を特定します。
そして、がんがどの程度広がっているか(ステージ)を正確に評価することが、適切な治療方針を立てる上で不可欠です。
確定診断に至るまでの道のり
診断は、問診から始まり、視診、触診、そしてより精密な検査へと進みます。医師は症状について詳しく尋ねた後、のどの状態を直接観察し、がんが疑われる部位の組織を採取して確定診断を下します。
視診・触診と内視鏡検査
まず、医師が口の中を直接見たり、首の周りを触ってしこりの有無を確認したりします。その後、鼻や口から細いカメラ(内視鏡)を挿入し、咽頭の粘膜を隅々まで詳しく観察します。
内視鏡検査は、医師が直接見ることができない咽頭の奥深くの状態を把握するために重要な検査です。
病理組織学的検査(生検)の役割
内視鏡検査でがんが疑われる病変が見つかった場合、その一部を少量採取します。これを「生検」と呼びます。採取した組織を顕微鏡で詳しく調べ、がん細胞の有無を確認する検査が「病理組織学的検査」です。
この検査によって、がんの診断が確定し、がんの種類(扁平上皮がんなど)も判明します。
がんの広がりを調べる検査
がんの診断が確定したら、次に治療計画を立てるために、がんの広がり(深さや周辺臓器への浸潤、リンパ節転移、遠隔転移)を詳細に調べる検査を行います。
咽頭がんの主な検査方法
| 検査の種類 | 目的 | 概要 |
|---|---|---|
| 内視鏡検査 | 病変の観察、生検 | 鼻や口からカメラを入れ、咽頭粘膜を直接見る。 |
| CT検査 | がんの広がり、リンパ節転移の評価 | X線を使って体の断面を撮影し、がんの大きさや周囲への広がりを調べる。 |
| MRI検査 | がんの深さや軟部組織への広がり | 磁気を利用して、CTでは分かりにくい筋肉や神経への広がりを詳細に評価する。 |
| PET-CT検査 | 遠隔転移の有無、再発の診断 | がん細胞がブドウ糖を多く取り込む性質を利用し、全身のがん細胞を検出する。 |
咽頭がんの治療法の種類と選択の考え方
咽頭がんの治療は、がんを治すこと(根治性)と、治療後の生活の質(QOL)を維持することのバランスを考えながら進めます。
咽頭は、食事や会話、呼吸といった生きる上で根幹となる機能に関わるため、これらの機能をできるだけ損なわない治療法の選択が重要です。
治療法は主に、放射線治療、手術、化学療法(抗がん剤)の3つがあり、がんのステージや部位、全身の状態、そして患者さん自身の希望を総合的に考慮して、最適な組み合わせを決定します。
治療の三本柱
咽頭がん治療の基本となるのは、放射線治療、手術、化学療法の3つの方法です。これらを単独で行うこともあれば、複数を組み合わせて治療効果を高める「集学的治療」を行うこともあります。
放射線治療の役割と方法
放射線治療は、高エネルギーのX線などをがん細胞に照射して破壊する治療法です。特に早期の咽頭がんでは、手術と同等の治療効果が期待でき、声を出す、飲み込むといった機能を温存できる可能性が高いという大きな利点があります。
治療は通常、週5日のペースで6〜7週間かけて行います。化学療法と同時に行うことで、治療効果を高めることもあります。
根治を目指す手術
手術は、がん細胞を物理的に取り除く治療法です。がんの部位や大きさによって、口の中からアプローチする方法や、首を切開する方法など、様々な術式があります。
進行がんの場合、がんが広がった範囲によっては、咽頭や喉頭の一部または全部を摘出する必要が生じることもあります。その際は、失われた機能を再建する手術も同時に行います。
主な治療法の比較
| 治療法 | 主な利点 | 主な欠点 |
|---|---|---|
| 放射線治療 | 機能温存が可能、身体的負担が少ない | 治療期間が長い、口内乾燥などの後遺症 |
| 手術 | がんを直接切除できる、治療期間が短い | 機能障害の可能性、身体的負担が大きい |
ステージと全身状態を考慮した治療選択
治療法の選択は、がんのステージが最も重要な判断材料となります。
早期がんであれば機能温存を優先した治療法が選択されることが多い一方、進行がんでは根治性を高めるために複数の治療を組み合わせる集学的治療が標準となります。
生存率を高める集学的治療
進行した咽頭がんに対しては、手術、放射線治療、化学療法を組み合わせた集学的治療を行います。
例えば、手術の前に化学療法を行ってがんを小さくしたり(術前化学療法)、手術後に再発を防ぐ目的で放射線治療や化学療法を行ったり(術後補助療法)します。
どの治療法をどの順番で組み合わせるかは、がんの特性や患者さんの体力などを考慮して、専門家チームが慎重に検討します。
治療法の選択にあたっては、それぞれのメリット・デメリットについて医師から十分な説明を受け、納得した上で決定することが大切です。
咽頭がんのステージ別標準治療(概要)
| ステージ | 主な治療方針 | 目標 |
|---|---|---|
| ステージⅠ・Ⅱ (早期がん) | 放射線治療 単独 or 手術 単独 | 機能温存と根治 |
| ステージⅢ・Ⅳ (進行がん) | 化学放射線療法 or 手術 + 術後治療 | 根治と生存率の向上 |
治療後に起こりうる合併症と生活への影響
咽頭がんの治療は、がんを取り除くだけでなく、その後の生活を見据えて行うことが重要です。治療法によっては、食事や会話といった日常生活に欠かせない機能に影響が及ぶことがあります。
どのような合併症が起こりうるのかを事前に理解し、その対処法やリハビリテーションについて知っておくことは、治療後の生活再建への不安を和らげ、前向きに取り組む助けとなります。
機能障害と向き合う
治療によって咽頭やその周辺の組織がダメージを受けると、様々な機能障害が生じることがあります。特に、嚥下(飲み込み)と構音(発声・会話)への影響は、生活の質に直結する問題です。
嚥下障害(飲み込みにくさ)と食事の工夫
放射線治療による粘膜の炎症や、手術によるのどの形の変化によって、食べ物や飲み物が飲み込みにくくなる「嚥下障害」が起こることがあります。むせやすくなったり、食事がうまく喉を通らなかったりします。
このような場合は、言語聴覚士による嚥下リハビリテーションを行ったり、食事の形態を工夫したり(刻み食、とろみ食など)することで、安全に食事を摂る手助けをします。
治療後に考えられる主な合併症
| 合併症 | 主な原因 | 対処法 |
|---|---|---|
| 嚥下障害 | 手術、放射線治療 | 嚥下リハビリ、食事形態の工夫 |
| 構音障害 | 手術(特に喉頭摘出) | 音声リハビリ、電気喉頭、食道発声 |
| 口内乾燥・味覚障害 | 放射線治療 | 保湿ケア、人工唾液、栄養指導 |
| リンパ浮腫 | リンパ節郭清(手術) | スキンケア、リンパドレナージ、弾性着衣 |
外見の変化と心理的ケア
手術によって首に傷が残ったり、治療の影響で体重が減少したりと、外見上の変化が起こることもあります。こうした変化は、患者さんの心理的な負担となることがあります。
一人で抱え込まず、医療スタッフや家族、あるいは同じ経験を持つ患者会の仲間などに相談することも大切です。必要に応じて、臨床心理士や精神科医によるサポートを受けることもできます。
再発や転移を防ぐための取り組み
咽頭がんの治療が無事に終了した後も、残念ながら再発や転移の可能性があります。
再発とは、最初にがんができた場所(原発巣)やその周辺に再びがんが現れること、転移とは、頸部リンパ節や肺、骨など、離れた臓器にがんが現れることです。
これらの変化をできるだけ早い段階で発見し、速やかに対応するために、治療後も定期的な検査と診察を継続することが極めて重要です。
治療後の定期的な経過観察
治療後の経過観察は、再発・転移の早期発見と、治療による後遺症の管理を目的として行います。
通院の頻度は、治療終了からの期間やがんのステージによって異なりますが、一般的には治療後2年間は1〜3ヶ月ごと、3年目以降は半年に1回、5年目以降は年に1回程度が目安となります。
定期検診の重要性
定期検診では、問診、視診、触診に加え、内視鏡検査や画像検査(CT、MRIなど)を組み合わせて行います。症状がないからといって自己判断で通院をやめてしまうと、再発の発見が遅れてしまう危険性があります。
医師の指示に従い、きちんと検診を受け続けることが、万が一の事態に備える最善の方法です。
- 問診・視診・触診
- 内視鏡検査
- 頸部超音波(エコー)検査
- CT・MRI検査
- 腫瘍マーカー(血液検査)
再発・転移の早期発見
定期検診に加えて、日々の体調変化に自分で気を配ることも大切です。
治療前と同じような症状(のどの痛み、声がれ、飲み込みにくさなど)や、新たな症状(持続する咳、体の痛み、首のしこりなど)が現れた場合は、次の検診を待たずに速やかに主治医に相談してください。
咽頭がんと生活習慣の関わり
咽頭がんの治療を乗り越え、再発を防ぐためには、がんの発生に関与した生活習慣を見直すことが重要です。
特に、最大の原因とされる喫煙と過度の飲酒の習慣を断つことは、再発リスクを低減させるだけでなく、二次がん(咽頭以外の場所に新たに発生するがん)の予防にもつながります。
また、治療で体力が落ちている体を回復させ、免疫力を維持するためにも、日々の生活習慣が大きな役割を果たします。
禁煙と節酒の重要性
喫煙と飲酒は、咽頭がんの最も強力なリスク因子です。治療後もこれらの習慣を続けることは、再発のリスクを高めるだけでなく、治療による副作用を悪化させたり、新たな病気を引き起こしたりする原因となります。
喫煙がもたらすリスクの再確認
禁煙は、咽頭がんの再発予防において最も効果的な取り組みの一つです。タバコの煙は、治療でダメージを受けたのどの粘膜の回復を妨げ、新たな発がんの火種となり得ます。
自力での禁煙が難しい場合は、禁煙外来などで専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
バランスの取れた食事
治療による嚥下障害や味覚障害があると、食事が思うように進まないことがあります。しかし、体の回復や免疫機能の維持には、十分な栄養が必要です。
管理栄養士と相談しながら、食べやすく、かつ栄養バランスの取れた食事を心がけることが大切です。
- 禁煙を継続する
- 飲酒を控える(できれば禁酒)
- 主食・主菜・副菜をそろえる
- 野菜や果物を積極的に摂る
- 適度な運動を習慣にする
よくある質問
咽頭がんについて、患者さんやご家族からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- 咽頭がんの生存率はどのくらいですか?
-
咽頭がんの生存率は、がんの発生部位、ステージ、そして治療法によって大きく異なります。一般的に、早期で発見されるほど生存率は高くなります。
HPV関連の中咽頭がんは、他のタイプに比べて予後が良い傾向があります。あくまでも全体の統計データであり、個々の患者さんの状況とは異なることを理解してください。
主治医からご自身の詳しい病状に基づいた見通しを聞くことが大切です。
ステージ別5年相対生存率の目安(全咽頭がん)
ステージ 5年相対生存率(目安) 概要 ステージⅠ 約80-90% がんは小さく、リンパ節転移がない状態。 ステージⅡ 約60-70% がんが少し大きくなるが、転移はないか軽度。 ステージⅢ・Ⅳ 約30-50% がんが進行し、リンパ節転移や周辺への広がりがある状態。 ※この数値はあくまで一般的な目安であり、がんの種類や個人の状態により異なります。 - HPVワクチンは中咽頭がんの予防になりますか?
-
はい、効果が期待できます。現在、日本で公費接種の対象となっているHPVワクチンは、子宮頸がんの原因となるHPV16型、18型などの感染を防ぐものですが、このHPV16型は中咽頭がんの主な原因でもあります。
したがって、HPVワクチンを接種することで、将来的なHPV関連中咽頭がんの発生を予防する効果が期待されています。
- 治療中の食事で気をつけることは何ですか?
-
放射線治療や化学療法の副作用で、口内炎や吐き気、味覚の変化などが起こり、食事が摂りにくくなることがあります。
刺激の強いもの(香辛料、熱いもの、酸っぱいもの)は避け、口当たりが良く、のどごしの良いものを選ぶとよいでしょう。栄養価の高いスープやゼリー、栄養補助食品などを活用するのも一つの方法です。
無理せず食べられるものを少しずつ、回数を分けて摂るように工夫してください。困ったときには、管理栄養士に相談することをお勧めします。
この記事では「咽頭がん」について解説しましたが、「のどのがん」には、声を出す声帯がある「喉頭(こうとう)」にできる「喉頭がん」もあります。
咽頭がんと喉頭がんは、発生する場所が近く、症状にも似ている点がありますが、性質や治療法が異なります。特に、声がれが主な初期症状となる喉頭がんは、早期発見が声の温存に直結する重要ながんです。
喫煙との関連が非常に強いことも特徴です。もし、声の変化が気になる方や、咽頭がんと喉頭がんの違いについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
以上
参考文献
SPINATO, Giacomo, et al. Multicenter research into the quality of life of patients with advanced oropharyngeal carcinoma with long‑term survival associated with human papilloma virus. Oncology Letters, 2017, 14.1: 185-193.
TAKAHASHI, Mai, et al. Quality of life analysis of HPV-positive oropharyngeal cancer patients in a randomized trial of reduced-dose versus standard chemoradiotherapy: 5-year follow-up. Frontiers in oncology, 2022, 12: 859992.
RANTA, Pihla, et al. Long‐term quality of life after treatment of oropharyngeal squamous cell carcinoma. The Laryngoscope, 2021, 131.4: E1172-E1178.
VAINSHTEIN, Jeffrey M., et al. Long-term quality of life after swallowing and salivary-sparing chemo–intensity modulated radiation therapy in survivors of human papillomavirus–related oropharyngeal cancer. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 2015, 91.5: 925-933.
RUEHLE, Alexander, et al. Surviving Elderly patients with Head-and-Neck squamous cell carcinoma—what is the long-term quality of life after curative Radiotherapy?. Cancers, 2021, 13.6: 1275.
BAXI, Shrujal S., et al. Long‐term quality of life in older patients with HPV‐related oropharyngeal cancer. Head & neck, 2018, 40.11: 2321-2328.
SILVER, Jennifer A. Longitudinal and comprehensive quality of life in patients with locally advanced human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma. McGill University (Canada), 2024.
VAINSHTEIN, Jeffrey M., et al. Long-term quality of life after swallowing and salivary sparing chemo-IMRT in survivors of HPV-related oropharyngeal cancer. International journal of radiation oncology, biology, physics, 2015, 91.5: 925.
SAMUELS, Stuart E., et al. Comparisons of dysphagia and quality of life (QOL) in comparable patients with HPV-positive oropharyngeal cancer receiving chemo-irradiation or cetuximab-irradiation. Oral oncology, 2016, 54: 68-74.
SCOTT, Susanne I., et al. Long‐term quality of life & functional outcomes after treatment of oropharyngeal cancer. Cancer medicine, 2021, 10.2: 483-495.