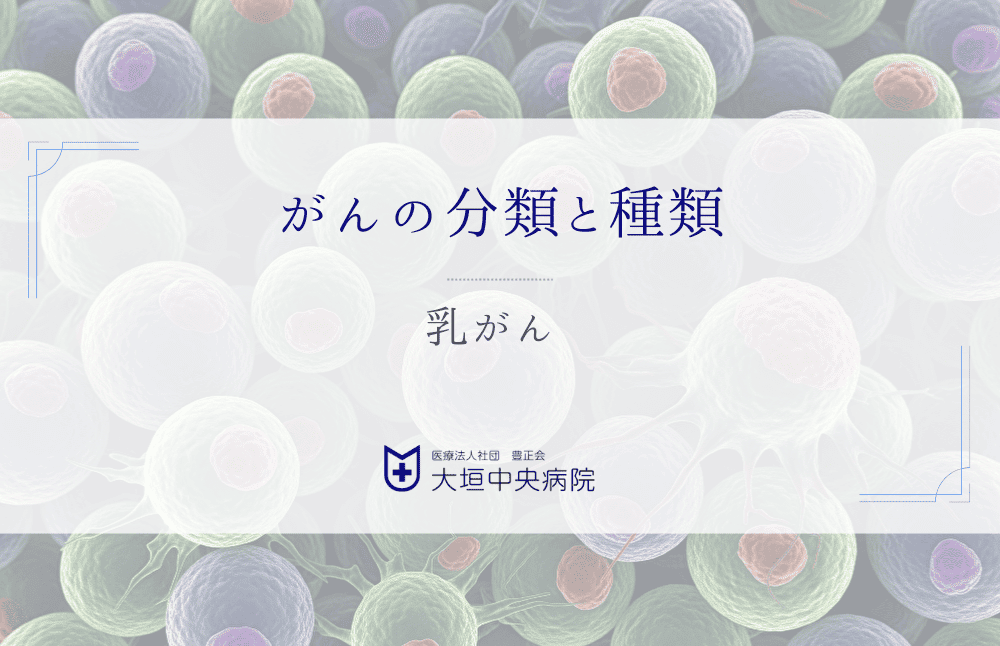乳がんは、日本人女性にとって最も身近な癌の一つです。9人に1人が生涯のうちに乳がんにかかるといわれており、誰にとっても他人事ではありません。
しかし、乳がんは早期に発見し、適切な治療を行えば、良好な経過を期待できる病気でもあります。そのためには、一人ひとりが乳がんに関する正しい知識を持ち、自分自身の体に関心を向けることが重要です。
この記事では、乳がんの症状や原因、検査、治療法といった基礎知識を分かりやすく解説し、あなたとあなたの大切な人の健康を守るための一助となることを目指します。
乳がんの概要と日本での発症状況
乳がんは、乳房の中にある乳腺という組織に発生する悪性の腫瘍です。まずは、この病気の基本的な情報と、日本における現状を理解することから始めましょう。
正しい知識は、いたずらに不安になることを防ぎ、冷静な判断と行動につながります。
乳がんとはどのような病気か
乳がんは、母乳を作る乳腺の細胞が異常に増殖することで発生します。増殖した癌細胞は、時間とともに周囲の組織に広がり(浸潤)、やがて血管やリンパ管を通って全身に広がる(転移)性質を持っています。
癌細胞が乳管や小葉の中にとどまっている状態を「非浸潤癌」、乳管や小葉の外にまで広がった状態を「浸潤癌」と呼びます。多くの乳がんは、この浸潤癌の段階で発見されます。
日本人女性と乳がん
現在、乳がんは日本人女性が最もかかりやすい癌であり、その数は年々増加傾向にあります。国立がん研究センターの統計によると、2019年には約9万8千人の女性が新たに乳がんと診断されました。
特に40代後半から60代後半にかけて発症のピークが見られますが、若い世代から高齢者まで幅広い年代で発症する可能性があります。
一方で、医療の進歩により生存率は向上しており、早期発見・早期治療の重要性がますます高まっています。
年代別の罹患リスク
乳がんの罹患率は年齢とともに上昇し、30代から増加し始め、40代後半から60代後半でピークを迎えます。その後も高齢になるまで高い水準で推移します。
| 年代 | 罹患率(人口10万対) | 特徴 |
|---|---|---|
| 30代 | 約30人 | リスクが増加し始める年代 |
| 40代後半 | 約170人 | 罹患率の最初のピーク |
| 60代前半 | 約220人 | 罹患率の2番目のピーク |
乳がんの主な症状と進行のサイン
乳がんは、早期の段階では自覚症状がほとんどないことも少なくありません。しかし、進行すると体に様々なサインが現れます。
日頃から自身の乳房の状態に関心を持ち、変化に気づくことが早期発見の第一歩です。
最も多い自覚症状「しこり」
乳がんの症状として最も多くみられるのが、乳房の「しこり」です。自分で触れて気づくことが多く、その特徴は様々ですが、一般的には硬くてごつごつしており、触ってもあまり動かないことが多いです。
痛みは伴わないことがほとんどで、「痛くないから大丈夫」と自己判断するのは危険です。一つでもしこりに気づいたら、必ず専門の医療機関を受診してください。
しこり以外の症状
しこり以外にも、乳がんのサインとなる症状はいくつかあります。これらの変化は、しこりよりも気づきにくい場合があるため、注意深く観察することが大切です。
- 乳房の皮膚のひきつれ、くぼみ、ただれ
- 乳頭の陥没や変形、湿疹
- 乳頭からの血液が混じった分泌物
- 乳房の左右差が目立つようになる
- わきの下の腫れやしこり
症状のセルフチェック方法
月に一度、生理が終わってから1週間後くらいの乳房が柔らかい時期に、セルフチェックを行う習慣をつけましょう。
鏡の前で目で見て、次に指で触れて確認します。指の腹を使い、乳房全体を「の」の字を書くように、あるいは肋骨に押し付けるようにして、しこりや変化がないかを確認します。
わきの下まで忘れずにチェックすることが重要です。
乳がんの原因と関係があるとされる要因
乳がんがなぜ発生するのか、その直接的な原因はまだ完全には解明されていません。しかし、長年の研究から、いくつかの要因が発症の可能性、すなわち「リスク」を高めることが分かってきました。
これらの要因を知ることは、予防や早期発見につながります。
乳がん発症の直接的な原因
乳がんの発生には、遺伝子の変異が関わっていると考えられています。多くの場合、この遺伝子変異は生まれつきのものではなく、生活習慣や環境要因が複雑に絡み合って後天的に生じます。
一部の乳がんでは、親から受け継いだ特定の遺伝子(BRCA1、BRCA2など)の変異が発症に強く関わっていることも知られています。
発症リスクを高める要因
乳がんの発症には、女性ホルモンであるエストロゲンが深く関わっています。エストロゲンにさらされる期間が長いほど、発症リスクが高まるとされています。
その他にも、生活習慣に関連する要因が複数指摘されています。
主なリスク要因
| カテゴリ | リスク要因 | 簡単な説明 |
|---|---|---|
| 身体・生殖関連 | 初経年齢が早い | エストロゲンにさらされる期間が長くなるため |
| 閉経年齢が遅い | 同上 | |
| 出産経験がない、または初産年齢が遅い | 妊娠・授乳期間はエストロゲンの分泌が抑えられるため | |
| 閉経後の肥満 | 閉経後は脂肪組織でエストロゲンが作られるため | |
| 生活習慣関連 | 飲酒習慣 | アルコールがエストロゲンの濃度を高める可能性があるため |
| 喫煙 | 直接的な因果関係は確立していないが、関連が指摘されている | |
| 運動不足 | 適度な運動はリスクを低下させることが分かっている | |
| その他 | 家族歴(血縁者に乳がん患者がいる) | 遺伝的な要因が関わる可能性があるため |
乳がんの検診方法と受診の目安
症状がない段階で乳がんを発見するために、定期的な検診は非常に重要です。検診にはいくつかの方法があり、それぞれの特徴を理解して、自分に合った方法で受診を続けることが大切です。
乳がん検診の重要性
乳がん検診の最大の目的は、自覚症状が現れる前の早期の段階でがんを発見することです。早期に発見できれば、治療の選択肢が広がり、体への負担が少ない治療で治癒を目指せる可能性が高まります。
また、生存率も格段に向上します。日本の自治体では、40歳以上の女性を対象に2年に1度の乳がん検診を推奨しています。
主な検査方法
乳がん検診で主に行われるのは、「マンモグラフィ検査」と「超音波(エコー)検査」です。
これらはがんを発見するための得意分野が異なるため、年齢や乳房の状態によって使い分けたり、併用したりします。
マンモグラフィ検査
乳房を専用の装置で挟み、X線撮影を行う検査です。特に、しこりとして触れる前の段階の微細な石灰化(癌の初期サインの一つ)を見つけるのに優れています。
検査時には乳房を圧迫するため、多少の痛みを伴うことがあります。脂肪の多い乳房(閉経後の女性に多い)では、病変が見つけやすいとされています。
超音波(エコー)検査
乳房に超音波をあて、その反射波を画像化して内部の状態を調べる検査です。放射線被ばくの心配がなく、痛みもありません。
マンモグラフィでは病変が見つかりにくい高濃度乳房(若い女性に多い)でも、しこりを見つけるのが得意です。ただし、微細な石灰化の発見は不得意とされています。
検査方法の比較
| 項目 | マンモグラフィ検査 | 超音波(エコー)検査 |
|---|---|---|
| 得意な所見 | 微細な石灰化 | しこり(腫瘤) |
| 得意な乳房タイプ | 脂肪性乳房(閉経後など) | 高濃度乳房(若年層など) |
| 痛み・被ばく | 圧迫による痛みあり・放射線被ばくあり | 痛みなし・被ばくなし |
癌としての乳がんの進行度と分類
乳がんと診断された場合、次に行うのは、がんがどのくらい進行しているのか、どのような性質を持っているのかを詳しく調べることです。
これらは「病期(ステージ)」と「サブタイプ」と呼ばれ、治療方針を決める上で極めて重要な情報となります。
病期(ステージ)分類の考え方
乳がんのステージは、がんの進行度合いを示す指標で、主に3つの要素から決定します。
- T因子: がんの大きさ(しこりの直径)
- N因子: わきの下など、乳房近くのリンパ節への転移の有無と個数
- M因子: 骨や肺、肝臓など、乳房から離れた臓器への転移(遠隔転移)の有無
これらの組み合わせによって、ステージは0期からⅣ期までの5段階に分類されます。ステージが上がるほど、がんが進行していることを意味します。
ステージ0からⅣまでの特徴
各ステージは、がんの広がり方によって定義されます。ステージが進むにつれて治療はより全身的なものとなり、生存率にも影響します。しかし、どのステージであっても治療法は存在します。
各ステージの概要と5年相対生存率
| ステージ | がんの状態 | 5年相対生存率の目安 |
|---|---|---|
| 0期 | 非浸潤癌。がんが乳管内にとどまっている。 | ほぼ100% |
| Ⅰ期 | しこりが2cm以下で、リンパ節転移がない。 | 約99% |
| Ⅱ期 | しこりが2cmを超えるか、リンパ節転移がある。 | 約95% |
| Ⅲ期 | がんが乳房の皮膚や胸壁に広がっているか、リンパ節転移が広がっている。 | 約80% |
| Ⅳ期 | 骨、肺、肝臓などへの遠隔転移がある。 | 約39% |
※生存率はあくまで統計データであり、個人の状況によって異なります。
乳がんのサブタイプ分類
乳がんは、一つのがん細胞から増殖したものであっても、その性質は様々です。
がん細胞の表面にある「ホルモン受容体」と「HER2(ハーツー)タンパク」という2つの物質の発現状態を調べることで、乳がんをいくつかのタイプ(サブタイプ)に分類します。
この分類は、薬物療法の効果を予測し、最適な治療法を選択するために非常に重要です。
サブタイプ別の特徴と治療方針
| サブタイプ | 特徴 | 主な薬物療法 |
|---|---|---|
| ルミナルAタイプ | ホルモン受容体陽性、HER2陰性。増殖スピードが比較的遅い。 | ホルモン療法 |
| ルミナルBタイプ | ホルモン受容体陽性、HER2陰性または陽性。Aタイプより増殖が速い。 | ホルモン療法、化学療法、分子標的治療 |
| HER2陽性タイプ | ホルモン受容体陰性、HER2陽性。増殖スピードが速い。 | 抗HER2薬(分子標的治療)、化学療法 |
| トリプルネガティブ | ホルモン受容体陰性、HER2陰性。増殖スピードが速い。 | 化学療法、免疫チェックポイント阻害薬など |
乳がんの治療法と選択の考え方
乳がんの治療は、がんを完全に取り除くこと、再発を防ぐこと、そして生活の質(QOL)を維持することを目指して行います。
治療法は一つではなく、がんの状態や患者さん自身の希望に応じて、複数の方法を組み合わせて進めます。
乳がん治療の三本柱
乳がんの治療は、大きく分けて「手術(外科療法)」「薬物療法」「放射線治療」の3つが中心となります。手術と放射線治療は、がんが発生した場所とその周辺に直接働きかける「局所療法」です。
一方、薬物療法は、血液に乗って全身に作用する「全身療法」であり、目に見えない微小な転移にも効果を期待できます。
手術(外科療法)
手術は、がん組織を物理的に取り除く治療法で、乳がん治療の基本となります。手術の方法には、乳房の一部とがんを切除する「乳房温存手術」と、乳房全体を切除する「乳房切除術(全摘術)」があります。
どちらを選択するかは、がんの大きさや広がり、患者さんの希望などを考慮して決定します。
また、わきの下のリンパ節への転移を調べるために「センチネルリンパ節生検」を行い、転移があればリンパ節郭清(かくせい)を追加することがあります。
薬物療法
薬物療法は、薬を使ってがん細胞の増殖を抑えたり、破壊したりする治療です。
手術の前に行い、がんを小さくして手術しやすくする目的(術前薬物療法)や、手術後に行い、再発を予防する目的(術後補助療法)で用いられます。
また、転移・再発した場合の治療の中心となります。薬の種類は、がんのサブタイプによって選択します。
主な薬物療法の種類
| 治療法 | 作用 | 対象となるサブタイプ |
|---|---|---|
| ホルモン療法 | 女性ホルモンの働きを抑え、がんの増殖を抑制する | ルミナルタイプ(ホルモン受容体陽性) |
| 化学療法(抗がん剤) | 細胞分裂が活発な細胞(がん細胞)を攻撃する | 多くのサブタイプ(特に増殖が速いタイプ) |
| 分子標的治療 | がん細胞の増殖に関わる特定の分子だけを狙い撃ちする | HER2陽性タイプなど |
| 免疫チェックポイント阻害薬 | 免疫ががん細胞を攻撃する力を高める | トリプルネガティブの一部など |
放射線治療
放射線治療は、高エネルギーのX線をがん細胞にあてて破壊する治療法です。主に、乳房温存手術後の再発予防のために行います。
手術で取り切れなかった可能性のある、目に見えないがん細胞をたたくのが目的です。通常、手術後、数週間にわたって毎日少しずつ照射します。
その他、骨転移による痛みを和らげる目的などでも用いられます。
乳がん治療に伴う副作用と日常生活の工夫
乳がんの治療は、がん細胞を攻撃する一方で、正常な細胞にも影響を与えるため、様々な副作用が現れることがあります。副作用の種類や程度は、治療法や個人によって異なります。
どのような副作用が起こりうるかを知り、対処法を学ぶことで、治療中の生活の質を保つことができます。
各治療法に共通する副作用
治療法にかかわらず、多くの患者さんが経験するのが「倦怠感」です。体がだるく、疲れやすい状態が続くことがあります。無理をせず、休息を十分にとることが大切です。
また、治療への不安やストレスから、食欲不振や不眠に悩むこともあります。
手術後の注意点
手術後は、傷の痛みのほか、腕の動かしにくさや、リンパ節郭清を行った場合に腕がむくむ「リンパ浮腫」が起こることがあります。
リンパ浮腫は、一度発症すると完治が難しい場合があるため、日頃からのスキンケアや体重管理、腕に負担をかけすぎないといった予防が重要です。
薬物療法による副作用とケア
薬物療法は全身に作用するため、副作用も多岐にわたります。化学療法では、脱毛、吐き気・嘔吐、口内炎、白血球の減少による感染症のリスク増加などが代表的です。
ホルモン療法では、ほてりやのぼせといった更年期障害に似た症状や、関節痛などがみられます。分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害薬にも、それぞれ特有の副作用があります。
副作用のセルフケア例
| 副作用 | セルフケアの工夫 | 注意点 |
|---|---|---|
| 脱毛 | 医療用ウィッグや帽子の活用、頭皮の保湿ケア | 治療が終われば再び生えてくることがほとんど |
| 吐き気 | 食事を小分けにする、消化の良いものを選ぶ、においの少ない食品を選ぶ | 我慢せず、医師に相談して吐き気止めを処方してもらう |
| 口内炎 | 刺激の少ない歯磨き粉を使う、こまめなうがい | 痛みが強い場合は、食事の工夫や医療機関への相談が必要 |
再発や転移を防ぐための経過観察とケア
乳がんの初期治療が終了した後も、再発や転移の可能性はゼロではありません。そのため、定期的な検査と診察(経過観察)を続けることが大切です。
また、日々の生活習慣を見直すことも、再発リスクを低減させる上で重要と考えられています。
再発・転移とは
再発とは、治療によって目に見えなくなったがんが、再び現れることです。
手術した側の乳房やその周辺の皮膚、リンパ節に起こる「局所・領域再発」と、骨や肺、肝臓、脳など、離れた臓E器にがんが現れる「遠隔転移」があります。
遠隔転移は、初期治療の時点ですでに血液やリンパの流れに乗って全身に散らばっていた、目に見えない微小ながん細胞が、時間を経て大きくなったものと考えられています。
定期的な検査の重要性
治療後は、再発の早期発見や、治療による副作用・後遺症の管理、反対側の乳房に新たながんが発生していないかなどを確認するために、定期的に医療機関を受診します。
診察では、問診、視触診のほか、必要に応じてマンモグラフィや超音波検査、血液検査などを行います。
受診の頻度は、治療後すぐは数ヶ月に1回、時間が経つにつれて半年に1回、1年に1回と間隔が長くなっていくのが一般的です。
日常生活で心がけること
再発を完全に防ぐ方法は確立されていませんが、いくつかの生活習慣が再発リスクに関係することが分かっています。
特に、肥満は再発リスクを高めることが指摘されているため、適正な体重を維持することが重要です。バランスの取れた食事と、ウォーキングなどの適度な運動を習慣づけることが推奨されます。
禁煙や節度ある飲酒も大切です。
乳がん患者と家族のためのサポート体制
乳がんの診断や治療は、身体的な負担だけでなく、精神的、経済的にも大きな影響を及ぼすことがあります。
患者さん本人と、それを支えるご家族が、安心して治療に向き合えるように、様々なサポート体制が用意されています。一人で抱え込まず、これらの支援を積極的に活用しましょう。
医療機関でのサポート
治療を受ける病院には、様々な専門家がいます。医師や看護師はもちろん、薬の専門家である薬剤師、医療費や生活に関する相談に乗ってくれる医療ソーシャルワーカーなどがいます。
全国のがん診療連携拠点病院などには「がん相談支援センター」が設置されており、その病院にかかっていなくても誰でも無料で相談できます。
患者会やピアサポート
同じ病気を経験した人々と話すことは、大きな心の支えになります。患者会では、治療に関する情報交換や、日常生活の工夫、悩みなどを共有することができます。
ピアサポートとは、同じような体験をした仲間(ピア)が、対等な立場で相談に乗ってくれる活動です。医療者とは異なる視点からのアドバイスや共感が、孤独感の軽減につながります。
公的な支援制度
がんの治療には高額な医療費がかかることがありますが、経済的な負担を軽減するための公的な制度があります。
また、治療のために仕事を休んだり、辞めたりした場合の生活を支える制度も利用できます。
利用できる主な公的支援制度
| 制度名 | 内容 | 相談窓口 |
|---|---|---|
| 高額療養費制度 | 医療機関での支払いが、所得に応じた自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度。 | 加入している公的医療保険(健康保険組合、市区町村など) |
| 傷病手当金 | 病気やけがで会社を休み、給与が支払われない場合に、生活を保障するために支給される。 | 加入している公的医療保険 |
| 障害年金 | 病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取れる年金。 | 年金事務所、市区町村の年金窓口 |
よくある質問
ここでは、乳がんに関して多くの方が抱く疑問についてお答えします。
- 乳がんは遺伝しますか?
-
全ての乳がんが遺伝するわけではありません。乳がん全体のうち、5〜10%程度が遺伝的要因が強く関わっている「遺伝性乳がん」と考えられています。
血縁者に乳がんや卵巣がんになった人が複数いる、若くして乳がんになった人がいる、といった場合には、遺伝カウンセリングについて主治医に相談してみることを検討してもよいでしょう。
- 男性も乳がんになりますか?
-
はい、男性も乳がんになることがあります。頻度は非常にまれで、乳がん全体の1%未満ですが、男性にも乳腺組織があるため発症する可能性があります。
症状は女性の場合と同じく、胸のしこりや乳頭からの分泌物などです。気づいたときには進行しているケースも多いため、男性も胸の変化には注意が必要です。
- 治療中の食事で気をつけることはありますか?
-
特定の食品が乳がんに良い、あるいは悪いといった科学的根拠は確立されていません。基本は、主食・主菜・副菜のそろったバランスの良い食事を心がけることです。
ただし、副作用で食欲がない時や吐き気がある時は、無理せず食べられるものを少量ずつ摂るように工夫しましょう。
白血球が減少している時期は、感染予防のために生ものを避けるなどの注意が必要な場合もあります。
- 仕事と治療は両立できますか?
-
多くの人が仕事と治療を両立しています。治療法や副作用の程度、仕事の内容によって状況は異なりますが、最近では通院で治療が可能な薬物療法も増えています。
会社の制度(休暇制度、時短勤務など)を確認し、上司や同僚に相談して理解を得ることが大切です。病院のがん相談支援センターでも、仕事に関する相談に応じてくれます。
- 乳房再建はどのようなものですか?
-
乳房再建は、乳房切除術で失われた乳房を、形成外科の技術を用いて再建することです。
自分の体の一部(お腹や背中の組織)を使う方法と、シリコンインプラントなどの人工物を使う方法があります。
再建を行うタイミングは、乳がんの手術と同時に行う「一次再建」と、手術後しばらく経ってから行う「二次再建」があります。保険適用も拡大しており、希望する人が増えています。
乳がんと同じく、女性にとって注意が必要ながんの一つに「子宮頸がん」があります。
子宮頸がんは、主にヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因で発生し、20代から30代の若い世代での発症が増加しているのが特徴です。
このがんも、定期的な検診によって、がんになる前の段階(前がん病変)で発見し、治療することが可能です。
女性の体を守るためには、乳がんだけでなく、子宮頸がんについても正しい知識を持つことが大切です。ご自身の健康管理の一環として、子宮頸がんの予防や検診についても理解を深めてみませんか。
以上
参考文献
ZUBAIR, M.; WANG, S.; ALI, N. Advanced approaches to breast cancer classification and diagnosis. Frontiers in Pharmacology, 2021, 11: 632079.
WAKS, Adrienne G.; WINER, Eric P. Breast cancer treatment: a review. Jama, 2019, 321.3: 288-300.
RIVAS, Fernando Wladimir Silva, et al. Comprehensive diagnosis of advanced-stage breast cancer: exploring detection methods, molecular subtypes, and demographic influences-A cross-sectional study. Clinics, 2024, 79: 100510.
ORRANTIA-BORUNDA, Erasmo, et al. Subtypes of breast cancer. Breast Cancer [Internet], 2022.
SO, Winnie KW, et al. Symptom clusters experienced by breast cancer patients at various treatment stages: a systematic review. Cancer Medicine, 2021, 10.8: 2531-2565.
TESTA, Ugo; CASTELLI, Germana; PELOSI, Elvira. Breast cancer: a molecularly heterogenous disease needing subtype-specific treatments. Medical Sciences, 2020, 8.1: 18.
PASHAYAN, Nora, et al. Personalized early detection and prevention of breast cancer: ENVISION consensus statement. Nature reviews Clinical oncology, 2020, 17.11: 687-705.
TRAYES, Kathryn P.; COKENAKES, Sarah EH. Breast cancer treatment. American family physician, 2021, 104.2: 171-178.
JOHNSON, Karen S.; CONANT, Emily F.; SOO, Mary Scott. Molecular subtypes of breast cancer: a review for breast radiologists. Journal of Breast Imaging, 2021, 3.1: 12-24.
BHUSHAN, Arya; GONSALVES, Andrea; MENON, Jyothi U. Current state of breast cancer diagnosis, treatment, and theranostics. Pharmaceutics, 2021, 13.5: 723.