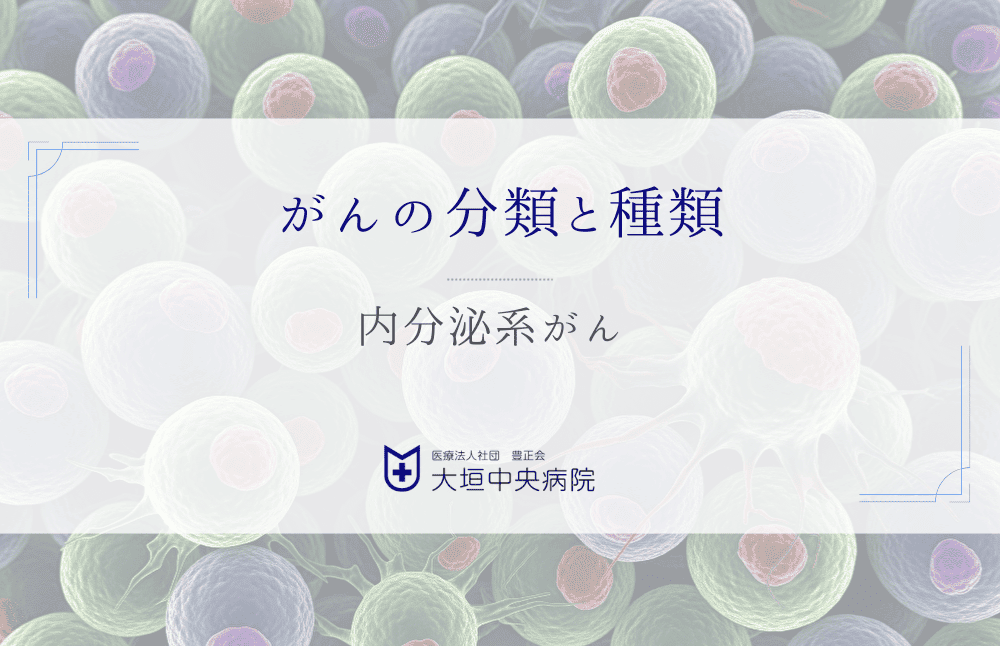私たちの体には、生命活動を維持するために不可欠な「ホルモン」を分泌する「内分泌臓器」が全身に存在します。内分泌系がんは、これらの臓器に発生する悪性腫瘍の総称です。
発生する臓器によってその性質や症状、治療法は大きく異なります。また、中には「希少がん」に分類されるものも少なくありません。
この記事では、内分泌系がんの全体像を掴み、代表的ながんである甲状腺がんや副腎がん、そして神経内分泌腫瘍(NET/NEC)などについて、その特徴から診断、治療法までを詳しく解説します。
内分泌系がんの概要と主な種類
私たちの体の機能を調整するホルモンは、内分泌腺と呼ばれる臓器で作られ、血液中に放出されます。このホルモンを産生する臓器群に発生する悪性腫瘍が内分泌系がんです。
全身に影響を及ぼすホルモンの異常や、腫瘍そのものによる圧迫など、多彩な症状が現れるのが特徴です。ここでは、内分泌系がんの基本的な知識と、その多様な種類について見ていきましょう。
内分泌系とホルモンの働き
内分泌系は、甲状腺、副腎、下垂体、膵臓(すいぞう)のランゲルハンス島、精巣、卵巣など、全身に点在する臓器や細胞で構成されます。
これらの器官が生み出すホルモンは、体の成長、代謝、ストレス反応、生殖機能など、生命を維持するための様々な働きを調整する化学物質です。
各ホルモンは特定の標的細胞に作用し、体のバランスを精密にコントロールしています。
内分泌系がんとは
内分泌系がんは、これらのホルモン産生細胞ががん化したものです。がん細胞が過剰にホルモンを産生する場合(機能性腫瘍)と、ホルモンを産生しない場合(非機能性腫瘍)があります。
機能性腫瘍では、特定のホルモンが過剰になることで特有の症状が現れ、病気の発見につながることがあります。
一方、非機能性腫瘍は、腫瘍が大きくなって周囲の臓器を圧迫するまで症状が出にくく、発見が遅れる傾向があります。
希少がんとしての一面
内分泌系がんの多くは、発生頻度が低く「希少がん」に分類されます。
希少がんとは、人口10万人あたりの年間発生数が6例未満のがんを指し、診断や治療に関する情報が少なく、専門とする医師や医療機関も限られるという課題があります。
そのため、正確な診断と適切な治療を受けるためには、経験豊富な専門医のもとで診療を進めることが重要です。
神経内分泌腫瘍(NET/NEC)について
内分泌系がんの中でも特別なグループとして、神経内分泌腫瘍があります。これは、神経細胞と内分泌細胞の両方の性質を併せ持つ「神経内分泌細胞」から発生する腫瘍です。
消化管や膵臓、肺など、全身の様々な場所に発生する可能性があります。
進行の速さによって、比較的おとなしい「神経内分泌腫瘍(NET)」と、増殖が速く悪性度の高い「神経内分泌がん(NEC)」に大別されます。
NETとNECの主な違い
| 項目 | 神経内分泌腫瘍(NET) | 神経内分泌がん(NEC) |
|---|---|---|
| 増殖の速さ | 比較的ゆっくり | 速い |
| 悪性度 | 低い~中間 | 高い |
| 治療方針 | 手術、薬物療法(ホルモン療法など) | 化学療法(抗がん剤治療)が中心 |
甲状腺がんの特徴と治療の考え方
甲状腺は、のどぼとけの下にある蝶のような形をした臓器で、体の新陳代謝を活発にする甲状腺ホルモンを分泌しています。
甲状腺がんは、内分泌系がんの中では比較的発生頻度が高く、特に女性に多く見られます。
多くは進行が緩やかで予後が良いとされますが、種類によっては進行が速いものもあり、正確な診断に基づく治療方針の決定が大切です。
甲状腺がんの主な種類と特徴
甲状腺がんは、組織の型(組織型)によっていくつかの種類に分類され、それぞれ性質や治療法が異なります。最も多いのが乳頭がんで、甲状腺がん全体の9割以上を占めます。
代表的な甲状腺がんの分類
| 種類 | 特徴 | 進行の速さ |
|---|---|---|
| 乳頭がん | 最も多く、リンパ節に転移しやすい | 非常にゆっくり |
| 濾胞がん | 血液の流れに乗って肺や骨などに転移しやすい | 比較的ゆっくり |
| 髄様がん | 遺伝性のことがある。カルシトニンを産生する | 様々 |
| 未分化がん | 非常にまれだが、進行が極めて速く悪性度が高い | 非常に速い |
診断のための検査
甲状腺がんの診断は、首のしこりや腫れをきっかけに行われることが多いです。問診や触診の後、より詳しく調べるために画像検査や細胞の検査を実施します。
これらの検査結果を総合的に判断して、がんの有無や種類、広がりを評価します。
超音波(エコー)検査と細胞診
超音波検査は、しこりの大きさ、形、内部の性状などを調べるのに有効な検査です。この検査でがんが疑われた場合、診断を確定するために穿刺吸引細胞診を行います。
これは、超音波でしこりの位置を確認しながら細い針を刺し、中の細胞を吸引して顕微鏡で調べる検査です。体への負担が少なく、診断精度も高い重要な検査です。
甲状腺がんの治療方針
甲状腺がんの治療の基本は手術による切除です。がんの種類、大きさ、広がり(転移の有無など)に応じて、甲状腺の切除範囲やリンパ節の郭清範囲を決定します。
手術後の状態によっては、追加の治療が必要になることもあります。
手術と薬物療法
手術では、がんのある側の甲状腺葉を切除する「葉切除」や、甲状腺をすべて摘出する「全摘術」などを行います。手術後は、甲状腺ホルモンが不足するため、ホルモン剤を内服して補充する必要があります。
また、進行した甲状腺がんに対しては、分子標的薬という種類の薬物療法を行うこともあります。
これらの薬剤は、がん細胞の増殖に関わる特定の分子の働きを妨げることで、がんの進行を抑える効果が期待できます。
放射性ヨウ素内用療法
甲状腺がんの中でも乳頭がんや濾胞がんは、甲状腺ホルモンの材料であるヨウ素を取り込む性質を持っています。この性質を利用したのが放射性ヨウ素内用療法です。
放射線を出すヨウ素をカプセルで内服すると、薬が甲状腺がんの細胞に集まり、内側から放射線を照射してがん細胞を破壊します。
主に、手術で取りきれなかった微小ながんや、肺などへの遠隔転移に対する治療として行います。
甲状腺がんの生存率について
国立がん研究センターのデータによると、甲状腺がんの5年相対生存率は非常に高く、特に乳頭がんや濾胞がんでは良好な経過を期待できます。
ただし、未分化がんのように進行が速いタイプや、発見が遅れた場合はこの限りではありません。早期発見と適切な治療が、良好な予後につながる鍵となります。
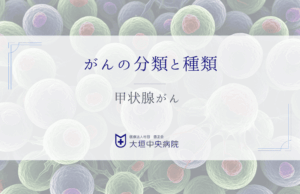
副腎がんの症状と診断方法
副腎は、左右の腎臓の上に乗っている小さな臓器で、生命維持に必要な様々なホルモンを分泌しています。
外側の皮質からはアルドステロン、コルチゾール、性ホルモンが、内側の髄質からはアドレナリンやノルアドレナリンが分泌されます。
副腎がんは非常にまれな希少がんであり、ホルモンを過剰に産生するタイプと、産生しないタイプに分けられます。
副腎がんによって引き起こされる症状
副腎がんの症状は、ホルモン産生の有無によって大きく異なります。機能性の場合はホルモン過剰による症状が、非機能性の場合は腫瘍が大きくなることによる圧迫症状が主体となります。
ホルモン過剰産生による主な症状
| 過剰なホルモン | 関連する症候群 | 主な症状 |
|---|---|---|
| コルチゾール | クッシング症候群 | 満月様顔貌、中心性肥満、高血圧、高血糖 |
| アルドステロン | 原発性アルドステロン症 | 高血圧、低カリウム血症 |
| 男性ホルモン | 男性化・思春期早発 | にきび、多毛、声の低音化 |
これらの症状は、他の病気でも見られることがあるため、副腎がんの発見が遅れる原因にもなります。気になる症状が続く場合は、内分泌を専門とする医師に相談することが重要です。
診断に至るまでの検査の流れ
症状や健康診断などで副腎の異常が疑われた場合、診断を確定し、治療方針を決めるためにいくつかの検査を段階的に行います。
ホルモンを産生しているかどうかを調べる検査と、腫瘍の場所や大きさを特定する検査を組み合わせて進めます。
- 血液検査・尿検査
- CT検査
- MRI検査
- 副腎静脈サンプリング
画像検査とホルモン検査
まず、血液検査や尿検査でホルモン値を測定し、ホルモンの過剰産生がないかを確認します。次に、CT検査やMRI検査といった画像検査で、副腎に腫瘍があるか、その大きさや周囲への広がりを評価します。
これらの検査で副腎がんが強く疑われ、手術が検討される場合には、さらに精密な検査を追加することもあります。
診断が難しい場合は、複数の専門家がいる施設でのセカンドオピニオンも有効な選択肢です。
治療法の選択
副腎がんの治療は、がんが副腎内にとどまっている場合、手術による切除が第一選択となります。手術でがんを完全に取り除くことが、根治を目指す上で最も重要です。
腫瘍が大きい場合や、周囲の臓器に浸潤している場合は、拡大手術が必要になることもあります。手術で取りきれない場合や、すでに他の臓器へ転移している場合には、薬物療法が中心となります。
ミトタンという薬剤が副腎がんに対する特有の治療薬として用いられます。
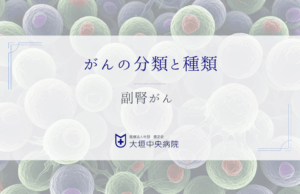
その他の内分泌系がんと関連疾患
甲状腺や副腎以外にも、ホルモンを分泌する臓器は体内に存在し、それぞれに腫瘍が発生する可能性があります。特に膵臓や消化管にできる神経内分泌腫瘍は、近年注目されています。
また、遺伝的な要因で複数の内分泌臓器に腫瘍ができやすい病気もあります。
膵臓に発生する神経内分泌腫瘍
膵臓には、血糖値を調節するインスリンやグルカゴンといったホルモンを分泌するランゲルハンス島という細胞の集まりがあります。膵神経内分泌腫瘍(pNET)は、この細胞から発生する比較的まれな腫瘍です。
ホルモンを過剰に産生する「機能性」と、産生しない「非機能性」に分けられます。
機能性pNETの代表的な種類
| 腫瘍名 | 過剰産生されるホルモン | 主な症状 |
|---|---|---|
| インスリノーマ | インスリン | 低血糖発作(意識障害、けいれん) |
| ガストリノーマ | ガストリン | 難治性の胃・十二指腸潰瘍 |
| グルカゴノーマ | グルカゴン | 血糖値の上昇、特徴的な皮疹 |
消化管神経内分泌腫瘍
消化管(胃、十二指腸、小腸、虫垂、大腸など)にも神経内分泌細胞は広く分布しており、そこから神経内分泌腫瘍が発生することがあります。
かつては「カルチノイド」と呼ばれていましたが、現在では神経内分泌腫瘍(NET)という名称に統一されています。
多くは無症状で、内視鏡検査(胃カメラや大腸カメラ)の際に偶然発見されることも少なくありません。
- 胃NET
- 十二指腸NET
- 小腸NET
- 虫垂NET
- 直腸NET
多発性内分泌腫瘍症(MEN)
多発性内分泌腫瘍症は、遺伝子の変異が原因で、複数の内分泌臓器に腫瘍(良性・悪性を含む)が発生しやすい遺伝性の病気です。原因となる遺伝子の種類によって1型(MEN1)と2型(MEN2)に大別されます。
MENが疑われる場合は、遺伝カウンセリングを受けた上で遺伝子検査を行うことがあります。血縁者にも同じ病気の可能性があるため、家族を含めた長期的なフォローアップが重要です。
MENの主な発生腫瘍
| 型 | 主な発生部位 |
|---|---|
| MEN1 | 下垂体、副甲状腺、膵臓 |
| MEN2 | 甲状腺(髄様がん)、副腎(褐色細胞腫)、副甲状腺 |
内分泌系がんの予防と再発防止のための経過観察
内分泌系がんの多くは、発生の明確な原因がわかっておらず、確実な予防法は確立されていません。
そのため、治療後の再発や新たな病変の出現を早期に発見するための、長期的な経過観察が非常に重要になります。
治療が終わった後も、定期的に専門医の診察を受け、必要な検査を継続することが、健やかな生活を維持する上で大切です。
治療後の定期的な経過観察の重要性
内分泌系がんの治療が終わった後も、体の中にわずかに残ったがん細胞が再び増殖し、再発する可能性があります。また、元の場所とは違う臓器にがんが現れる「転移」が起こることもあります。
特に、進行が緩やかなタイプのがんでは、治療から5年、10年以上経ってから再発することもあるため、長期にわたるフォローアップが必要です。
経過観察で行う主な検査
経過観察の間隔や検査内容は、がんの種類、進行度、行われた治療法などによって異なります。主治医と相談しながら、個々の状態に合わせた計画を立てて進めます。
| 検査の種類 | 目的 | 具体例 |
|---|---|---|
| 血液検査 | 腫瘍マーカーやホルモン値の変動を調べる | サイログロブリン(甲状腺がん)、クロモグラニンA(NET)など |
| 画像検査 | 局所再発や遠隔転移の有無を確認する | 超音波検査、CT、MRI、PET検査、ソマトスタチン受容体シンチグラフィ |
| 内視鏡検査 | 消化管NETの再発をチェックする | 胃カメラ、大腸カメラ |
ホルモン補充療法と体調管理
手術で甲状腺や副腎などの内分泌臓器を摘出した場合、その臓器が作っていたホルモンが不足し、体に様々な不調が現れます。これを防ぐために、不足したホルモンを薬で補う「ホルモン補充療法」を行います。
例えば、甲状腺を全摘した場合は甲状腺ホルモン薬を、副腎を摘出した場合は副腎皮質ホルモン薬を生涯にわたって服用する必要があります。
薬を正しく服用し、定期的な血液検査でホルモンバランスを適切に保つことが、治療後のQOL(生活の質)を維持する上で重要です。
よくある質問
- 内分泌系がんは遺伝しますか?
-
ほとんどの内分泌系がんは遺伝しませんが、一部に遺伝が強く関与するものがあります。
代表的なものとして、甲状腺髄様がんや副腎褐色細胞腫の一部が含まれる「多発性内分泌腫瘍症(MEN)」や、家族性甲状腺髄様がんなどがあります。
血縁者に同じような病気の方がいる場合は、主治医にそのことを伝え、遺伝カウンセリングなどについて相談することをお勧めします。
- 治療によるホルモンバランスの乱れはどのように対処しますか?
-
手術や薬物療法によってホルモンを産生する臓器の機能が損なわれた場合、ホルモン補充療法を行います。これは、不足しているホルモンを薬として内服する治療法です。
定期的に血液検査を行い、ホルモン値を適切な範囲に保つように薬の量を調整します。
体調の変化を感じた際には、自己判断で薬をやめたり量を変更したりせず、必ず主治医や薬剤師に相談することが大切です。
- 国立がん研究センターなどの専門機関で相談できますか?
-
はい、相談できます。国立がん研究センターをはじめとするがん診療連携拠点病院では、がんに関する様々な相談を受け付ける「がん相談支援センター」を設置しています。
希少がんであることの多い内分泌系がんについては、情報が少なく不安を感じることも多いと思います。
このような施設では、病気のこと、治療法、療養生活のことなど、専門の相談員が無料で対応してくれます。セカンドオピニオンについても相談可能です。
- 神経内分泌腫瘍(NET)の生存率はどのくらいですか?
-
神経内分泌腫瘍(NET)の生存率は、腫瘍が発生した臓器、腫瘍の悪性度(グレード)、病気の進行度(ステージ)、転移の有無などによって大きく異なります。
一般的に、進行が緩やかで悪性度の低いNETは、たとえ転移があったとしても長期的な経過をたどることが多いとされます。
一方で、増殖が速い神経内分泌がん(NEC)は、予後が厳しい傾向にあります。詳しい予後については、ご自身の病状を最もよく把握している主治医に確認することが重要です。
以上
参考文献
URI, Inbal; GROZINSKY-GLASBERG, Simona. Current treatment strategies for patients with advanced gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NETs). Clinical diabetes and endocrinology, 2018, 4.1: 16.
KALISZEWSKI, Krzysztof, et al. Advances in the diagnosis and therapeutic management of gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms (GEP-NENs). Cancers, 2022, 14.8: 2028.
DEL RIVERO, Jaydira, et al. Systemic therapy for tumor control in metastatic well-differentiated gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors: ASCO guideline. Journal of clinical oncology, 2023, 41.32: 5049-5067.
ITO, Tetsuhide, et al. JNETS clinical practice guidelines for gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms: diagnosis, treatment, and follow-up: a synopsis. Journal of gastroenterology, 2021, 56.11: 1033-1044.
CIVES, Mauro; STROSBERG, Jonathan. An update on gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors. Oncology, 2014, 28.9: 749-749.
SEDLACK, Andrew JH, et al. Update in the management of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors. Cancer, 2024, 130.18: 3090-3105.
MODLIN, Irvin M., et al. Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours. The lancet oncology, 2008, 9.1: 61-72.
MOHAMED, Amr; STROSBERG, Jonathan R. Medical management of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors: current strategies and future advances. Journal of nuclear medicine, 2019, 60.6: 721-727.
DONADIO, Mauro D.; BRITO, Ângelo B.; RIECHELMANN, Rachel P. A systematic review of therapeutic strategies in gastroenteropancreatic grade 3 neuroendocrine tumors. Therapeutic Advances in Medical Oncology, 2023, 15: 17588359231156218.
GARCIA-CARBONERO, Rocio, et al. ENETS consensus guidelines for high-grade gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors and neuroendocrine carcinomas. Neuroendocrinology, 2016, 103.2: 186-194.