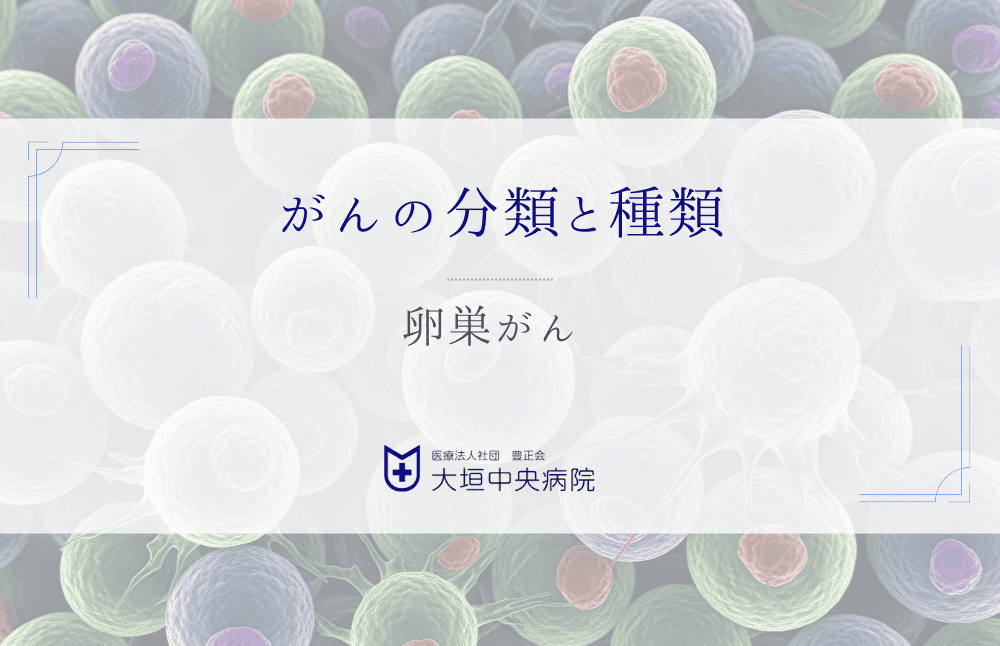卵巣がんは、初期には自覚できる症状がほとんどなく、「沈黙のがん(サイレントキラー)」とも呼ばれます。そのため、発見が遅れがちになる傾向があり、多くの女性にとって大きな不安の種です。
しかし、自身の身体が発するささいなサインに気づき、卵巣がんに関する正しい知識を持つことは、がんと向き合い、より良い治療選択をする上で非常に重要です。
この記事では、卵巣がんの基本的な情報から、診断方法、標準的な治療、そして遺伝との深い関わりまでを網羅的に解説し、患者さんとそのご家族が抱える不安を和らげ、希望を持って歩むための一助となることを目指します。
卵巣がんの基本知識 – 発生部位と特徴
卵巣がんと向き合う第一歩は、その発生部位である「卵巣」の役割と、がんの基本的な特徴を理解することから始まります。
骨盤の奥深くに位置するこの小さな臓器が、なぜがんの温床となり得るのか、その背景を知ることが大切です。
卵巣の働きとがんの発生部位
卵巣は子宮の両側に一つずつ存在する、親指の頭ほどの大きさの臓器です。
女性の性周期をコントロールする女性ホルモン(エストロゲンとプロゲステロン)を分泌し、妊娠に必要な卵子を成熟させて排出(排卵)するという、二つの重要な役割を担っています。
卵巣がんは、この卵巣を構成するさまざまな細胞から発生する悪性腫瘍の総称です。
卵巣の主な機能
| 機能 | 内容 | 関連するがん |
|---|---|---|
| 卵子の成熟と排卵 | 妊娠の成立に不可欠な卵子を育て、放出する。 | 胚細胞腫瘍 |
| 女性ホルモンの分泌 | エストロゲンやプロゲステロンを分泌し、女性らしい身体を維持する。 | 性索間質性腫瘍 |
| 表面の保護 | 卵巣の表面は上皮細胞という一層の細胞で覆われている。 | 上皮性卵巣がん |
卵巣がんの主な特徴
卵巣がんの最大の原因はまだ完全には解明されていませんが、いくつかのリスク因子が知られています。
排卵の回数が多いこと(出産経験がない、初経が早い、閉経が遅いなど)が、卵巣表面の上皮が修復と再生を繰り返す過程で、がん化の一因になると考えられています。
また、子宮内膜症を持つ人は、卵巣がん(特に類内膜がんや明細胞がん)を発症するリスクが少し高まることが分かっています。
なぜ卵巣がんは「沈黙のがん」と呼ばれるのか
卵巣がんは、他のがんと比較しても特に発見が難しいことで知られています。その理由は、卵巣が位置する場所と、がんの進行様式にあります。
症状が出ないまま静かに進行するため、多くの人が気づかないうちに進展してしまうのです。
自覚症状が現れにくい構造的な理由
卵巣は、骨盤の奥深く、周りにスペースがある場所に位置しています。そのため、腫瘍がある程度の大きさになるまで、周囲の臓器を圧迫することがありません。
痛みや不快感といった自覚症状が出にくく、がんが静かに成長するための「猶予」を与えてしまうのです。これが「沈黙のがん」と呼ばれるゆえんです。
進行してから気づくケースが多い背景
症状が乏しいため、多くの場合はんがお腹全体に広がり、腹水が溜まるなど、進行した状態(進行がん)になってから発見されます。
お腹が張る、食欲がないといった症状で医療機関を受診し、初めて卵巣がんが判明するケースは少なくありません。
有効な検診方法が確立されていないことも、早期発見を難しくしている一因です。
卵巣がんと他の婦人科がんの初期症状の比較
| がんの種類 | 主な初期症状 | 発見のきっかけ |
|---|---|---|
| 卵巣がん | ほとんどない、または非特異的(腹部の張りなど) | 進行してからの症状、他の理由での検査 |
| 子宮頸がん | 不正出血、性交時出血 | 症状、子宮頸がん検診 |
| 子宮体がん | 不正出血(特に閉経後) | 症状(不正出血) |
初期症状が見逃されやすい理由と注意すべき兆候
卵巣がんの初期症状は、他の病気や日常的な体調不良と非常によく似ています。そのため、多くの人が「いつものこと」と見過ごしてしまいがちです。
しかし、注意深く自身の身体の変化を観察することで、早期発見につながるサインを捉えることも可能です。
日常的な不調と似ている初期症状
卵巣がんによって現れる可能性のある初期の症状は、胃腸の不調や便秘、加齢による体型の変化などと区別がつきにくいものばかりです。
これらの症状が一つだけ現れるというよりは、複数が持続的に続く場合に注意が必要です。
腹部の膨満感や違和感
最もよく見られる症状の一つが、お腹の張りです。食べ過ぎでもないのにお腹が張る、ウエストがきつくなった、といった変化が挙げられます。
これは、腫瘍そのものが大きくなることや、腹水が溜まることが原因で起こります。食欲不振や、少し食べただけですぐに満腹感を覚えるといった症状も伴うことがあります。
頻尿や便秘
腫瘍が大きくなるにつれて、前方に位置する膀胱や後方にある直腸を圧迫することがあります。その結果、トイレが近くなったり(頻尿)、便が出にくくなったり(便秘)することがあります。
これらは非常にありふれた症状であるため、卵巣がんのサインとはなかなか結びつきません。
注意すべき初期症状
- お腹の張り、膨満感
- 食欲不振、早期満腹感
- 骨盤部や腹部の痛み
- 頻尿、尿意切迫感
- 原因不明の体重減少または増加
注意すべきサインとセルフチェックの重要性
上記のような症状が2週間以上続く場合や、徐々に悪化する場合には、婦人科の受診を検討することが大切です。
特に、ご家族に乳がんや卵巣がんになった方がいる場合や、子宮内膜症の診断を受けている方は、定期的な婦人科検診を心がけることが重要です。
初期症状と間違えやすい他の疾患
| 卵巣がんの可能性のある症状 | 考えられる他の疾患・状態 |
|---|---|
| 腹部の膨満感 | 過敏性腸症候群、便秘、消化不良 |
| 頻尿 | 膀胱炎、過活動膀胱 |
| 骨盤痛 | 月経困難症、子宮内膜症、骨盤内炎症性疾患 |
卵巣がんの種類と組織型による違い
「卵巣がん」と一括りに呼ばれますが、実際には発生した細胞の種類(組織型)によって、いくつかの異なるタイプに分類されます。
この組織型の違いは、がんの性質、進行の速さ、治療法への反応性などに大きく影響するため、正確な診断が治療方針を決定する上で極めて重要です。
主な卵巣がんの分類
卵巣がんは、発生起源によって大きく3つに分けられます。日本で発生する卵巣がんの約90%は「上皮性卵巣がん」です。
上皮性卵巣がん
卵巣の表面を覆う上皮細胞から発生するがんで、最も頻度が高いタイプです。さらにいくつかの組織型に細分化され、それぞれ性質が異なります。
進行した状態で発見されることが多いのが特徴です。
胚細胞腫瘍
卵子のもとになる胚細胞から発生する腫瘍です。比較的若い世代(10代~20代)に多く見られます。
進行が速いものが多いですが、化学療法(抗がん剤治療)が非常によく効くという特徴があります。
性索間質性腫瘍
ホルモンを産生する性索間質細胞から発生する腫瘍です。他のタイプと比べて稀で、比較的ゆっくり進行することが多いです。
腫瘍がホルモンを産生するため、不正出血や月経異常などの症状で気づかれることもあります。
組織型ごとの特徴と治療方針への影響
特に上皮性卵巣がんは、組織型によって治療方針や予後が変わってきます。例えば、漿液性がんは最も多く、BRCA遺伝子変異との関連が深いことが知られています。
一方で明細胞がんは、抗がん剤が効きにくいことがあり、子宮内膜症との関連が指摘されています。
卵巣がんの主な組織型と特徴(上皮性)
| 組織型 | 頻度 | 特徴 |
|---|---|---|
| 漿液性がん | 最も多い | BRCA遺伝子変異との関連が深い。進行が速い傾向。 |
| 類内膜がん | 2番目に多い | 子宮内膜症との関連。比較的予後は良好。 |
| 明細胞がん | 比較的多い | 子宮内膜症との関連。抗がん剤が効きにくいことがある。 |
| 粘液性がん | 比較的少ない | 腫瘍が大きくなりやすい。虫垂などからの転移との鑑別が必要。 |
腫瘍マーカーと画像検査による診断方法
卵巣がんが疑われる場合、確定診断とがんの広がりを正確に把握するために、いくつかの検査を組み合わせて行います。
内診から始まり、血液検査、画像検査を経て、最終的には手術で摘出した組織を調べる病理診断でがんの種類を確定します。
診断の第一歩となる内診と超音波検査
婦人科での診察では、まず内診(触診)と経腟超音波検査(エコー検査)を行います。内診では、医師が指を腟に入れ、もう一方の手でお腹を押さえることで、子宮や卵巣の大きさ、形、硬さなどを調べます。
超音波検査では、プローブと呼ばれる細い器具を腟内に挿入し、卵巣の内部の様子や腫瘍の有無、その性状(液体が溜まった袋状か、固形成分があるかなど)を詳細に観察します。
血液検査で調べる腫瘍マーカーの役割
腫瘍マーカーは、がん細胞が作り出す特殊な物質で、血液検査で測定します。卵巣がんの診断補助や、治療効果の判定、再発のモニタリングに有用です。
ただし、腫瘍マーカーの値は、がん以外の要因(子宮内膜症、月経、妊娠、炎症など)でも上昇することがあり、逆にがんがあっても正常値を示すこともあるため、この検査だけでがんの有無を確定することはできません。
CA125などの代表的なマーカー
卵巣がん、特に漿液性がんで高値を示すことが多い代表的な腫瘍マーカーがCA125です。その他にも、組織型によってCA19-9やCEAなどが参考にされます。
これらのマーカーを複数組み合わせることで、診断の精度を高めます。
CT・MRIによる画像診断の重要性
超音波検査で卵巣の腫れが見つかった場合、さらに詳しい情報を得るためにCT検査やMRI検査といった画像検査を行います。
これらの検査は、腫瘍の大きさや性質、周囲の臓器への広がり(浸潤)、リンパ節や他の臓器への転移の有無を評価するために不可欠です。
この情報が、後の手術計画や治療方針を立てる上で重要な判断材料となります。
卵巣がんの診断に用いる主な検査
| 検査名 | 目的 | わかること |
|---|---|---|
| 内診・超音波検査 | 卵巣の腫れの有無や性状の確認 | 腫瘍の大きさ、形、内部の様子 |
| 腫瘍マーカー(血液検査) | 診断の補助、治療効果判定、再発の監視 | CA125などの値。がんの勢いの指標。 |
| CT・MRI検査 | がんの広がり(ステージ)の評価 | 腫瘍の詳細な位置、転移の有無 |
病期分類と治療方針の決定プロセス
各種検査によって得られた情報をもとに、がんがどの程度進行しているかを評価します。これを病期(ステージ)分類と呼びます。
ステージは、がんの治療方針を決定し、今後の見通し(予後)を予測するための最も重要な指標の一つです。
FIGO分類に基づくステージの定義
卵巣がんの病期分類には、国際産科婦人科連合(FIGO)が定めた分類法を世界共通で用います。この分類は、主に手術の際に行う所見に基づいて最終的に決定されます。
ステージはⅠ期からⅣ期までに分けられ、数字が大きくなるほどがんが進行していることを意味します。
ステージごとのがんの広がり
ステージは、がんが卵巣内にとどまっているか、骨盤内に広がっているか、腹腔内(お腹の中)や他の臓器にまで転移しているかによって決まります。
卵巣がんのFIGO病期分類(簡略版)
| ステージ | がんの広がり |
|---|---|
| Ⅰ期 | がんが片方または両方の卵巣に限局している状態。 |
| Ⅱ期 | がんが骨盤内(子宮、卵管など)に広がっている状態。 |
| Ⅲ期 | がんが骨盤を越えて腹腔内に広がっている(腹膜播種)、または後腹膜リンパ節に転移がある状態。 |
| Ⅳ期 | がんが肝臓や肺など、腹腔を越えた遠隔臓器に転移している状態(遠隔転移)。 |
総合的に判断する治療方針
最終的な治療方針は、この手術によって確定したステージ、がんの組織型、患者さん自身の年齢や全身状態、合併症の有無、そして何よりも患者さんの希望などを総合的に考慮して決定します。
医師と患者さんが十分に話し合い、納得のいく治療法を選択することが大切です。
手術と化学療法を組み合わせた標準治療
卵巣がんの治療は、手術と化学療法(抗がん剤治療)を組み合わせるのが基本です。
がんを物理的に取り除く手術と、全身に散らばった可能性のあるがん細胞を叩く化学療法を組み合わせることで、根治を目指し、再発のリスクを低減させます。
治療の基本となる手術(開腹手術)
卵巣がん治療の根幹をなすのが手術です。手術の目的は、病期を正確に診断することと、がん組織を可能な限り取り除くことの二つです。
お腹を縦に大きく切開する開腹手術が標準的な方法です。
腫瘍を可能な限り取り除く初回腫瘍減量手術
進行した卵巣がんでは、目に見えるがんを全て取り除くこと(完全切除)が、その後の予後を大きく改善することが分かっています。
そのため、両側の卵巣と卵管、子宮、大網(胃から垂れ下がっている脂肪の膜)、そして転移している可能性のあるリンパ節や腹膜などを切除します。これを初回腫瘍減量手術と呼びます。
手術後に行う化学療法(抗がん剤治療)
手術で目に見えるがんを取り除いた後も、画像には映らない微小ながん細胞が体内に残っている可能性があります。
これらの細胞が将来的に再発の原因となるため、術後に化学療法を行い、全身のがん細胞を攻撃します。これを術後補助化学療法と呼びます。
代表的な抗がん剤の種類と投与方法
卵巣がんの化学療法では、タキサン系薬剤(パクリタキセルなど)とプラチナ系薬剤(カルボプラチンなど)を組み合わせるTC療法が標準治療として広く行われています。
通常、3~4週間に1回の点滴を、合計6回程度繰り返します。
化学療法で考慮する点
- 治療スケジュール
- 副作用の種類と程度
- 副作用への対策(支持療法)
- 治療効果の評価
維持療法の導入とPARP阻害薬
初回化学療法がよく効いた後、がんの再発を遅らせることを目的として、維持療法を行うことがあります。
特に、BRCA遺伝子変異がある場合や、相同組換え修復欠損(HRD)という状態が認められる卵巣がんに対しては、PARP阻害薬という種類の分子標的薬が維持療法として高い効果を発揮します。
この薬は、がん細胞が持つDNA修復機能の弱点を突いて、がん細胞だけを選択的に死滅させる働きをします。
遺伝性要因とBRCA遺伝子変異の関係
卵巣がんの中には、特定の遺伝子の変異が原因で発症するものがあります。その代表が「遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)」です。
自分のがんが遺伝と関係しているかを知ることは、ご自身の今後の治療方針だけでなく、血縁者の健康管理にとっても重要な情報となります。
遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)とは
HBOCは、BRCA1またはBRCA2という遺伝子の生まれつきの変異が原因で、乳がんや卵巣がん、その他のがん(前立腺がん、膵臓がんなど)になりやすくなる遺伝性の疾患です。
卵巣がんと診断された患者さんのうち、約15~20%がHBOCであると報告されています。
BRCA1/2遺伝子変異とがんのリスク
BRCA1/2遺伝子は、本来、傷ついたDNAを修復し、がんの発生を抑える働きを持っています。
しかし、この遺伝子に変異があると、その機能が十分に働かなくなり、がんを発症するリスクが高まります。
BRCA遺伝子変異と生涯がん発症リスク
| がんの種類 | 一般女性のリスク | BRCA1/2変異保持者のリスク |
|---|---|---|
| 乳がん | 約9% | 46~87% |
| 卵巣がん | 約1.6% | 17~63% |
遺伝子検査の意義とカウンセリング
卵巣がんと診断された場合、BRCA1/2遺伝子検査を受けることが推奨されます。検査で遺伝子変異が見つかると、PARP阻害薬という効果的な治療薬(維持療法)の選択肢が生まれます。
また、血縁者も同じ遺伝子変異を持つ可能性があり、その方々が早期発見のための検診やリスク低減手術といった対策を考えるきっかけにもなります。
遺伝子検査を受ける前には、遺伝カウンセリングを通じて、検査の意義や結果がもたらす影響について十分に理解することが大切です。
経過観察と再発時の対応方法
初回治療が無事に終了した後も、卵巣がんは再発する可能性があるため、定期的な経過観察が欠かせません。万が一再発した場合でも、さまざまな治療選択肢があります。
希望を失わず、主治医と相談しながら最善の道を探していくことが重要です。
定期的な検査による経過観察の重要性
治療後は、再発の兆候を早期に発見するために、定期的に通院して検査を受けます。
通常、治療終了後1~2年は1~3か月ごと、3~5年目は3~6か月ごと、それ以降は1年ごとといった頻度で診察や検査を行います。
経過観察で行う主な検査
- 問診・内診
- 腫瘍マーカー(CA125など)の測定
- 超音波検査
- 必要に応じたCTやMRIなどの画像検査
再発のサインと早期発見
再発のサインは、初発時と同様に腹部の張りや痛み、食欲不振といった症状のほか、腫瘍マーカーの上昇などがあります。
定期検査でこれらの変化を捉えることが、再発を早期に発見し、速やかに治療を開始することにつながります。
再発時の治療選択肢
卵巣がんが再発した場合の治療は、再発した時期、場所、範囲、過去の治療内容、患者さんの全身状態などを考慮して決定します。
治療の主体は再び化学療法(抗がん剤治療)となります。
再発時期に応じた化学療法の選択
初回化学療法の終了から再発までの期間が長いほど、プラチナ系薬剤が再び効く可能性が高いと考えます。期間に応じて、使用する抗がん剤の種類を選択します。
分子標的薬であるベバシズマブを併用することもあります。BRCA遺伝子変異がある場合には、PARP阻害薬が治療選択肢となります。手術が可能な場合には、再度腫瘍を摘出することも検討します。
再発を繰り返すこともありますが、その都度、その時点での最善の治療法を考えていきます。
よくある質問
卵巣がんについて、患者さんやご家族からよく寄せられる質問にお答えします。
- 卵巣がんは予防できますか?
-
残念ながら、卵巣がんを確実に予防する方法は現在のところありません。しかし、リスクを下げることが知られている方法として、低用量ピルの長期間の服用があります。
ピルは排卵を抑制するため、卵巣への負担が減り、結果的にがん化のリスクを低減すると考えられています。また、出産経験もリスクを下げることが分かっています。
遺伝的なリスクが高い(HBOCなど)場合には、リスク低減卵管卵巣摘出術(RRSO)という予防的な手術を選択することもあります。
- 治療による副作用はどのようなものがありますか?
-
治療法によって副作用は異なります。手術では、術後の痛みや癒着、リンパ浮腫などが起こる可能性があります。
化学療法(抗がん剤治療)では、吐き気、脱毛、倦怠感、口内炎、手足のしびれ、白血球や血小板が減少する骨髄抑制などが代表的です。
これらの副作用の多くは、吐き気止めや痛み止め、白血球を増やす薬などを用いる「支持療法」によって、症状を和らげることができます。
副作用の出方には個人差があるため、つらい症状は我慢せず、医療スタッフに相談することが大切です。
- 妊娠・出産への影響はありますか?
-
卵巣がんの治療は、妊娠・出産する能力(妊孕性)に大きな影響を与えます。標準的な手術では両側の卵巣と子宮を摘出するため、治療後に妊娠することはできません。
しかし、がんがごく早期(ⅠA期やⅠC期の一部)で、特定の組織型であり、将来的に妊娠を強く希望する場合には、「妊孕性温存手術」を検討できることがあります。
これは、がんにかかっている側の卵巣と卵管のみを切除し、子宮と反対側の卵巣・卵管を残す方法です。
ただし、再発のリスクなども考慮する必要があるため、適応は慎重に判断します。
- 治療費はどのくらいかかりますか?
-
卵巣がんの治療にかかる費用は、ステージや治療内容、入院期間などによって大きく異なります。日本には公的医療保険制度があり、医療費の自己負担は原則1~3割です。
さらに、自己負担額が一定の上限を超えた場合に、超過分が払い戻される「高額療養費制度」を利用できます。
治療を始める前に、病院の相談窓口やソーシャルワーカーに相談し、経済的な支援制度について情報を得ておくと安心です。
同じ女性特有のがんであっても、卵巣がんと子宮頸がんは、その原因や予防・発見の方法が大きく異なります。
子宮頸がんは、主にHPV(ヒトパピローマウイルス)というウイルスの感染が原因で発生し、ワクチンで予防したり、定期的な検診でがんになる前の段階で発見したりすることが可能です。
ご自身の体を守るためには、卵巣がんだけでなく、子宮頸がんについても正しい知識を持つことが重要です。
子宮頸がんの予防、検診、そして治療について、さらに理解を深めてみませんか。
以上
参考文献
BAST JR, Robert C., et al. Biomarkers and strategies for early detection of ovarian cancer. Cancer epidemiology, biomarkers & prevention, 2020, 29.12: 2504-2512.
HONG, Mun-Kun; DING, Dah-Ching. Early diagnosis of ovarian cancer: A comprehensive review of the advances, challenges, and future directions. Diagnostics, 2025, 15.4: 406.
BAKER, Tina. Early detection, symptoms, and Treatment options for Ovarian Cancer. Int. J. Adv. Eng. Technol. Innovations, 2024, 10.2: 332-343.
JACOBS, Ian J.; MENON, Usha. Progress and challenges in screening for early detection of ovarian cancer. Molecular & Cellular Proteomics, 2004, 3.4: 355-366.
BONIFÁCIO, Vasco DB. Ovarian cancer biomarkers: moving forward in early detection. Tumor Microenvironment: The Main Driver of Metabolic Adaptation, 2020, 355-363.
DAS, Sreyashi, et al. Biomarkers in cancer detection, diagnosis, and prognosis. Sensors, 2023, 24.1: 37.
MANASA, G., et al. Biomarkers for early diagnosis of ovarian carcinoma. ACS Biomaterials Science & Engineering, 2022, 8.7: 2726-2746.
NGUYEN, Long, et al. Biomarkers for early detection of ovarian cancer. Women’s health, 2013, 9.2: 171-187.
SINGH, Alka; GUPTA, Sameer; SACHAN, Manisha. Epigenetic biomarkers in the management of ovarian cancer: current prospectives. Frontiers in cell and developmental biology, 2019, 7: 182.
SAHU, Shreya A.; SHRIVASTAVA, Deepti. A comprehensive review of screening methods for ovarian masses: towards earlier detection. Cureus, 2023, 15.11.