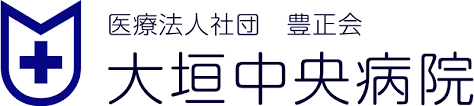がんという病気は、遺伝や生活習慣が主な原因と考えられがちです。しかし、実は特定のウイルスや細菌への感染が、がん発症の引き金になる場合があることは、まだ広く知られていないかもしれません。
特に、日本人に多い胃がんの発生には、「ヘリコバクター・ピロリ菌(ピロリ菌)」という細菌が深く関係しています。
この記事では、がんの原因となりうる感染症の中でも、細菌感染に焦点を当てて解説します。
ピロリ菌がどのようにして胃がんのリスクを高めるのか、その詳しい仕組みから、検査や治療、そして予防法まで、皆さまの疑問や不安に寄り添いながら、分かりやすくお伝えします。
「がん」は遺伝だけじゃない – 見過ごされがちな感染症のリスク
がんの発症には、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。
親族にがんを経験した方がいると遺伝を心配する声も聞きますが、実際には食生活や喫煙、飲酒といった生活習慣、そして環境要因の影響も大きいことがわかっています。
これらに加えて、近年重要視されているのが「感染症」というリスク要因です。特定のウイルスや細菌が、がんを引き起こす原因の一つになるのです。
特に細菌感染は、自覚症状がないまま進行することも多く、見過ごされやすい傾向にあります。
がん発症の要因は一つではない
がんの発生は、単一の原因で説明できるものではありません。
遺伝的な素因を持つ人が、発がんリスクを高める生活習慣を続けることで発症に至るケースもあれば、特定の環境下で発がん物質にさらされることが引き金になることもあります。
感染症もその一つであり、がん全体の約20%は、ウイルスや細菌などの病原体への感染が原因と推計されています。この事実を知ることは、がん予防の新たな視点を持つ上で非常に重要です。
感染症が原因となるがんの割合
| 病原体の種類 | 関連する主ながん | 世界のがんにおける割合(推定) |
|---|---|---|
| ヘリコバクター・ピロリ菌 | 胃がん、胃MALTリンパ腫 | 約5.5% |
| ヒトパピローマウイルス (HPV) | 子宮頸がん、中咽頭がん | 約5.2% |
| B型・C型肝炎ウイルス (HBV, HCV) | 肝細胞がん | 約4.9% |
なぜ感染症が見過ごされやすいのか
細菌感染ががんの原因として見過ごされやすい理由の一つは、感染してから発症するまでの期間が非常に長いことです。
例えば、ピロリ菌は幼少期に感染することが多いですが、実際に胃がんを発症するのは50代以降が中心です。また、感染していても、多くの場合はっきりとした症状が現れません。
軽い胃の不快感や胃もたれといった症状で済むため、それががんのリスクにつながっているとは考えにくいのです。そのため、定期的な検査の重要性がより一層高まります。
なぜ細菌に感染すると、がんになることがあるのか
細菌に感染しただけで、なぜがんという深刻な病気につながるのでしょうか。その背景には、私たちの体内で起こる防御反応が深く関わっています。
細菌が体内に侵入し、特定の臓器にすみ着くと、免疫システムがこれを排除しようと攻撃を始めます。
この戦いが長期間にわたって続くと、「慢性的な炎症」という状態に陥り、ここからがん細胞が生まれる環境が作られてしまうのです。
慢性的な「炎症」ががんの温床に
炎症は、本来体を守るための正常な反応です。しかし、細菌の感染が続くと、炎症もまた終わりなく続きます。この慢性炎症の状態では、細胞の修復と破壊が絶えず繰り返されます。
細胞は分裂・増殖する際に、遺伝子をコピーしますが、この頻度が増えれば増えるほど、コピーミス、すなわち遺伝子の変異が起こる確率が高まります。
この遺伝子変異が積み重なることで、正常な細胞ががん細胞へと姿を変えていくのです。慢性的な炎症は、いわばがん細胞が生まれる土壌を耕しているような状態といえます。
細菌が作り出す発がん物質
細菌の中には、それ自体が発がん性を持つ物質を作り出すものもあります。
細菌は代謝の過程でさまざまな化学物質を産生しますが、その一部が私たちの細胞の遺伝子を直接傷つけ、がん化を促すことがあります。
また、細菌が出す毒素が細胞の増殖を異常に活発化させたり、細胞死を抑制したりすることで、がんの発生を後押しすることも知られています。
このように、細菌は炎症を介した間接的な方法だけでなく、直接的な方法でもがんの発生に関与します。
細菌感染からがん発症への流れ
| 段階 | 体内で起きていること | 主な影響 |
|---|---|---|
| 1. 感染・定着 | 細菌が特定の臓器(例 胃)にすみ着く | 免疫システムが作動開始 |
| 2. 慢性炎症 | 免疫細胞による攻撃が長期化し、組織の破壊と修復が続く | 細胞分裂が活発化し、遺伝子変異のリスクが増大 |
| 3. がん化 | 遺伝子変異の蓄積により、正常な細胞ががん細胞に変化する | がん細胞の無秩序な増殖が始まる |
胃がんの主な引き金 – ヘリコバクター・ピロリ菌の正体
数ある細菌の中でも、がんとの関係が特に明確に証明されているのが「ヘリコバクター・ピロリ菌」です。この細菌は、主に人の胃の中に生息しています。
世界保健機関(WHO)の専門組織である国際がん研究機関(IARC)は、ピロリ菌を「確実な発がん因子」として分類しており、特に胃がん発症の最大の原因であると結論付けています。
日本は胃がんの発生率が高い国の一つですが、その背景にはピロリ菌の高い感染率が関係していると考えられています。
ヘリコバクター・ピロリ菌とはどんな細菌か
ヘリコバクター・ピロリ菌は、数本のべん毛を持つ、らせん形をした細菌です。このべん毛をスクリューのように回転させて、胃の中を活発に動き回ることができます。
胃の中は、食べ物を消化するために強い酸性(胃酸)に保たれており、ほとんどの細菌は生きていけません。
しかし、ピロリ菌は「ウレアーゼ」という酵素を産生し、胃の粘液に含まれる尿素からアンモニアを作り出すことで、自身の周りの胃酸を中和し、過酷な環境下で生き延びることができます。
世界と日本におけるピロリ菌感染率
| 地域・国 | 年代 | 推定感染率 |
|---|---|---|
| 開発途上国 | 全年代 | 70%以上 |
| 先進国 | 全年代 | 30-40% |
| 日本 | 50代以上 | 約50%以上 |
ピロリ菌と胃がんの密接な関係
多くの研究から、ピロリ菌に感染している人は、感染していない人に比べて胃がんになるリスクが5倍以上に高まることが報告されています。
日本の研究では、ピロリ菌感染者のうち、年間約0.5%の人が胃がんを発症するともいわれています。
これは、ピロリ菌感染が胃の粘膜に慢性的な炎症(慢性胃炎)を引き起こし、それが長年にわたって続くことで、胃の粘膜が萎縮し(萎縮性胃炎)、最終的に一部ががん化するためです。
つまり、ピロリ菌感染は、胃がんへと続く長い道のりの出発点といえるのです。
ピロリ菌が胃の中で行っていること – 慢性炎症からがん化への道のり
ピロリ菌が胃の中に定着すると、そこから胃がんの発症までには、数十年という長い年月をかけた段階的な変化が起こります。
ピロリ菌は巧みな戦略で胃酸から身を守りながら、胃の粘膜にじわじわとダメージを与え続けます。
この絶え間ない攻撃が、慢性胃炎や胃潰瘍を引き起こし、やがてがんのリスクを高める土壌を作り上げていくのです。その詳細な道のりを見ていきましょう。
胃酸から身を守るピロリ菌の戦略
ピロリ菌が胃の中で生き延びるための最大の武器は、前述した「ウレアーゼ」という酵素です。この酵素を使って作り出したアンモニアは、強いアルカリ性です。
これにより、ピロリ菌の周囲の胃酸を中和し、自身が生存できる環境を確保します。しかし、このアンモニアは胃の粘膜細胞にとっては有害な物質であり、直接細胞を傷つけ、炎症を引き起こす原因となります。
つまり、ピロリ菌の生存戦略そのものが、胃の健康を損なうことにつながっているのです。
慢性胃炎(萎縮性胃炎)への進行
ピロリ菌の感染が続くと、胃の粘膜では常に炎症が起こっている状態、すなわち「慢性胃炎」となります。炎症が長期化すると、胃の粘膜は徐々に薄く、やせ細っていきます。
これを「萎縮性胃炎」と呼びます。胃の粘膜が萎縮すると、胃酸を分泌する機能が低下し、消化不良や胃もたれといった症状が現れやすくなります。
この萎縮性胃炎は、胃がんの前段階の状態(前がん病変)と考えられており、がん発症のリスクが著しく高まった状態です。
胃粘膜の変化の段階
| 段階 | 胃の状態 | 主な症状 |
|---|---|---|
| 正常な胃 | 粘膜に炎症や萎縮がない健康な状態 | 特になし |
| 慢性胃炎 | ピロリ菌感染により、粘膜に持続的な炎症が起きている | 無症状または軽い胃の不快感 |
| 萎縮性胃炎 | 炎症が長期化し、胃の粘膜が薄くなった状態 | 胃もたれ、消化不良 |
胃潰瘍や十二指腸潰瘍の発症
ピロリ菌は、慢性胃炎だけでなく、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の原因にもなります。
ピロリ菌が出す毒素やアンモニアが胃の粘膜を直接傷つけたり、胃酸の分泌を乱したりすることで、粘膜が深くえぐれて潰瘍ができます。
胃潰瘍や十二指腸潰瘍と診断された人のうち、ピロリ菌感染者は非常に高い割合を占めます。これらの病気もまた、胃のがん化リスクと無関係ではありません。
- 胃痛(特に空腹時や夜間)
- 胸やけ
- 吐き気
- 黒い便(タール便)
胃がんだけではない – 他の細菌とがんの関連性
がんとの関係でピロリ菌は非常に有名ですが、研究が進むにつれて、他の細菌も特定のがんの発症に関与している可能性が指摘され始めています。
私たちの体には、皮膚や口の中、そして腸内など、さまざまな場所に多種多様な細菌が生息しており、「常在細菌叢(さいきんそう)」と呼ばれる生態系を形成しています。
この細菌のバランスが崩れることが、がんを含むさまざまな病気のリスクにつながると考えられています。
MALTリンパ腫とピロリ菌
胃がん以外で、ピロリ菌との強い関連が確立されている病気に「胃MALTリンパ腫」があります。これは、胃の粘膜に関連するリンパ組織(MALT)から発生する、比較的まれな悪性リンパ腫の一種です。
この病気の患者の約90%がピロリ菌に感染しており、早期の段階であれば、ピロリ菌の除菌治療を行うだけで、がんが縮小・消失することがあります。
これは、ピロリ菌による慢性的な免疫刺激が、リンパ球の異常な増殖を引き起こしていることを示唆しています。
胆道がんと特定の腸内細菌
胆道がん(胆管がん、胆のうがん)の発症にも、特定の細菌感染が関与している可能性が研究されています。胆道は、肝臓で作られた胆汁を十二指腸へ送るための管です。
この胆道に細菌が感染し、慢性的な炎症が続くと、胆管の細胞ががん化するリスクが高まると考えられています。
特に、特定の種類の細菌が産生する二次胆汁酸という物質が、発がんを促進する作用を持つことが指摘されています。
がんと関連が疑われる細菌の例
| 細菌の種類(例) | 関連が疑われるがん | 考えられる作用 |
|---|---|---|
| フソバクテリウム・ヌクレアタム | 大腸がん | がん細胞への接着、免疫抑制 |
| クラミジア・トラコマチス | 子宮頸がん(HPVとの共同作用) | 慢性炎症、HPV感染の持続化 |
| ポルフィロモナス・ジンジバリス(歯周病菌) | 口腔がん、食道がん、膵臓がん | 慢性炎症、発がん物質の産生 |
大腸がんと細菌叢(さいきんそう)のバランス
近年、大腸がんと腸内細菌叢(腸内フローラ)の関係が注目を集めています。私たちの腸内には数百兆個もの細菌が生息し、消化吸収の補助や免疫機能の調節など、重要な役割を担っています。
しかし、食生活の乱れなどによって腸内環境が悪化し、悪玉菌が増えると、腸内で発がんを促進する物質が作られやすくなります。
特定の悪玉菌が大腸の粘膜に慢性的な炎症を引き起こしたり、がん細胞の増殖を促したりすることが、大腸がんのリスクを高める一因と考えられています。
あなたは大丈夫?感染リスクが高い人の特徴
ピロリ菌は、どのような人が感染しやすいのでしょうか。現在の日本の衛生環境を考えると、成人になってから新たに感染するケースはまれです。
感染の多くは、免疫力がまだ十分に発達していない幼少期、特に5歳頃までに起こると考えられています。感染経路やリスク要因を知ることで、ご自身やご家族が検査を受けるべきかどうかの判断材料になります。
感染経路は主に幼少期
ピロリ菌の主な感染経路は、まだ完全には解明されていませんが、「経口感染」が最も有力視されています。
具体的には、ピロリ菌に感染している親から子へ、食べ物の口移しなどを通じて感染するケースが多いと考えられています。
また、かつては衛生状態が良くなく、井戸水などを飲用していた時代に育った世代では、水を通じて感染した可能性も指摘されています。
上下水道が整備された現代の日本では、こうした感染リスクは大幅に減少しています。
胃の不調を感じやすい人の特徴
ピロリ菌に感染していても、必ずしも症状が出るとは限りません。しかし、以下のような胃の不調を慢性的に感じている場合は、ピロリ菌感染が原因となっている可能性があります。
これらの症状は、ピロリ菌が引き起こす慢性胃炎や胃潰瘍のサインかもしれません。もちろん、他の病気の可能性もあるため、気になる症状があれば自己判断せず、専門の病院を受診することが大切です。
注意すべき症状のリスト
- 慢性的な胃もたれ
- 食後の膨満感
- 胸やけ
- 原因不明の貧血
- 軽い胃の痛み
家族に胃がんや胃潰瘍の経験者がいる場合
血縁関係のあるご家族(親、兄弟姉妹、子)の中に、胃がんや胃潰瘍、十二指腸潰瘍を経験した方がいる場合は、注意が必要です。
これは、遺伝的な体質が似ていることに加え、幼少期に同じ生活環境で過ごし、家族内でピロリ菌の感染が起きている可能性が高いからです。
ご家族の病歴は、ご自身のピロリ菌感染リスクを考える上で重要な手がかりとなります。該当する方は、一度ピロリ菌の検査を受けることを検討するとよいでしょう。
どうすれば見つけられる?ピロリ菌の検査方法
ピロリ菌に感染しているかどうかは、簡単な検査で調べることができます。検査方法には、胃内視鏡(胃カメラ)を使う方法と使わない方法があり、それぞれに特徴があります。
どの検査が適しているかは、個人の症状や健康状態、検査の目的によって異なります。医師と相談の上、適切な方法を選択することが重要です。ここでは、代表的な検査方法を紹介します。
検査を受けるタイミング
ピロリ菌の検査は、健康診断のオプションとして受けられるほか、胃の不調で病院を受診した際に勧められることがあります。
特に、前述したような慢性的な胃の症状がある方や、血縁者に胃がんの経験者がいる方は、積極的に検査を検討する価値があります。
また、バリウム検査で胃炎の疑いを指摘された場合も、精密検査として内視鏡検査と同時にピロリ菌検査を行うことが一般的です。
内視鏡を使う検査
胃内視鏡検査は、胃の粘膜の状態を直接観察できるという大きな利点があります。
ピロリ菌感染に特徴的な胃炎の所見を確認できるだけでなく、検査中に胃の組織を少量採取し、それを調べてピロリ菌の有無を確定診断します。
がんや潰瘍の有無も同時に確認できるため、最も確実で情報量の多い検査方法です。
内視鏡で採取した組織を用いる検査法
| 検査方法 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| 迅速ウレアーゼ試験 | 採取した組織を特殊な試薬に入れ、色の変化で判定する | 短時間(1-2時間)で結果がわかる |
| 培養法 | 組織を特殊な環境で培養し、ピロリ菌を増殖させて確認する | 菌の薬剤耐性を調べられるが、結果に数日かかる |
| 組織鏡検法 | 組織を染色して顕微鏡で観察し、菌の存在を直接確認する | 菌の量や炎症の程度も評価できる |
内視鏡を使わない検査
内視鏡を使わない検査は、体への負担が少ないというメリットがあります。
主に、ピロリ菌の除菌治療が成功したかどうかの効果判定に用いられることが多いですが、初めての感染診断(スクリーニング)に利用されることもあります。
これらの検査で陽性となった場合は、胃の状態を詳しく調べるために、改めて内視鏡検査が必要になることがあります。
- 尿素呼気試験
- 抗体測定(血液・尿)
- 便中抗原測定
【検診】自分のリスクを知る「ABC検診」
近年の健康診断では、血液検査で「ピロリ菌感染の有無」と「胃粘膜の萎縮度(ペプシノゲン法)」を調べ、その組み合わせで胃がんリスクを判定する「ABC検診」が普及しています。
- A群(健康): ピロリ菌(-)、萎縮(-)。リスクはほぼゼロです。
- B群(要除菌): ピロリ菌(+)、萎縮(-)。胃がんはまだ発生しにくいですが、除菌が必要です。
- C群(高リスク): ピロリ菌(+)、萎縮(+)。胃がんのリスクが高いため、内視鏡検査が必須です。
- D群(超高リスク): ピロリ菌(-)、萎縮(+)。萎縮が進みすぎてピロリ菌が棲めなくなった状態です。直ちに精密検査が必要です。
※検診結果がB・C・D群だった方は、症状がなくても必ず消化器内科を受診しましょう。
感染がわかったら – 除菌治療とがん予防への期待
ピロリ菌の検査で陽性と診断された場合、除菌治療を行うことが推奨されます。除菌治療は、胃がんの予防に非常に効果的であることが多くの研究で証明されています。
胃がんの原因となる細菌を取り除くことで、慢性的な炎症を抑え、がんへと続く負の連鎖を断ち切ることが期待できます。治療は比較的簡単で、多くの場合、保険適用で受けることができます。
除菌治療の進め方
ピロリ菌の除菌治療は、薬の内服によって行います。一般的に、2種類の「抗菌薬」と、胃酸の分泌を抑える「プロトンポンプ阻害薬(PPI)」という薬の、合計3種類を1日2回、7日間連続で服用します。
この治療法は「3剤併用療法」と呼ばれています。医師の指示通りにきちんと薬を飲みきることが、除菌を成功させるために非常に重要です。
【治療の流れ】薬を飲んで終わりではありません
除菌治療は、薬を飲み終わった後も重要です。
- 一次除菌: 3種類の薬を朝夕2回、7日間飲みます。
- 判定検査: 薬を飲み終わってから4週間以上あけて、本当に菌が消えたかを確認する検査(尿素呼気試験など)を受けます。
- 二次除菌(失敗した場合): 一次除菌で菌が残っていた場合は、薬の種類を変えて再度7日間飲みます。(ここまで保険適用です)
※「薬を飲んだから大丈夫」と自己判断せず、必ず**「判定検査」**を受けて除菌成功を確認してください。
除菌治療の成功率と保険適用
この一次除菌治療による成功率は、約80~90%と報告されています。残念ながら除菌に失敗した場合は、抗菌薬の種類を変更して二次除菌を行います。
二次除菌まで含めると、95%以上の人で除菌が成功します。除菌治療は、以下の条件を満たす場合に健康保険が適用されます。
保険診療で除菌治療が可能な疾患
| 対象疾患 | 備考 |
|---|---|
| 内視鏡検査において胃炎と診断された場合 | ピロリ菌感染の証明が必要 |
| 胃潰瘍・十二指腸潰瘍 | 再発予防のために除菌が強く推奨される |
| 胃MALTリンパ腫 | 除菌が第一選択の治療となる |
除菌による胃がん予防の効果
ピロリ菌を除菌することで、胃がんの発生リスクを約3分の1から3分の2程度にまで減少させることができると報告されています。
特に、胃の粘膜の萎縮が進んでいない、比較的若い年齢で除菌するほど、その予防効果は高いと考えられています。
ただし、注意しなければならないのは、除菌が成功したからといって、胃がんのリスクがゼロになるわけではないという点です。
除菌後も定期的な胃の検査が重要な理由
除菌治療を行うまでに長年続いてきた胃の炎症や萎縮は、除菌後すぐには元に戻りません。
すでに蓄積された発がんリスクは残存するため、除菌に成功した後も、定期的に(年に1回程度)胃内視鏡検査を受け、胃の状態を確認し続けることが極めて重要です。
早期発見できれば、胃がんは治癒率の高いがんの一つです。除菌を「がん予防の終わり」ではなく、「本格的な予防の始まり」と捉えましょう。
よくある質問
- ピロリ菌を除菌すれば、絶対に胃がんになりませんか?
-
いいえ、絶対ではありません。除菌治療によって胃がんになるリスクは大幅に減少しますが、ゼロにはなりません。
特に、除菌した時点ですでに胃の粘膜の萎縮が進んでいる場合は、除菌後もがんが発生する可能性があります。
そのため、除菌が成功した後も、定期的な胃内視鏡検査を続けることが非常に重要です。
- 除菌治療に副作用はありますか?
-
副作用が起こる可能性があります。主なものとして、軟便や下痢、味覚異常、発疹などが報告されています。
ほとんどは軽い症状で、服薬を中止すれば改善しますが、まれに重いアレルギー反応や出血を伴う大腸炎が起こることもあります。
治療中に気になる症状が現れた場合は、自己判断で服薬を中止せず、速やかに処方を受けた病院や医師に相談してください。
- 家族がピロリ菌陽性でした。自分も検査を受けるべきですか?
-
検査を受けることをお勧めします。ピロリ菌は幼少期に家庭内で感染することが多いと考えられています。
そのため、ご両親や兄弟姉妹に感染者がいる場合、ご自身も感染している可能性が比較的高くなります。特に、ご家族に胃がんの既往歴がある場合は、積極的に検査を検討してください。
- 一度除菌に成功すれば、再感染することはありませんか?
-
成人における再感染は非常にまれです。日本の衛生環境は良好なため、日常生活でピロリ菌に再感染するリスクは極めて低いと考えられています。
除菌後の検査で再び陽性となった場合、再感染よりも、前回の除菌が実は不成功であった(菌が残っていた)可能性が高いとされます。
- ヨーグルトなどの食品でピロリ菌はいなくなりますか?
-
特定の成分を含むヨーグルトなどが、ピロリ菌の活動を弱める効果を持つ可能性は研究されていますが、食品だけでピロリ菌を完全に胃の中からなくすこと(除菌)はできません。
ピロリ菌の除菌には、医療機関で処方される抗菌薬などを用いた確実な治療が必要です。食品はあくまで補助的な役割と考えるのが適切です。
がんの原因は多岐にわたりますが、中でも、寄生虫の感染が特定のがんのリスクを高めることが知られています。
例えば、東南アジアの一部地域で見られる肝吸虫(かんきゅうちゅう)は、胆管がんの重要なリスク因子です。
寄生虫とがんの関連性についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
参考文献
SIPPONEN, P. Gastric cancer—a long-term consequence of Helicobacter pylori infection?. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 1994, 29.sup201: 24-27.
OHBA, Reina; IIJIMA, Katsunori. Pathogenesis and risk factors for gastric cancer after Helicobacter pylori eradication. World Journal of Gastrointestinal Oncology, 2016, 8.9: 663.
SIPPONEN, P.; HYVÄRINEN, H. Role of Helicobacter pylori in the pathogenesis of gastritis, peptic ulcer and gastric cancer. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 1993, 28.sup196: 3-6.
ZHANG, Rong-Guang, et al. Role of Helicobacter pylori infection in pathogenesis of gastric carcinoma. World journal of gastrointestinal pathophysiology, 2016, 7.1: 97.
ZHANG, Xiao-Ying; ZHANG, Pei-Ying; ABOUL-SOUD, Mourad AM. From inflammation to gastric cancer: Role of Helicobacter pylori. Oncology letters, 2017, 13.2: 543-548.
YANG, Hang; WEI, Bin; HU, Bing. Chronic inflammation and long-lasting changes in the gastric mucosa after Helicobacter pylori infection involved in gastric cancer. Inflammation Research, 2021, 70.10: 1015-1026.
KUMAR, Sushil; PATEL, Girijesh Kumar; GHOSHAL, Uday C. Helicobacter pylori-induced inflammation: possible factors modulating the risk of gastric cancer. Pathogens, 2021, 10.9: 1099.
WANG, Fei, et al. Helicobacter pylori-induced gastric inflammation and gastric cancer. Cancer letters, 2014, 345.2: 196-202.
WROBLEWSKI, Lydia E.; PEEK JR, Richard M.; WILSON, Keith T. Helicobacter pylori and gastric cancer: factors that modulate disease risk. Clinical microbiology reviews, 2010, 23.4: 713-739.
SALVATORI, Silvia, et al. Helicobacter pylori and gastric cancer: pathogenetic mechanisms. International journal of molecular sciences, 2023, 24.3: 2895.
がんの感染性要因に戻る