造血器腫瘍は、血液細胞(白血球、赤血球、血小板)やリンパ球が作られる骨髄やリンパ節などの「造血器」から発生するがんの総称で、「血液のがん」とも呼ばれます。
血液やリンパの流れに乗って全身に広がる性質を持つため、多くの場合、手術で取り除くという治療法は適しません。代表的なものに「白血病」「悪性リンパ腫」「多発性骨髄腫」があります。
これらの病気は、がん化する細胞の種類や病気の進行速度によって、さまざまなタイプに分かれます。
この記事では、それぞれの病気の基本的な特徴、症状、検査、そして治療法について解説し、患者さんやご家族が病気と向き合うための知識を提供します。
白血病という「血液のがん」を知る
白血病は、血液細胞のもとになる細胞(造血幹細胞)や、そこから分かれて成長する途中の若い血液細胞(芽球)ががん化し、無秩序に増え続ける病気です。
異常な細胞(白血病細胞)が骨髄を占拠することで、正常な血液細胞が作られなくなり、貧血、出血、感染症といったさまざまな症状を引き起こします。
病気の進行速度や、がん化する細胞の種類によって分類されます。
白血病とは何か – 血液細胞のがん化
正常な血液細胞と造血の働き
私たちの血液は、主に赤血球、白血球、血小板という3種類の細胞から成り立っています。これらの血液細胞は、骨の中心部にある骨髄で、すべての血液細胞のもとである「造血幹細胞」から作られます。
造血幹細胞は、骨髄系幹細胞とリンパ系幹細胞に分かれ、それぞれがさらに分化・成熟を繰り返して、最終的に機能を持った血液細胞となり、血液中に放出されます。この一連の流れを「造血」と呼びます。
白血病細胞の発生と増殖
白血病は、この造血の過程にあるいずれかの段階の細胞で遺伝子に異常が生じ、がん化することで発症します。がん化した白血病細胞は、正常なコントロールを失って自律的に増殖し続けます。
その結果、骨髄内が白血病細胞でいっぱいになり、正常な造血が著しく妨げられます。これにより、健康な赤血球、白血球、血小板が減少し、体にさまざまな異常をもたらします。
白血病の主な種類と特徴
白血病は、病気の進行速度によって「急性」と「慢性」に、がん化する細胞の系統によって「骨髄性」と「リンパ性」に大別され、これらを組み合わせて主に4つのタイプに分類します。
急性白血病と慢性白血病の違い
急性白血病は、分化能力を失った未熟な血液細胞(芽球)ががん化し、急速に増殖する病気です。進行が速く、数週間から数か月の単位で重篤な状態になるため、迅速な診断と治療の開始が必要です。
一方、慢性白血病は、ある程度成熟した段階の血液細胞ががん化するもので、ゆっくりと進行します。初期には自覚症状がほとんどないことも少なくありません。
骨髄性白血病とリンパ性白血病
骨髄性白血病は、骨髄系幹細胞から分化する途中の細胞(赤血球、顆粒球、血小板などにつながる系統)ががん化するものです。
リンパ性白血病は、リンパ系幹細胞から分化するリンパ球の系統ががん化します。これらの区別は、治療方針を決定する上で非常に重要です。
白血病の症状と診断
初期に現れるサイン
白血病細胞が骨髄で増えることで正常な血液細胞が減少するため、それぞれの細胞の機能低下に応じた症状が現れます。
赤血球の減少による貧血症状(動悸、息切れ、倦怠感)、血小板の減少による出血傾向(鼻血、歯ぐきからの出血、あざ)、そして正常な白血球の減少による免疫力の低下(発熱、感染症にかかりやすくなる)が主な症状です。
確定診断に至る検査
血液検査で血液細胞の数や種類の異常を調べ、白血病が疑われる場合には、骨髄検査(骨髄穿刺・骨髄生検)を行います。
骨髄検査は、骨盤の骨などに針を刺して骨髄液や組織を採取し、顕微鏡で細胞の種類や数を詳しく調べる検査です。これにより、白血病細胞の有無やその割合を確認し、確定診断を下します。
さらに、染色体検査や遺伝子検査で白血病細胞の特性を詳しく調べ、病型を特定し治療方針を決定します。
急性白血病の主な分類
| 分類 | 好発年齢 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 急性骨髄性白血病 (AML) | 成人に多い | 多様な病型が存在し、遺伝子異常に基づいた分類が治療選択に重要。 |
| 急性リンパ性白血病 (ALL) | 小児に多いが成人でも発症 | リンパ球系の前駆細胞ががん化。中枢神経系への浸潤に注意が必要。 |
| 慢性骨髄性白血病 (CML) | 成人に多い | フィラデルフィア染色体という特徴的な染色体異常が見られる。 |
白血病の治療法
化学療法 – 治療の中心
白血病治療の基本は、抗がん剤を用いた化学療法です。
特に急性白血病では、強力な化学療法によって骨髄内の白血病細胞を根絶させる「寛解導入療法」を行い、まずは寛解(骨髄中の白血病細胞が5%未満になる状態)を目指します。
寛解に至った後も、再発を防ぐために、さらに化学療法を繰り返す「地固め療法」や「維持療法」が必要です。
造血幹細胞移植という選択肢
強力な化学療法や放射線療法で患者自身の骨髄を破壊した後、健康な提供者(ドナー)または自分自身の造血幹細胞を移植する方法です。
再発リスクが高い場合や、化学療法だけでは治癒が難しいと考えられる場合に行います。
移植には強い副作用や合併症のリスクも伴うため、患者さんの年齢や全身状態、病気の種類などを総合的に判断して適応を決定します。
分子標的薬の役割
がん細胞が持つ特定の分子だけを狙い撃ちして、その働きを妨げる薬です。
慢性骨髄性白血病(CML)では、原因となる遺伝子異常(BCR-ABL遺伝子)の働きを抑える分子標的薬の登場により、治療成績が飛躍的に向上しました。
特定の遺伝子異常を持つ急性白血病の一部でも、分子標的薬が化学療法と組み合わせて使用されます。
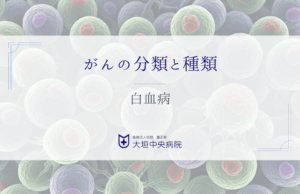
悪性リンパ腫 – リンパ系に発生するがん
悪性リンパ腫は、白血球の一種であるリンパ球ががん化する病気です。リンパ球は、リンパ節、脾臓、扁桃腺といったリンパ系組織に存在し、全身を巡って体を細菌やウイルスから守る免疫の役割を担っています。
このリンパ球ががん化するため、悪性リンパ腫は全身のあらゆる場所に発生する可能性があります。非常に多くの病型(タイプ)が存在し、それぞれ進行の速さや性質が異なります。
悪性リンパ腫の基礎知識
リンパ系の役割と構造
リンパ系は、リンパ管、リンパ節、そして脾臓や胸腺などのリンパ組織から構成されるネットワークです。リンパ管は血管のように全身に張り巡らされ、その中をリンパ液が流れています。
リンパ節はリンパ管の途中にあり、フィルターのように病原体や異物を捕捉し、免疫反応の中心的な場所として機能します。悪性リンパ腫は、このリンパ系のどこからでも発生し得ます。
悪性リンパ腫の発生原因
多くの悪性リンパ腫では、明確な原因は分かっていません。
しかし、一部のリンパ腫では、特定のウイルス感染(EBウイルス、HTLV-1など)や、免疫不全状態、自己免疫疾患などが発症のリスクを高めることが知られています。
遺伝子の異常が積み重なって発症すると考えられていますが、生活習慣との直接的な関連は明らかになっていません。
主な種類 – ホジキンリンパ腫と非ホジキンリンパ腫
悪性リンパ腫は、組織の中に「リード・シュテルンベルク細胞」という特徴的な大型の腫瘍細胞が存在するかどうかで、「ホジキンリンパ腫」と「非ホジキンリンパ腫」の2つに大きく分けられます。
この分類は、治療方針を決定する上で最も基本的なものです。
ホジキンリンパ腫の特徴
比較的まれなタイプで、若い世代(15-35歳)と高齢者(50歳以上)に発症のピークがあります。
多くの場合、首や胸部のリンパ節から発生し、予測可能な順序で隣接するリンパ節へと広がっていく傾向があります。治療によく反応し、治癒を目指せる可能性が高いリンパ腫です。
多様な非ホジキンリンパ腫
悪性リンパ腫の大部分を占めるのが非ホジキンリンパ腫です。がん化するリンパ球の種類(B細胞、T細胞、NK細胞)や成熟度によって、数十種類以上の非常に多くの病型に細かく分類されます。
進行の速さも、年単位でゆっくり進む「低悪性度」のものから、月単位で急速に進行する「中・高悪性度」のものまで多様です。
悪性リンパ腫でみられる症状
リンパ節の腫れ – 最も多い症状
最も一般的な症状は、首、わきの下、足の付け根などにあるリンパ節の痛みがない腫れです。通常、腫れは硬く、ゴムのような感触で、徐々に大きくなります。
ただし、リンパ節は感染症などでも腫れるため、腫れが長引く場合や、複数の場所で腫れが見られる場合には注意が必要です。
全身に現れるB症状
原因不明の38度以上の発熱、寝具を交換するほど大量の寝汗、そして半年で10%以上の意図しない体重減少という3つの全身症状は「B症状」と呼ばれます。
これらの症状は、病気が活発に進行しているサインであり、病期分類や治療方針の決定において重要な指標となります。
診断と病期分類
生検による確定診断
悪性リンパ腫の診断を確定するためには、腫れているリンパ節などの組織の一部を外科的に切除して調べる「生検」が必要です。
採取した組織を顕微鏡で観察し、どのような種類のリンパ腫細胞が増殖しているかを詳細に調べる病理診断を行います。
これにより、ホジキンか非ホジキンか、さらに非ホジキンリンパ腫であればどの病型かを特定します。
治療方針を決めるための病期(ステージ)
診断が確定したら、病気が体のどの範囲まで広がっているかを調べるために、CTやPET-CTなどの画像検査や骨髄検査を行います。
この病気の広がり具合を「病期(ステージ)」といい、Ⅰ期からⅣ期までに分類します。病期とリンパ腫の病型、そして患者さんの全身状態などを総合的に評価し、最適な治療法を決定します。
非ホジキンリンパ腫の代表的な病型
| 病型 | 細胞の種類 | 進行度・悪性度 |
|---|---|---|
| びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 | B細胞 | 中-高悪性度(進行が速い) |
| 濾胞性リンパ腫 | B細胞 | 低悪性度(進行が緩やか) |
| MALTリンパ腫 | B細胞 | 低悪性度(進行が緩やか) |
悪性リンパ腫の治療戦略
化学療法と放射線療法の組み合わせ
治療の基本は、複数の抗がん剤を組み合わせる多剤併用化学療法です。非ホジキンリンパ腫で最も多い「びまん性大細胞型B細胞リンパ腫」では、R-CHOP療法という治療法が標準的に行われます。
病気の広がりが限られている限局期の場合には、化学療法の後に放射線療法を追加することもあります。
抗体療法と分子標的薬
B細胞リンパ腫の多くでは、B細胞の表面にあるCD20というタンパク質を標的とする「リツキシマブ」という抗体薬が化学療法と併用されます。
この抗体療法は、正常な細胞への影響を抑えながら、がん細胞を効率的に攻撃することができます。その他にも、新しい分子標的薬や免疫の働きを利用する治療薬の開発が進んでいます。
自家造血幹細胞移植
再発した場合や、初回治療で効果が不十分な高リスクのリンパ腫に対して行われる治療法です。
あらかじめ患者さん自身の造血幹細胞を採取・凍結保存しておき、大量の化学療法を行った後に、その保存しておいた造血幹細胞を体内に戻すことで、骨髄の造血機能を回復させます。
これを「自家移植」と呼びます。
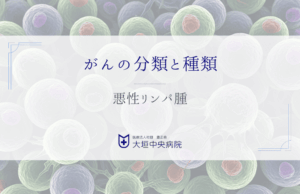
多発性骨髄腫(血液がん)- 骨髄で形質細胞ががん化
多発性骨髄腫は、リンパ球の一種である「形質細胞」ががん化し、骨髄の中で異常に増殖する病気です。形質細胞は、体内に侵入した異物と戦うための「抗体」を産生する重要な役割を担っています。
しかし、がん化した骨髄腫細胞は、役に立たない異常な抗体(Mタンパク)を大量に作り出すとともに、骨を破壊したり、正常な造血を妨げたりして、さまざまな症状を引き起こします。
多発性骨髄腫とはどのような病気か
形質細胞の働きとがん化
正常な形質細胞は、ウイルスや細菌などの特定の抗原に反応して、それに対応する抗体を産生します。
一方、骨髄腫細胞は、単一のクローン(同一の性質を持つ細胞集団)から成り、機能的に意味のない単一種類の抗体(Mタンパク)だけを過剰に産生し続けます。
これらの骨髄腫細胞が骨髄内で増え続けるのが多発性骨髄腫です。
Mタンパクの産生と影響
骨髄腫細胞が産生するMタンパクは、血液中に大量に蓄積します。
これにより、血液がドロドロになり血流が悪くなる「過粘稠度症候群」を引き起こしたり、腎臓に沈着して腎機能を低下させたりする原因となります。
また、正常な抗体の産生が抑制されるため、免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります。
多発性骨髄腫が引き起こす主な症状
骨の痛みや骨折 – 骨病変
骨髄腫細胞は、骨を壊す細胞(破骨細胞)を活性化させる物質を放出します。
これにより、全身の骨、特に背骨や肋骨、骨盤などがもろくなり、骨の痛みや、ささいなきっかけでの骨折(病的骨折)を引き起こします。
また、骨からカルシウムが溶け出し、血液中のカルシウム濃度が高くなる「高カルシウム血症」も起こりえます。
腎機能の低下
Mタンパクの一部(ベンス・ジョーンズタンパク)が尿中に排出される際に、腎臓の尿細管に障害を与え、腎機能が悪化します。高カルシウム血症や脱水も腎機能障害を助長する要因となります。
初期には自覚症状がないことも多いですが、進行すると透析が必要になることもあります。
貧血と感染症のリスク
白血病と同様に、骨髄腫細胞が骨髄を占拠することで、正常な赤血球や白血球の産生が妨げられます。
その結果、貧血による倦怠感や息切れ、白血球減少による易感染性(特に肺炎や尿路感染症)が見られます。
診断のための検査
血液検査と尿検査 – Mタンパクの検出
診断の第一歩は、血液検査や尿検査でMタンパクを検出することです。電気泳動という方法で、タンパク質の種類を詳しく調べ、Mタンパクの存在とその量を確認します。
また、貧血の有無、腎機能、カルシウム値なども評価します。
骨髄検査の重要性
確定診断には骨髄検査が必須です。骨髄液を採取し、骨髄中の形質細胞の割合を調べます。全有核細胞のうち、クローナルな形質細胞が10%以上を占める場合に、多発性骨髄腫と診断されます。
同時に、染色体検査で予後に関わる異常の有無も確認します。
画像検査による骨病変の評価
全身の骨の状態を調べるために、レントゲン検査、CT、MRI、PET-CTなどの画像検査を行います。
骨に穴が開いたように見える「打ち抜き像(パンチアウトリージョン)」や、骨折の有無を確認し、病気の進行度を評価します。
多発性骨髄腫の診断基準(CRAB基準)
症候性の多発性骨髄腫の診断には、以下のCRAB基準と呼ばれる臓器障害の有無が重要です。
- C (Calcium): 高カルシウム血症(血清カルシウム値が基準値上限より1 mg/dL超高い)
- R (Renal): 腎機能障害(クレアチニンクリアランスが40 mL/分未満、または血清クレアチニン値が2 mg/dL超)
- A (Anemia): 貧血(ヘモグロビン値が10 g/dL未満、または基準値下限より2 g/dL超低い)
- B (Bone): 骨病変(レントゲン、CT、PET-CTのいずれかで1カ所以上の骨融解性病変を認める)
多発性骨髄腫の治療
治療の目標と基本的な考え方
多発性骨髄腫は、現在の医療では完治させることが難しい病気とされています。
そのため、治療の目標は、病気の進行を抑え、症状を和らげ、できるだけ長く良好な生活の質(QOL)を維持することに置かれます。
治療の開始時期は、CRAB基準などの臓器障害が認められた時点が一般的です。
薬物療法 – プロテアソーム阻害薬と免疫調節薬
近年の治療の進歩は著しく、新しい作用を持つ薬剤が次々と登場しています。
骨髄腫細胞の増殖に重要なタンパク質分解酵素(プロテアソーム)の働きを阻害する「プロテアソーム阻害薬」や、免疫系に働きかけて骨髄腫細胞を攻撃したり、その増殖を抑えたりする「免疫調節薬」が治療の中心です。
これらの薬剤をステロイドなどと組み合わせて使用します。
自家造血幹細胞移植の適用
65歳程度までの比較的若く、全身状態が良好な患者さんに対しては、大量化学療法と自家造血幹細胞移植を組み合わせる治療法が標準的に行われます。
これにより、より深い寛解状態を目指し、病状が安定している期間を長くすることが期待できます。
主な治療薬の分類
| 薬剤の種類 | 主な薬剤名(一般名) | 作用の概要 |
|---|---|---|
| プロテアソーム阻害薬 | ボルテゾミブ、カルフィルゾミブ | 骨髄腫細胞内の不要なタンパク質分解を阻害し、細胞死を誘導する。 |
| 免疫調節薬 (IMiDs) | レナリドミド、ポマリドミド | 免疫細胞を活性化させ、骨髄腫細胞の増殖を抑制する。 |
| 抗体薬 | ダラツムマブ、エロツズマブ | 骨髄腫細胞の表面にある特定の分子を標的として攻撃する。 |
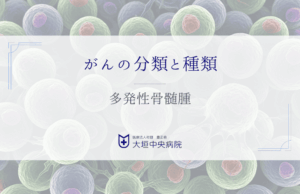
造血器腫瘍には、これまで解説した白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫以外にも、骨髄異形成症候群(MDS)や骨髄増殖性腫瘍(MPN)など、さまざまな種類の病気が存在します。
これらの疾患は、それぞれ異なる特徴や経過をたどり、専門的な理解が必要です。
より詳しい情報や、その他の特殊な血液の病気について知りたい方は、こちらの「その他の特殊な腫瘍」の記事もあわせてご覧ください。
あなたの病気への理解をさらに深める一助となるでしょう。
参考文献
FREIREICH, Emil J., et al. The hematologic malignancies: Leukemia, lymphoma, and myeloma. Cancer, 1984, 54.S2: 2741-2750.
HOWELL, Debra A., et al. Time-to-diagnosis and symptoms of myeloma, lymphomas and leukaemias: a report from the Haematological Malignancy Research Network. BMC blood disorders, 2013, 13.1: 9.
TAYLOR, Justin; XIAO, Wenbin; ABDEL-WAHAB, Omar. Diagnosis and classification of hematologic malignancies on the basis of genetics. Blood, The Journal of the American Society of Hematology, 2017, 130.4: 410-423.
RODRIGUEZ-ABREU, D.; BORDONI, A.; ZUCCA, E. Epidemiology of hematological malignancies. Annals of oncology, 2007, 18: i3-i8.
COWAN, Andrew J., et al. Diagnosis and management of multiple myeloma: a review. Jama, 2022, 327.5: 464-477.
ROSMARIN, Alan. Leukemia, lymphoma, and myeloma. Cancer: Prevention, early detection, treatment and recovery, 2019, 299-316.
GERECKE, Christian, et al. The diagnosis and treatment of multiple myeloma. Deutsches Ärzteblatt International, 2016, 113.27-28: 470.
KYLE, Robert A.; RAJKUMAR, S. Vincent. Treatment of multiple myeloma: a comprehensive review. Clinical Lymphoma and Myeloma, 2009, 9.4: 278-288.
HUH, Jooryung. Epidemiologic overview of malignant lymphoma. The Korean journal of hematology, 2012, 47.2: 92.
DOODY, Michele Morin, et al. Leukemia, lymphoma, and multiple myeloma following selected medical conditions. Cancer causes & control, 1992, 3.5: 449-456.

