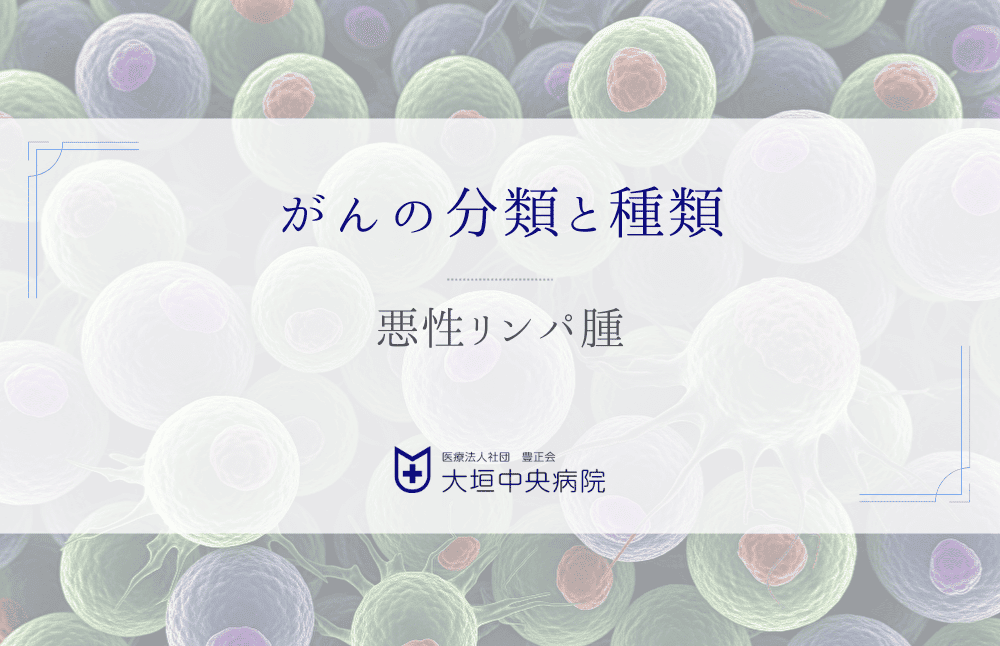悪性リンパ腫は、血液のがんの一種で、免疫システムを担うリンパ系組織から発生します。全身のあらゆる場所に発症する可能性があり、その症状や進行速度は多様です。
この記事では、悪性リンパ腫の基礎知識から、具体的な症状、診断、治療法、そして予後について、専門的な情報を分かりやすく解説します。
悪性リンパ腫とは – リンパ系のがんの基礎知識
この章では、悪性リンパ腫がどのような病気であるか、その基本的な概念を解説します。
私たちの体を守る免疫システムの一部であるリンパ系が、どのようにしてがんの発生場所となるのか、その仕組みを理解することは、病気と向き合う上での第一歩となります。
体を守るリンパ系とリンパ球の役割
リンパ系は、リンパ管、リンパ節、脾臓、胸腺などから構成され、全身に網の目のように張り巡らされています。その中を流れるリンパ液には、白血球の一種であるリンパ球が含まれています。
リンパ球は、体内に侵入した細菌やウイルスなどの異物を攻撃・排除する、免疫システムの主役です。この重要なリンパ球が何らかの原因でがん化し、無秩序に増殖を始める病気が悪性リンパ腫です。
リンパ系組織の広がり
リンパ系は全身に存在するため、悪性リンパ腫は首やわきの下のリンパ節だけでなく、胃や腸、脳といったリンパ節以外の臓器(節外臓器)にも発生する可能性があります。
これが、悪性リンパ腫が多彩な症状を示す一因です。
悪性リンパ腫と白血病の違い
悪性リンパ腫と白血病は、どちらも「血液のがん」に分類されるため混同されやすいですが、その性質には明確な違いがあります。病気の発生場所と増殖の仕方が異なります。
発生場所と増殖形式の相違点
| 項目 | 悪性リンパ腫 | 白血病 |
|---|---|---|
| 主な発生場所 | リンパ節、脾臓など | 骨髄 |
| 増殖の仕方 | 多くは固形の腫瘤(しこり)を形成 | がん細胞が血液中にあふれ出る |
| 主な初期症状 | リンパ節の腫れ、しこり | 貧血、出血傾向、発熱 |
この違いから、診断のアプローチや治療戦略も異なります。
リンパ腫ではリンパ節の「しこり」が診断のきっかけになることが多いのに対し、白血病は血液検査の異常から発見されることが少なくありません。
リンパ腫の分類 – ホジキンと非ホジキンの違い
悪性リンパ腫は、単一の病気ではありません。顕微鏡で見たときの細胞の顔つきによって、大きく二つの種類に分けられます。
この分類は、治療方針や病気の見通しを考える上で非常に重要です。
組織型による二大別
悪性リンパ腫は、まず「ホジキンリンパ腫」と「非ホジキンリンパ腫」の2種類に大別します。この分類は、リード・シュテルンベルク細胞という特徴的な巨大細胞の有無によって決まります。
この細胞があればホジキンリンパ腫、なければ非ホジキンリンパ腫と診断します。
ホジキンリンパ腫と非ホジキンリンパ腫の比較
| 特徴 | ホジキンリンパ腫 | 非ホジキンリンパ腫 |
|---|---|---|
| 日本での頻度 | 約5-10% | 約90-95% |
| 特徴的な細胞 | リード・シュテルンベルク細胞が存在 | リード・シュテルンベルク細胞が存在しない |
| 病気の広がり方 | 比較的規則的にリンパ節を伝って進行 | 不規則に全身へ広がりやすい |
非ホジキンリンパ腫の多様な種類
日本人では、悪性リンパ腫の9割以上を非ホジキンリンパ腫が占めます。
非ホジキンリンパ腫は、さらにがん化したリンパ球の種類(B細胞かT細胞/NK細胞か)と、病気の進行速度(悪性度)によって、約100種類もの細かい病型(サブタイプ)に分類されます。
細胞の種類による分類
リンパ球にはB細胞とT細胞、NK細胞といった種類があり、どの細胞ががん化したかによって性質が異なります。
- B細胞リンパ腫
- T細胞/NK細胞リンパ腫
非ホジキンリンパ腫の大部分はB細胞リンパ腫です。
日本における非ホジキンリンパ腫の主な種類
| サブタイプ(病型) | 細胞の種類 | 進行速度(悪性度) |
|---|---|---|
| びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 | B細胞 | 中〜高悪性度 |
| 濾胞性リンパ腫 | B細胞 | 低悪性度 |
| MALTリンパ腫 | B細胞 | 低悪性度 |
がん化の過程 – リンパ球が悪性化する過程
なぜ健康なリンパ球ががん細胞に変わってしまうのでしょうか。ここでは、悪性リンパ腫が発生する背景にある要因と、遺伝との関係について解説します。
多くの場合はっきりとした原因は不明ですが、いくつかのリスク因子が知られています。
リンパ球に起こる遺伝子の異常
悪性リンパ腫は、リンパ球の中にある遺伝子に、後天的に(生まれてから後に)傷がつくこと(体細胞変異)が積み重なって発生します。
これは、親から子へと受け継がれる遺伝情報に異常があるわけではありません。したがって、親がリンパ腫だからといって、その子どもがリンパ腫になりやすいということは基本的にありません。
発症に関わるリスク因子
悪性リンパ腫の直接的な原因はほとんど解明されていませんが、発症のリスクを高めると考えられるいくつかの要因が特定されています。
特定されている原因とリスク因子
| 分類 | 具体的な因子 | 関連するリンパ腫の種類 |
|---|---|---|
| ウイルス・細菌 | EBウイルス、HTLV-1、ピロリ菌など | 一部の非ホジキンリンパ腫 |
| 免疫不全 | 自己免疫疾患、臓器移植後の免疫抑制剤 | 非ホジキンリンパ腫全般 |
| その他 | 加齢、特定の化学物質への曝露 | 非ホジキンリンパ腫全般 |
初期症状と進行 – 見逃してはいけないサイン
悪性リンパ腫の症状は、発生した場所や病気の種類によって様々です。しかし、中には特徴的なサインもあります。
ここでは、どのような症状に注意すべきか、特に見逃されやすい初期症状について詳しく解説します。
最も多い初期症状「痛みのないしこり」
悪性リンパ腫の最も一般的で、かつ見過ごされやすい初期症状は、痛みを伴わないリンパ節の腫れや「しこり」です。特に首、わきの下、足の付け根など、リンパ節が多く集まる場所に現れやすいです。
通常、感染症でリンパ節が腫れる際は痛みを伴いますが、リンパ腫のしこりは痛みがないことが多いため、「大したことはない」と自己判断し、受診が遅れる原因となることがあります。
全身に現れるB症状
病気が進行すると、全身に影響が及ぶことがあります。中でも「B症状」と呼ばれる3つの特徴的な全身症状は、病気の活動性を示す重要なサインです。
B症状の具体的な内容
- 原因不明の38℃以上の発熱
- 寝具を取り替えるほどの寝汗
- 半年で10%以上の意図しない体重減少
これらのB症状(特に発熱)がみられる場合、病気が活発な状態にあることを示唆し、治療方針を決定する上で重要な情報となります。
その他の注意すべき症状
B症状以外にも、発生場所によって多彩な症状を引き起こします。胸にできれば咳や息切れ、お腹にできれば腹痛や腹部膨満感などが現れることがあります。
また、原因不明の全身の倦怠感や皮膚のかゆみが続く場合も注意が必要です。
診断の手順 – 病理検査から病期分類まで
悪性リンパ腫が疑われる場合、正確な診断を下し、病気が体のどこまで広がっているかを調べるために、いくつかの検査を行います。
診断を確定させ、適切な治療方針を立てるために、これらの検査はとても大切です。
診断を確定させるための生検
悪性リンパ腫の診断を確定させるために、最も重要な検査が「生検」です。これは、腫れているリンパ節などの組織の一部を外科的に採取し、顕微鏡で詳しく調べる病理検査です。
この検査によって、がん細胞の有無だけでなく、ホジキンリンパ腫か非ホジキンリンパ腫か、さらに細かい種類(病型)まで確定します。
病気の広がりを調べる画像検査
診断が確定したら、次に病気の広がり、すなわち病期(ステージ)を決定するために画像検査を行います。
主な画像検査とその目的
| 検査名 | 目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| CT検査 | 全身のリンパ節の腫れや臓器への広がりを評価 | X線で体の断面を撮影する |
| PET/CT検査 | がん細胞の活動性を評価し、微小な病変を発見 | がん細胞のブドウ糖代謝を利用して画像化する |
PET/CT検査は、より正確なステージ診断や、治療効果の判定に役立ちます。
病期(ステージ)の決定
検査結果を総合して、病気がどの程度広がっているかをステージで分類します。一般的に「アン・アーバー分類」を用い、I期からIV期までの4段階に分けます。
アン・アーバー分類によるステージ
| ステージ | 病変の広がり |
|---|---|
| I期 | 1つのリンパ節領域のみに病変がある |
| II期 | 横隔膜の同じ側にある2つ以上のリンパ節領域に病変がある |
| III期 | 横隔膜の両側にまたがってリンパ節領域に病変がある |
| IV期 | リンパ節以外の臓器に広範囲に病変が広がっている |
リンパ腫の場合、IV期であっても全身に効果が及ぶ化学療法などによって治癒を目指せるケースが多くあります。
もし気になる症状があれば、まずは専門の診療科である血液内科を受診することが重要です。
がん治療の実際 – 薬物療法と放射線治療の組み合わせ
悪性リンパ腫の治療は、この数十年で大きく進歩しました。治療法は、病気の種類やステージ、患者さん自身の体の状態などを総合的に考慮して決定します。
ここでは、中心となる治療法について解説します。
治療の三本柱
悪性リンパ腫の治療は、主に「化学療法」「放射線治療」「分子標的薬」の3つを組み合わせて行います。
- 化学療法(抗がん剤治療)
- 放射線治療
- 分子標的薬治療
中心となる化学療法
化学療法は、抗がん剤を用いて全身のがん細胞を攻撃する治療法で、多くのリンパ腫治療の根幹をなします。複数の薬剤を組み合わせる「多剤併用化学療法」が標準的です。
例えば、B細胞リンパ腫に対しては、分子標的薬であるリツキシマブと複数の抗がん剤を組み合わせるR-CHOP療法などが広く行われます。
その他の治療法
放射線治療は、高エネルギーのX線を病変部に照射し、がん細胞を破壊する局所的な治療法です。病変が限られている早期のリンパ腫や、化学療法の補助として用います。
分子標的薬は、がん細胞が持つ特定の分子だけを狙い撃ちする薬で、正常な細胞への影響を抑えながら高い効果が期待できます。
予後と生存率 – 病型別の治療成績データ
悪性リンパ腫と診断されたとき、多くの方が病気の今後の見通し(予後)や生存率について気にします。
ここでは、統計データに基づいた予後について解説しますが、これらの数字はあくまで平均的なものであり、一人ひとりの未来を示すものではないことを理解することが大切です。
生存率の考え方
生存率は、同じがんと診断された人のうち、特定の期間後(通常は5年後)に生存している人の割合を示す統計データです。
悪性リンパ腫全体の5年相対生存率は約70%ですが、この数値は病気の種類、ステージ、年齢など多くの要因によって大きく異なります。
病型別の5年生存率の目安
治療成績は病型によって大きく異なります。以下に代表的なリンパ腫の5年生存率の目安を示します。これはあくまで参考値であり、個々の状況によって結果は異なります。
主なリンパ腫の5年生存率データ
| リンパ腫の種類 | ステージ | 5年生存率の目安 |
|---|---|---|
| ホジキンリンパ腫 | 限局期(I, II期) | 約90% |
| 非ホジキンリンパ腫(全体) | 限局期(I, II期) | 約70-80% |
| 非ホジキンリンパ腫(全体) | 進行期(III, IV期) | 約50-60% |
治療法の進歩により、これらのデータは常に改善傾向にあります。予後については、主治医とよく話し合い、正しい情報を得ることが重要です。
再発への対処 – 二次治療の選択肢
治療によってがんが検出できなくなる「寛解」に至った後も、残念ながら一部の患者さんでは病気が再び現れる「再発」を経験することがあります。
しかし、再発した場合でも、次なる治療の選択肢があります。希望を失わずに治療に取り組むことが大切です。
再発時の治療方針
再発した場合の治療は、初回治療の内容、再発までの期間、患者さんの全身状態などを考慮して慎重に決定します。
初回とは異なる薬剤を用いた化学療法(救援化学療法)や、より強力な治療法を検討します。
強力な治療法としての造血幹細胞移植
救援化学療法で再び寛解が得られた場合、その状態を維持するために「造血幹細胞移植」を行うことがあります。
これは、大量の化学療法や放射線治療で体内のリンパ腫細胞を徹底的に叩いた後、あらかじめ採取しておいた自分自身の、あるいはドナーから提供された造血幹細胞を体に戻す治療法です。
その他の二次治療
近年では、CAR-T細胞療法のような新しい免疫療法や、次々と登場する新規薬剤など、治療の選択肢は増え続けています。
再発した場合でも、主治医と相談しながら最善の治療法を探していくことになります。
よくある質問
- 悪性リンパ腫は遺伝しますか?
-
いいえ、基本的に遺伝しません。悪性リンパ腫は、親から子へ受け継がれる遺伝子の異常ではなく、生まれてから後に個人のリンパ球に発生する後天的な遺伝子異常が原因です。
そのため、血縁者に悪性リンパ腫の患者さんがいても、ご自身が発症しやすくなるわけではありません。
- 首にしこりがあります。何科を受診すればよいですか?
-
首やわきの下などのしこりや、原因不明の発熱といった悪性リンパ腫を疑う症状がある場合、まずは血液疾患の専門家である「血液内科」を受診することを推奨します。
もし、かかりつけ医がいる場合は、まずそちらに相談し、専門医を紹介してもらうのも良いでしょう。
- ステージIVと診断されました。もう治らないのでしょうか?
-
そんなことはありません。悪性リンパ腫におけるステージIVは、他の固形がん(胃がんや肺がんなど)のステージIVとは意味合いが異なります。
リンパ腫は本質的に全身に広がりうる病気ですが、化学療法などの薬物療法が全身に行き渡りやすいため、ステージIVであっても治癒を目指せるケースはあります。希望を持って治療に臨むことが大切です。
悪性リンパ腫と同じく、血液のがんの一種に「多発性骨髄腫」があります。これは、リンパ球の一種である形質細胞ががん化し、主に骨髄で増殖する病気です。
骨の痛みや骨折、貧血、腎機能障害など、悪性リンパ腫とは異なる特徴的な症状を示します。血液のがんに関する理解をさらに深めたい方は、以下の記事もご参照ください。
参考文献
ANSELL, Stephen M.; ARMITAGE, James. Non-Hodgkin lymphoma: diagnosis and treatment. In: Mayo Clinic Proceedings. Elsevier, 2005. p. 1087-1097.
ANSELL, Stephen M. Non-Hodgkin lymphoma: diagnosis and treatment. In: Mayo Clinic Proceedings. Elsevier, 2015. p. 1152-1163.
SILKENSTEDT, Elisabeth, et al. B-cell non-Hodgkin lymphomas. The Lancet, 2024, 403.10438: 1791-1807.
CRISCI, Stefania, et al. Overview of targeted drugs for mature B-cell non-hodgkin lymphomas. Frontiers in oncology, 2019, 9: 443.
AL-NAEEB, Anna Bowzyk, et al. Non-hodgkin lymphoma. Bmj, 2018, 362.
HENNESSY, Bryan T.; HANRAHAN, Emer O.; DALY, Peter A. Non-Hodgkin lymphoma: an update. The lancet oncology, 2004, 5.6: 341-353.
EL-MALLAWANY, Nader Kim; CAIRO, Mitchell S. Advances in the diagnosis and treatment of childhood and adolescent B-cell non-Hodgkin lymphoma. Clin Adv Hematol Oncol, 2015, 13.2: 113-123.
REITER, Alfred. Diagnosis and treatment of childhood non-Hodgkin lymphoma. ASH Education Program Book, 2007, 2007.1: 285-296.
COFFEY, J.; HODGSON, D. C.; GOSPODAROWICZ, M. K. Therapy of non-Hodgkin’s lymphoma. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 2003, 30.Suppl 1: S28-S36.
COFFEY, J.; HODGSON, D. C.; GOSPODAROWICZ, M. K. Therapy of non-Hodgkin’s lymphoma. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 2003, 30.Suppl 1: S28-S36.
JIANG, Manli; BENNANI, N. Nora; FELDMAN, Andrew L. Lymphoma classification update: B-cell non-Hodgkin lymphomas. Expert review of hematology, 2017, 10.5: 405-415.