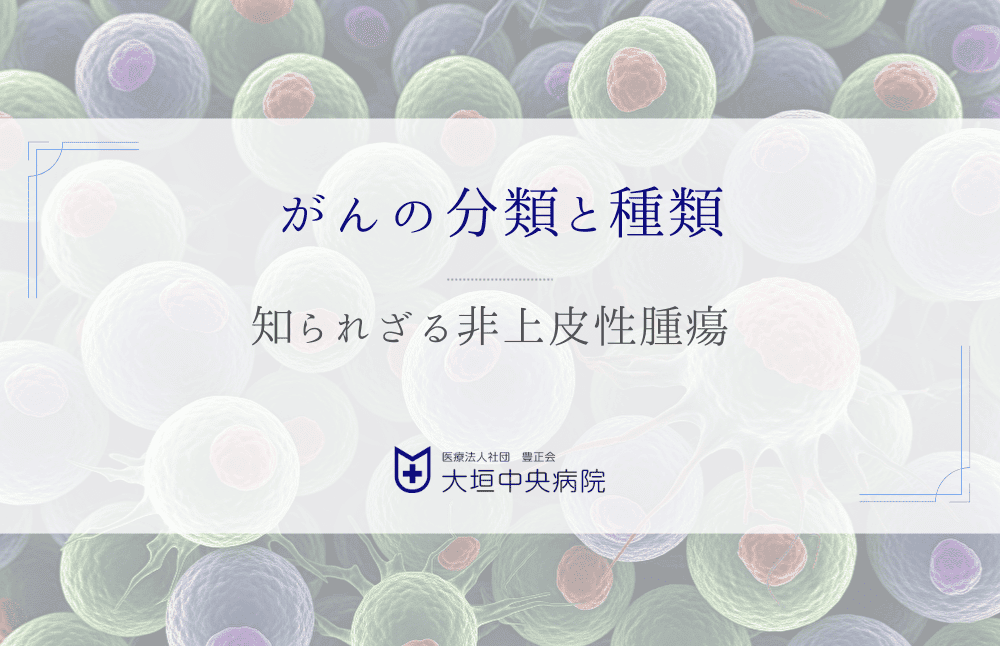「がん」と聞くと、多くの方が胃がんや肺がんのような「癌腫」を思い浮かべるかもしれません。
しかし、私たちの体を構成する骨や筋肉、神経、脂肪といった組織から発生する「非上皮性腫瘍(肉腫)」という、もう一つのがんのグループが存在します。
これらは発生頻度が低く「希少がん」に分類されるものが多いため、情報が少なく不安を感じる方も少なくありません。
この記事では、非上皮性腫瘍の全体像から、代表的な種類ごとの特徴、診断や治療の課題まで、患者さんとご家族が病気を正しく理解するための一助となる情報を提供します。
非上皮性腫瘍とは何か – 上皮以外の組織から発生するがんの全体像
私たちの体を形作る細胞は、大きく「上皮性」と「非上皮性」に分けられます。非上皮性腫瘍は、後者の細胞から発生する悪性腫瘍の総称です。
一般的に「がん」と呼ばれるものの多くが上皮細胞由来の「癌腫」であるのに対し、非上皮性腫瘍は骨、軟骨、筋肉、脂肪、血管、神経といった、体を支え、つなぐ組織から発生します。
これらは総称して「肉腫(サルコーマ)」とも呼ばれ、その種類は50種類以上にも及びます。
癌腫と肉腫の根本的な違い
癌腫と肉腫は、発生する細胞の種類が違うだけでなく、病気の性質にも違いが見られます。例えば、転移の仕方がその一つです。
癌腫はリンパ節を通って転移を広げることが多いのに対し、肉腫は血液の流れに乗って肺などの遠隔臓器に転移(血行性転移)しやすい傾向があります。この違いは治療戦略にも影響を与えます。
発生母地と主な転移経路
| 項目 | 癌腫(上皮性腫瘍) | 肉腫(非上皮性腫瘍) |
|---|---|---|
| 発生する組織 | 臓器の表面を覆う上皮細胞(胃、肺、大腸など) | 骨、軟骨、筋肉、脂肪、神経など |
| 主な転移の経路 | リンパ行性転移 | 血行性転移(特に肺) |
希少がんとしての側面
非上皮性腫瘍の多くは、発生頻度が極めて低い「希少がん」に分類されます。希少がんであることは、患者さんがいくつかの課題に直面することを意味します。
情報が少ない、診断できる専門医や医療機関が限られる、治療法の開発が進みにくいといった点です。そのため、正確な情報を得て、適切な治療にたどり着くことが非常に重要になります。
基本的な治療戦略
非上皮性腫瘍の治療は、腫瘍の種類、悪性度、進行度によって異なりますが、基本となるのは「手術」「化学療法」「放射線治療」の三つの柱です。
これらを単独で、あるいは組み合わせて治療を進めます。
- 手術(外科治療)
- 化学療法(抗がん剤治療)
- 放射線治療
特に、転移がない限局性の肉腫に対しては、手術による完全な切除が根治を目指す上での基本となります。
神経系腫瘍の特徴 – 神経鞘腫から悪性末梢神経鞘腫瘍まで
神経系から発生する非上皮性腫瘍は、末梢神経を包む「神経鞘(しんけいしょう)」という組織から生じます。多くは良性ですが、中には悪性のものも存在し、正確な診断が求められます。
手術が治療の基本となりますが、神経の機能温存が大きな課題です。
良性と悪性の境界
神経系腫瘍の代表格である「神経鞘腫」は、ほとんどが良性です。しかし、中には「悪性末梢神経鞘腫瘍(MPNST)」という悪性度の高い肉腫も存在します。
これらは神経線維腫症1型(NF1)という遺伝性疾患を持つ方に発生しやすいことが知られています。良性か悪性かの判断は、最終的に切除した組織の病理診断によって確定します。
神経系腫瘍の診断プロセス
| 検査段階 | 主な検査方法 | 目的 |
|---|---|---|
| 初期評価 | MRI、CTなどの画像検査 | 腫瘍の大きさ、場所、周囲組織との関係を把握 |
| 確定診断 | 生検による病理診断 | 良性か悪性か、腫瘍の正確な種類を特定 |
治療における専門医の役割
神経系腫瘍の手術では、腫瘍を完全に取り除きつつ、重要な神経機能をいかに温存するかが鍵となります。手足の動きや感覚に関わる神経に腫瘍ができた場合、手術の難易度は非常に高くなります。
そのため、肉腫の治療経験が豊富な整形外科医や脳神経外科医、形成外科医といった専門医による治療が重要です。
脂肪肉腫という脂肪のがん – 成人軟部悪性腫瘍で多い病型
脂肪肉腫は、脂肪細胞に由来する悪性腫瘍で、成人の軟部肉腫の中では比較的頻度の高い種類です。
太ももやお腹の奥(後腹膜)など、体の深い部分に発生することが多く、大きくなるまで症状が出ないことも少なくありません。
多様なサブタイプと悪性度
脂肪肉腫は、単一の病気ではありません。組織の見た目や遺伝子の特徴によって、いくつかのサブタイプ(病型)に分類されます。
このサブタイプによって、悪性度や転移・再発のしやすさが大きく異なります。
主な脂肪肉腫のサブタイプ
| サブタイプ名 | 特徴 | 主な治療法 |
|---|---|---|
| 高分化型脂肪肉腫 | 悪性度が低く、転移は稀。局所での再発が問題となる。 | 手術 |
| 脱分化型脂肪肉腫 | 高分化型から変化して発生。悪性度が高く、転移のリスクがある。 | 手術、化学療法 |
| 粘液型脂肪肉腫 | 比較的若い世代にも発生。特定の遺伝子異常を持つ。 | 手術、放射線治療 |
再発を防ぐための治療戦略
脂肪肉腫の治療の基本は、手術で腫瘍を完全に取り除くことです。特に、腫瘍の周りの正常な組織を含めて広く切除する「広範切除」が、局所での再発を防ぐために重要です。
悪性度の高いタイプや、手術で腫瘍が取りきれない可能性がある場合には、化学療法や放射線治療を組み合わせることもあります。治療後も定期的な検査で、再発の監視を続けることが大切です。
平滑筋肉腫の実態 – 子宮・消化管・血管壁に発生する腫瘍
平滑筋肉腫は、血管の壁や消化管、子宮など、内臓の壁を構成する「平滑筋」という筋肉から発生する悪性腫瘍です。
体のさまざまな場所に発生する可能性があり、発生部位によって症状や治療法が異なります。
子宮に発生する平滑筋肉腫
子宮にできる平滑筋肉腫は、子宮肉腫の中で最も多いタイプです。良性の「子宮筋腫」と見分けることが難しい場合があり、不正出血や腹部の張りといった症状で発見されることがあります。
治療は、子宮を摘出する手術が基本となります。
転移と治療の難しさ
平滑筋肉腫は、肺や肝臓などに血行性転移を起こしやすい性質を持っています。転移が見つかった場合や、手術で取りきれない場合には、化学療法が主な治療となります。
しかし、効果のある薬剤が限られており、治療が難しいがんの一つとされています。そのため、新しい治療薬の開発が期待されています。
発生部位による症状の違い
| 発生部位 | 主な症状 |
|---|---|
| 子宮 | 不正出血、月経異常、腹部の圧迫感 |
| 消化管 | 腹痛、下血、貧血 |
| 後腹膜 | 自覚症状が出にくく、大きくなってから発見されることが多い |
GIST(消化管間質腫瘍)- 特殊な治療が可能ながん
GIST(ジスト)は、消化管間質腫瘍の略称で、胃や小腸の壁の内部にある特殊な細胞(カハールの介在細胞)から発生する肉腫の一種です。
かつては治療が難しいがんでしたが、近年、特定の分子を狙い撃ちする「分子標的薬」の登場により、治療法が大きく進歩しました。
GISTの発生と診断
GISTの発生部位で最も多いのは胃で、次いで小腸です。症状は腹痛や吐き気、貧血などですが、無症状で検診の内視鏡検査などで偶然発見されることもあります。
診断を確定するためには、内視鏡で組織の一部を採取し、病理診断で特徴的なタンパク質(KITやDOG1)を確認します。
遺伝子検査に基づく分子標的薬の選択
GISTの発生には、KITやPDGFRAといった特定の遺伝子の異常が関わっています。そのため、治療方針を決める上で遺伝子検査が非常に重要です。
この遺伝子の異常が、がん細胞の増殖のスイッチとなっています。分子標的薬は、このスイッチをピンポイントでオフにすることで、がんの増殖を抑えます。
GIST治療で用いられる主な分子標的薬
| 治療の段階 | 薬剤名(一般名) | 主な標的 |
|---|---|---|
| 一次治療 | イマチニブ | KIT、PDGFRA |
| 二次治療 | スニチニブ | KIT、PDGFRA、VEGFRなど |
| 三次治療以降 | レゴラフェニブなど | 複数の標的 |
手術と薬物療法の組み合わせ
転移のないGISTでは、手術による切除が第一選択です。しかし、腫瘍が大きい場合や、再発のリスクが高いと判断された場合には、手術の前後に分子標的薬を使用することがあります。
手術で取りきれないほど進行した場合や、転移・再発した場合には、分子標的薬による治療が中心となります。
横紋筋肉腫の二面性 – 小児型と成人型で異なる予後
横紋筋肉腫は、骨格筋(手足を動かす筋肉)になるはずの未熟な細胞から発生する悪性腫瘍です。主に小児や思春期の若者に発生しますが、成人でも見られます。
小児に多い「胎児型」と、比較的年長の子どもや成人に多い「胞巣型」という、大きく二つのタイプがあり、性質が異なります。
小児に多い代表的な固形がん
横紋筋肉腫は、小児がんの中では代表的な固形がんの一つです。頭頸部、泌尿生殖器、手足など、体のあらゆる場所に発生する可能性があります。
同じく小児の骨に発生しやすい腫瘍として「ユーイング肉腫」があり、これらはいずれも希少がんです。
集学的治療の重要性
横紋筋肉腫の治療は、手術、化学療法、放射線治療を組み合わせた「集学的治療」が基本です。特に化学療法が治療の要であり、複数の抗がん剤を組み合わせて強力な治療を行います。
治療強度は、腫瘍の発生部位、大きさ、転移の有無、そして組織型(胎児型か胞巣型か)によって細かく決定します。
- 強力な多剤併用化学療法
- 可能な限りの腫瘍摘出術
- 局所制御のための放射線治療
予後を左右する因子
予後は、これらの集学的治療によって大きく改善しましたが、依然としていくつかの因子に左右されます。胞巣型は胎児型に比べて悪性度が高く、治療が難しい傾向にあります。
また、診断時に転移がある場合や、治療後に再発した場合の予後は厳しいのが現状です。
希少がんの診断課題 – 病理診断の専門性と重要性
非上皮性腫瘍の多くが分類される「希少がん」は、その稀さゆえに診断が非常に難しいという大きな課題を抱えています。正しい治療方針は、正しい診断から始まります。
そのため、診断のプロセス、特に病理診断の質が治療成績を大きく左右します。
なぜ診断が難しいのか
希少がんは種類が非常に多く、一つ一つの腫瘍の見た目も多様です。中には、他の一般的ながんと似た特徴を持つものもあり、見分けるのが困難な場合があります。
経験の少ない病理医では、正確な診断を下すのが難しいケースも少なくありません。
病理診断における専門医の役割
肉腫の病理診断には、高度な専門知識と豊富な経験が必要です。
病理医は、顕微鏡でがん細胞の顔つきを見るだけでなく、免疫染色という特殊な染色法や、遺伝子検査の結果などを統合的に判断して、最終的な診断を下します。
肉腫の症例を数多く経験している専門医による診断は、治療の第一歩として極めて重要です。
正確な病理診断のための要素
| 要素 | 内容 | 重要性 |
|---|---|---|
| 形態学的評価 | 顕微鏡での細胞・組織の観察 | 基本的な診断の土台 |
| 免疫染色 | 細胞が持つタンパク質を調べる | 腫瘍の由来を特定する手がかり |
| 遺伝子検査 | 腫瘍に特有の遺伝子異常を検出 | 確定診断や治療薬選択に直結 |
セカンドオピニオンの活用
診断や治療方針について、主治医以外の医師の意見を聞く「セカンドオピニオン」は、希少がんの患者さんにとって特に有益です。
特に病理診断に関するセカンドオピニオン(病理コンサルテーション)は、診断の精度を高める上で大きな意味を持ちます。
診断が確定しない、あるいは提案された治療法に疑問がある場合には、積極的にセカンドオピニオンを求めることを検討しましょう。
分子標的薬が変えた治療 – 一部の非上皮性腫瘍での進歩
近年のがん治療の進歩の中でも、分子標的薬の登場は画期的な出来事でした。
従来の抗がん剤が、がん細胞だけでなく正常な細胞にもダメージを与えてしまうのに対し、分子標的薬はがん細胞の増殖に関わる特定の分子だけを狙い撃ちします。
この治療法は、一部の非上皮性腫瘍の治療を大きく変えました。
GIST治療における革命
分子標的薬の成功例として最も有名なのが、消化管間質腫瘍(GIST)に対する治療です。GISTの多くは、KITという遺伝子の異常によって引き起こされます。
分子標的薬であるイマチニブは、このKITタンパク質の働きを阻害することで、劇的な治療効果を示しました。これにより、手術ができない進行GISTの患者さんの予後は飛躍的に向上しました。
治療薬選択と遺伝子検査
分子標的薬が効果を発揮するためには、その標的となる分子ががん細胞に存在することが前提となります。そのため、治療開始前に遺伝子検査を行い、薬が効くタイプのがんかどうかを調べることが重要です。
GIST以外にも、特定の遺伝子異常を持つ軟部肉腫など、分子標的薬の対象となる腫瘍が少しずつ増えています。
- デモイド腫瘍
- 炎症性筋線維芽細胞腫瘍(IMT)
- 胞巣状軟部肉腫
今後の展望と課題
すべての非上皮性腫瘍に有効な分子標的薬があるわけではありません。また、長期間使用していると薬が効かなくなる「耐性」という問題も生じます。
現在、新たな標的を探す研究や、耐性を克服するための新しい薬剤の開発が世界中で進められています。
代表的な分子標的薬と対象疾患
| 薬剤名(一般名) | 主な対象疾患 | 標的分子 |
|---|---|---|
| イマチニブ | GIST、皮膚線維肉腫 | KIT, PDGFRA/B |
| パゾパニブ | 進行性軟部肉腫 | VEGFR, PDGFRなど |
| トラベクテジン | 進行性軟部肉腫 | DNAに結合 |
多様な発生部位と症状 – 早期発見を困難にする要因
非上皮性腫瘍は、全身のあらゆる場所に発生する可能性があります。手足などの四肢、お腹の中(腹腔・後腹膜)、胸の中、頭頸部など、発生部位によって現れる症状はさまざまです。
また、初期には症状がほとんどないことも多く、それが早期発見を難しくする一因となっています。
症状なき「しこり」に注意
手足にできる軟部肉腫の多くは、初期には痛みを伴わない「しこり」として自覚されます。痛みがないため放置され、大きくなってから医療機関を受診するケースが少なくありません。
急に大きくなってきた、サイズが5cm以上ある、体の深い部分にある、といった特徴を持つしこりには注意が必要です。
腹腔内・後腹膜の腫瘍
お腹の中にできる腫瘍は、かなり大きくなるまで無症状のことがほとんどです。お腹の張りや不快感、食欲不振、あるいは他の病気の検査で偶然発見されることもあります。
GISTや平滑筋肉腫、脂肪肉腫などがこの部位に好発します。
転移・再発の監視の重要性
治療後も、非上皮性腫瘍は局所での再発や、肺などへの遠隔転移のリスクを伴います。
そのため、治療が終わった後も、定期的にCTやMRIなどの画像検査を受け、再発や転移が起きていないかを注意深く監視していくことが非常に大切です。
もし再発や転移が見つかっても、早期であれば次の治療に繋げられる可能性があります。
よくある質問
- 肉腫と診断されました。どの診療科にかかればよいですか?
-
肉腫の治療は、発生した部位や腫瘍の種類によって専門とする診療科が異なります。
骨や手足の軟部組織にできた場合は整形外科、お腹の中のGISTや平滑筋肉腫などは消化器外科、子宮肉腫は婦人科が中心となります。
しかし、最も重要なのは「肉腫の治療経験が豊富な医師・医療機関」を選ぶことです。
まずは主治医と相談し、必要であれば肉腫を専門とするがんセンターや大学病院への紹介を検討してもらいましょう。
- セカンドオピニオンを受けたいのですが、主治医に失礼になりませんか?
-
セカンドオピニオンは、患者さんが納得して治療を受けるための正当な権利です。多くの医師はその重要性を理解しており、失礼にあたることはありません。
むしろ、患者さんが積極的に治療に関わろうとする姿勢として、好意的に受け止める医師がほとんどです。
セカンドオピニオンを希望する際は、遠慮なく主治医にその旨を伝え、紹介状や検査データを提供してもらいましょう。
- 治療法の選択で迷っています。何を基準に考えればよいですか?
-
治療法の選択は、医学的なエビデンス(科学的根拠)に基づいて行われるのが基本です。
まずは、ご自身の病状(腫瘍の種類、進行度など)に対して、標準治療(現時点で最も効果が期待できるとされている治療)が何かを主治医から詳しく説明してもらうことが大切です。
その上で、治療による効果の期待値と、副作用などのデメリットを天秤にかけ、ご自身の価値観やライフスタイルも考慮して、最終的な方針を決定していきます。
分子標的薬の適応を調べるための遺伝子検査など、判断材料となる検査についても確認しましょう。
治療法選択の判断材料
判断材料 確認すべきことの例 医学的根拠 標準治療は何か、治療成績(生存率、再発率など) 治療の利益と不利益 期待される効果、副作用の種類と程度、生活への影響 個人の価値観 仕事や家庭との両立、治療期間、費用、希望する生活の質
以上
参考文献
HART, Jesse; YANG, Heejae; OU, Jao. Non-epithelial Tumors. In: General Pathology Student Guide: With AMBOSS Shortcuts. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2024. p. 150-159.
ZHANG, Lizhi. Malignant mesenchymal tumors. In: Surgical Pathology of Liver Tumors. Cham: Springer International Publishing, 2015. p. 295-322.
SCHWARZKOPF, Eugenia; BOLAND, Patrick. Mesenchymal and Non‐Epithelial tumors of the pelvis. Surgical Management of Advanced Pelvic Cancer, 2021, 283-297.
ZEVALLOS-GIAMPIETRI, Eduardo-Alfredo; BARRIONUEVO, Carlos. Proximal-type epithelioid sarcoma: report of two cases in the perineum: differential diagnosis and review of soft tissue tumors with epithelioid and/or rhabdoid features. Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology, 2005, 13.3: 221-230.
PANTANOWITZ, Liron; CHIVUKULA, Mamatha. Serous fluid: metastatic sarcomas, melanoma, and other non-epithelial neoplasms. CytoJournal, 2022, 19: 15.
MIETTINEN, Markku. Primary soft tissue tumors with epithelial differentiation. Modern Soft Tissue Pathology: Tumors and Non‐Neoplastic Conditions, 2017, 744-776.
KUMAR, Dhruv. Pathology of bone and soft tissue sarcomas. In: Sarcoma: A Multidisciplinary Approach to Treatment. Cham: Springer International Publishing, 2017. p. 23-41.
FRANCHI, Alessandro. Epithelial tumors. In: Pathology of sinonasal tumors and tumor-like lesions. Cham: Springer International Publishing, 2019. p. 85-145.
ALODAINI, Amal A. Uterine mesenchymal tumors: updates on pathology, molecular landscape, and therapeutics. Medicina, 2024, 60.7: 1085.
FUKUNAGA, Masaharu. Pathology of Non-epithelial Ovarian Tumors. Frontiers in Ovarian Cancer Science, 2017, 115-141.