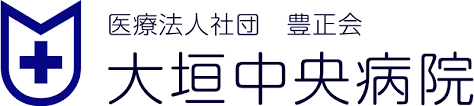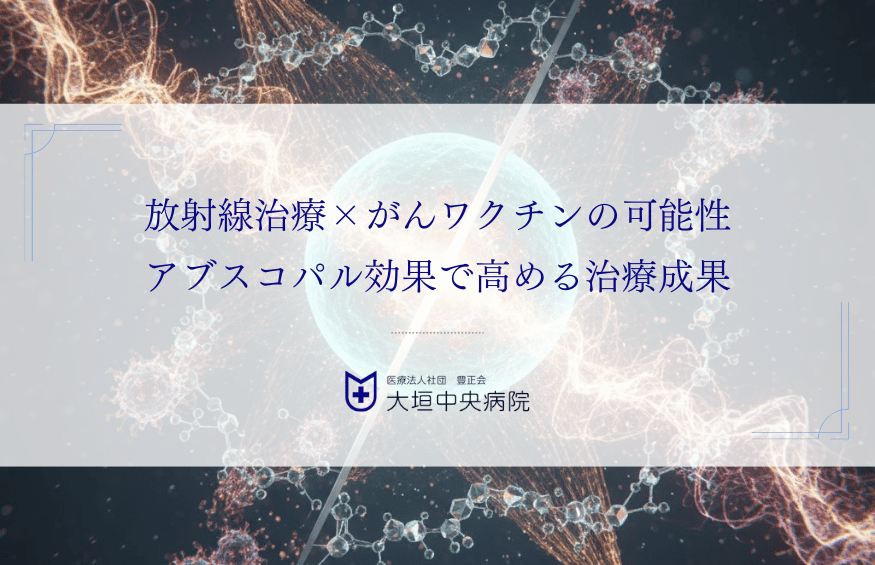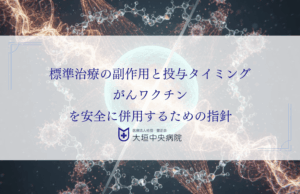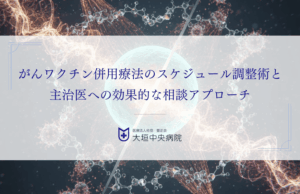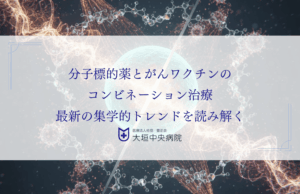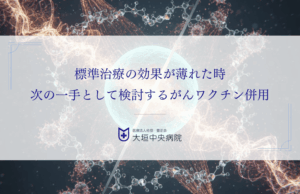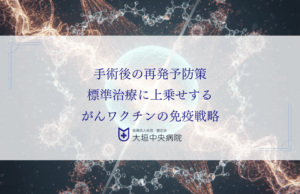局所的な治療であるはずの放射線照射が、遠く離れた場所にある転移がんまで縮小させる現象をご存知でしょうか。
これは「アブスコパル効果」と呼ばれ、がん治療において長年注目され続けている現象です。しかし、この現象が自然に発生する確率は極めて低いのが現実でした。
そこで現在、この奇跡のような現象を意図的に引き起こし、治療効果を確実なものにするために研究が進められているのが、放射線治療とがんワクチン(免疫療法)の組み合わせです。
本記事では、なぜこの二つを組み合わせることで治療成果が高まるのか、その理由と具体的な仕組みについて詳しく解説し、新たな選択肢を模索する方々へ希望となる情報をお届けします。
放射線治療がもたらす免疫原性細胞死の意義
放射線治療は、がん細胞を破壊する過程で「免疫原性細胞死」を誘導し、がん抗原の放出と免疫系の活性化シグナルを通じて、全身的な免疫反応の引き金となる重要な役割を果たします。
がん細胞の破壊と抗原の放出
放射線治療は、高エネルギーのX線や粒子線をがん病巣に照射し、がん細胞のDNAを切断することで増殖能力を奪います。
この時、放射線によって傷ついたがん細胞は、アポトーシス(プログラムされた細胞死)やネクローシス(壊死)といった形で死滅します。
重要なのは、この細胞死の過程において、通常は細胞の中に隠されている「がん抗原(がんの目印となるタンパク質)」が細胞の外へ大量に放出される点です。
放出されたがん抗原は、周囲に存在する免疫細胞、特に樹状細胞によって取り込まれます。
樹状細胞は免疫の司令塔とも言える存在であり、取り込んだ抗原を分解し、その情報を攻撃部隊であるT細胞へと伝えます。
すなわち、放射線治療はがんを小さくするだけでなく、体内で「自家製のがんワクチン」を作っているような状態を生み出していると言えます。
この現象を有効活用できるかどうかが、治療成果を左右する鍵となります。
免疫寛容の解除と攻撃の合図
がん細胞は賢く、免疫細胞からの攻撃を避けるために、自らを隠したり、免疫細胞の働きを抑制したりする能力を持っています。これを「免疫寛容」や「免疫逃避」と呼びます。
通常の状態では、免疫細胞はがん細胞を「異物」として認識できず、攻撃を開始しません。
しかし、放射線照射によってがん細胞がストレスを受けると、カルレティキュリンなどの「私を食べて」というシグナル物質を細胞表面に出したり、HMGB1などの危険信号を周囲に撒き散らしたりします。
放射線治療の役割と免疫への影響
| 視点 | 直接的な作用 | 免疫系への波及効果 |
|---|---|---|
| 細胞レベル | DNA二重鎖切断による細胞死の誘導 | がん抗原および危険信号(DAMPs)の放出 |
| 組織レベル | 腫瘍の縮小、血管損傷 | 局所炎症の誘発、免疫細胞の浸潤促進 |
| 全身レベル | 基本的には影響なし(局所のみ) | 活性化T細胞の循環による遠隔転移への攻撃可能性 |
これらのシグナルは、眠っていた免疫システムを強制的に目覚めさせる役割を果たします。放射線治療によって局所の炎症反応が誘発されると、免疫細胞ががん病巣に集まりやすくなります。
これまで免疫抑制状態にあったがんの微小環境が変化し、免疫細胞が活動しやすい環境へと整えられていくのです。
この環境変化こそが、がんワクチン療法の効果を最大化するための土台となります。
局所治療が全身治療へ変わる瞬間
従来の考え方では、放射線治療はあくまで「照射した場所だけを治す」局所療法でした。
しかし、前述のように免疫システムが活性化され、がん抗原を記憶したT細胞(キラーT細胞)が血液やリンパ液に乗って全身を巡り始めると、話は変わります。
これらのT細胞は、照射していない他の臓器にある転移巣も見つけ出し、攻撃するようになります。
これが放射線治療が局所療法の枠を超え、全身療法としての性質を帯びる瞬間です。
ただ、放射線治療単独では、この免疫活性化の力が不十分な場合が多く、強力な免疫抑制ブレーキがかかっている進行がんにおいては、十分な全身効果が得られないことがあります。
そこで、免疫の力をさらに後押しするがんワクチンの併用が必要となるのです。
アブスコパル効果の正体と発現の難しさ
アブスコパル効果の本質は、局所治療をきっかけとした全身的な抗腫瘍免疫の活性化ですが、患者体内の免疫抑制環境がその発現を阻んでおり、自然発生は極めて稀な現象です。
アブスコパル効果の歴史と定義
「アブスコパル(Abscopal)」という言葉は、ラテン語の「ab(離れた)」と「scopus(標的)」を組み合わせた造語で、1953年にモール(Mole)によって提唱されました。
かつては原因不明の不思議な現象とされていましたが、近年の免疫学の発展により、その正体が「免疫介在性の抗腫瘍効果」であることが明らかになりました。
つまり、放射線によって破壊されたがん細胞から放出された抗原を免疫細胞が認識し、全身をパトロールして同じ抗原を持つがん細胞を攻撃した結果です。
この効果が発現すれば、手術が難しい多発性の転移がんに対しても、一箇所の放射線治療をきっかけに全身の病変を制御できる可能性があります。
これは進行がんの患者様にとって非常に大きな希望となります。
自然発生が稀である理由
理論上は素晴らしいアブスコパル効果ですが、実際の臨床現場で放射線治療単独によってこの現象が観察されることは極めて稀です。
その主な理由は、がん患者様の体内では強い「免疫抑制」が働いているためです。
がん細胞は免疫チェックポイント分子を使ったり、制御性T細胞などの抑制的な細胞を呼び寄せたりして、免疫の攻撃にブレーキをかけ続けています。
アブスコパル効果の発生条件整理
| 要素 | 通常の状態(発生しない) | アブスコパル効果発現時 |
|---|---|---|
| 抗原提示 | 不十分または免疫寛容により無視される | 樹状細胞が抗原を認識し、T細胞へ伝達成功 |
| T細胞の活性 | 不活性または腫瘍微小環境で疲弊 | 活性化し、血流に乗り全身を循環 |
| 遠隔転移巣 | 増大を続ける | 免疫細胞の攻撃により縮小・消失 |
放射線によって一時的に免疫のスイッチが入ったとしても、この強力なブレーキを解除しきれなければ、全身を巡るほどの強い攻撃力を持ったT細胞は育ちません。
また、放出された抗原を樹状細胞がうまく取り込めない、あるいは樹状細胞が成熟しないといった理由でも、免疫反応は途中で止まってしまいます。
だからこそ、自然発生を待つのではなく、人為的に免疫をブーストする介入が必要なのです。
現代医療における再現への挑戦
現在、世界中でアブスコパル効果を確実に引き出すための臨床試験が行われています。その中心的な戦略が、免疫チェックポイント阻害薬やがんワクチンとの併用です。
免疫のブレーキを外す薬や、免疫のアクセルを強く踏むワクチンを組み合わせることで、放射線治療が作った「きっかけ」を無駄にせず、強力な全身性の免疫反応へと増幅させようとしています。
単独では弱い火種を、併用療法によって大きな炎に変えること。これが現代におけるアブスコパル効果狙いの治療戦略の核心です。
特にがんワクチンは、特定の抗原に対する攻撃力をピンポイントで高めることができるため、効率的な免疫誘導が期待されています。
がんワクチンの種類とそれぞれの役割
樹状細胞ワクチンやペプチドワクチンなど、がんワクチンには複数の種類が存在し、それぞれ異なるメカニズムで免疫系を教育してがん細胞への特異的な攻撃力を高めます。
樹状細胞ワクチンの特徴
樹状細胞は、免疫システムにおける「司令塔」の役割を果たします。この樹状細胞を患者様の血液から取り出し、体外でがん抗原を取り込ませて教育し、再び体内に戻すのが樹状細胞ワクチンです。
人工的に培養・活性化された樹状細胞は、体内で強力にT細胞へ攻撃指令を出します。
放射線治療と併用する場合、放射線によって死滅したがん細胞から放出される多様な抗原を、強化された樹状細胞が効率よく拾い上げるため、相乗効果が期待できます。
また、患者様自身の細胞を使うため、副作用が比較的少ないのも特徴です。
ペプチドワクチンの仕組み
ペプチドとは、タンパク質の断片のことです。特定のがん細胞に多く発現している抗原タンパク質の一部(ペプチド)を人工的に合成し、これを皮下注射などで投与します。
体内に入ったペプチドは、体内の樹状細胞に取り込まれ、それが目印となってT細胞が活性化されます。
主要ながんワクチンの比較
| ワクチン種類 | 主成分 | 主な作用機序 |
|---|---|---|
| 樹状細胞ワクチン | 患者本人の樹状細胞 | 司令塔細胞を強化し、T細胞へ正確な指令を送る |
| ペプチドワクチン | 合成抗原ペプチド | 特定の目印(抗原)を認識させ、T細胞を誘導する |
| mRNAワクチン | 抗原の遺伝情報 | 体内で抗原タンパク質を作らせ、免疫反応を起こす |
ペプチドワクチンは、あらかじめ攻撃目標が定まっているため、その抗原を持つがん細胞に対して鋭い攻撃力を発揮します。
放射線治療と組み合わせることで、放射線で弱ったがん細胞に対して、ペプチドで訓練されたT細胞が追い打ちをかけるような形での治療が可能になります。
その他のがんワクチン療法
上記以外にも、がん細胞そのものを使う全がん細胞ワクチンや、DNAやmRNAを使った遺伝子ワクチンなどの研究も進んでいます。
これらは、より多くの抗原情報を免疫系に提示したり、より強く免疫を刺激したりすることを目的としています。
どのワクチンを選択するかは、患者様のHLA(白血球の型)やがんの種類、発現している抗原の種類によって慎重に決定する必要があります。
放射線治療とがんワクチンの相乗効果
放射線治療による抗原放出とがんワクチンによる免疫教育を組み合わせることで、単独療法では成し得ない強力な免疫反応と持続的な抗腫瘍効果を生み出します。
In Situ Vaccination(生体内ワクチン)という概念
この併用療法を理解する上で重要なキーワードが「In Situ Vaccination(その場でのワクチン化)」です。
放射線治療によってがん病巣そのものをワクチンの原料(抗原の供給源)に変え、そこにがんワクチン(免疫の教育係)を加えることで、体内全体を巨大なワクチン工場にするという考え方です。
通常のがんワクチン療法では、特定の一種類あるいは数種類の抗原しか標的にできないことがあります。
しかし、放射線によってがん細胞が破壊されると、その患者様固有の多種多様な抗原が一気に放出されます。
ここで免疫系が適切に刺激されれば、未知の抗原も含めた「オーダーメイドの攻撃部隊」が体内で作られることになり、がんの多様性に対応できる可能性が高まります。
免疫抑制環境の打破
がんの組織内は、免疫細胞にとって非常に過酷な環境です。
酸素が少なく、免疫を抑える物質が充満しているため、せっかくワクチンでT細胞を活性化しても、がん病巣に到達した途端に無力化されてしまうことが課題でした。
放射線治療は、この環境を一変させます。血管の透過性を高めてT細胞ががん組織に入り込みやすくしたり、炎症性サイトカインの分泌を促して免疫細胞を呼び寄せたりします。
つまり、放射線治療が「道を切り拓き」、がんワクチンによって訓練された「精鋭部隊」がその道を通って本丸を攻める、という連携プレーが成立するのです。
併用によるメリットの整理
- がん細胞の破壊に伴い、ネオアンチゲンを含む多種多様な抗原が一挙に供給され、免疫系の標的認識能力が向上すること。
- 腫瘍微小環境が免疫抑制的な状態から炎症性の状態へと変化し、免疫細胞が腫瘍内部へ浸潤しやすくなること。
- 強力な免疫応答の結果として長期的な免疫記憶が形成され、将来的な再発リスクの低減に寄与すること。
メモリーT細胞による長期的な監視
治療効果が一過性で終わらないことも、この併用療法の大きな利点です。強力に活性化された免疫反応の結果、がんの特徴を記憶した「メモリーT細胞」が体内に残ります。
その結果、もし将来的に微小ながん細胞が再増殖しようとしても、免疫システムが即座に反応して排除することが期待できます。
再発予防の観点からも、放射線とワクチンの併用は理にかなった戦略と言えます。
免疫細胞の働きとミクロな視点
樹状細胞による抗原提示、キラーT細胞の増殖と攻撃、そして腫瘍環境の改善という一連の細胞レベルでの連携が、アブスコパル効果を現実に導く鍵となります。
樹状細胞の成熟と移動
放射線照射を受けた組織では、DAMPs(ダメージ関連分子パターン)と呼ばれる危険信号が放出されます。未熟な樹状細胞はこの信号を感知して活性化し、がん抗原を取り込みながら成熟します。
成熟した樹状細胞はリンパ管を通って近くのリンパ節へと移動します。この移動こそが、免疫応答のスタートラインです。
細胞たちの連携プレー
| 細胞名 | 役割 | 併用療法における重要性 |
|---|---|---|
| 樹状細胞 | 抗原提示、司令塔 | 放射線で放出された抗原を拾い、T細胞へ伝える |
| キラーT細胞 | 実行部隊 | 全身を巡り、原発巣および転移巣を攻撃する |
| 制御性T細胞 | 免疫の抑制 | 放射線や併用薬により、この細胞の妨害を抑えることが重要 |
がんワクチン(特に樹状細胞ワクチン)を併用する場合、元気で質の良い樹状細胞が大量に供給されるため、この初期段階が強力に後押しされます。
キラーT細胞の教育と増殖
リンパ節に到着した樹状細胞は、取り込んだがん抗原の情報をヘルパーT細胞やキラーT細胞(細胞傷害性T細胞)に提示します。
「この顔つきの細胞を攻撃せよ」という指名手配書が渡されるイメージです。情報を受け取ったキラーT細胞は、爆発的に増殖し、リンパ節を出て血流に乗ります。
通常、がん患者様の体内ではこの教育プロセスがうまくいかないことが多いですが、ワクチンの併用により、明確な指令を受けたT細胞を効率よく増やすことができます。
Cold TumorをHot Tumorへ
免疫学的に、免疫細胞が浸潤しておらず免疫反応が起きていないがんを「Cold Tumor(冷たい腫瘍)」、逆に免疫細胞が活発に攻撃しているがんを「Hot Tumor(熱い腫瘍)」と呼びます。
多くのがんはCold Tumorであり、これが免疫療法の効きにくい原因です。放射線治療は、炎症を起こすことでCold TumorをHot Tumorへと転換させる力を持っています。
Hotになった腫瘍は、ワクチンによって誘導されたT細胞にとって格好の標的となります。
適応となるがんの種類と条件
固形がん全般に可能性が開かれていますが、治療効果を最大限に引き出すためには、患者様の免疫機能や標的病変の状態を慎重に見極める必要があります。
固形がん全般への可能性
肺がん、乳がん、前立腺がん、膵臓がん、頭頸部がん、悪性黒色腫(メラノーマ)などの固形がんに対して、この併用療法は広く検討されています。
特に、放射線治療の感受性が高いがんであれば、多くの抗原放出が期待できるため、免疫誘導のきっかけを作りやすくなります。
また、これまでの標準治療が効かなくなった進行がんや再発がんにおいても、新たな治療の選択肢として検討されます。
免疫状態の評価
この治療の主役は、あくまで患者様自身の「免疫力」です。
したがって、リンパ球数が極端に少ない場合や、重篤な自己免疫疾患がある場合、あるいは抗がん剤治療直後で骨髄機能が著しく低下している場合は、十分な効果が得られない可能性があります。
治療前には血液検査などで免疫の状態を詳細に評価し、免疫細胞が戦える状態にあるかを確認する必要があります。
適応を検討する主な要素
- 放射線照射が安全かつ有効に行える標的病変が体内に少なくとも一箇所存在すること。
- 血液中のリンパ球数などが一定水準に保たれており、患者自身の免疫機能が維持されていること。
- 特定のワクチン(ペプチドワクチン等)を使用する場合は、HLA型(白血球の型)が適合していること。
標的となる病変の有無
アブスコパル効果を狙うためには、放射線を照射するための「標的病変」が必要です。照射によって安全に抗原を放出させられるサイズや場所にある腫瘍が存在することが条件となります。
全ての腫瘍に照射するのではなく、あくまで免疫を起動させるための「スイッチ」として一箇所あるいは数箇所を選定して照射を行います。
治療の流れとスケジューリング
放射線照射とワクチン投与のタイミングを最適化し、免疫反応の波に乗るような綿密な治療計画を立てることが、成功への鍵を握ります。
事前の検査と計画
まず、CTやMRI、PET検査などでがんの広がりを確認し、どの病変に放射線を当てるかを決定します。
同時に、血液検査(HLA検査や免疫機能検査)を行い、どのがんワクチンが適合するかを選定します。
樹状細胞ワクチンを行う場合は、成分採血(アフェレーシス)を行い、血液から単球を取り出してワクチンの製造を開始します。
放射線照射の実施
放射線治療のスケジュールは、通常の根治照射とは異なる場合があります。
免疫を刺激するためには、一度に大量の放射線を当てる「寡分割照射(1回大線量で数回照射)」などが有効であるという研究報告が多くあります。通常、数日から数週間にわたって照射が行われます。
一般的な治療タイムライン例
| フェーズ | 主な内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 準備期 | 免疫検査、HLA検査、採血(ワクチン製造用) | 治療開始の2〜3週間前 |
| 治療期 | 放射線照射とがんワクチンの投与 | 1〜2ヶ月間(同時または連続) |
| 評価期 | 画像診断、血液検査による効果判定 | 治療終了から1〜3ヶ月後 |
ワクチンの投与タイミング
ワクチンの投与時期については、放射線治療と同時、あるいは放射線治療の直後が適していると考えられています。
放射線によって抗原が放出されているまさにそのタイミングで、免疫細胞が活性化している必要があるためです。
具体的なスケジュールは、使用するワクチンの種類や患者様の状態によって個別化されます。数週間おきに複数回の投与を行うのが一般的です。
効果判定とフォローアップ
治療後は、画像検査や腫瘍マーカー、免疫学的指標を用いて効果を判定します。アブスコパル効果は即座に現れるとは限らず、数ヶ月かけてゆっくりと腫瘍が縮小していくこともあります。
また、一見腫瘍が大きくなったように見えても、実は免疫細胞が集まって炎症を起こしているだけ(シュードプログレッション)の場合もあるため、慎重な経過観察が必要です。
副作用とリスク管理
局所的な炎症と全身的な免疫反応のバランスを適切にコントロールし、自己免疫疾患などのリスクを管理しながら治療を進めることが重要です。
放射線治療による局所的な副作用
放射線治療の副作用は、基本的に照射した部位に限定されます。皮膚の赤み(皮膚炎)、照射部位周辺の臓器の炎症(例えば肺なら放射線肺臓炎、食道なら食道炎)などが挙げられます。
これらは予測可能なものが多く、対症療法でコントロールできる場合がほとんどです。
想定される副作用とその対策
| 症状の種類 | 具体例 | 主な対策・処置 |
|---|---|---|
| 局所反応 | 照射野の皮膚炎、注射部位の硬結 | 保湿剤、軟膏処置、冷やす |
| 全身反応 | 発熱、倦怠感、関節痛 | 解熱鎮痛剤の使用、安静、水分補給 |
| 免疫関連有害事象 | 間質性肺炎、腸炎、甲状腺機能障害 | 早期発見、ステロイド投与、免疫抑制剤 |
がんワクチンによる全身反応
がんワクチンは免疫反応を利用するため、注射部位の赤みや腫れ、発熱、倦怠感といったインフルエンザ様症状が出ることがあります。
これらは免疫が活性化している証拠でもあり、通常は数日で軽快します。重篤な副作用は稀ですが、アレルギー反応などには注意が必要です。
併用療法特有の注意点
併用によって免疫が強力に活性化される結果、正常な細胞まで攻撃してしまう「自己免疫疾患」のような症状が現れる可能性はゼロではありません。
間質性肺炎や大腸炎、内分泌障害などが報告されています。しかし、医師は定期的な検査でこれらの兆候を早期に発見し、ステロイド剤の使用などで適切に対処する体制を整えています。
リスクを恐れすぎるのではなく、リスクを知った上で適切な管理を受けることが大切です。
Q&A
- 放射線治療とワクチンを併用すれば必ず転移巣は消えますか?
-
残念ながら、すべての患者様で遠隔転移が消失するわけではありません。
アブスコパル効果の発現率は向上していますが、がんの種類や遺伝子変異、個々の免疫状態によって効果には個人差があります。
しかし、単独治療では効果が期待できなかった症例でも、併用によって病勢コントロールが可能になるケースは増えており、治療の選択肢として検討する価値は十分にあります。
- 治療中に痛みはありますか?
-
放射線照射そのものに痛みや熱さは伴いません。治療中にじっとしている必要はありますが、撮影のような感覚で終わります。
がんワクチンの投与は皮下注射や皮内注射で行われるため、一般的な予防接種と同じようなチクリとする痛みはありますが、耐えられないような激痛を伴う処置ではありません。
安心して受けていただけます。
- 抗がん剤治療中でも受けられますか?
-
抗がん剤の種類や時期によっては併用が可能な場合もありますし、逆に抗がん剤によって免疫機能が低下している時期は避けたほうが良い場合もあります。
また、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬との併用に関しては、相乗効果が期待できる組み合わせもあります。
主治医と現在の治療状況を詳しく共有し、適切なタイミングを相談することが大切です。
- 標準治療の免疫チェックポイント阻害薬との違いは何ですか?
-
オプジーボやキイトルーダなどの免疫チェックポイント阻害薬は、免疫細胞にかかった「ブレーキを外す」薬です。
一方、がんワクチンは免疫細胞に攻撃目標を教え、「アクセルを踏む」役割を果たします。これらは作用点が異なるため、競合するものではありません。
むしろ、放射線治療、免疫チェックポイント阻害薬、がんワクチンの三者を組み合わせることで、さらに強力な効果を目指す治療戦略も研究されています。
参考文献
JOHNSON, C. Bryce; JAGSI, Reshma. The promise of the abscopal effect and the future of trials combining immunotherapy and radiation therapy. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 2016, 95.4: 1254-1256.
CRAIG, Daniel J., et al. The abscopal effect of radiation therapy. Future Oncology, 2021, 17.13: 1683-1694.
REYNDERS, Kobe, et al. The abscopal effect of local radiotherapy: using immunotherapy to make a rare event clinically relevant. Cancer treatment reviews, 2015, 41.6: 503-510.
NG, John; DAI, Tong. Radiation therapy and the abscopal effect: a concept comes of age. Annals of translational medicine, 2016, 4.6: 118.
JATOI, Ismail; BENSON, John R.; KUNKLER, Ian. Hypothesis: can the abscopal effect explain the impact of adjuvant radiotherapy on breast cancer mortality?. NPJ Breast Cancer, 2018, 4.1: 8.
ASHRAFIZADEH, Milad, et al. Abscopal effect in radioimmunotherapy. International immunopharmacology, 2020, 85: 106663.
BRIX, Nikko, et al. Abscopal, immunological effects of radiotherapy: narrowing the gap between clinical and preclinical experiences. Immunological reviews, 2017, 280.1: 249-279.
LIU, Yang, et al. Abscopal effect of radiotherapy combined with immune checkpoint inhibitors. Journal of hematology & oncology, 2018, 11.1: 104.
RÜCKERT, Michael, et al. Combinations of radiotherapy with vaccination and immune checkpoint inhibition differently affect primary and abscopal tumor growth and the tumor microenvironment. Cancers, 2021, 13.4: 714.
NGWA, Wilfred, et al. Using immunotherapy to boost the abscopal effect. Nature Reviews Cancer, 2018, 18.5: 313-322.