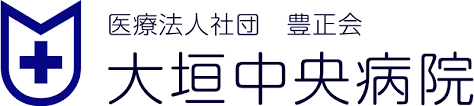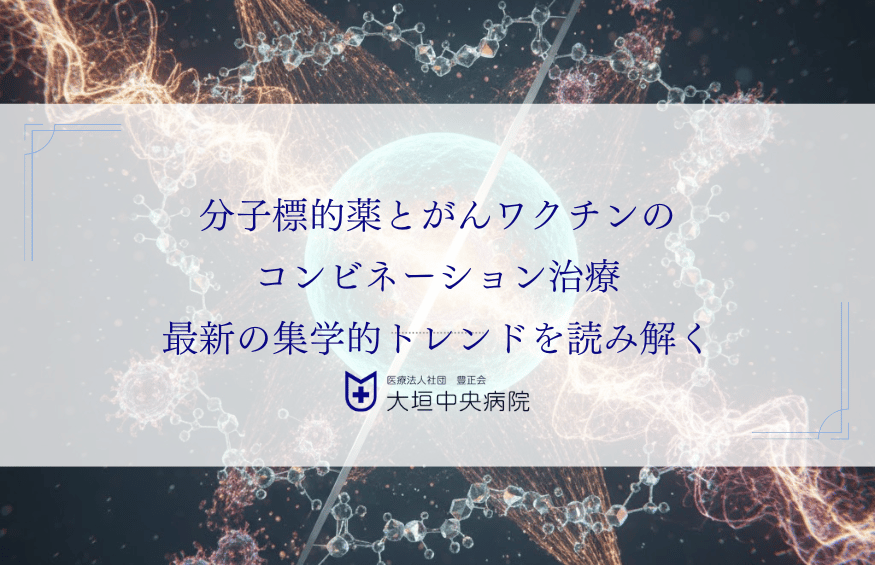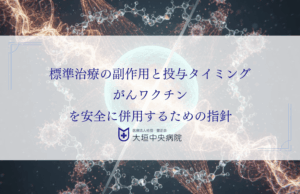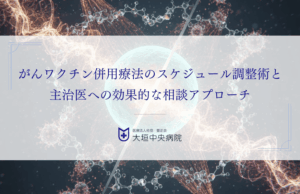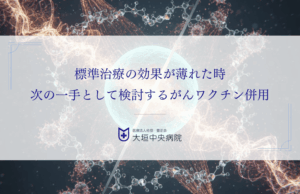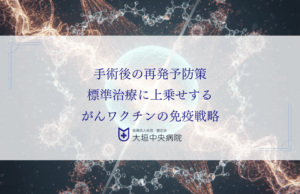がん治療の領域において、個々の患者が持つ遺伝子変異や免疫環境に合わせた精密医療が進展しています。
中でも、がん細胞の特定の分子を狙い撃ちにする「分子標的薬」と、患者自身の免疫力を特異的に向上させる「がんワクチン」を組み合わせる治療法は、互いの利点を増幅し合う集学的アプローチとして大きな注目を集めています。
単独の治療では克服が難しかった耐性問題や腫瘍微小環境の壁に対し、多角的に作用することで治療効果の底上げを図ることが可能です。
本稿では、この二つの異なる作用原理を持つ治療法がどのように融合し、新しい治療の地平を切り拓いているのか、その相乗効果の核心と実践的な知識について詳しく解説します。
分子標的薬とがんワクチンの相乗効果が生み出す治療の可能性
分子標的薬とがんワクチンを併用することで、がん細胞への直接的な攻撃と免疫系による持続的な監視という二つの作用が重なり合い、単独療法よりも高い奏効率と再発予防効果が期待されます。
分子標的薬ががん細胞を攻撃して崩壊させる際に放出される抗原を、がんワクチンによって活性化された免疫細胞が効率よく認識するという好循環を生み出すことができます。
がん細胞の「視認性」を高める相互作用
がん細胞は、免疫細胞からの攻撃を逃れるために、自らの目印となる抗原を隠蔽したり、免疫抑制物質を放出したりして身を守ります。ここで分子標的薬が重要な役割を果たします。
特定の分子標的薬は、がん細胞にストレスを与えることで、細胞表面に「免疫細胞に見つけられやすい目印」を強制的に提示させる働きがあります。
その結果、がんワクチンによって教育され、特定の敵を探し回っているキラーT細胞(細胞傷害性T細胞)が、隠れていたがん細胞を発見しやすくなります。
この現象は免疫原性細胞死(ICD)と呼ばれる反応とも関連しており、単にがん細胞を減らすだけでなく、その死に方によって周囲の免疫細胞を刺激し、攻撃の連鎖を引き起こすきっかけを作ります。
つまり、分子標的薬が「露払い」を行い、がんワクチンが「本隊」として突入するような連携が体内で成立するのです。
相乗効果の概要
| 治療法 | 主な役割 | 併用によるメリット |
|---|---|---|
| 分子標的薬 | がん細胞の増殖シグナル遮断・細胞死誘導・微小環境の調整 | がん抗原の放出を促し、免疫細胞が攻撃しやすい環境を作る |
| がんワクチン | 特異的抗原に対するT細胞の誘導・活性化・免疫記憶の形成 | 標的薬で弱ったがん細胞を効率的に排除し、長期的な再発を防ぐ |
腫瘍微小環境の改善による免疫細胞の浸潤促進
がん組織の周囲には、腫瘍微小環境と呼ばれる特殊な場が形成されています。
この環境内では、血管が異常な構造になっていたり、免疫を抑制する細胞が集まっていたりするため、通常の免疫細胞はがんの深部まで到達できません。
一部の分子標的薬、特に血管新生阻害薬などは、この乱れた血管構造を正常化させる作用を持ちます。
血管が正常化すると、血液の流れに乗って運ばれてきた、がんワクチン由来の活性化リンパ球が、腫瘍の内部へとスムーズに侵入できるようになります。
物理的な障壁を取り除くことで、ワクチンの効果を最大限に発揮させる土壌を整えるのです。この環境整備こそが、コンビネーション治療における重要な戦略の一つです。
薬剤耐性の克服に向けた多角的アプローチ
分子標的薬の課題として、長期間の使用によりがん細胞が変異し、薬が効かなくなる「耐性」の出現が挙げられます。
がん細胞は生存するために、攻撃されているシグナル伝達経路とは別の回路を使って増殖しようとします。
しかし、がんワクチンを併用している場合、異なる作用経路で攻撃が継続されるため、薬剤耐性を持ったクローン(変異細胞)が増殖する隙を与えません。
免疫系は多様な抗原に対応できる柔軟性を持っているため、分子標的薬の攻撃を回避しようと変化したがん細胞に対しても、即座に対応して排除する可能性があります。
このように、作用点の異なる治療を重ねることは、がんの逃げ道を塞ぐという意味で非常に合理的です。
分子標的薬の基本原理とがん種別の適合性
分子標的薬は、がん細胞の増殖や生存に関わる特定のタンパク質や遺伝子を標的とし、その機能を阻害することで治療効果を発揮するため、正常細胞へのダメージを抑えつつ高い治療効果が望めます。
この治療を成功させるには、患者さんのがん細胞が標的となる特定の分子を持っているかどうかを事前に検査することが極めて重要です。
低分子化合物と抗体医薬の違い
分子標的薬は大きく分けて、細胞の中に入り込んで作用する「低分子化合物」と、細胞の表面にある受容体などに結合する「抗体医薬」の二種類が存在します。
低分子化合物は、細胞内のシグナル伝達経路(チロシンキナーゼなど)を阻害することで、がん細胞に「増殖せよ」という命令が伝わるのを断ち切ります。
経口投与が可能な薬剤が多く、通院での治療が容易である点も特徴です。
一方、抗体医薬は点滴や注射で投与され、がん細胞の表面にある特定のタンパク質にピンポイントで結合します。
この結合は、増殖シグナルをブロックするだけでなく、免疫細胞がその抗体を目印にしてがん細胞を攻撃する「抗体依存性細胞傷害活性(ADCC活性)」を誘発することもあります。
このADCC活性は免疫システムを利用した攻撃であるため、がんワクチンとの親和性が高いと言えます。
主な標的分子一覧
| 標的分子 | 主に対象となるがん種 | 作用の方向性 |
|---|---|---|
| EGFR | 非小細胞肺がん、大腸がん、頭頸部がん | 増殖シグナルの遮断 |
| HER2 | 乳がん、胃がん、唾液腺がん | 増殖因子の受容体阻害 |
| VEGF | 大腸がん、非小細胞肺がん、腎細胞がん | 血管新生の阻害(兵糧攻め) |
主要な標的分子と対応するがん種
分子標的薬が狙う「標的」は、がんの種類によって異なります。
例えば、肺がんではEGFR遺伝子変異やALK融合遺伝子などが重要な標的となりますし、乳がんではHER2タンパクの過剰発現が治療方針を決定づけます。
これらの分子はがん細胞の増殖スイッチそのものであり、ここを抑え込むことで劇的な腫瘍縮小効果が見込めます。
また、特定のがん種に限らず、遺伝子変異があれば臓器横断的に使用できる薬剤も登場しています。
NTRK融合遺伝子やMSI-High(高頻度マイクロサテライト不安定性)などのバイオマーカーを持つ固形がんに対しては、臓器の種類を問わず効果が期待できる薬剤も承認されており、個別化医療の進展を象徴しています。
コンビネーション治療における薬剤選択の視点
がんワクチンと組み合わせる分子標的薬を選ぶ際には、単にがん細胞を殺傷する能力だけでなく、「免疫系にどのような影響を与えるか」という視点が重要です。
例えば、一部の分子標的薬は、免疫を抑制する制御性T細胞(Treg)の働きを抑える効果があることがわかっています。
逆に、免疫細胞そのものの活性を落としてしまうような薬剤との併用は慎重になる必要があります。
主治医は、がんの遺伝子変異のタイプと、患者さんの免疫状態の両方を考慮し、互いの効果を相殺せず、むしろ増強し合えるような薬剤の組み合わせを検討します。
がんワクチンの種類と免疫システムへの作用
がんワクチン療法は、患者さんの体内にがん細胞特有の目印(抗原)を認識させ、免疫システムを「戦闘モード」に切り替えることで、自身の力でがんを攻撃させる治療法であり、抗原の種類や投与方法によって作用機序が異なります。
それぞれのアプローチが持つ特性を理解することは、最適なコンビネーション治療を選択する上で重要です。
ペプチドワクチンによる特異的攻撃の誘導
ペプチドワクチンは、がん細胞の表面に出現する特定のタンパク質の断片(ペプチド)を人工的に合成し、体内に投与する方法です。
このペプチドが「指名手配写真」のような役割を果たし、体内の樹状細胞などの抗原提示細胞に取り込まれます。
主なワクチンタイプ
- ペプチドワクチン
がん特有のタンパク質断片を使用し、特定のHLA型を持つ患者に対して強い免疫誘導を行う。 - 樹状細胞ワクチン
患者自身の免疫細胞を培養・加工し、抗原提示能力を最大化してから体内に戻す個別化治療。 - mRNAワクチン/DNAワクチン
ウイルスのワクチンと同様の技術を応用し、がん抗原の設計図を投与して体内で抗原を作らせる新しい手法。
情報を受け取った樹状細胞は、リンパ節に移動してキラーT細胞にその情報を伝達します。訓練を受けたキラーT細胞は、血液に乗って全身を巡り、同じ目印を持つがん細胞だけを狙って攻撃します。
化学療法と異なり、正常な細胞を傷つけにくいため、副作用が比較的軽微であることも特徴の一つです。
樹状細胞ワクチンによる指令塔の強化
樹状細胞ワクチンは、免疫の司令塔である樹状細胞を体外で培養・活性化させてから体に戻す、より直接的な方法です。まず患者さんの血液から単球を取り出し、樹状細胞へと分化させます。
そこにがん細胞の目印となる抗原や、あるいは患者さん自身のがん組織(ライセート)を取り込ませます。
十分に「敵の情報」を記憶した樹状細胞を体内に戻すことで、体内でのT細胞への指令出しを強力にサポートします。
患者さん自身の細胞を使うため、拒絶反応のリスクが極めて低く、個々の免疫状態に合わせたオーダーメイドに近い治療が可能となります。
ネオアンチゲンワクチンという新しい潮流
近年注目されているのが、個々の患者さんのがん細胞に生じた遺伝子変異由来の抗原(ネオアンチゲン)を標的とするワクチンです。
正常細胞には存在せず、その人のがん細胞だけに存在する全く新しい抗原を狙うため、免疫細胞が「異物」として認識する力が非常に強く、強力な攻撃力を引き出せます。
次世代シーケンサーを用いて患者さんのがん組織と正常組織の遺伝子を比較解析し、最も免疫反応を起こしやすい変異箇所を特定してワクチンを製造します。
完全な個別化医療であり、分子標的薬との併用において、より精密な攻撃が可能になると期待されています。
腫瘍微小環境を標的とした治療戦略の融合
がん細胞が生存しやすいように作り変えられた「腫瘍微小環境」を正常化させることは、コンビネーション治療の成否を分ける鍵となります。
分子標的薬とがんワクチンの併用は、この「がんの城塞」を内側と外側の両面から攻略し、免疫細胞が活躍できるフィールドを整えるために非常に有効な戦略です。
血管新生阻害薬による環境の正常化
がんは急速に増殖するために、新しい血管を次々と作らせて酸素や栄養を取り込もうとします。
しかし、このように急造された血管は構造が未熟で、隙間だらけだったり、血流が滞っていたりします。
この状態は、免疫細胞が腫瘍内部へ浸透するのを阻む物理的な障壁となります。
微小環境への作用機序
| 作用の段階 | 分子標的薬の働き | がんワクチンの働き |
|---|---|---|
| 準備段階 | 異常血管の正常化・免疫抑制細胞の減少 | 樹状細胞などの抗原提示細胞の活性化 |
| 攻撃段階 | がん細胞の死滅と抗原放出の促進 | 活性化T細胞による特異的な破壊活動 |
| 維持段階 | 再増殖シグナルの持続的遮断 | 免疫記憶による長期的な監視体制の確立 |
VEGF(血管内皮増殖因子)などを標的とする血管新生阻害薬を使用すると、異常な血管が淘汰され、比較的正常な血管構造が回復します。
こうして血流が改善すると、がんワクチンによって活性化されたT細胞が腫瘍の深部まで到達できるようになります。
また、腫瘍内の酸素状態が改善することで、免疫細胞の活性も維持されやすくなります。
免疫抑制シグナルの解除とワクチンの連動
腫瘍微小環境には、免疫のブレーキ役となる細胞や物質が充満しています。
例えば、がん細胞はPD-L1というタンパク質を出してT細胞の攻撃を止めようとしますし、制御性T細胞や骨髄由来抑制細胞(MDSC)といった細胞を呼び寄せて免疫を眠らせようとします。
一部の分子標的薬は、これらの免疫抑制細胞の数を減らしたり、その機能を弱めたりする作用を持っています。
抑制が外れた状態でがんワクチンによる刺激が加わると、T細胞は邪魔されることなく攻撃に集中できます。
つまり、分子標的薬が「ブレーキを外し」、がんワクチンが「アクセルを踏む」という関係性が成り立ちます。
低酸素状態の改善と免疫活性の維持
腫瘍内部はしばしば低酸素状態に陥っており、これは免疫細胞にとって過酷な環境です。低酸素状態では、アデノシンなどの代謝産物が蓄積し、これがT細胞の働きを強力に抑制してしまいます。
分子標的薬によって血流が適正化され、酸素供給が改善されることは、単に薬を届けるだけでなく、免疫細胞が元気な状態で戦えるフィールドを整えるという意味でも重要です。
がんワクチンでどんなに強力なT細胞を育てても、戦場が戦える環境でなければ効果は半減します。
環境改善効果を持つ薬剤との併用は、ワクチンのポテンシャルを浪費させないための賢明な戦略と言えるでしょう。
特定の分子標的薬クラスごとの併用効果
分子標的薬には多くの種類が存在し、それぞれの薬剤クラスによって免疫系への影響やがんワクチンとの相性は異なるため、特性を見極めた選択が必要です。
ここでは、代表的な薬剤クラスとがんワクチンを組み合わせた際に期待される具体的な効果について掘り下げます。
チロシンキナーゼ阻害薬(TKI)との連携
チロシンキナーゼ阻害薬(TKI)は、細胞内の情報伝達に関わる酵素を阻害する薬剤群です。
これらの一部、例えば肺がんで使われるEGFR阻害薬や、腎がんなどで使われるマルチキナーゼ阻害薬などは、がん細胞を直接叩くだけでなく、免疫細胞の認識力を高める効果が報告されています。
TKIによる攻撃を受けたがん細胞は、細胞表面の抗原提示分子(MHCクラスI)の発現量を増やすことがあります。
その変化を受けて、がんワクチンによって誘導されたT細胞が、より容易に標的を見つけられるようになります。
また、一部のTKIは免疫抑制的なサイトカインの産生を抑える働きもあり、免疫環境を「攻撃型」にシフトさせる手助けをします。
薬剤クラスごとの免疫作用
| 薬剤クラス | 主な作用対象 | 免疫系へのプラスの影響 |
|---|---|---|
| チロシンキナーゼ阻害薬 | 細胞内シグナル伝達 | 抗原提示分子の増加・免疫抑制因子の減少 |
| 血管新生阻害薬 | VEGF受容体など | T細胞の腫瘍内浸潤促進・低酸素の改善 |
| PARP阻害薬 | DNA修復酵素 | DNA損傷による炎症誘導・免疫細胞の誘引 |
PARP阻害薬とDNA損傷応答の利用
PARP阻害薬は、DNAの修復機能を阻害することで、がん細胞にダメージを蓄積させて死滅させる薬剤です。
特にBRCA遺伝子変異を持つがん(乳がん、卵巣がん、前立腺がんなど)で高い効果を発揮します。
この薬剤によってがん細胞のDNAが不安定になると、細胞質内にDNA断片が漏れ出し、これが強い炎症シグナル(STING経路の活性化など)を引き起こします。
この炎症シグナルは、自然免疫系を強力に刺激し、樹状細胞などの抗原提示細胞を腫瘍部位に呼び寄せます。
このタイミングでがんワクチンが作用していると、集まってきた免疫細胞に対して効率よく敵の情報を渡すことができ、非常に強い抗腫瘍免疫が成立する可能性があります。
HER2標的薬と抗体依存性免疫反応
HER2陽性の乳がんや胃がんで使用されるトラスツズマブなどの抗体医薬は、それ自体が免疫細胞(NK細胞など)を呼び寄せるADCC活性を持っています。
ここにHER2ペプチドなどを用いたがんワクチンを併用すると、抗体による攻撃と、ワクチンによるT細胞の攻撃という「二重の特異的攻撃」が可能になります。
また、抗体医薬ががん細胞を破壊することで放出された抗原を取り込み、さらに免疫が活性化するという「エピトープ・スプレディング」と呼ばれる現象も期待されます。
これは、最初に狙っていた抗原以外のがん抗原に対しても免疫が反応し始める現象で、治療効果の幅と深さを増すことにつながります。
副作用管理と治療継続のためのポイント
コンビネーション治療は高い効果が期待できる反面、二つの異なる治療法を行うため、副作用の現れ方も複雑になる可能性があり、適切な管理が不可欠です。
治療を中断せずに効果を最大限に引き出すためには、予想される反応を理解し、早期に対処することが大切です。
免疫関連有害事象(irAE)への理解
がんワクチンは免疫を活性化させる治療であるため、過剰に活性化した免疫が正常な細胞まで攻撃してしまう「免疫関連有害事象(irAE)」が起こることがあります。
皮膚の発疹、下痢、甲状腺機能の異常、間質性肺炎などが代表的です。分子標的薬との併用によって、これらの頻度が変わったり、特有の症状が出たりする可能性があります。
主な副作用の傾向
- 皮膚症状
発疹、乾燥、注射部位の反応。事前の保湿と清潔保持で重症化を防ぐ。 - 消化器症状
下痢、口内炎、食欲不振。脱水を防ぐための水分補給と、早期の対症療法が必要。 - 全身症状
発熱、疲労感、倦怠感。免疫反応の一環であることが多いが、休息と栄養管理で対応する。
しかし、irAEの発現は、体内で免疫がしっかりと反応している証拠であるという側面もあります。重要なのは、些細な体調の変化を見逃さず、医療チームと共有することです。
早期発見できれば、休薬やステロイド剤の使用などでコントロール可能なケースがほとんどです。
重複する副作用への対策
分子標的薬も種類によっては、皮膚障害(手足症候群や発疹)や下痢、疲労感を引き起こします。
がんワクチンの副反応(注射部位の腫れや微熱、倦怠感)と症状が重なる場合、患者さんの苦痛が増す恐れがあります。特に皮膚トラブルはQOL(生活の質)を著しく下げる要因となります。
治療開始前から保湿剤によるスキンケアを行ったり、整腸剤を予防的に使用したりするなど、支持療法を徹底することで、これらの副作用を最小限に抑えることが可能です。
医療者側も、併用による毒性のプロファイルを慎重にモニタリングし、投与量やスケジュールの調整を行います。
定期的なモニタリングの重要性
コンビネーション治療中は、通常の血液検査や画像検査に加えて、免疫の状態を調べる検査を行うことがあります。
リンパ球の数や比率、炎症マーカーなどをチェックし、免疫が過剰に反応していないか、あるいは抑制されていないかを確認します。
また、肝機能や腎機能、心機能など、薬剤の代謝に関わる臓器の数値も慎重に追跡します。安全に治療を続けるためには、患者さん自身の「いつもと違う」という感覚が重要な情報源となります。
どんな小さな違和感でも伝える姿勢が、重篤な副作用を防ぐ防波堤となります。
治療開始前の検査と適格性の判断
分子標的薬とがんワクチンのコンビネーション治療は、誰にでも無条件に行えるわけではなく、適切な対象者を見極めるプロセスが必要です。
最大の効果を得るためには、その治療法が患者さんのがんの性質や体質に合っているかを、事前の詳細な検査で見極める必要があります。
がん遺伝子パネル検査(CGP)の役割
分子標的薬を使用するためには、標的となる遺伝子変異が存在するかどうかを確認する必要があります。これには、一度に数百種類の遺伝子を調べる「がん遺伝子パネル検査」が有用です。
手術や生検で採取したがん組織、あるいは血液(リキッドバイオプシー)を用いて解析を行います。
この検査によって、標準治療では見つからなかった稀な遺伝子変異が見つかることもあり、治療の選択肢が広がります。また、腫瘍遺伝子変異量(TMB)が高いかどうかも分かります。
TMBが高いがんは、がん細胞の特徴となる抗原が多く発生しているため、がんワクチンの効果が出やすい傾向にあるとされています。
治療適合性確認の流れ
| 検査項目 | 目的 | 判明すること |
|---|---|---|
| 遺伝子パネル検査 | 標的分子の有無を確認 | 使用可能な分子標的薬、TMB(変異量)、MSI(不安定性) |
| HLA検査 | 免疫細胞への抗原提示能力の型を確認 | 使用可能なペプチドワクチンの種類 |
| PD-L1発現検査 | 免疫抑制状態の確認 | 免疫チェックポイント阻害薬併用の可能性など |
HLA検査と免疫学的適合性
ペプチドワクチンなど多くのがんワクチン治療では、白血球の型である「HLA型」が適合している必要があります。
HLAは細胞表面にあるトレーのようなもので、ここに抗原ペプチドを乗せてT細胞に提示します。
このHLAの型がワクチンに含まれるペプチドと合致しないと、免疫細胞に情報が伝わらず、効果が発揮されません。
日本人の約6割が保有する「HLA-A24」型など、主要な型に対応したワクチンが多く開発されていますが、事前に血液検査で自身のHLA型を確認することは治療の大前提となります。
不適合の場合は、HLA型に関わらず効果が期待できる別の種類のワクチンや、全長タンパクを用いた方法などを検討します。
治療開始のタイミングと全身状態
集学的治療を成功させるためには、治療を開始する時期も重要です。
免疫細胞が極端に疲弊している末期の状態よりも、ある程度全身状態が良好で、免疫系が応答できる余力が残っている時期の方が、ワクチンの効果は高くなります。
また、腫瘍量が多すぎる場合、免疫の力だけで抑え込むのは難しいため、手術や放射線、あるいは事前の薬物療法で腫瘍を減らしてから(デバルキング)、残存する微小病変をコンビネーション治療で叩くという戦略が採られることもあります。
主治医は、がんの進行度、臓器の機能、栄養状態、そしてこれまでの治療歴を総合的に判断し、この強力な治療カードを切る適切なタイミングを見定めます。
Q&A
- 他の抗がん剤治療を受けている最中でも、この治療を始められますか?
-
多くのケースで併用は可能ですが、現在受けている抗がん剤の種類や時期、血液検査のデータなどを総合的に判断する必要があります。
一部の抗がん剤は免疫細胞の働きを一過性に弱めることがあるため、ワクチンの投与スケジュールを調整したり、休薬期間を利用したりするなどの工夫が行われます。
主治医との綿密な連携によって、現在の治療を妨げずに相乗効果を狙うプランを立てます。
- 分子標的薬に耐性ができてしまった場合、もう効果は期待できませんか?
-
分子標的薬単独で耐性が生じた場合でも、がんワクチンを組み合わせることで再びがんの進行を抑えられる可能性があります。
耐性ができたがん細胞は性質が変化していますが、その変化に伴って新しい抗原が出現している場合があり、ワクチンによって再教育された免疫細胞がそれを標的として攻撃できるからです。
耐性克服はコンビネーション治療の大きな目的の一つです。
- 標準治療と比べて、副作用は強くなりますか?
-
一般的に、従来の殺細胞性抗がん剤を複数組み合わせるような治療に比べると、分子標的薬とがんワクチンの併用は、正常細胞へのダメージが限定的であるため、吐き気や脱毛、骨髄抑制といった副作用は軽い傾向にあります。
ただし、免疫に関連した特有の副作用(皮膚症状や発熱など)が現れることがあります。重篤化することは稀ですが、体調の変化には注意を払う必要があります。
- 治療の効果はどれくらいの期間で現れますか?
-
個人差やがんの種類によって異なりますが、免疫が十分に活性化し、腫瘍に対して攻撃を始めるまでには数週間から数ヶ月かかることが一般的です。
即効性を期待するというよりは、じっくりと免疫を育て、長く効果を持続させる治療です。
そのため、画像検査ですぐに縮小が見られなくても、長期的に病勢が安定(SD)していれば、治療効果が出ていると判断されることもあります。
参考文献
HODGE, James W., et al. The tipping point for combination therapy: cancer vaccines with radiation, chemotherapy, or targeted small molecule inhibitors. In: Seminars in oncology. WB Saunders, 2012. p. 323-339.
LI, Feifei; ZHAO, Changqi; WANG, Lili. Molecular‐targeted agents combination therapy for cancer: developments and potentials. International journal of cancer, 2014, 134.6: 1257-1269.
ZANOTTA, Serena, et al. Enhancing dendritic cell cancer vaccination: the synergy of immune checkpoint inhibitors in combined therapies. International Journal of Molecular Sciences, 2024, 25.14: 7509.
CHENG, Wen-Fang, et al. Fusion protein vaccines targeting two tumor antigens generate synergistic anti-tumor effects. PloS one, 2013, 8.9: e71216.
YIN, Xiaotao, et al. Synergistic antitumor efficacy of combined DNA vaccines targeting tumor cells and angiogenesis. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2015, 465.2: 239-244.
MOUGEL, Alice, et al. Synergistic effect of combining sunitinib with a peptide-based vaccine in cancer treatment after microenvironment remodeling. Oncoimmunology, 2022, 11.1: 2110218.
MONDINI, Michele, et al. Synergy of radiotherapy and a cancer vaccine for the treatment of HPV-associated head and neck cancer. Molecular cancer therapeutics, 2015, 14.6: 1336-1345.
ANDERSEN, Mads Hald, et al. Cancer treatment: the combination of vaccination with other therapies. Cancer Immunology, Immunotherapy, 2008, 57.11: 1735-1743.
FOTIN‐MLECZEK, Mariola, et al. Highly potent mRNA based cancer vaccines represent an attractive platform for combination therapies supporting an improved therapeutic effect. The journal of gene medicine, 2012, 14.6: 428-439.
FU, Rao, et al. Combination therapy with oncolytic virus and T cells or mRNA vaccine amplifies antitumor effects. Signal Transduction and Targeted Therapy, 2024, 9.1: 118.