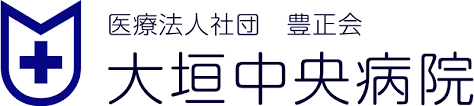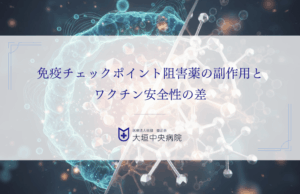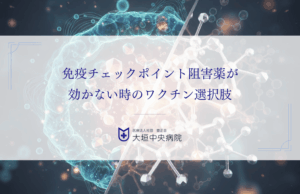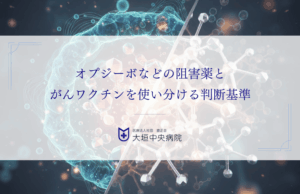進行がん治療の領域において、免疫チェックポイント阻害薬とがんワクチンの併用療法は、従来の単剤治療では到達し得なかった治療効果を目指す新たな選択肢として注目を集めています。
ブレーキを解除して免疫細胞を動かす阻害薬と、攻撃目標を明確に指示してアクセルを踏むがんワクチン。
この二つを組み合わせることで、がん細胞に対する攻撃力を相乗的に高め、標準治療が奏功しなかった症例や、転移・再発を繰り返す進行がんに対して、力強い対抗手段を提供しようという試みです。
本記事では、この併用療法がなぜ進行がんに対して有効な手立てとなり得るのか、その理論的背景から実際の治療判断に至るまでを詳しく解説します。
免疫チェックポイント阻害薬とがんワクチンの基本概念
併用療法を理解するためには、それぞれの薬剤が持つ役割を明確に区別することが重要です。
阻害薬は免疫細胞の活動を抑制するブレーキを外す役割を担い、がんワクチンは攻撃すべきがん細胞の特徴を免疫細胞に教え込む役割を果たします。
両者が補完し合うことで、より精度の高い免疫応答を実現します。
免疫チェックポイント阻害薬の役割
私たちの体には、免疫システムが暴走して自分自身の正常な細胞まで攻撃しないようにするための制御機能、すなわち「免疫チェックポイント」が備わっています。
がん細胞はこの仕組みを悪用し、免疫細胞(特にT細胞)に対して「攻撃するな」という抑制シグナルを送ることで、免疫からの攻撃を回避しています。
免疫チェックポイント阻害薬は、このがん細胞が出す抑制シグナルを遮断する薬剤です。具体的には、PD-1やPD-L1、CTLA-4といった分子に結合し、がん細胞がかけた「ブレーキ」を強制的に解除します。
その結果、本来の攻撃力を取り戻したT細胞が、再びがん細胞を認識し、排除へと向かう環境を整えます。
しかし、この薬剤単独では、そもそも攻撃を担当するT細胞ががん組織に十分に存在しない場合、ブレーキを外しても車が走らないのと同様に、十分な効果を発揮できないという課題があります。
がんワクチンの役割
がんワクチンは、がん細胞特有の目印(抗原)を免疫システムに提示し、その目印を持つ細胞だけを狙って攻撃するようT細胞を教育する治療法です。
感染症のワクチンがウイルスの特徴を記憶させるのと同様に、がんワクチンは体内の樹状細胞などの抗原提示細胞を介して、がん細胞を攻撃する専用の兵隊(細胞傷害性T細胞)を新たに作り出し、増殖させます。
この治療法の最大の強みは、正常な細胞を傷つけずにがん細胞だけを狙い撃ちにする「特異性」にあります。
樹状細胞ワクチン療法やペプチドワクチン療法など、いくつかの種類が存在しますが、いずれも免疫の「アクセル」を踏み込み、攻撃部隊をがん局所へと送り込むことを主眼としています。
ただし、強力な攻撃部隊を送り込んでも、がん細胞側が強力なブレーキ(免疫チェックポイント)をかけている場合、現場に到着したT細胞が十分に機能できないという壁に直面することがあります。
二つの治療法が目指す方向性
これら二つの治療法は、それぞれが免疫サイクルの異なる段階に作用します。
がんワクチンは免疫応答の始動段階である「プライミング相(T細胞の活性化と増殖)」を強化し、免疫チェックポイント阻害薬はがん細胞への攻撃を実行する「エフェクター相(がん細胞の破壊)」における阻害要因を取り除きます。
これらを併用することは、攻撃部隊を増やして現場に送り込むと同時に、現場での活動を妨げる障害物を撤去するという、理にかなった戦略です。
単独では突破できなかったがんの防御網を、多角的なアプローチで攻略することこそが、この併用療法の目指す方向性です。
進行がんにおいては、がん細胞の数も多く、免疫抑制環境も強固であるため、単一のアプローチではなく、複数の角度から免疫システムを支援することが治療の鍵となります。
各治療法の主な機能と併用による補完関係
| 治療法 | 主な作用 | 課題(単剤の場合) |
|---|---|---|
| 免疫チェックポイント阻害薬 | 免疫のブレーキ解除(抑制シグナルの遮断) | 攻撃するT細胞が不足していると効果が薄い |
| がんワクチン | 免疫のアクセル(攻撃標的の教育とT細胞増殖) | がん側の抑制環境によりT細胞が機能不全に陥る |
| 併用療法 | 攻撃部隊の増強と活動環境の整備 | それぞれの弱点を補い合い、治療強度を高める |
併用療法が注目される医学的な背景
併用療法が必要とされる最大の理由は、単独の薬剤では克服困難な「がんの生存戦略」に対抗するためです。
多くのがんは免疫からの逃避機構を複数持っており、一つの経路を遮断しても別の経路で生き延びようとしますが、併用療法はこの逃げ道を塞ぎ、治療効果の底上げを図るために重要な役割を果たします。
単剤治療における限界
免疫チェックポイント阻害薬は画期的な薬として登場しましたが、すべての患者に対して劇的な効果を示すわけではありません。
奏功率はがん種によって異なりますが、単剤では2割から3割程度にとどまるケースも少なくありません。この原因の一つとして、がん組織内にリンパ球(T細胞)がほとんど入り込んでいない状態が挙げられます。
免疫細胞が排除されている、あるいは無視されている状態では、いくらブレーキを外しても攻撃が始まりません。
このような状態を打破するために、外部から免疫を刺激し、強制的にT細胞をがん組織へと動員するきっかけが必要となります。ここでワクチンの力が求められます。
単剤では反応しなかった「免疫学的におとなしい腫瘍」に対しても、ワクチンが着火剤となって免疫反応を引き起こすことが期待されます。
単剤治療が効きにくい主な要因
- がん組織へのリンパ球浸潤が乏しい(Cold Tumor)
- がん細胞が標的となる抗原を隠蔽している
- 複数の免疫抑制分子が同時に働いている
腫瘍微小環境(TME)の克服
がん細胞の周囲には、単にがん細胞があるだけではなく、血管、線維芽細胞、そして様々な免疫細胞が集まって「腫瘍微小環境(TME)」と呼ばれる独自の社会を形成しています。
進行がんのTMEは、免疫細胞の攻撃を無力化する極めて過酷な環境となっています。制御性T細胞(Treg)や骨髄由来抑制細胞(MDSC)といった免疫を抑える細胞が集まり、攻撃役のT細胞を疲弊させてしまいます。
併用療法は、このTMEの質を変えることを目指します。ワクチンによって活性化された新鮮なT細胞がTMEに大量に流入することで、抑制的な環境を攻撃的な環境へと転換させます。
これを「Cold Tumor(冷たい腫瘍)」から「Hot Tumor(熱い腫瘍)」への転換と呼びます。環境そのものを変えることで、長期的な治療効果の維持を狙います。
免疫記憶の形成と持続性
がん治療において重要なのは、一時的にがんを小さくすることだけではなく、再発を防ぐことです。そのためには、免疫システムにがんの特徴を記憶させる「免疫記憶」の形成が必要です。
免疫チェックポイント阻害薬は、一度活性化した免疫反応を持続させる効果がありますが、どの細胞を記憶すべきかという指示は出しません。
一方でがんワクチンは、特定の抗原に対する記憶T細胞の形成を促します。併用療法を行うことで、強力かつ特異的な記憶T細胞が効率よく誘導され、体内に長く留まることが期待されます。
そうすることで、微小な残存がん細胞や、将来的な再発の芽に対しても、免疫システムが継続的に監視し、排除する体制を整えることができます。
免疫システムを活性化させる相乗効果の原理
併用療法における相乗効果は、単なる足し算ではありません。ワクチンによって始動した免疫反応を、阻害薬が増幅し、持続させるという一連の流れを生み出します。
この連携プレーにより、免疫システムは最大限の能力を発揮し、がん細胞を追い詰めます。
T細胞のプライミングと活性化
治療の第一段階は、樹状細胞などの抗原提示細胞ががんの情報をT細胞に伝える「プライミング」から始まります。がんワクチンはこの過程を強力に後押しします。
ワクチン由来の抗原を取り込んだ樹状細胞は、リンパ節へと移動し、そこで未熟なT細胞に対して「この顔をした敵を攻撃せよ」という情報を伝達します。
通常、がん患者の体内ではこの情報伝達がスムーズにいかないことが多いのですが、ワクチンによって高濃度のアジュバント(免疫賦活剤)と共に抗原が提示されることで、爆発的な数のT細胞が活性化します。
ここで重要なのは、この初期段階からCTLA-4阻害薬などのチェックポイント阻害薬を併用することで、プライミング段階での抑制も解除し、より多くのT細胞を戦場へ送り出す準備が整う点です。
がん細胞への浸潤と攻撃力
活性化したT細胞は血液に乗って全身を巡り、がん組織へとたどり着きます。しかし、がん組織への侵入(浸潤)は容易ではありません。血管壁のバリアや、腫瘍内部の圧力などが障壁となります。
活性化レベルの高いT細胞は、ケモカインと呼ばれる誘引物質に反応しやすく、高い浸潤能力を持ちます。
腫瘍内部に入り込んだ後、T細胞はがん細胞を認識して攻撃を開始します。
この際、細胞傷害性顆粒(パーフォリンやグランザイム)を放出してがん細胞を破壊しますが、この攻撃力を持続させるためにPD-1/PD-L1阻害薬が重要な働きをします。
現場での「疲れ」を防ぎ、最後まで攻撃を完遂させるのです。
併用療法による免疫活性化の段階的な流れ
| 段階 | 体内で起こる現象 | 併用療法のメリット |
|---|---|---|
| 始動 | 樹状細胞がT細胞に標的を提示 | ワクチンが明確な標的を与え、強力な動員をかける |
| 移動・浸潤 | T細胞が血管からがん組織へ侵入 | 活性化されたT細胞は組織内への浸潤能力が高い |
| 攻撃 | がん細胞を破壊し排除する | 阻害薬が現場でのブレーキを防ぎ、攻撃を持続させる |
免疫抑制シグナルの解除
がん細胞は攻撃を受けると、生き残るためにPD-L1というタンパク質を細胞表面に発現させ、T細胞のPD-1に結合して攻撃をやめさせようとします。これを「適応免疫抵抗性」と呼びます。
つまり、ワクチンで強力に攻撃すればするほど、がん細胞側も必死に防御を固めようとするのです。
この防御策を先回りして無効化するのが、免疫チェックポイント阻害薬です。ワクチンによる攻撃が強まれば強まるほど、阻害薬の役割は重要になります。
攻撃と防御解除のタイミングが噛み合うことで、がん細胞は逃げ場を失います。
また、破壊されたがん細胞からは新たな抗原が放出され、それがまた新たなT細胞を刺激するという「がん免疫サイクル」の好循環が回り始めます。
進行がん治療における併用療法の強み
進行がん治療において併用療法が強みを発揮するのは、全身に散らばったがん細胞を包括的に叩く力と、従来の治療法に抵抗性を示したがんに対する打開力を持つ点です。
局所療法では対応しきれない病態に対し、全身性の免疫システムを利用して対抗します。
転移巣や再発巣へのアプローチ
進行がんの多くは、原発巣だけでなく、肺や肝臓、骨、脳などに遠隔転移しています。手術や放射線治療は目に見える局所の腫瘍には有効ですが、全身に散らばった微細な転移巣すべてに対処することは困難です。
併用療法によって訓練された免疫細胞は、全身の血管をパトロールするため、画像検査では見つからないような小さな転移巣も見つけ出して攻撃することができます。
また、ある一箇所の腫瘍を攻撃することで活性化した免疫が、離れた場所にある別の腫瘍も縮小させる「アブスコパル効果」のような現象も、併用療法によってより高い頻度で起こることが期待されます。
全身病としての進行がんに対して、全身防御システムである免疫をフル活用することは、理にかなった戦略と言えます。
標準治療抵抗性の克服
抗がん剤や分子標的薬による標準治療は、一定期間は効果を発揮しますが、やがてがん細胞が薬剤耐性を獲得し、薬が効かなくなる時期が訪れます。
こうしたいわゆる「耐性化」した進行がんに対しても、免疫療法は全く異なる原理で作用するため、効果が期待できます。
特に、従来の化学療法によってがん細胞が破壊されると、その死骸から新たな抗原が放出されます。
このタイミングで併用療法を行うことで、死滅しつつあるがん細胞の情報を免疫系に効率よく取り込ませ、耐性化した細胞を含めた残存腫瘍を一掃するチャンスが生まれます。
既存の治療手立てがなくなった段階でも、新たな可能性を切り拓くことができる点が大きな強みです。
個別化医療としての可能性
がんは患者一人ひとりによって遺伝子の変異パターンが異なり、持っている抗原も違います。
近年では、手術検体や生検組織を用いて遺伝子解析を行い、その患者のがんに特有の「ネオアンチゲン(新生抗原)」を特定する技術が進歩しています。
この情報を元にカスタムメイドのワクチンを作成し、阻害薬と併用する治療法は、究極の個別化医療と言えます。
既製品の薬剤を投与するだけでなく、患者自身の体内で何が起きているかを解析し、その患者のがんに最も適した標的を設定して攻撃を仕掛ける。
このため、無駄な攻撃を減らし、治療効果を最大化することが可能になります。
併用療法が適していると考えられるがんの状態
- 標準治療で効果が不十分、または再発した場合
- 複数の臓器に転移が見られる進行がん
- 高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)などの特定のバイオマーカーを持つがん
治療開始前に知っておくべき副作用とリスク管理
高い効果が期待できる一方で、免疫の力を強力に活性化させるため、副作用のリスクも相応に存在します。
自分自身の正常な細胞を攻撃してしまう自己免疫反応や、ワクチン特有の局所反応について正しく理解し、適切なリスク管理のもとで治療を受けることが重要です。
免疫関連有害事象(irAE)の理解
免疫チェックポイント阻害薬を使用すると、本来がん細胞に向けられるべき攻撃の矛先が、誤って正常な臓器に向いてしまうことがあります。これを「免疫関連有害事象(irAE)」と呼びます。
皮膚の発疹やかゆみ、下痢、大腸炎、甲状腺機能障害、間質性肺炎、1型糖尿病など、全身のあらゆる臓器に起こる可能性があります。
併用療法では、免疫反応がより強く引き起こされるため、単剤治療に比べてirAEの発現頻度や重症度がやや高くなる傾向があります。しかし、これらは決して制御不能なものではありません。
定期的な検査と、患者自身による体調変化の気づきがあれば、早期に対処し、重篤化を防ぐことができます。少しでも「いつもと違う」と感じたら、すぐに担当医に伝える体制を作っておくことが大切です。
注意すべき主な免疫関連副作用と症状
| 影響部位 | 主な症状 | 注意点 |
|---|---|---|
| 皮膚 | 発疹、強いかゆみ、白斑 | 比較的早期に出やすい。保湿や軟膏で対応可能 |
| 消化器 | 止まらない下痢、腹痛、血便 | 脱水を防ぐ。重症化すると大腸炎のリスクあり |
| 呼吸器 | 空咳、息切れ、呼吸苦 | 間質性肺炎の兆候。早急な画像診断が必要 |
ワクチン特有の反応
がんワクチンに特有の副作用としては、接種部位の反応が最も一般的です。注射した場所が赤く腫れたり、痛みや熱感を伴ったりすることがあります。
また、インフルエンザワクチンなどを接種した時と同様に、一時的な発熱や倦怠感、関節痛が見られることもあります。
これらは免疫システムが正常に反応し、活性化しようとしている証拠でもあります。多くの場合は数日で軽快し、解熱鎮痛剤などでコントロール可能です。
アナフィラキシーのような重篤なアレルギー反応は稀ですが、投与直後は医療機関内で状態観察を行うなど、安全対策は徹底されています。
早期発見と対応の重要性
併用療法の副作用管理において最も重要なのは、患者と医療チームの連携です。副作用は治療開始直後に出ることもあれば、数ヶ月経ってから、あるいは治療終了後に出現することもあります。
いつどのような症状が出るか予測が難しいため、継続的なモニタリングが必要です。
定期的な血液検査や画像検査はもちろんのこと、日々の生活の中での自覚症状の変化を見逃さないことが、安全に治療を継続する鍵となります。
副作用が出た場合には、休薬やステロイド剤の投与など、確立された対処法があります。恐れすぎるのではなく、正しい知識を持って向き合う姿勢が求められます。
治療の流れと実際のスケジュール
この治療法を選択する場合、いきなり薬剤を投与するのではなく、事前の詳細な検査から始まり、計画的に治療が進められます。
個々の患者の状態に合わせてスケジュールが調整されますが、一般的な流れを把握しておくことで、見通しを持って治療に臨むことができます。
検査と適合性の確認
最初に行うのは、この治療法が適しているかを見極めるためのスクリーニング検査です。
血液検査で肝機能や腎機能、感染症の有無を確認するほか、がん組織を用いた遺伝子検査や免疫染色を行い、PD-L1の発現状況や腫瘍遺伝子変異量(TMB)、マイクロサテライト不安定性(MSI)などを調べます。
自家がんワクチンやネオアンチゲンワクチンなど、患者自身の組織を使用するタイプのワクチンの場合は、手術や生検で採取した腫瘍組織の保存状態や量が十分かどうかも確認します。
HLA型(白血球の型)の検査が必要になることもあります。これらの情報をもとに、どの薬剤とどのワクチンを組み合わせるのがベストかを慎重に検討します。
投与の順序と間隔
治療計画が決定すると、実際の投与スケジュールが組まれます。一般的には、免疫チェックポイント阻害薬は2週間から4週間に1回のペースで点滴投与されます。
がんワクチンは種類によって異なりますが、初期(導入期)は1〜2週間に1回程度頻回に皮下注射を行い、免疫を一気に立ち上げます。
その後、維持期に入るとワクチンの接種間隔は広がり、月1回程度になることが多いです。阻害薬とワクチンを同日に投与することもあれば、反応を見るためにずらすこともあります。
外来通院での治療が基本となりますが、初回投与時や副作用の懸念がある場合は、短期入院で様子を見ることもあります。
一般的な治療スケジュールの例
| 時期 | アクション | 頻度の目安 |
|---|---|---|
| 導入期(1-2ヶ月目) | 免疫の急速な立ち上げ | ワクチン:週1〜2回 阻害薬:2〜3週に1回 |
| 維持期(3ヶ月目以降) | 効果の維持と記憶形成 | ワクチン:月1回 阻害薬:3〜4週に1回 |
| 評価期 | CT/MRIによる効果判定 | 2〜3ヶ月ごとに実施 |
経過観察と効果判定
治療開始後は、定期的に画像診断(CT、MRI、PETなど)を行い、腫瘍の大きさや数に変化があるかを評価します。
免疫療法特有の現象として、治療初期に一時的に腫瘍が大きくなったように見える「偽増大(シュードプログレッション)」が起こることがあります。
これは腫瘍の中に免疫細胞が大量に入り込んだことによる一時的な腫れであり、実際には治療が効いているサインである可能性があります。
そのため、安易に「効いていない」と判断して治療を中止するのではなく、症状の悪化がない限りは慎重に経過を観察します。
また、腫瘍マーカーの推移や免疫反応の強さを示す血液データの変化なども総合的に判断し、治療を継続するか、あるいは別の手段に切り替えるかを決定していきます。
この治療法を選択する際の判断基準
すべての進行がん患者にとってこの併用療法が適しているわけではありません。
医学的なエビデンスに基づき、治療効果が期待できる条件を満たしているか、そして患者自身の体が治療に耐えうる状態にあるかを見極めることが、成功への第一歩です。
がんの種類と遺伝子変異の状態
現在、併用療法の効果が特に期待されているのは、悪性黒色腫(メラノーマ)、肺がん、腎細胞がん、頭頸部がんなどです。
これらのがんは比較的免疫原性が高く(免疫に見つけられやすく)、治療反応が良い傾向にあります。
また、がん細胞の遺伝子変異が多いタイプ(高TMB)や、DNA修復機能に異常があるタイプ(MSI-High)は、正常細胞との違いが際立っているため、免疫システムが「異物」として認識しやすく、併用療法の良い適応となります。
逆に、免疫細胞が全く入り込んでいないタイプの腫瘍に対しては、プライミング効果の高いワクチンを選ぶなど、戦略的な工夫が必要になります。
患者の全身状態と免疫機能
免疫療法は、患者自身の免疫力を利用してがんと戦う治療法です。
そのため、極端に体力が低下している場合や、栄養状態が悪い場合、重篤な自己免疫疾患を合併している場合は、十分な効果が得られない、あるいは副作用のリスクが高まる可能性があります。
パフォーマンスステータス(PS)と呼ばれる全身状態の指標が良いこと、主要な臓器機能(肝、腎、心、肺)が保たれていることが前提となります。
また、ステロイド剤などの免疫抑制剤を常用している場合は、治療効果を弱めてしまう可能性があるため、調整が必要です。自身の体力と免疫の予備能力を医師と相談し、冷静に判断することが大切です。
医療機関選びのポイント
この併用療法は高度な専門性を要するため、どこの病院でも受けられるわけではありません。
特に、自由診療で提供されるワクチン療法と、保険診療の阻害薬を組み合わせる場合や、治験として実施される場合など、制度的な枠組みも複雑です。
医療機関を選ぶ際は、がん免疫療法の専門医が在籍しているか、副作用発生時のバックアップ体制(救急対応や専門科との連携)が整っているかを確認することが重要です。
また、遺伝子パネル検査などの詳細な解析に基づいた提案ができるかどうかも、質の高い治療を受けるための判断材料となります。
確認すべき医療機関のチェックリスト
- がん薬物療法専門医や免疫療法の経験豊富な医師がいるか
- 夜間や休日の副作用対応体制が整備されているか
- 治療内容、費用、リスクについて納得いくまで説明があるか
よくある質問
- 標準治療と比べてどちらを優先すべきですか?
-
原則として、科学的根拠(エビデンス)が確立されている標準治療が最優先となります。
標準治療は多くの臨床試験を経て、現時点で最も生存期間を延長することが証明されている治療法だからです。
併用療法は、標準治療の効果が不十分だった場合や、標準治療と並行して行える場合、あるいは臨床試験(治験)として提案される場合に検討されるべき選択肢です。
独断で標準治療を中断することは推奨されませんので、主治医とよく相談することが大切です。
- どんな種類のがんでも効果がありますか?
-
理論上は多くのがん種に対して効果が期待できますが、実際にはがんの種類や個々の患者の免疫状態によって効果には差があります。
現時点では、悪性黒色腫、肺がん、腎がんなどで高い実績がありますが、消化器がんや乳がんなどでも研究が進み、効果が認められるケースが増えています。
重要なのは「がんの名前」だけでなく、そのがんが持つ「免疫学的な特徴」ですので、事前の詳細な検査によって効果の予測を行います。
- 高齢でも治療を受けることは可能ですか?
-
年齢そのものによる制限は基本的にはありません。高齢であっても、全身状態が良好で、日常生活に支障がなく、内臓機能が保たれていれば治療を受けることは十分に可能です。
実際、多くの高齢の患者が免疫療法を受けています。
ただし、加齢に伴い免疫機能自体が変化していることや、脱水などの副作用に対する予備能力が低い場合があるため、若年者よりも慎重な経過観察が必要となります。
- 一度効果が出ればずっと続きますか?
-
免疫療法の大きな特徴の一つに、効果の持続性(ロングテール効果)があります。
一度免疫システムががんを「敵」として正しく認識し、免疫記憶が形成されれば、治療を終了した後も長期にわたってがんの増殖を抑え続けられる可能性があります。
すべての患者で効果が永続するわけではありませんが、化学療法と比較して、効果が長く続く傾向にあることは、この治療法の大きな希望と言えます。
参考文献
MOUGEL, Alice; TERME, Magali; TANCHOT, Corinne. Therapeutic cancer vaccine and combinations with antiangiogenic therapies and immune checkpoint blockade. Frontiers in immunology, 2019, 10: 467.
ZANOTTA, Serena, et al. Enhancing dendritic cell cancer vaccination: the synergy of immune checkpoint inhibitors in combined therapies. International Journal of Molecular Sciences, 2024, 25.14: 7509.
ZHAO, Jing, et al. Safety and efficacy of therapeutic cancer vaccines alone or in combination with immune checkpoint inhibitors in cancer treatment. Frontiers in pharmacology, 2019, 10: 1184.
WANG, Xiupeng, et al. Synergistic anti-tumor efficacy of a hollow mesoporous silica-based cancer vaccine and an immune checkpoint inhibitor at the local site. Acta Biomaterialia, 2022, 145: 235-245.
KLEPONIS, Jennifer; SKELTON, Richard; ZHENG, Lei. Fueling the engine and releasing the break: combinational therapy of cancer vaccines and immune checkpoint inhibitors. Cancer biology & medicine, 2015, 12.3: 201-208.
YI, Ming, et al. Synergistic effect of immune checkpoint blockade and anti-angiogenesis in cancer treatment. Molecular cancer, 2019, 18.1: 60.
HE, Mengying, et al. Immune checkpoint inhibitor‐based strategies for synergistic cancer therapy. Advanced Healthcare Materials, 2021, 10.9: 2002104.
CHYUAN, I.-Tsu; CHU, Ching-Liang; HSU, Ping-Ning. Targeting the tumor microenvironment for improving therapeutic effectiveness in cancer immunotherapy: focusing on immune checkpoint inhibitors and combination therapies. Cancers, 2021, 13.6: 1188.
SWART, Maarten; VERBRUGGE, Inge; BELTMAN, Joost B. Combination approaches with immune-checkpoint blockade in cancer therapy. Frontiers in oncology, 2016, 6: 233.
MORSE, Michael A.; LYERLY, H. Kim. Checkpoint blockade in combination with cancer vaccines. Vaccine, 2015, 33.51: 7377-7385.