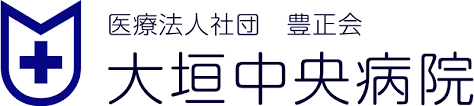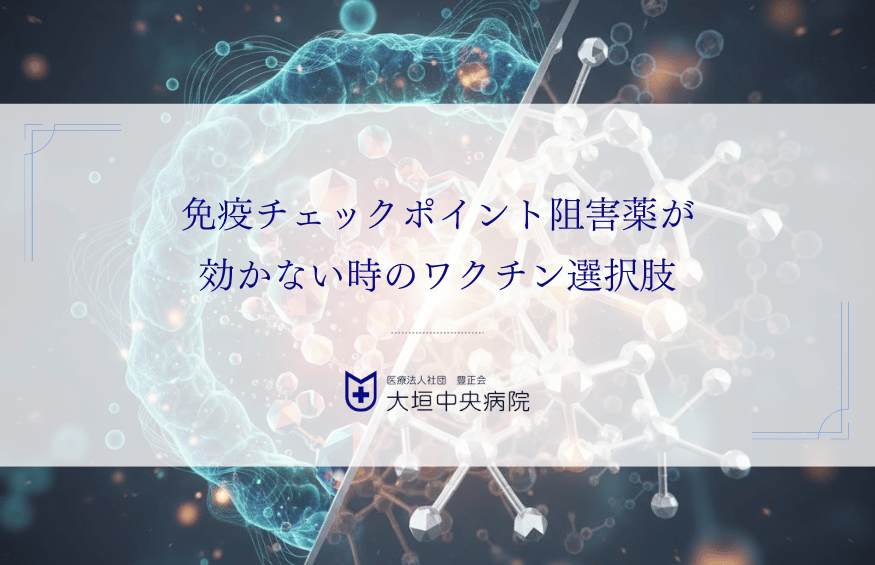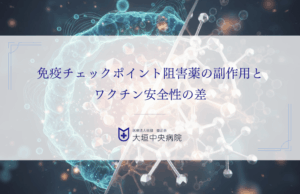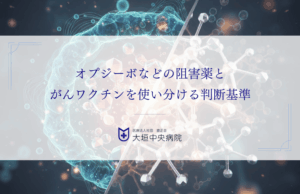免疫チェックポイント阻害薬による治療を受けたにもかかわらず、期待した効果が得られなかったり、一度は効いたものの途中から効果が薄れてしまったりして、次の治療法を模索している方は少なくありません。
現在の標準治療において重要な位置を占める免疫チェックポイント阻害薬ですが、実は単独での奏功率は限定的であることが分かっています。
しかし、薬が効かなかったからといって、免疫療法全ての可能性が閉ざされたわけではありません。
むしろ、免疫チェックポイント阻害薬が効かなかった原因を補う形で「がんワクチン」を取り入れることが、眠っている免疫細胞を再び呼び覚ます鍵になります。
この記事では、なぜ薬が効かないのかという根本的な理由を紐解きながら、その壁を乗り越えるための有力な選択肢であるがんワクチンについて、専門的な知見を交えて詳しく解説します。
免疫チェックポイント阻害薬が効かない主な原因と免疫環境
免疫チェックポイント阻害薬が効果を発揮できない最大の理由は、がん細胞を攻撃する役割を担うキラーT細胞が、がん組織の中に十分に存在していないか、あるいはがん細胞を敵として正しく認識できていないことにあります。
この薬は、免疫細胞にかかっているブレーキを外す役割を果たしますが、そもそもエンジンである免疫細胞が動いていなければ、ブレーキを外しても車は進みません。
つまり、攻撃部隊であるT細胞が不在の状態で薬を投与しても、がんに対する攻撃は始まらないのです。
がん組織内に免疫細胞が入り込めないコールド腫瘍の問題
がん組織の環境は、免疫細胞が浸潤しているかどうかによって大きく二つに分類します。一つは免疫細胞が十分に集まっている「ホット腫瘍」、もう一つは免疫細胞がほとんど存在しない「コールド腫瘍」です。
免疫チェックポイント阻害薬が著しい効果を示すのは、主にホット腫瘍の場合です。
すでにがん組織内に攻撃準備の整ったT細胞が存在しているため、薬によってブレーキを解除するだけで一気に攻撃が始まります。
一方で、コールド腫瘍ではT細胞ががん組織の周囲で足止めを食らっていたり、そもそも呼び寄せられていなかったりします。
この状態では、いくら免疫チェックポイント阻害薬を使って攻撃指令を出しても、実行部隊が現場にいないため効果が現れません。
日本人の多くのがん患者様において、このコールド腫瘍の状態が免疫チェックポイント阻害薬の効果を妨げる大きな障壁となっています。
したがって、治療を成功させるには、まずこのコールドな環境をホットな環境へと変える工夫が必要です。
がん細胞による目印の隠蔽と抗原提示の欠如
免疫細胞ががん細胞を攻撃するためには、がん細胞特有の目印(抗原)を認識する必要があります。しかし、がん細胞は生き残りをかけて、この目印を細胞表面から隠してしまうことがあります。
これを「抗原提示の消失」または「ダウンレギュレーション」と呼びます。
主要組織適合遺伝子複合体(MHC)クラスIという分子が目印を提示する役割を持ちますが、がん細胞はこのMHCクラスIの発現を低下させることで、免疫細胞の監視から逃れようとします。
目印が見えなくなったがん細胞は、免疫細胞にとっては正常細胞と区別がつきにくく、透明人間のような存在になります。
この状態では、免疫チェックポイント阻害薬によってT細胞を活性化させても、攻撃対象を見つけられずに空回りを続けてしまいます。この認識不足を解消し、再びがん細胞を目立たせるための対策が必要となります。
免疫抑制細胞による攻撃部隊への妨害工作
がん組織の中には、がん細胞を助けるような働きをする細胞も存在します。これらを免疫抑制細胞と呼び、代表的なものに制御性T細胞(Tregs)や骨髄由来抑制細胞(MDSC)があります。
これらの細胞は、本来体を守るはずのキラーT細胞の働きを強力に抑え込み、がん細胞にとって居心地の良い環境を作り出します。
免疫チェックポイント阻害薬を使っても効果が出ない場合、これらの抑制細胞が放出する物質によって、キラーT細胞が疲弊(エグゾースション)させられている可能性があります。
ブレーキを外そうとする薬の力以上に、現場での妨害工作が強ければ、免疫システムは機能不全に陥ります。
この強い抑制環境を打ち破るには、単にブレーキを外すだけでなく、アクセルを強く踏み込むような新たな刺激を加えることが重要です。
免疫環境の分類と特徴
| 腫瘍のタイプ | 免疫細胞の状態 | 阻害薬への反応性 |
|---|---|---|
| ホット腫瘍 | がん組織内に多数浸潤している | 高い効果が期待できる |
| コールド腫瘍 | がん組織内にほとんどいない | 効果が出にくい |
| 免疫除外型 | 組織の周囲に集まるが中に入れない | 工夫が必要 |
がんワクチンが果たす役割と免疫システムの再起動
がんワクチンは、免疫チェックポイント阻害薬が効かなかった患者様に対して、免疫システムにがんの特徴を改めて教育し、強力な攻撃部隊を新たに作り出すという決定的な役割を果たします。
阻害薬が「ブレーキの解除」であるのに対し、がんワクチンは「エンジンの点火」および「アクセル」の役割を担います。
がん細胞の目印を明確に提示することで、体内の樹状細胞やT細胞を刺激し、特異的な攻撃能力を持ったCTL(細胞傷害性T細胞)を誘導します。
コールド腫瘍をホット腫瘍へ転換させるプライミング効果
がんワクチンの最大の強みは、免疫細胞が不在だったコールド腫瘍に対して、人為的に免疫反応を引き起こせる点にあります。
ワクチンによって体内に入れた抗原(がんの目印)を樹状細胞が取り込み、リンパ節でT細胞に提示します。教育を受けたT細胞は活性化して増殖し、血流に乗って全身を巡り、がん組織へと集結します。
この一連の流れによって、これまで免疫細胞がいなかったがん組織の中に、新たに教育されたT細胞が浸潤するようになります。これを「プライミング(呼び水)」効果と呼びます。
がん組織が免疫細胞で満たされることで、腫瘍環境はコールドからホットへと変化し、攻撃の土台が整います。この環境変化こそが、後の治療効果を大きく左右する分岐点となります。
獲得免疫系への特異的な標的提示
私たちの体には、自然免疫と獲得免疫という二つの防御システムがあります。がんワクチンが主に働きかけるのは、より強力で精密な攻撃力を持つ獲得免疫系です。
自然免疫は即効性がありますが攻撃力は限定的です。一方、獲得免疫の主役であるキラーT細胞は、特定の標的を狙い撃ちにする高い能力を持っています。
ワクチン療法では、患者様のがん細胞が持っている特定のタンパク質(抗原)を標的として設定します。
その結果として、正常な細胞を傷つけることなく、がん細胞だけをピンポイントで攻撃するよう免疫システムに指令を出します。
漠然とした免疫強化ではなく、敵の顔写真を配って指名手配するように明確なターゲットを示すことで、攻撃の精度と強さを飛躍的に高めます。
免疫記憶の形成と長期的な監視体制の構築
一度教育を受けたT細胞の一部は、「メモリーT細胞」として体内に長く留まります。これは、はしかや水疱瘡のワクチンを打つと二度とかからないのと同じ原理です。
がんワクチンによって誘導されたメモリーT細胞は、体の中をパトロールし続け、もし再びがん細胞が増殖しようとしたり、微小な転移が見つかったりした際に、即座に反応して攻撃を再開します。
免疫チェックポイント阻害薬の効果が一過性で終わってしまった場合でも、ワクチンを併用することでこの免疫記憶を強化し、再発や転移を長期にわたって抑え込む監視体制を作ることが期待できます。
これは化学療法のような一時的な細胞殺傷効果とは異なり、体が本来持っている防御機能を永続的に高めるという点で大きな意義があります。
治療法による役割の違い
- 免疫チェックポイント阻害薬:免疫細胞のブレーキを解除する
- がんワクチン:免疫細胞に敵を認識させ攻撃を指令する
- 化学療法:増殖の速い細胞を直接攻撃する
選択可能な主なワクチン療法の種類と特徴
現在、臨床や自由診療の現場で提供されているがんワクチンにはいくつかの種類があり、それぞれ製造方法や体への作用の仕方が異なります。
患者様のがんの状態や保有するHLA(白血球の型)、さらにはこれまでの治療歴に合わせて、どの種類のワクチンが適しているかを見極めることが重要です。
患者様の状態に応じて、ペプチドワクチン、樹状細胞ワクチン、mRNAワクチンなど、特性の異なる手法から最適なものを選択します。
ペプチドワクチンの作用と利便性
ペプチドワクチンは、がん細胞の表面に出ている目印となるタンパク質の断片(ペプチド)を人工的に合成し、それを投与する治療法です。現在最も多くの研究が行われ、実施数も多いワクチンタイプです。
特定のがん抗原(例えばWT1やMAGE3など)を発現しているがんに対して、その抗原の一部を注射することで、免疫細胞に「この目印を持つ細胞を攻撃せよ」と教え込みます。
このワクチンの利点は、比較的安価で製造が容易であり、既製品として準備できる場合があるため、治療開始までの期間が短いことです。
ただし、効果を発揮するためには、患者様のHLA型とペプチドの型が一致している必要があります。日本人の約6割が持つHLA-A24型など、特定の型に対応したペプチドが多く開発されています。
樹状細胞ワクチンの高い抗原提示能力
樹状細胞ワクチンは、免疫の司令塔と呼ばれる樹状細胞そのものを体外で培養し、がんの目印を取り込ませてから体内に戻す治療法です。患者様自身の血液から成分採血を行い、未熟な細胞を取り出して樹状細胞へと分化させます。そこにがんの目印(人工抗原や患者様自身のがん組織)を与えて教育し、活性化した状態で体内に戻します。
この方法は、体内で自然に起こる免疫反応の一部を、条件の整った体外で確実に行うため、非常に強力な抗原提示能力を持ちます。
T細胞に対して直接的に攻撃指令を伝えることができるため、効率よくキラーT細胞を誘導できるのが特徴です。自分の細胞を使うため副作用のリスクは低いですが、細胞培養に高度な技術と施設を要します。
mRNAワクチンなどの新規モダリティ
近年、感染症予防ワクチンの成功により注目を集めているのがmRNAワクチンです。これはがん抗原の設計図となる遺伝子物質(mRNA)を脂質の膜で包んで投与する方法です。
体内の細胞がこのmRNAを取り込むと、一時的にがん抗原を作り出し、それを免疫システムが認識することで強い免疫反応が誘導されます。
mRNAワクチンの強みは、複数の抗原を同時にターゲットにできる点や、個々の患者様のがん遺伝子変異に合わせた完全オーダーメイドのワクチン(ネオアンチゲンワクチン)を迅速に製造できる可能性がある点です。
まだ研究段階のものが多いですが、従来のペプチドワクチンよりも強力な免疫誘導能を持つとして期待が高まっています。
ワクチンタイプ別の特徴比較
| ワクチンの種類 | 主な特徴 | 対象となる患者様 |
|---|---|---|
| ペプチドワクチン | 人工抗原を投与、実績豊富 | HLA型が適合する方 |
| 樹状細胞ワクチン | 自身の細胞を培養して使用 | 自分の免疫力を最大化したい方 |
| mRNAワクチン | 遺伝子情報を使用、強い誘導能 | 臨床試験等に参加できる方 |
免疫チェックポイント阻害薬との併用による相乗効果
免疫チェックポイント阻害薬が単独で効かなかった場合でも、がんワクチンと併用することで、劇的な治療効果の改善が期待できることが分かってきました。
これを「併用療法」と呼び、現在の免疫療法研究の主流となっています。アクセル(ワクチン)とブレーキ解除(阻害薬)を同時に行うことで、互いの弱点を補完し合い、相乗効果を生み出します。
アクセルとブレーキ解除の同時アプローチ
先述の通り、がんワクチンはT細胞を教育してがん組織へ送り込み(アクセル)、コールド腫瘍をホット腫瘍へと変えます。
しかし、せっかく集まったT細胞も、がん細胞からの反撃に遭うとブレーキをかけられて動きが止まってしまいます。ここで免疫チェックポイント阻害薬の出番です。
ワクチンによって誘導されたT細胞にかかるブレーキを即座に外すことで、T細胞は疲弊することなく攻撃を継続できます。
また、免疫チェックポイント阻害薬単独では反応しなかった患者様でも、ワクチンによって新しいT細胞が供給されることで、薬が作用する対象(T細胞)が増え、結果として薬の効果が現れるようになります。
つまり、ワクチンが薬の効果を引き出す呼び水となるのです。
リチャレンジ治療としての可能性
一度免疫チェックポイント阻害薬を使用して効果がなくなり、治療を中止した後に、ワクチンを加えて再度同じ阻害薬を使用することを「リチャレンジ」といいます。
通常、耐性がついた薬は再度使っても効果は期待できませんが、ワクチンの併用によって免疫環境がガラリと変わることで、再び感受性を取り戻すケースが報告されています。
この戦略は、使える薬剤の選択肢が尽きてしまった患者様にとって大きな希望となります。
薬剤を変更するのではなく、体内の環境を変えることで既存の薬を再利用するという考え方は、免疫療法ならではの特長です。
化学療法や放射線療法との組み合わせ
併用療法の相手は免疫チェックポイント阻害薬に限りません。抗がん剤(化学療法)や放射線療法とも組み合わせることがあります。
例えば、放射線照射によってがん細胞を破壊すると、がん細胞内部の抗原が大量に放出されます。このタイミングでワクチンを投与すると、免疫細胞が抗原を認識しやすくなり、ワクチンの効果が増強されます。
これを「アブスコパル効果」の増強と捉えることもあります。このように、複数の治療を戦略的に組み合わせることで、単独では崩せなかったがんの防壁を突破します。
併用療法の狙い
- T細胞の誘導と活性化維持の両立
- 薬剤耐性の克服と感受性の回復
- 免疫抑制環境の解除
自分のがんに合わせた個別化医療の重要性
がんワクチン治療において最も重要な要素の一つが「個別化」です。
がん細胞の特徴は患者様一人ひとり異なり、同じ肺がんや胃がんであっても、がん細胞が出している目印(抗原)や遺伝子の変異パターンは千差万別です。
したがって、万人共通のワクチンではなく、自分の免疫システムが認識できる抗原を使ったワクチンを選ぶことが、治療成功の鍵を握ります。
ネオアンチゲン解析による完全個別化
近年注目されているのが「ネオアンチゲン(新生抗原)」を標的としたワクチンです。がん細胞の遺伝子変異によって新しく生まれた異常なタンパク質をネオアンチゲンと呼びます。
これは正常な細胞には絶対に存在しないため、免疫細胞が「明らかな異物」として認識しやすく、極めて強力な攻撃を誘発します。
ネオアンチゲンワクチンを作るためには、患者様のがん組織と正常組織の遺伝子を解析し(ゲノム解析)、その人だけに存在する変異を特定する必要があります。
手間と時間はかかりますが、自分専用の抗原を用いるため、既製品のワクチンよりも高い特異性と効果が期待できます。これが究極の個別化医療と言われる所以です。
HLA検査と適合抗原の選定
ペプチドワクチンなど既存の抗原を使用する場合、HLA(ヒト白血球抗原)の型を調べることが必須です。
HLAは免疫細胞に抗原を提示する際のお皿のような役割をしており、このお皿の形が合わないと、いくらワクチンを打っても免疫細胞に情報が伝わりません。
日本人に多いHLA-A24やA02といった型に対応したワクチンは多く存在しますが、稀な型の場合は適合するワクチンが見つからないこともあります。
事前の血液検査で自身のHLA型を正確に把握し、それに合致した抗原セットを選ぶことが、無駄な治療を避けるためにも大切です。
免疫プロファイリングによる治療戦略の立案
単にワクチンを選ぶだけでなく、現在の体内の免疫状態を詳しく調べる「免疫プロファイリング」も重要です。リンパ球の数やバランス、制御性T細胞の比率、PD-L1の発現状況などを総合的に解析します。
このデータに基づき、まずは免疫抑制を解除すべきか、あるいは攻撃部隊を増やすべきかといった優先順位を決定します。
例えば、免疫抑制細胞が非常に多い状態でワクチンだけを打っても効果は薄いため、低用量の抗がん剤を先行させて抑制細胞を減らすといった前処置を行うこともあります。
個々の免疫状態に合わせた微調整こそが、専門機関に求められる技術です。
個別化治療のレベル
| レベル | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 完全個別化 | ネオアンチゲン解析 | 自分だけの変異を標的、高精度 |
| 部分個別化 | HLA適合ペプチド選択 | 複数の既製抗原から選択、迅速 |
| 非個別化 | 共有抗原単一投与 | 広く見られる抗原を使用、簡便 |
治療を受けるためのステップと医療機関選び
免疫チェックポイント阻害薬が効かないと判断された後、ワクチン療法への移行を検討する際、どのような手順で進めればよいのでしょうか。
自由診療を含めた選択肢となるため、患者様自身が能動的に情報を集め、信頼できる医療機関を選ぶ必要があります。
専門機関での検査から治療スケジュールの策定、効果判定まで、納得のいくプロセスを経ることが治療成功への第一歩です。
専門クリニックでのカウンセリングと検査
まずはがん免疫療法を専門とするクリニックや病院のセカンドオピニオンや初診相談を予約します。ここではこれまでの治療経過(使用した薬剤、期間、効果判定の画像データなど)を詳細に伝えます。
その上で、ワクチン治療が適応可能かどうかを判断するための事前検査を行います。
検査には血液検査によるHLAタイピングや免疫機能検査、場合によっては保存されているがん組織(パラフィンブロック)を用いた病理検査や遺伝子解析が含まれます。
これらの結果が出るまでには2週間から1ヶ月程度かかる場合があるため、今の治療を継続しながら並行して準備を進めることが望ましいです。
治療スケジュールの策定と投与開始
検査結果に基づき、使用するワクチンの種類や抗原、投与スケジュールが決定されます。多くのワクチン療法では、最初の数回は1〜2週間おきに頻繁に投与し、免疫を一気に立ち上げる「初期免疫」を行います。
その後は2週間〜1ヶ月おきに間隔を空けて投与し、免疫を維持する期間に入ります。
免疫チェックポイント阻害薬を継続しながらワクチンを追加する場合は、主治医との連携が必要です。
標準治療を行っている病院と、ワクチンを行うクリニックが異なる場合、双方の医師が情報を共有できる体制を作ることが、安全な併用療法の基盤となります。
効果判定と治療の継続判断
ワクチン療法の効果判定は、投与開始から3ヶ月〜6ヶ月後に行うのが一般的です。
CTやMRI画像による腫瘍の大きさの変化だけでなく、腫瘍マーカーの推移や、血液中の免疫細胞(特異的CTL)が増えているかどうかの免疫学的モニタリングも参考にします。
免疫療法は効果が現れるまでに時間がかかることがあり、画像上一時的に腫瘍が大きくなったように見えても、実は免疫細胞が集まって炎症を起こしているだけの「偽増悪(シュードプログレッション)」の可能性もあります。
即座に無効と判断せず、免疫反応の兆候を見逃さない専門的な評価が必要です。
確認すべき検査項目
- HLAタイピング検査
- がん抗原の発現検査
- 免疫機能・抑制状態の解析
FAQ
免疫チェックポイント阻害薬の効果不足に直面した患者様が抱く、併用療法の可否や副作用、期間や年齢制限といった切実な疑問に対し、医学的な根拠に基づいて回答します。
- 標準治療の抗がん剤と同時にワクチンを受けられますか?
-
はい、受けることが可能です。
むしろ、抗がん剤の種類によっては、がん細胞を破壊して抗原を放出させたり、免疫抑制細胞を減らしたりする作用があるため、ワクチンとの相性が良いものもあります。
ただし、抗がん剤の副作用で骨髄抑制が強く出て白血球が極端に減少している時期は、ワクチンの効果が出にくいため、投与のタイミングを調整する必要があります。
主治医とワクチン担当医が連携してスケジュールを組むことが大切です。
- ワクチンの副作用はどのようなものがありますか?
-
一般的に、がんワクチンの副作用は軽度であることが多いです。最も頻度の高いものは、注射部位の赤み、腫れ、痛み、硬結(しこり)などの局所反応です。
また、免疫が活性化する過程で、一時的な発熱や倦怠感が見られることがありますが、多くは数日で自然に軽快します。
免疫チェックポイント阻害薬と併用する場合は、阻害薬由来の免疫関連副作用(間質性肺炎や大腸炎など)に注意が必要ですが、ワクチン自体が重篤な副作用を引き起こすことは稀です。
- 効果が出るまでにどれくらいの期間がかかりますか?
-
免疫療法は、自身の免疫細胞を教育し、増やしてからがんを攻撃するという機序を経るため、即効性は期待しにくい治療法です。
個人差はありますが、一般的には治療開始から3ヶ月程度経過した時点で最初の評価を行います。
早い方では数回の投与で腫瘍マーカーの低下などの反応が見られますが、じっくりと時間をかけて効果が現れる「遅発性効果」を示すことも免疫療法の特徴の一つです。
- 高齢でもワクチン治療を受けることはできますか?
-
基本的に年齢制限はありません。ご自身の免疫細胞を利用する治療であるため、全身状態が比較的保たれており、通院が可能であれば、80代以上の高齢の方でも受けることができます。
体力への負担が少ないため、強い抗がん剤治療に耐えられない高齢の患者様にとって、QOL(生活の質)を維持しながら取り組める有力な選択肢となります。
ただし、免疫機能自体が極端に低下している場合は効果が出にくいこともあるため、事前の免疫機能検査が推奨されます。
参考文献
瀬谷司. 抗がん免疫アジュバントとがんワクチン療法の確立. 上原記念生命科学財団研究報告集, 2017, 31: 7p.
岡本正人; オカモトマサト. 複合免疫療法の開発~ 免疫チェックポイント阻害剤と癌ワクチン~. 2020.
池田裕明; 原田直純. がん治療ワクチンの可能性. 薬剤学, 2016, 76.1: 32-38.
TARTOUR, Eric. Anti-cancer vaccines: What future in anti-cancer immunotherapy strategies?. Biologie Aujourd’hui, 2018, 212.3-4: 69-76.
赤塚美樹; 内容紹介. がん免疫療法の展開と展望. 現代医, 2020, 67: 37-45.
石川剛; 内藤裕二; 伊藤義人. 消化器がん領域における免疫療法開発の現況と展望. 京都府立医科大学雑誌/京都府立医科大学雑誌編集委員会 編, 2017, 126.6: 391-403.
熊井琢美. 頭頸部癌に対する革新的免疫療法の開発. 日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会誌, 2024, 4.3: 123-126.
篠原周一, et al. ネオ抗原の同定と抗原特異的免疫療法の開発. 臨床血液, 2020, 61.9: 1433-1439.