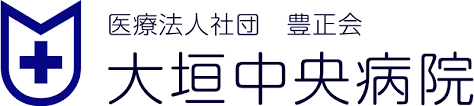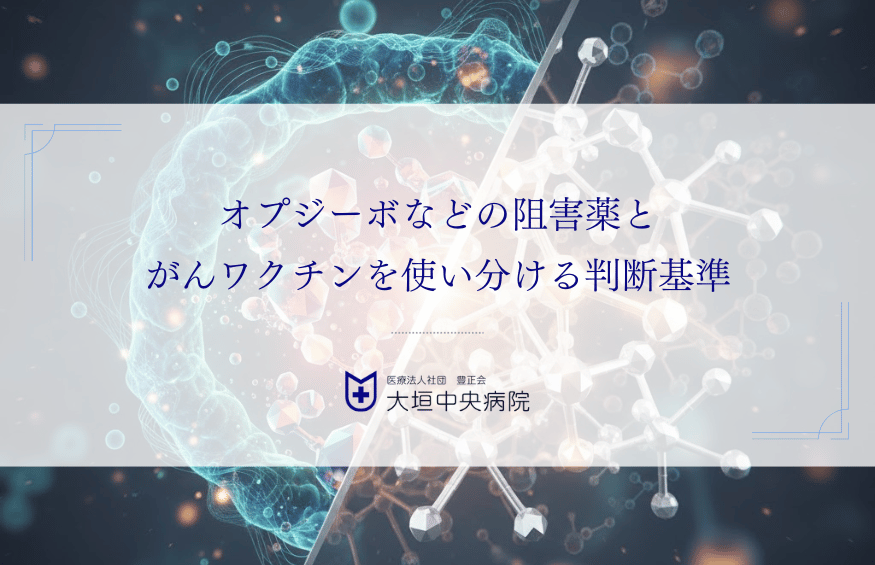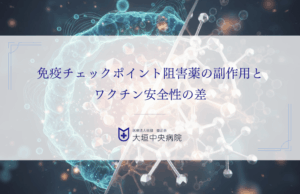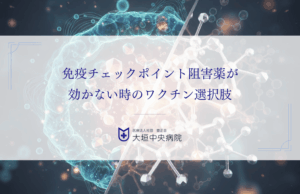免疫療法には大きく分けて、免疫細胞のブレーキを外して攻撃力を高める「オプジーボなどの免疫チェックポイント阻害薬」と、がんの目印を免疫細胞に覚え込ませる「がんワクチン」の二つが存在します。
どちらを選ぶべきかは、患者さん一人ひとりのがんの性質や体内の免疫環境によって大きく異なります。
本記事では、がん細胞の遺伝子変異量や免疫細胞の集まり具合を示すホット腫瘍・コールド腫瘍といった概念、さらには副作用のリスクや病状の進行度など、多角的な視点から両者を使い分けるための具体的な判断基準について解説します。
ご自身の状況に合った治療法を見極めるための一助としてください。
免疫チェックポイント阻害薬とがんワクチンの基本的な作用機序の違い
免疫チェックポイント阻害薬とがんワクチンは、どちらも患者さん自身の免疫力を利用してがんを攻撃しますが、そのアプローチは「ブレーキを外す」か「アクセルを踏んでハンドルを切る」かという点で根本的に異なります。
この仕組みの違いを理解することが、自身の体内でどのような反応が起きるかをイメージし、納得のいく治療選択を行うための第一歩となります。
免疫のブレーキを解除する阻害薬の働き
私たちの体には、免疫細胞が暴走して自分自身の正常な細胞まで攻撃してしまわないよう、免疫にブレーキをかける仕組みが備わっています。これを免疫チェックポイントと呼びます。
がん細胞はこの仕組みを悪用し、免疫細胞に対して「私は攻撃する相手ではない」という偽の信号を送ることで攻撃を回避しています。
オプジーボをはじめとする免疫チェックポイント阻害薬は、この偽の信号を遮断することで、がん細胞がかかっていたブレーキを強制的に解除します。
ブレーキが解除されると、本来の攻撃力を取り戻したT細胞(リンパ球の一種)は、再びがん細胞を異物として認識し、破壊活動を再開します。
この治療法は、すでに体内にがんを攻撃する準備ができているT細胞が存在する場合に極めて高い効果を発揮します。
つまり、エンジンはかかっているがブレーキが踏まれている状態の車に対し、ブレーキを外して走らせるようなイメージです。
治療法の役割比較
| 比較項目 | 免疫チェックポイント阻害薬 | がんワクチン |
|---|---|---|
| 基本的な役割 | 免疫のブレーキを解除する | 免疫に攻撃目標を教える |
| 作用のイメージ | 停止している攻撃を再開させる | 攻撃部隊を新たに育成する |
| T細胞への影響 | 疲弊したT細胞を活性化する | 特異的なT細胞を増やす |
攻撃目標を教え込むがんワクチンの役割
一方、がんワクチンは免疫細胞に対して「これが攻撃すべき敵の顔だ」と明確な標的を教え込む役割を果たします。
がん細胞は正常な細胞から変異して生まれるため、免疫細胞にとっては正常な細胞との区別がつきにくい場合があります。
がんワクチンは、がん細胞特有のタンパク質(抗原)の一部を体内に投与することで、樹状細胞などの司令塔となる細胞に情報を伝達します。
情報を受け取った樹状細胞は、攻撃の実行部隊であるT細胞に対して標的を提示し、攻撃命令を下します。その結果、それまでがん細胞を認識できていなかったT細胞が活性化し、狙いを定めて攻撃を開始します。
阻害薬がブレーキを外すのに対し、ワクチンはアクセルを踏み込みながら、正しい方向へハンドルを切る役割を担います。
特に、体内にがんを攻撃するT細胞が少ない場合に、その数を増やして戦闘態勢を整えるために重要です。
どちらも自分自身の免疫力を利用する点は共通
アプローチは異なりますが、両者に共通しているのは「外部から毒を入れてがんを殺す」のではなく、「患者さん自身の免疫システムを再起動させる」という点です。
従来の抗がん剤は、細胞分裂が活発な細胞を無差別に攻撃するため、正常な細胞も大きなダメージを受けました。
しかし、免疫療法は免疫細胞が主役であるため、特定の条件下では副作用を抑えつつ、長期的な効果持続を期待できます。
この共通点は、治療の効果が出るまでに時間がかかる場合があるという特徴にもつながります。免疫細胞が活性化し、増殖し、がん細胞にたどり着いて攻撃を完了するまでには一定の期間が必要です。
そのため、即効性を求める場合よりも、じっくりと自身の体質を変えてがんに対抗する力を養うという意味合いが強くなります。
両者の違いと共通点を踏まえた上で、次項からの具体的な使い分け基準を見ていきましょう。
がんのタイプや遺伝子変異量による適性の判断
がん細胞が持っている遺伝子の特徴や変異の量は、免疫療法が効くかどうかの重要な予測因子となります。
特に、遺伝子変異が多いがんは免疫細胞に見つけられやすく、阻害薬が良い適応となる傾向がありますが、変異が少ない場合でもワクチンの標的となる抗原が存在すれば、そちらが有力な選択肢となります。
遺伝子変異が多いがんでの阻害薬の優位性
がん細胞の遺伝子に傷がたくさんついている状態を「高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)」や「高い腫瘍遺伝子変異量(TMB-High)」と呼びます。
遺伝子の変異が多いということは、それだけ正常な細胞とは異なる異常なタンパク質(ネオアンチゲン)がたくさん作られていることを意味します。
これらは免疫細胞にとって格好の目印となるため、本来であれば免疫系から激しい攻撃を受けるはずです。
しかし、変異が多いがんは生き残るために強力なブレーキ(PD-L1など)をかけて免疫を抑制していることが多々あります。
このような状況では、オプジーボなどの阻害薬を使ってブレーキさえ外してやれば、すでに周囲に集まっている大量の免疫細胞が一気にがんを攻撃し始めます。
肺がんやメラノーマ、一部の大腸がんなどで阻害薬が著効するのは、こうした遺伝的背景が関係しています。
遺伝子変異と免疫応答の関連要素
- 変異が多いほど、免疫細胞が敵として認識する目印が増える
- MSI-Highの固形がんは、臓器横断的に阻害薬の良い適応となる
- 喫煙や紫外線が原因のがんは変異が多く、阻害薬が効きやすい傾向がある
特定の抗原を持つがんに対するワクチンの強み
一方で、遺伝子変異がそれほど多くないがん(MSI-Stableなど)の場合、免疫細胞はがんを異物として認識しづらいため、阻害薬単独では効果が出にくいことがあります。
しかし、変異の総数は少なくても、そのがんに特有の「目印(腫瘍関連抗原)」が強く発現している場合があります。例えば、WT1やNY-ESO-1といった特定の抗原です。
このようなケースでは、その特定の抗原を標的としたがんワクチンを使うことで、免疫システムに「この目印を持つ細胞を攻撃せよ」とピンポイントで指示を出せます。
阻害薬が「全体的な攻撃許可」を出すのに対し、ワクチンは「指名手配書」を配るようなものです。
変異量が少なく、自然な免疫反応が起きにくいがんに対しては、ワクチンによる能動的な免疫誘導が必要となる場面が多くなります。
マイクロサテライト不安定性検査の重要性
これらを判断するために重要となるのが、マイクロサテライト不安定性(MSI)検査や、遺伝子パネル検査です。
治療を開始する前に組織を採取して遺伝子の状態を調べることで、そのがんが「免疫原性が高い(免疫に見つかりやすい)タイプ」なのか、「免疫原性が低い(免疫に見つかりにくい)タイプ」なのかを判別します。
この検査結果は、治療方針を決定する羅針盤となります。
MSI-Highであれば阻害薬を第一選択として検討し、そうでなければ他の薬物療法を優先するか、あるいは臨床試験レベルでのがんワクチンの適用や、阻害薬との併用を模索するといった判断が可能になります。
科学的なデータに基づいて戦略を立てることが、無駄な治療を避け、効果を最大化するために大切です。
免疫環境の状態であるホット腫瘍とコールド腫瘍の見極め
がん組織の中に免疫細胞がどれくらい入り込んでいるかという「腫瘍微小環境」の状態は、治療効果を左右する最大の要因の一つです。
免疫細胞がすでに浸潤している「ホット腫瘍」と、排除されている「コールド腫瘍」では、選ぶべき戦術が真逆になります。
免疫細胞が浸潤しているホット腫瘍への対応
「ホット腫瘍」とは、がん細胞の周囲や内部にリンパ球(T細胞など)がたくさん集まっていて、炎症を起こしている状態の腫瘍を指します。
これは、免疫システムがすでにがんを敵として認識し、攻撃しようと集まってきている証拠です。しかし、がん細胞が巧みにブレーキをかけているため、攻撃が寸止めされています。
この状態であれば、新たに免疫細胞を呼び寄せる必要はありません。すでに現場にいる兵隊の足枷を外すだけで十分な戦力になります。
したがって、ホット腫瘍に対しては免疫チェックポイント阻害薬が極めて有効です。薬剤を投与することで、待機していたT細胞が一斉に攻撃を開始し、ドラマチックな腫瘍縮小効果をもたらすことが期待できます。
免疫細胞が少ないコールド腫瘍へのアプローチ
対照的に「コールド腫瘍」は、がん組織の中に免疫細胞がほとんど存在しない状態です。
がん細胞が免疫細胞の侵入を物理的に阻んでいたり、免疫を呼び寄せる物質を出していなかったりするため、周囲は静まり返っています。
この状態でいくら阻害薬を使ってブレーキを外しても、肝心の攻撃する兵隊(T細胞)がいなければ何も起こりません。
ここでがんワクチンの出番となります。コールド腫瘍に対しては、まずがんワクチンを使って免疫システムを刺激し、キラーT細胞を体内で増殖させ、がん組織へと誘導する必要があります。
つまり、冷え切った環境に火をつけて「ホット」な状態に変える(Turn Cold to Hot)ことが、ワクチンの重要な使命です。
コールド腫瘍の患者さんには、阻害薬単独よりもワクチンを含めたアプローチを検討する意義が大きくなります。
腫瘍環境による治療適性
| 腫瘍タイプ | 免疫細胞の状態 | 推奨される治療戦略 |
|---|---|---|
| ホット腫瘍 | 多数浸潤している | 阻害薬でブレーキを解除する |
| コールド腫瘍 | ほとんどいない | ワクチンで誘導し環境を変える |
| アルタード腫瘍 | 周囲にはいるが中に入れない | 微小環境の壁を壊す薬剤を併用 |
腫瘍微小環境を変えるための戦略
最近の研究では、コールド腫瘍をいかにしてホット腫瘍に変えるかが大きなテーマとなっています。
がんワクチンだけでなく、放射線治療や一部の抗がん剤を先行して行うことでがん細胞を破壊し、そこから漏れ出る抗原によって免疫を呼び寄せる方法(免疫原性細胞死の誘導)も試みられています。
また、がん細胞を守っている壁のような線維組織を分解する薬剤や、血管を正常化する薬剤を併用することで、免疫細胞ががん組織の深部まで到達できるように環境を整えることも重要です。
単純に薬を選ぶだけでなく、がんという城の守りをどう崩し、攻め入りやすい環境を作るかという視点で、阻害薬とワクチン、その他の治療法を組み合わせる判断が求められます。
病期や治療のタイミングによる使い分けの考え方
がんと診断された時点での進行度(ステージ)や、これまでにどのような治療を受けてきたかというタイミングも、阻害薬とワクチンのどちらを選ぶべきかの重要な判断材料です。
一般的に、目に見える大きな腫瘍がある場合と、手術後の微小な残存がんを叩く場合では、求められる役割が異なります。
進行がんや転移がある場合の標準的な選択
ステージ4の進行がんや、他の臓器への転移が見られる場合、現在では多くの種類のがんで免疫チェックポイント阻害薬が標準治療として組み込まれています。
これは、大規模な臨床試験によって生存期間の延長が証明されているためです。
大きな腫瘍塊がある場合、それに対抗するには強力かつ全身的な免疫反応が必要であり、阻害薬による広範な免疫活性化が理にかなっています。
特に、抗がん剤治療が効かなくなった後の二次治療、あるいは最初からの一次治療として、単剤または抗がん剤との併用で阻害薬が使用されます。
この段階では、エビデンス(科学的根拠)が確立している阻害薬を優先的に使用し、病勢をコントロールすることが最優先事項となります。
手術後の再発予防におけるワクチンの可能性
一方、手術で目に見えるがんを取りきった後の「再発予防」の段階では、がんワクチンの強みが活きる可能性があります。
この時期は体内に残っているがん細胞の数(微小残存病変)が非常に少ないため、免疫抑制の力も弱く、ワクチンによって誘導されたT細胞が効率よく残党を処理できると期待されるからです。
大量のがん細胞が存在する状況では、ワクチンの力だけでは押し切れないことも多いですが、敵が少数であれば、特異的な免疫部隊を送り込むことで完全治癒を目指せる可能性が高まります。
現在、術後補助療法としてのがんワクチンの臨床試験も数多く行われており、副作用が比較的少ない点も、長期的に体調を管理する必要がある術後の時期に適しています。
治療フェーズごとの選択肢例
- 進行・再発期は、エビデンス豊富な阻害薬が主軸となる
- 術後の微小残存病変に対しては、ワクチンの標的攻撃が期待される
- 腫瘍量が少ない時期ほど、ワクチンの誘導効果が発揮されやすい
標準治療終了後の選択肢としての検討
標準治療(手術、放射線、既認可の薬物療法)をすべてやり尽くし、治療法がないと言われた段階で、自由診療としてのがんワクチンを検討する患者さんも少なくありません。
この段階では、全身状態が保たれていることが前提となりますが、副作用の強い抗がん剤をこれ以上続けられない場合などに、QOL(生活の質)を維持しながら免疫能を維持・向上させる目的でワクチンが選択されることがあります。
ただし、末期の状態で免疫機能が極端に低下していると、ワクチンを投与しても反応が起きにくいという現実は直視する必要があります。
そのため、できるだけ早い段階、あるいは他の治療と並行して免疫の状態が良い時期に検討を開始することが、ワクチンのポテンシャルを引き出す鍵となります。
副作用のリスクと患者の全身状態を考慮した選択
どのような治療にもメリットとデメリットがあります。特に免疫療法は、従来の抗がん剤とは異なる独特の副作用が現れることがあります。
患者さんの体力、持病の有無、そして生活スタイルに合わせて、許容できるリスクの範囲内で薬剤を選ぶことが安全な治療継続には必要です。
自己免疫疾患のような症状が出る阻害薬のリスク
免疫チェックポイント阻害薬は、全身の免疫のブレーキを外すため、活性化した免疫細胞が正常な臓器まで攻撃してしまうことがあります。これを免疫関連有害事象(irAE)と呼びます。
間質性肺炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害など、全身のあらゆる臓器で炎症が起こる可能性があります。
これらの副作用は、時に重篤化し、命に関わることもあります。
そのため、もともと間質性肺炎を持っている人や、自己免疫疾患(リウマチや膠原病など)の既往がある患者さんに対しては、阻害薬の使用は慎重になる必要があります。
あるいは、使用するとしても厳密なモニタリング体制が整った病院で行うことが絶対条件となります。
比較的軽微な反応で済むワクチンの特徴
対して、がんワクチンは特定の標的のみを攻撃するように免疫を誘導するため、全身的な自己免疫反応は起こりにくいという特徴があります。
主な副作用は、注射部位の赤みや腫れ、発熱、倦怠感といった、インフルエンザワクチン接種後に見られるような軽度で一時的なものが中心です。
このため、高齢で体力が低下している方や、重篤な副作用を懸念して強力な治療を避けたい方にとっては、がんワクチンの方が身体への負担が少ない選択肢となり得ます。
仕事や日常生活を続けながら治療を行いたいというニーズに対しても、通院頻度や副作用の軽さの面でワクチンが適している場合があります。
主な副作用の比較
| 項目 | 免疫チェックポイント阻害薬 | がんワクチン |
|---|---|---|
| 発生頻度の高い症状 | 皮膚炎、倦怠感、下痢、甲状腺異常 | 注射部位反応、一過性の発熱 |
| 重篤なリスク | 間質性肺炎、劇症1型糖尿病など | アナフィラキシー(極めて稀) |
| 管理の難易度 | 専門医による全身管理が必要 | 比較的管理しやすい |
合併症を持つ患者における安全性評価
腎機能や肝機能が低下している患者さんにおいて、従来の抗がん剤は使用量が制限されることがありましたが、免疫療法薬の多くは代謝経路が異なるため、使用可能なケースがあります。
しかし、阻害薬による免疫反応が臓器障害を悪化させるリスクはゼロではありません。
がんワクチンは、成分自体が体内で分解されやすく、臓器への蓄積毒性が少ないため、合併症を持つ患者さんでも比較的安全に実施できることが多いです。
もちろん、医師と相談の上で慎重に判断する必要がありますが、「全身状態があまり良くないが、何か治療をしたい」という場面で、低侵襲なワクチン療法が選択のテーブルに上がることは理にかなっています。
検査データに基づいた科学的なバイオマーカーの活用
「やってみないとわからない」という要素が強かったかつての免疫療法とは異なり、現在では事前に効果をある程度予測するための検査(バイオマーカー)が充実してきています。
これらのデータを読み解くことで、阻害薬が効きそうか、それともワクチンを併用すべきかという判断をより精密に行うことができます。
PD-L1発現率が示す薬剤の効果予測
最も一般的に用いられる指標が、がん細胞の表面に現れる「PD-L1」というタンパク質の量です。
このPD-L1ががん細胞に多く発現している(陽性率が高い)場合、それはがんがPD-L1を使って免疫に強くブレーキをかけていることを意味します。
つまり、阻害薬でその結合をブロックすれば、劇的な効果が期待できる可能性が高いと判断されます。
肺がんなどの治療方針決定においては、このPD-L1の発現率(TPSスコアなど)を測定し、スコアが高ければ阻害薬単剤、低ければ抗がん剤との併用、といった具体的な振り分けが行われています。
逆にPD-L1が陰性の場合は、阻害薬単独では効果が出にくいため、他の手段を模索する必要があります。
腫瘍遺伝子変異量TMBの測定意義
前述したTMB(Tumor Mutational Burden)も重要な数値です。遺伝子パネル検査などでTMBが高い(TMB-High)と判定された場合、がん細胞表面には多種多様なネオアンチゲンが出現していると推測されます。
これは免疫にとって見つけやすい標的が山ほどある状態なので、阻害薬の良い適応となります。
TMBが低い場合は、ネオアンチゲンが少なく、自然な免疫反応が起きにくい状態です。
このような患者さんに対しては、人工的に強力な抗原を提示するがんワクチンや、免疫反応を強制的に引き起こすウイルス療法などが、理論的に必要なアプローチとして浮上してきます。
主要なバイオマーカーとその意味
| バイオマーカー | 数値の意味 | 判断への影響 |
|---|---|---|
| PD-L1発現率 | ブレーキ分子の多さ | 高いほど阻害薬が効きやすい傾向 |
| TMB(遺伝子変異量) | がんの異物らしさ | 高いほど免疫反応が起きやすい |
| MSI(マイクロサテライト) | DNA修復機能の異常 | MSI-Highなら阻害薬が著効しやすい |
新抗原ネオアンチゲンの解析技術
さらに進んだ技術として、個々の患者さんのがん細胞の遺伝子をすべて解析し、その人だけの「ネオアンチゲン」を特定する技術が実用化されつつあります。
この技術によって、「あなたのがんにはこの変異があるから、この部分を標的としたワクチンを作れば効くはずだ」という、完全オーダーメイドの治療設計が可能になります。
既存のマーカーで阻害薬の効果が期待できない場合でも、このネオアンチゲン解析を行うことで、その患者さん特有の弱点を見つけ出し、そこを攻めるパーソナルがんワクチンを作製するという新たな道が開けます。
データに基づいた個別化医療の実現こそが、今後の判断基準の核となっていくでしょう。
併用療法という選択肢と相乗効果への期待
これまでは「阻害薬か、ワクチンか」という二者択一の視点で解説してきましたが、現在の免疫療法のトレンドは「併用」にシフトしています。
それぞれの弱点を補い合い、長所を掛け合わせることで、単独では太刀打ちできなかったがんを攻略しようという動きが活発です。
両者を組み合わせるアクセルとブレーキの理論
阻害薬(ブレーキ解除)とワクチン(アクセルとハンドル)を併用するのは、理論的に非常に強力です。ワクチンによって攻撃能力を持ったT細胞を増やし、がん組織へ送り込みます。
そして、がん組織に到達したT細胞ががん細胞の反撃(ブレーキ)に遭ったところで、阻害薬を使ってその妨害を排除します。
この組み合わせを用いることで、「兵隊はいるがブレーキをかけられている」あるいは「ブレーキは外れたが兵隊がいない」という片手落ちの状態を解消し、循環する免疫サイクルを回し続けることが可能になります。
特にコールド腫瘍を治療する際には、この併用戦略がブレイクスルーになると期待されています。
既存の抗がん剤や放射線との組み合わせ
免疫療法同士の組み合わせだけでなく、従来の抗がん剤や放射線治療との併用も重要です。例えば、抗がん剤でがん細胞を破壊すると、がんの中から大量の抗原がばら撒かれます。
これを免疫系が感知するタイミングで阻害薬を投入することで、相乗効果を狙います(免疫原性細胞死の利用)。
また、放射線治療にはアブスコパル効果といって、照射した部位のがんが壊れることで免疫が活性化し、照射していない離れた場所のがんまで縮小する現象が知られています。
この効果を阻害薬やワクチンで増強しようという試みも、実際の臨床現場で行われています。
治療効果を高めるための複合的な戦略
このように、使い分けの判断基準は「AかBか」という単純なものではなく、「今の体の状態には、どの組み合わせが必要か」という複合的なパズルを解く作業に似ています。
医師は、エビデンス、患者さんの体力、がんの性質、経済的な事情などを総合的に勘案してレシピを組み立てます。
患者さん自身も、「自分のがんは免疫が反応しやすいタイプなのか」「ブレーキがかかっているだけなのか、そもそも兵隊がいないのか」といった視点を持つことで、主治医からの提案をより深く理解し、納得して治療方針を選択できるようになります。
最適な治療戦略は、固定されたものではなく、病状の変化とともに柔軟に見直していくものです。
よくある質問
- どちらの治療法が自分に合っているか自分で判断できますか?
-
ご自身だけで完全に判断することは困難です。がんの遺伝子タイプ、PD-L1の発現状況、腫瘍の微小環境、全身の臓器機能など、専門的な検査データを総合的に分析する必要があるからです。
しかし、本記事で解説した「ホット腫瘍・コールド腫瘍」や「副作用の違い」などの知識を持つことで、主治医に対して「私のがんは免疫細胞が集まっているタイプですか?」といった具体的な質問ができるようになり、納得のいく治療選択につながります。
- 副作用が起きた場合はすぐに治療を中止する必要がありますか?
-
副作用の程度によります。軽度であれば、対症療法(解熱剤やステロイド外用薬など)を行いながら治療を継続できることが多いです。
しかし、免疫チェックポイント阻害薬による間質性肺炎や1型糖尿病など、重篤な副作用の兆候が見られた場合は、直ちに休薬し、ステロイドパルス療法などの適切な処置を行う必要があります。
自己判断で我慢せず、些細な変化でもすぐに医療機関へ連絡することが大切です。
- 標準治療を受けながらがんワクチンを接種することは可能ですか?
-
医学的には可能な場合が多いですが、実施するタイミングや組み合わせには注意が必要です。
例えば、抗がん剤によって骨髄機能が強く抑制されている時期にワクチンを打っても、免疫細胞が十分に作られず効果が得られない可能性があります。
一方で、抗がん剤の休薬期間や維持療法中などに併用することで相乗効果を狙う戦略もあります。主治医と、ワクチンを提供する医師の連携のもとで計画を立てることが重要です。
- 高齢でも免疫療法を受けることはできますか?
-
はい、可能です。免疫療法は細胞分裂を直接阻害する抗がん剤とは異なり、全身の細胞へのダメージが比較的少ないため、高齢者でも忍容性が高い(副作用に耐えられる)ケースが多く見られます。
実際に75歳以上の患者さんでも効果を上げている報告は多数あります。
ただし、加齢に伴う免疫機能の低下や、持病(併存疾患)の状態を慎重に評価した上で、薬剤の種類や投与量を調整するなどの配慮は必要となります。
参考文献
谷川啓司. 癌免疫細胞療法: 樹状細胞ワクチン及び活性化リンパ球療法. 国際抗老化再生医療学会雑誌= The journal of World Academy of Anti-Aging & Regenerative Medicine (WAARM) Society/国際抗老化再生医療学会 編, 2024, 6: 12-19.
瀬谷司. 抗がん免疫アジュバントとがんワクチン療法の確立. 上原記念生命科学財団研究報告集, 2017, 31: 7p.
岩堀幸太; 和田尚. がん免疫療法の効果予測診断法. ファルマシア, 2017, 53.1: 45-48.
北野滋久, et al. 免疫チェックポイント阻害薬治療の展開~ 肺癌以外の領域~. 肺癌, 2024, 64.3: 158-167.
河上裕. 効果的な複合がん免疫療法開発のためのがん免疫微小環境の個別化制御. 臨床血液, 2018, 59.7: 939-944.
佐藤工, et al. 抗癌療法としての免疫チェックポイント阻害剤の効果予測因子の同定. 聖マリアンナ医科大学雑誌, 2016, 43.4: 237-243.
熊井琢美. 頭頸部癌に対する革新的免疫療法の開発. 日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会誌, 2024, 4.3: 123-126.
河上裕. 免疫チェックポイント阻害によるがん治療. 臨床血液, 2015, 56.10: 2186-2194.
北野滋久. がん免疫療法の最前線. 日本内科学会雑誌, 2017, 106.12: 2645-2658.
清水哲男. 肺癌治療における免疫療法の展望. 日大医学雑誌, 2016, 75.4: 161-163.