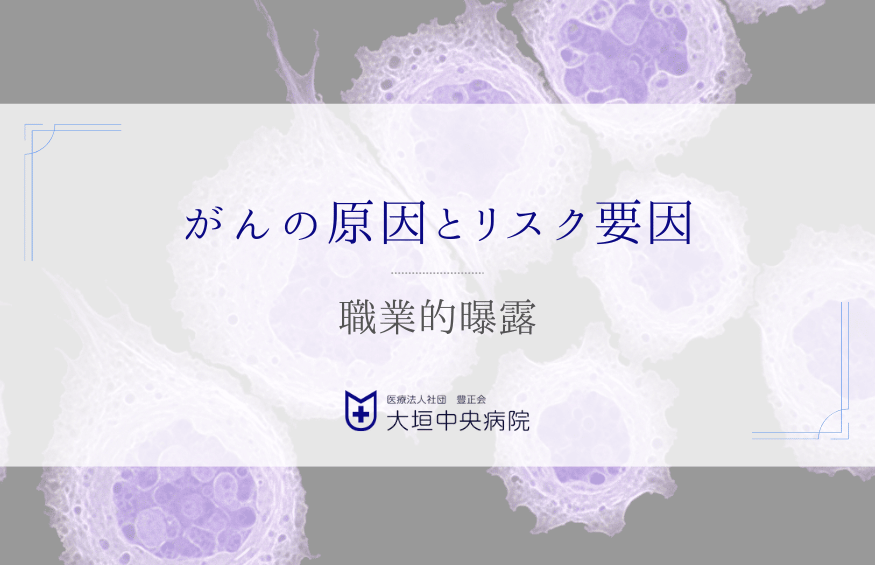「がん」と診断されたとき、その原因は生活習慣や遺伝的要因にあると考える方が多いかもしれません。
しかし、仕事の内容や職場の環境が、がんの発症に深く関わっている可能性があることは、あまり知られていないかもしれません。これが「職業がん」です。
毎日通う職場に、知らず知らずのうちに健康を脅かすリスクが潜んでいるとしたら、それは決して他人事ではありません。
この記事では、職業がんとは何か、どのような仕事や物質が危険因子となるのか、そして自分と大切な家族を守るために何ができるのかを、一つひとつ丁寧に解説します。
「職業がん」という言葉を知っていますか?
仕事が原因で発症するがんを「職業がん」と呼びます。特定の化学物質やアスベスト(石綿)のような粉じん、特殊な放射線などに長期間さらされる(曝露する)ことで、がんになるリスクが高まります。
多くの職業がんには、曝露を開始してから発症するまでの「潜伏期間」が非常に長いという特徴があります。
時には10年、20年以上経ってから症状が現れることもあり、原因が仕事にあると気づきにくいことが課題の一つです。
過去には、特定の工場や建設現場で働いていた人々が、退職後かなり経ってから肺がんや中皮腫などを発症した事例が社会問題となりました。
これらの事例を通じて、職業がんの存在と、その対策や労災認定の重要性が広く認識されるようになりました。
職業がんの定義と歴史
職業がんとは、国際がん研究機関(IARC)などが科学的根拠に基づき「発がん性がある」と分類した物質や作業工程に、仕事を通じて曝露することが原因で発生するがんの総称です。
その歴史は古く、18世紀のイギリスで煙突掃除人に皮膚がんが多発したことから研究が始まりました。
日本では、高度経済成長期に多用されたアスベストによる健康被害が深刻な問題となり、国を挙げた対策が進められています。
職業がんの認定は、仕事と発症との因果関係を医学的、社会的に証明する労災認定の制度を通じて行われます。
職業がんと労災保険制度
仕事が原因でがんになったと認められた場合、労働者災害補償保険(労災保険)の対象となります。治療費や休業中の生活費などが給付される重要な制度です。
しかし、潜伏期間が長いことや、生活習慣など他のがんリスク要因との区別が難しいことから、因果関係の証明が容易でないケースも少なくありません。
過去の事例や医学的知見の蓄積により、認定基準は少しずつ整備されていますが、依然として課題は残っています。
職業がんの主な事例
| 原因物質・要因 | 関連する主な疾患 | 主な関連業種 |
|---|---|---|
| アスベスト(石綿) | 悪性中皮腫、肺がん | 建設業、造船業、断熱材製造 |
| ベンゼン | 白血病 | 化学工場、印刷業、製靴業 |
| 塩化ビニルモノマー | 肝血管肉腫 | 化学物質製造業 |
あなたの職場は安全?発がん性物質と作業環境のリスク
私たちの身の回りには、便利で快適な生活を支える多くの化学物質が存在します。
しかし、その中には、長期間にわたって体内に取り込まれることで、がんを引き起こす可能性がある「発がん性物質」も含まれています。
特に職場では、家庭よりも高濃度の化学物質や粉じんに曝露するリスクがあります。
どのような物質が危険で、どのような作業環境がリスクを高めるのかを理解し、適切な対策を講じることが自身の健康を守る上で重要です。
リスクとなる主な原因物質
がんの原因となりうる物質は多岐にわたります。固体、液体、気体と形状もさまざまで、呼吸や皮膚接触を通じて体内に侵入します。
代表的なものには、アスベストや結晶性シリカなどの鉱物性の粉じん、ベンゼンやホルムアルデヒドなどの有機溶剤、ヒ素やクロムなどの金属類があります。
これらの原因物質は、特定の臓器に蓄積し、細胞の遺伝子を傷つけることでがんを発生させると考えられています。
発がん性物質の分類
| 分類 | 概要 | 代表的な物質 |
|---|---|---|
| グループ1 | ヒトに対して発がん性がある | アスベスト、ベンゼン、ヒ素 |
| グループ2A | ヒトに対しておそらく発がん性がある | 結晶性シリカ、紫外線 |
| グループ2B | ヒトに対して発がん性の可能性がある | ホルムアルデヒド、溶接ヒューム |
危険な作業環境とは
原因物質が存在するだけでは、必ずしもリスクが高いわけではありません。その物質をどのくらいの濃度で、どのくらいの期間、どのような方法で取り扱うかが重要になります。
例えば、換気が不十分な室内で粉じんが舞う作業や、適切な保護具を着用せずに有機溶剤を取り扱う作業は、曝露のリスクを著しく高めます。作業環境の管理が、職業がんの予防において極めて大切です。
曝露リスクを高める環境要因
- 換気の不十分な屋内作業
- 粉じんやミストが飛散する環境
- 化学物質の漏洩
- 保護具の不適切な使用
もしかして自分も?職業がんのリスクが高い仕事とは
職業がんは、特定の業種や職種で働く人々に発症リスクが高いことが知られています。過去から現在に至るまで、様々な調査や研究によって、どのような仕事に危険が潜んでいるかが明らかになってきました。
もちろん、これらの仕事に従事するすべての人ががんになるわけではありませんが、リスクを認識し、適切な予防策を講じることは非常に重要です。
ここでは、特に注意が必要とされる代表的な業種をいくつか紹介します。
建設業と解体業
建設業、特に古い建物の解体現場では、過去に使用された建材からアスベストの粉じんが飛散するリスクがあります。アスベストは、肺がんや悪性中皮腫の主要な原因物質です。
吸い込んでから数十年という長い潜伏期間を経て発症するため、過去に従事していた方も注意が必要です。
また、トンネル工事などでは、岩石を削る際に発生する結晶性シリカの粉じんも肺がんのリスクを高めます。
建設現場での主なリスク
| 作業内容 | 曝露リスクのある物質 | 関連するがん |
|---|---|---|
| 建築物の解体・改修 | アスベスト | 肺がん、悪性中皮腫 |
| トンネル掘削 | 結晶性シリカ | 肺がん |
| 塗装 | 有機溶剤、クロム | 肺がん、膀胱がん |
製造業・化学工業
化学物質を製造したり、製品の加工に使用したりする現場では、様々な発がん性物質への曝露リスクが存在します。
例えば、ベンゼンを扱う化学工場や印刷工場では白血病のリスクが、塩化ビニルを製造する工場では肝血管肉腫という特殊ながんのリスクが知られています。
金属加工の際に発生する金属ヒューム(蒸気が凝固した微粒子)や、塗装作業で使う有機溶剤も、肺がんや膀胱がんの原因となることがあります。
その他の高リスク業種
上記以外にも、職業がんのリスクが指摘される業種は数多くあります。例えば、農業では長期間の紫外線曝露による皮膚がんのリスクや、特定の農薬との関連が研究されています。
また、医療現場で働く放射線技師は、電離放射線によるがんのリスク管理が重要です。自分の仕事内容と、そこで扱われている物質について関心を持つことが、リスクの早期発見につながります。
アスベスト、ベンゼン – 原因物質で異なるがんの種類
職業がんを引き起こす原因物質は数多くありますが、その物質によって発症しやすいがんの種類は異なります。
これは、物質が体内に取り込まれた後、特定の臓器に蓄積しやすかったり、特定の細胞に作用しやすかったりするためです。
ここでは、職業がんの原因として特に知られているアスベストとベンゼンを例に挙げ、それぞれがどのようながんを引き起こすのかを詳しく見ていきます。
アスベスト(石綿)と関連するがん
アスベストは、極めて細い繊維状の鉱物で、吸い込むと肺の奥深くまで到達し、長期間体内に留まります。
このアスベスト繊維が肺や胸膜(肺を覆う膜)を刺激し続けることで、がんが発生します。潜伏期間が20年から50年と非常に長いのが特徴です。
アスベストが引き起こす代表的な疾患
| 疾患名 | 発生部位 | 特徴 |
|---|---|---|
| 悪性中皮腫 | 胸膜、腹膜など | アスベスト曝露との関連が極めて強いがんで、治療が難しい。 |
| 肺がん | 肺 | 喫煙とアスベスト曝露が重なると、リスクが飛躍的に高まる。 |
| 石綿肺 | 肺 | 肺が線維化する病気で、がんではないが呼吸機能が低下する。 |
ベンゼンと関連するがん
ベンゼンは、無色透明の液体で、有機溶剤として広く使われてきました。揮発性が高く、呼吸を通じて容易に体内に吸収されます。
ベンゼンは特に、血液をつくる骨髄の細胞にダメージを与え、血液のがんである白血病を引き起こすことが確立されています。比較的短い潜伏期間(5年から15年程度)で発症することもあります。
ベンゼンの主な用途と健康影響
- 化学製品の原料
- 塗料やインクの溶剤
- ガソリンの成分
その他の化学物質とがんリスク
アスベストやベンゼン以外にも、多くのがん原因物質が特定されています。
例えば、塩化ビニルモノマーは肝臓のがん(肝血管肉腫)を、ヒ素は肺がんや皮膚がんを、クロムやニッケルは肺がんを引き起こすことが知られています。
これらの物質を扱う職場では、厳重な曝露対策が求められます。
化学物質と関連がんの例
| 化学物質 | 関連する主ながん |
|---|---|
| ヒ素およびその化合物 | 肺がん、皮膚がん、膀胱がん |
| 六価クロム化合物 | 肺がん、上気道がん |
| コールタール、ピッチ | 皮膚がん、肺がん |
見過ごさないで – 職業性のがんに見られる兆候
職業がんは、曝露から発症までの潜伏期間が長いことが多く、初期には自覚症状がほとんどないことも珍しくありません。そのため、気づいたときには病状が進行しているケースもあります。
しかし、どんな病気でも早期発見・早期治療が重要であることに変わりはありません。体のささいな変化に気づき、それが職業的曝露と関連している可能性を疑うことが、手遅れにならないための第一歩です。
定期的な健康診断と共に、自身の体調変化に注意を払う習慣が大切です。
注意すべき初期症状
職業がんの症状は、発生した臓器によって様々です。肺がんであれば咳や痰、息切れ、胸の痛みなどが、皮膚がんであれば治りにくい湿疹やいぼ、ほくろの変化などが見られます。
これらの症状は、風邪や加齢によるものと自己判断してしまいがちですが、長く続く場合や悪化する場合には、専門医に相談することが重要です。
その際には、ご自身の職歴(どのような仕事で、何を扱っていたか)を医師に伝えることが、正確な診断の助けになります。
臓器別の主な初期症状
| がんの種類 | 注意すべき初期症状の例 |
|---|---|
| 肺がん・中皮腫 | 長引く咳、血痰、息切れ、胸痛 |
| 皮膚がん | 治らない湿疹、いぼ・ほくろの形や色の変化、出血 |
| 膀胱がん | 痛みを伴わない血尿 |
| 白血病 | 原因不明の発熱、貧血、あざ、出血しやすい |
健康診断の重要性
症状がない段階でがんを発見するために、健康診断は極めて有効な手段です。特に、有害な業務に従事する労働者に対しては、労働安全衛生法に基づき、事業者が特殊健康診断を実施する義務があります。
この診断では、扱う物質に応じて特定の検査項目(例えば、じん肺健診の胸部X線検査や、特定化学物質健診の尿検査など)が設定されています。
会社の健康診断を必ず受診することはもちろん、退職後も自治体のがん検診などを定期的に利用し、継続的に健康状態を確認することが大切です。
特殊健康診断の目的
- 職業性疾病の早期発見
- 作業環境や作業方法の問題点の把握
- 健康障害の未然防止
自分と家族を守るために – 明日からできる予防と対策
職業がんのリスクを知ることは、不安に繋がるかもしれません。しかし、最も重要なのは、そのリスクを理解した上で、適切な予防と対策を実践することです。
職業がんは、原因となる物質や環境への曝露を防ぐ、あるいは最小限にすることで、その多くが予防可能です。対策は、事業者(会社)が講じるべきものと、労働者(働く人)自身ができるものに分けられます。
双方の協力によって、安全な職場環境は実現します。
労働者自身ができる予防策
働く私たち一人ひとりが、日々の業務の中で意識的に行動することが予防の基本です。会社が定めた作業手順やルールを守ることはもちろん、支給された保護具を正しく着用することが重要です。
また、作業場での飲食や喫煙を避ける、作業後は手や顔をよく洗うといった基本的な行動も、有害物質を体内に取り込むリスクを減らす上で効果的です。
個人で実践する予防対策
| 対策の種類 | 具体的な行動例 |
|---|---|
| 保護具の着用 | 防じんマスク、防毒マスク、保護手袋、保護衣などを正しく装着する。 |
| 作業場の衛生 | 作業場での飲食・喫煙をしない。作業衣をこまめに洗濯する。 |
| 作業後のケア | 手洗い、うがい、シャワーを徹底する。 |
| 健康管理 | 定期的に健康診断を受ける。禁煙やバランスの取れた食事を心がける。 |
事業者が講じるべき対策
労働者の安全と健康を守ることは、事業者の最も重要な責務の一つです。
労働安全衛生法では、事業者に対して、危険な化学物質をより安全なものに代替すること、発散源を密閉する設備や局所排気装置を設置すること、作業環境測定を実施して環境を評価することなどを義務付けています。
また、労働者への安全衛生教育も事業者の重要な役割です。
リスクについて話し合える職場環境
職場の安全衛生に関する問題は、事業者と労働者が協力して取り組むことが大切です。
危険だと感じることや、改善してほしい点があれば、上司や安全衛生委員会などに相談できる風通しの良い職場環境が求められます。
自分の健康を守るために、疑問や不安を一人で抱え込まず、声を上げることが重要です。
労災認定のポイント – 知っておきたい社会の支援と相談窓口
万が一、がんと診断され、その原因が仕事にあるのではないかと考えた場合、労働者災害補償保険(労災保険)制度の利用を検討することになります。
労災として認定されると、治療費の給付や休業中の所得補償など、様々な支援を受けることができます。
しかし、申請手続きは複雑で、仕事と病気の因果関係を証明する必要があるため、専門的な知識が求められます。一人で悩まず、専門の機関に相談することが、適切な支援への第一歩です。
労災認定の基本的な考え方
労災認定では、「業務遂行性」と「業務起因性」という二つの要件が判断されます。「業務遂行性」とは、労働者が事業者の管理下で業務に従事していたことを指し、多くの場合問題となりません。
重要なのは「業務起因性」で、これは病気(がん)が仕事に起因して発症したといえるか、という医学的な因果関係の証明です。
具体的には、発がん性物質への十分な曝露歴があること、医学的にその物質とがんの関連が認められていること、他の有力な原因がないことなどが総合的に判断されます。
労災申請から認定までの流れ
労災の申請は、労働者本人またはその遺族が、所轄の労働基準監督署長に対して行います。申請には、医師の診断書や、これまでの職歴、具体的な作業内容などをまとめた書類が必要です。
申請後、労働基準監督署は、本人や会社、関係者への聞き取り調査や、専門医への意見照会などを行い、労災に該当するかどうかを決定します。
申請に必要な情報の例
- 診断書(病名、発症時期など)
- 職歴(会社名、在籍期間、担当業務)
- 作業内容の詳細(使用していた化学物質、作業環境など)
- 同僚の証言
困ったときの相談窓口
労災の申請を個人で行うのは困難な場合が多いため、専門の相談窓口を活用することが重要です。
全国の労働局や労働基準監督署には相談窓口が設けられているほか、労働組合や、職業がんの問題に取り組むNPO法人、弁護士なども力になってくれます。
特に、過去の認定事例や医学的知見に詳しい専門家の助言は、申請を円滑に進める上で大きな助けとなります。
主な相談先一覧
| 機関名 | 主な役割 |
|---|---|
| 労働基準監督署 | 労災申請の受付、調査、認定を行う行政機関。 |
| 労働組合 | 組合員の労働条件や安全衛生に関する相談、会社との交渉支援。 |
| 弁護士・社会保険労務士 | 法的な手続きの代理、書類作成のサポート。 |
| 職業がん・アスベスト関連のNPO法人 | 専門的な情報提供、患者や家族の相談支援、交流の場の提供。 |
よくある質問
- どのくらいの期間、有害物質を扱うと職業がんのリスクがありますか?
-
一概に「何年間」と明確な基準を示すことは困難です。リスクは、扱っていた物質の種類、曝露の濃度、期間、頻度、そして個人の感受性など、多くの要因によって左右されます。
一般的には、高濃度の発がん性物質に長期間曝露するほどリスクは高まります。重要なのは、曝露期間の長短だけでなく、どのような物質にどの程度のレベルで曝露したかという「曝露歴」です。
少しでも不安がある場合は、専門医や相談機関に自身の職歴を詳しく伝えて相談することが大切です。
- 退職してから何年も経っていますが、労災申請はできますか?
-
はい、退職後でも労災申請は可能です。職業がんの多くは潜伏期間が長いため、退職後に発症するケースが少なくありません。
労災保険の給付を受ける権利には時効がありますが、その起算点は「権利を行使できるようになった時」からとなります。
例えば、療養補償給付であれば治療費を支払った日の翌日から2年、遺族補償給付であれば労働者が亡くなった日の翌日から5年です。
時効の問題は複雑ですので、まずは労働基準監督署や弁護士などの専門家に速やかに相談してください。
- 会社が協力してくれない場合、どうすればよいですか?
-
労災申請において、事業主の証明が得られない、あるいは会社が協力的でないというケースは残念ながら存在します。
しかし、事業主の証明がなくても労災申請は可能です。その場合、労働基準監督署が、会社への聞き取り調査などを通じて事実関係を確認します。
過去の同僚の証言や、自分自身で記録していた作業日誌なども、有力な証拠となる場合があります。
会社が非協力的な場合は、一人で抱え込まず、労働組合や弁護士などの第三者に相談し、サポートを求めることが重要です。
- 喫煙習慣があるのですが、肺がんになっても職業がんとして認められますか?
-
喫煙が肺がんの最大の原因であることは事実ですが、喫煙習慣があるからといって、職業がんの可能性が完全に否定されるわけではありません。
例えば、アスベストを扱う労働者が喫煙していた場合、肺がんのリスクはアスベスト曝露のみ、あるいは喫煙のみの場合に比べて飛躍的に高まることが知られています(相乗効果)。
このような場合、仕事による曝露が相対的にどの程度発症に寄与したかを判断し、労災認定されるケースは数多くあります。
喫煙歴がある場合でも、まずは職歴と病状を専門家に相談してみることが大切です。
職業的ながんリスクは、化学物質や粉じんだけではありません。屋外での作業が多い方は「紫外線」、医療や特定の工業分野で働く方は「電離放射線」への曝露も、がんの原因となり得ます。
これらは目に見えないため、知らず知らずのうちに影響を受けている可能性があります。
紫外線による皮膚がんのリスクや、放射線業務における被ばく管理の重要性について、より詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
参考文献
DELCLOS, George L.; LERNER, Seth P. Occupational risk factors. Scandinavian journal of urology and nephrology, 2008, 42.sup218: 58-63.
BAAN, Robert; BOUVARD, Véronique. A review of human carcinogens—part F: chemical agents and related occupations. The lancet oncology, 2009.
RIM, Kyung-Taek. Occupational cancers with chemical exposure and their prevention in Korea: a literature review. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2013, 14.6: 3379-3391.
CHERRIE, John W. Reducing occupational exposure to chemical carcinogens. Occupational medicine, 2009, 59.2: 96-100.
CLAPP, Richard W.; JACOBS, Molly M.; LOECHLER, Edward L. Environmental and occupational causes of cancer new evidence, 2005–2007. Reviews on environmental health, 2008, 23.1: 1.
MICALLEF, Claire Marant, et al. Occupational exposures and cancer: a review of agents and relative risk estimates. Occupational and Environmental Medicine, 2018, 75.8: 604-614.
FENGA, Concettina. Occupational exposure and risk of breast cancer. Biomedical reports, 2016, 4.3: 282-292.
LOOMIS, Dana, et al. Identifying occupational carcinogens: an update from the IARC Monographs. Occupational and environmental medicine, 2018, 75.8: 593-603.
BOFFETTA, Paolo. Epidemiology of environmental and occupational cancer. Oncogene, 2004, 23.38: 6392-6403.
FALZONE, Luca, et al. Occupational exposure to carcinogens: Benzene, pesticides and fibers. Molecular medicine reports, 2016, 14.5: 4467-4474.